時代の変化に安易に適応するのではなく、
変化を疑うことから「哲学」は始まる
今の社会がおかしな方向に向かっているのではないか、と感じる人は増えているかもしれません。が、多くの人は世の中に適応することをよしと考えているので、世界や社会の変化を簡単には疑えません。
安易に適応ばかりしていると、人は考えることをやめ、全体主義に走ってしまう恐れがある。それを防ぐには哲学を通じて物事を根本から考えることが有効です。ただし哲学を学ぶには既存の答えを疑い、自分の価値観が根本から突き崩される覚悟が必要です。
例えば古代ギリシャ哲学の徳の一つ「パレーシア」は「危険を冒してでも真理を話すこと」を意味していて、ソクラテスはそれによって世界が間違った方向に進まないよう歯止めをかけてきた。
炎上の多い今の社会でそれを実践することは難しいですが、個々人がその視点を持つことが、社会を動かす原動力になるはずです。
ニーチェ、マルクス、フロイト
現代思想の礎に立ち返る
哲学者が根本から物事を考えられるのは、私たちが使っている言葉の定義を徹底的に考え直すからです。それはさまざまな言葉がどう使われてきたか知り、大量の書物のネットワークを頭に配置することでもあります。
そこでまずは田中正人、斎藤哲也の『哲学用語図鑑』を哲学のカタログとして読むことで語彙を増やすのがいいでしょう。
今の哲学がどう形作られたか知るために、次は、現代思想の礎を築いた3人、フリードリヒ・ニーチェ、カール・マルクス、ジークムント・フロイトの思想に触れましょう。
彼らの問題意識を学び、彼らの構想した社会や人間のあり方をインストールすることは、これからの世界が進む方向を検証するうえで役立つはずです。
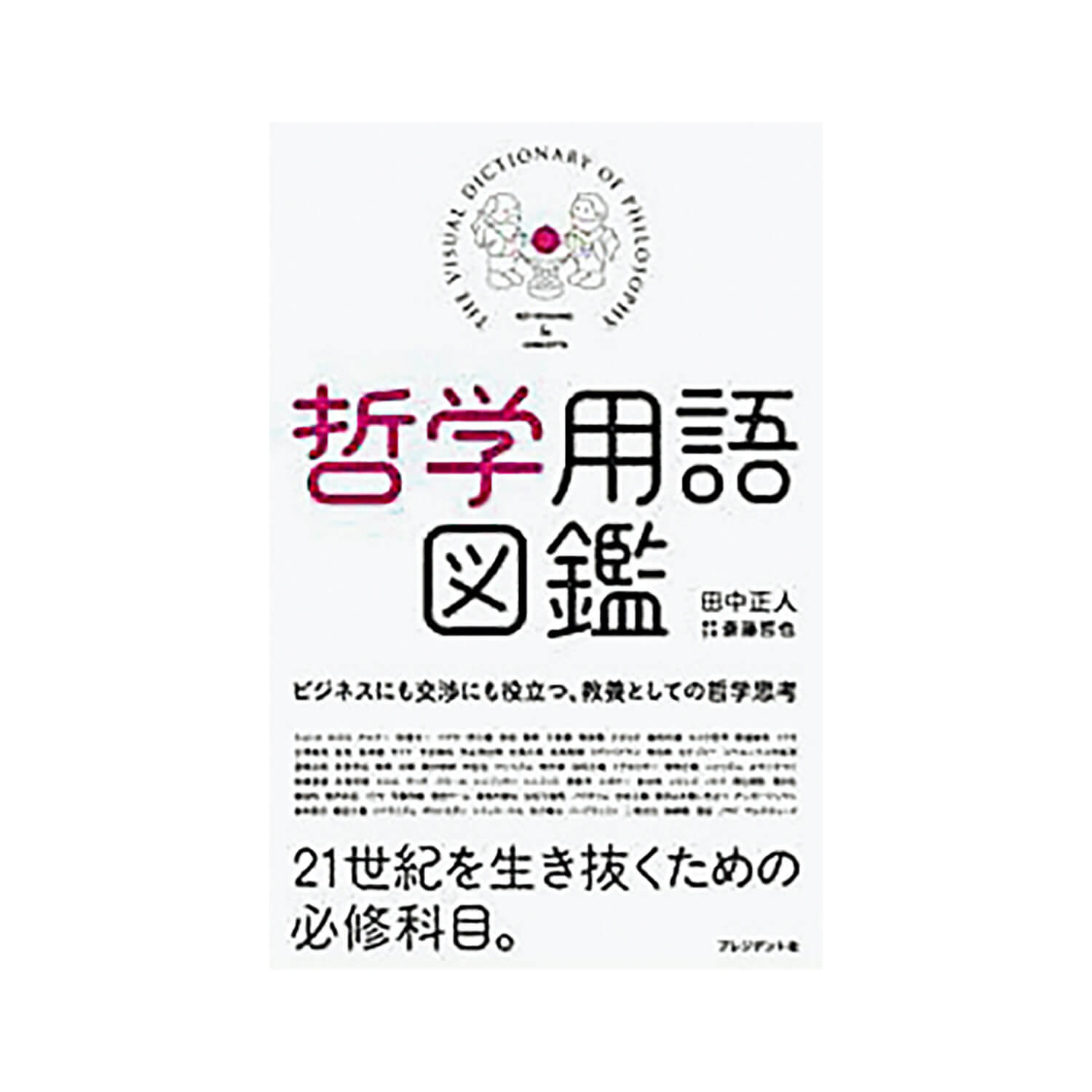
ピタゴラスからサンデルまで、重要な哲学者70人をピックアップし、200語以上に及ぶ概念を簡易なビジュアルとともに紹介。教養としての哲学を身につけるための知のカタログ。プレジデント社/¥1,800
ニーチェは、大勢順応的な生き方から離脱することを考えていました。石川輝吉『ニーチェはこう考えた』を読んで彼の人となりをつかんだら、彼の哲学書をパラパラ読んでみると孤独に生きることの強さやマジョリティにおもねらず価値を転換する勇気が理解できるでしょう。
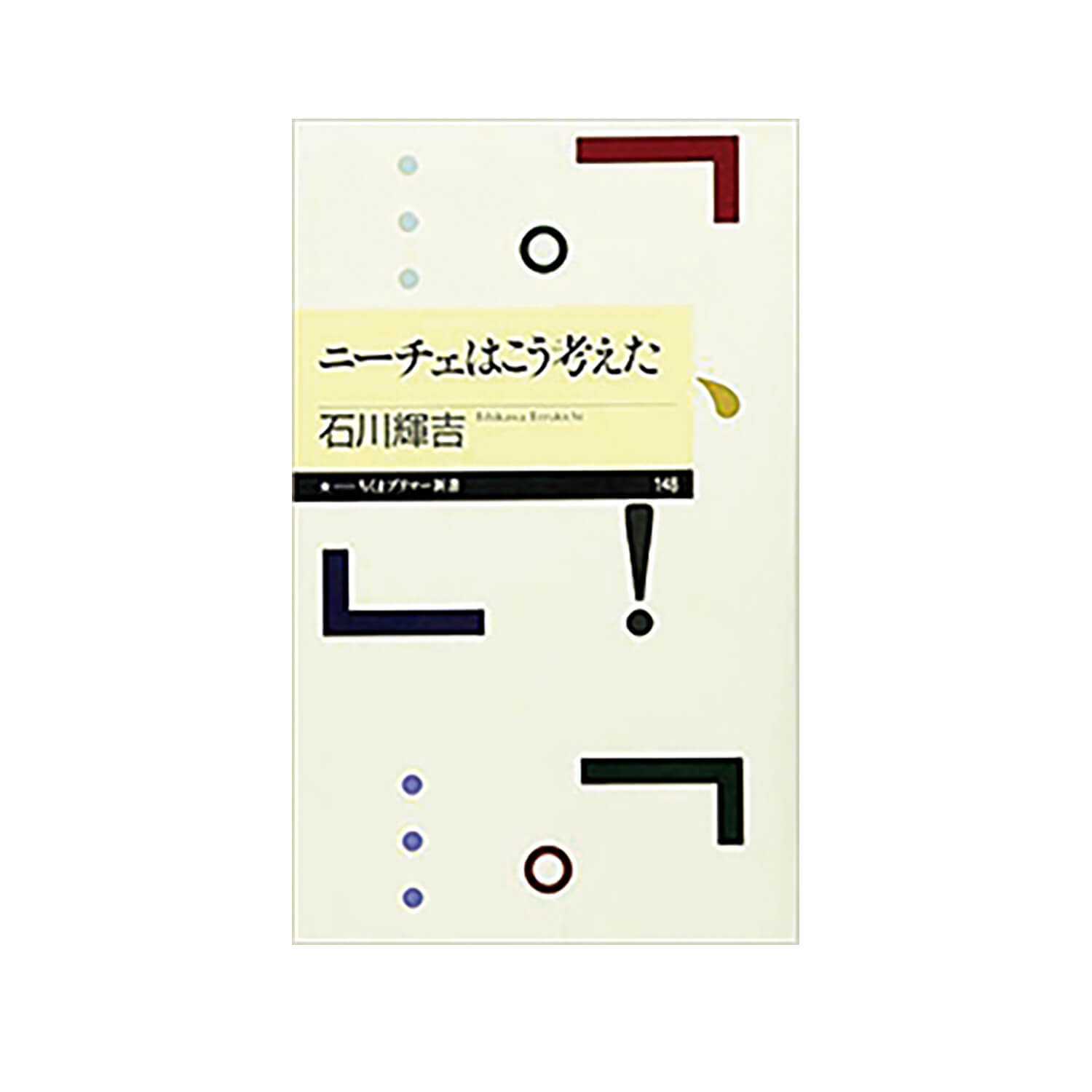
「超人」や「神の死」など数多くの新たな概念を提起したニーチェはもともと挫折してばかりの青年だった。現実の「どうしようもなさ」と格闘するニーチェの姿から、彼の思想を知る。ちくまプリマー新書/¥780
続いてマルクスの思想は社会主義国のイメージが強く、冷戦後はもはや「潰えた夢」と思われがちですが、白井聡『武器としての「資本論」』はマルクスの本質を改めてわかりやすく取り出し、現代の資本主義が生む息苦しさを打破しようとしています。
モノもサービスも“商品”に変えてしまう現代とは別の可能性を考えるうえでマルクスの思想は今なお有効です。
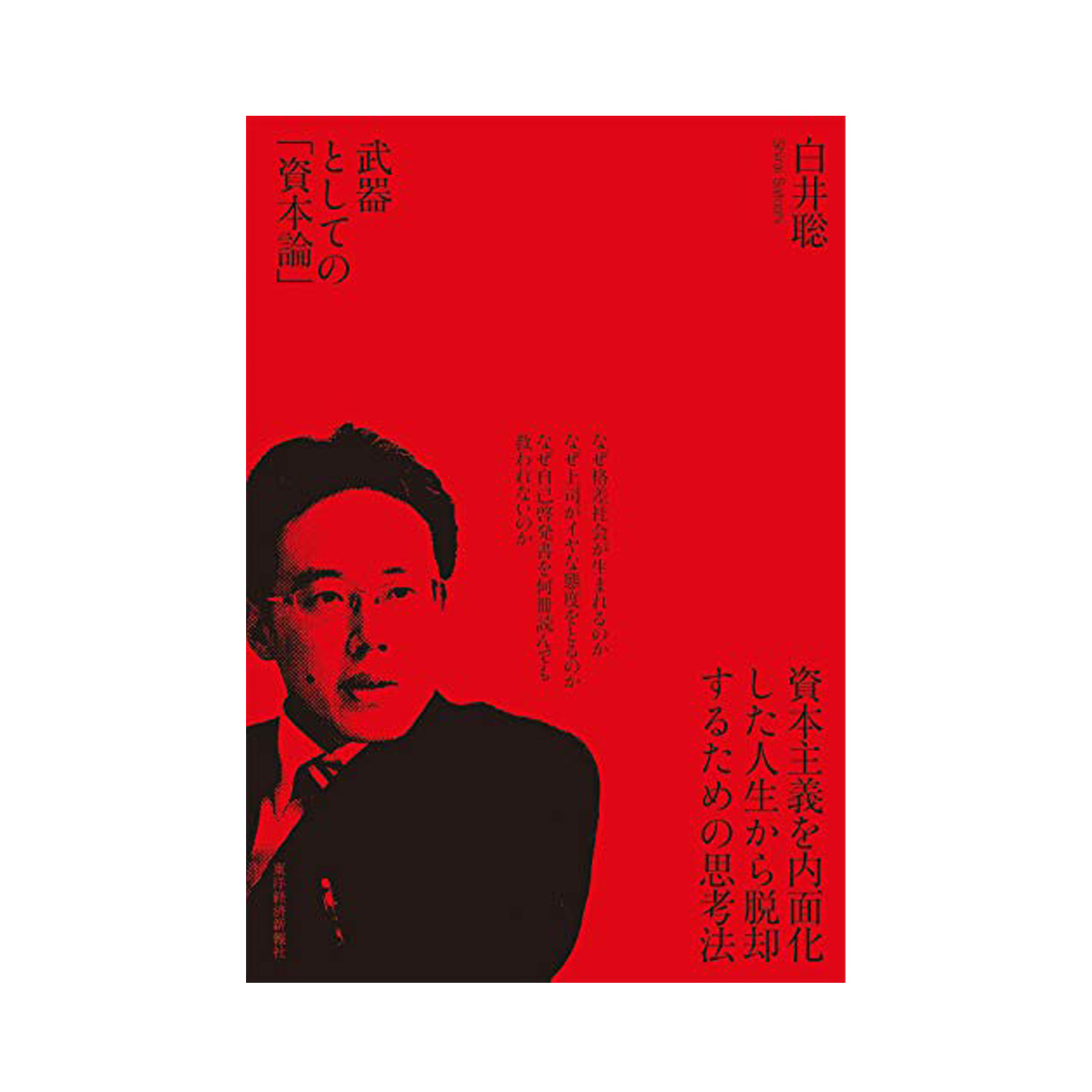
なぜ格差はなくならず、社会の息苦しさは増すばかりなのか。商品や包摂など『資本論』の中心概念から資本主義の欺瞞を暴き、知られざるマルクスの可能性を切り開く。東洋経済新報社/¥1,600
最後にフロイトは精神分析の発明者であり、無意識という概念によって、現代につながる人間像の基礎を作った存在です。しかし、立木康介『露出せよ、と現代文明は言う』を読めば現代社会が“無意識”の領域に無自覚、なんならそれらをなくそうという方向に進んでいることがわかります。
現代は誰もが自由意志に基づいて行動し、意識も感情もすべて開示されるものだと捉えられている。が、本来人間は無意識に左右されながら自分の意思とは異なるふうにも生きていくものなのに、すべてを決定できると思い込んでいたら、自分が嫌だと思うことは一つも受け入れられなくなるでしょう。
国家や企業はこうした状況につけ込み、ストレスをなくすために多くのサービスを提供することで人々を資本主義の論理のなかに包摂、つまり取り込んでいます。
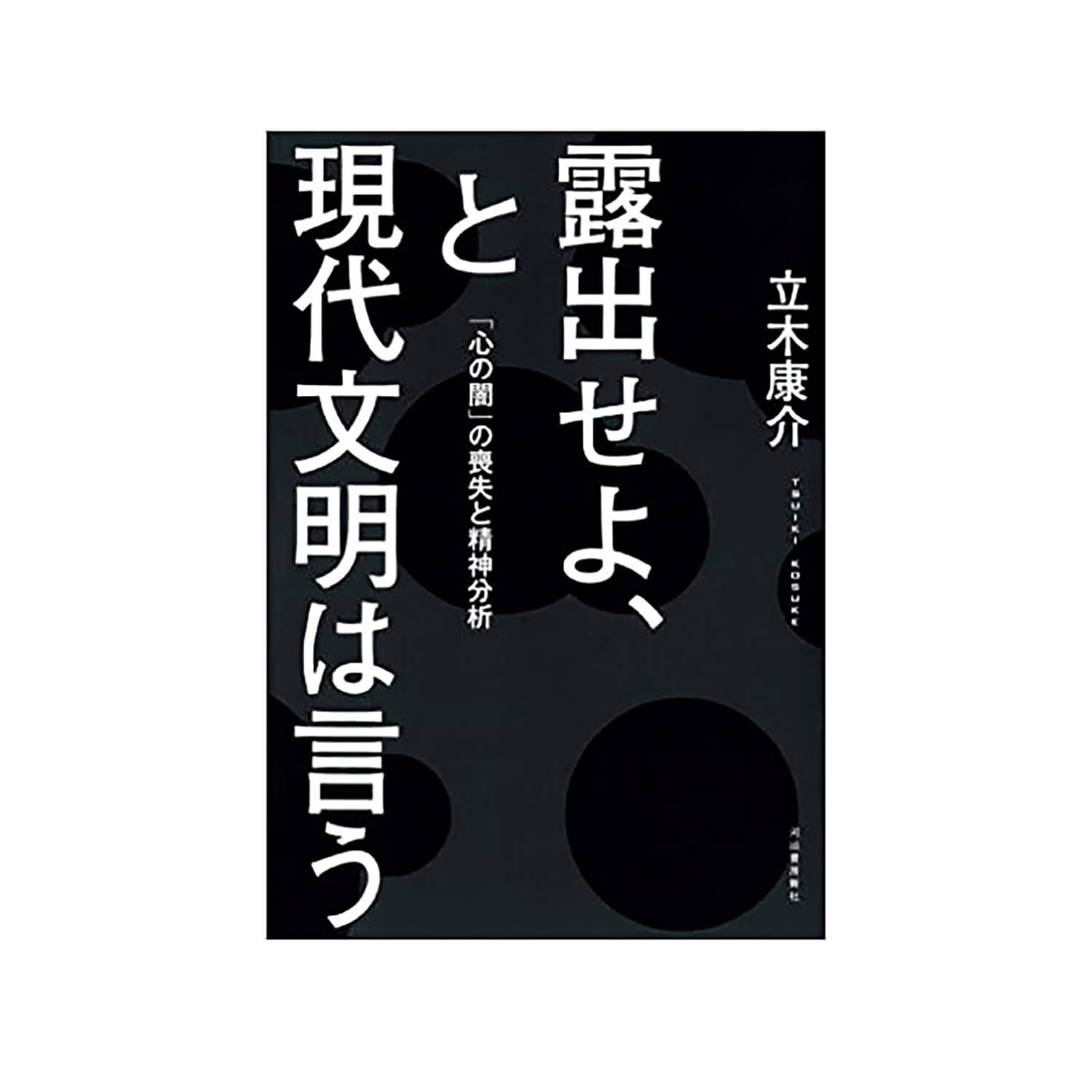
しばしば犯罪報道で語られる「心の闇」は本当に存在するのか。人の内面が「秘匿」するものから「露出」するものになったことで社会がどう変わりつつあるのか考える。河出書房新社/¥2,400
こうした現代思想の礎を踏まえると、今の社会や人々が反ニーチェ・反マルクス・反フロイト的な方向へと向かっていることに気づきます。先人たちが築き上げた教養は役に立たないものだとされ、人間が培ってきた「知」が軽んじられてしまっている。
確かにこうした書籍を通じて哲学を勉強することは時間も手間もかかるし、すぐに答えが出るわけでもない。世間の流れに合わせて生きる方が楽しく過ごせる人も少なくないでしょう。しかも哲学を勉強すればするほど求められる知識も増え、手放しで気楽に何かを考えることは難しくなるかもしれません。
でも同時に、自分がこれまで何も考えられていなかったことにも気づくでしょう。その状態を通過することで初めて哲学を学ぶ意味が生まれてくるし、主体的に世界の動きを捉えられるようになるはずです。















