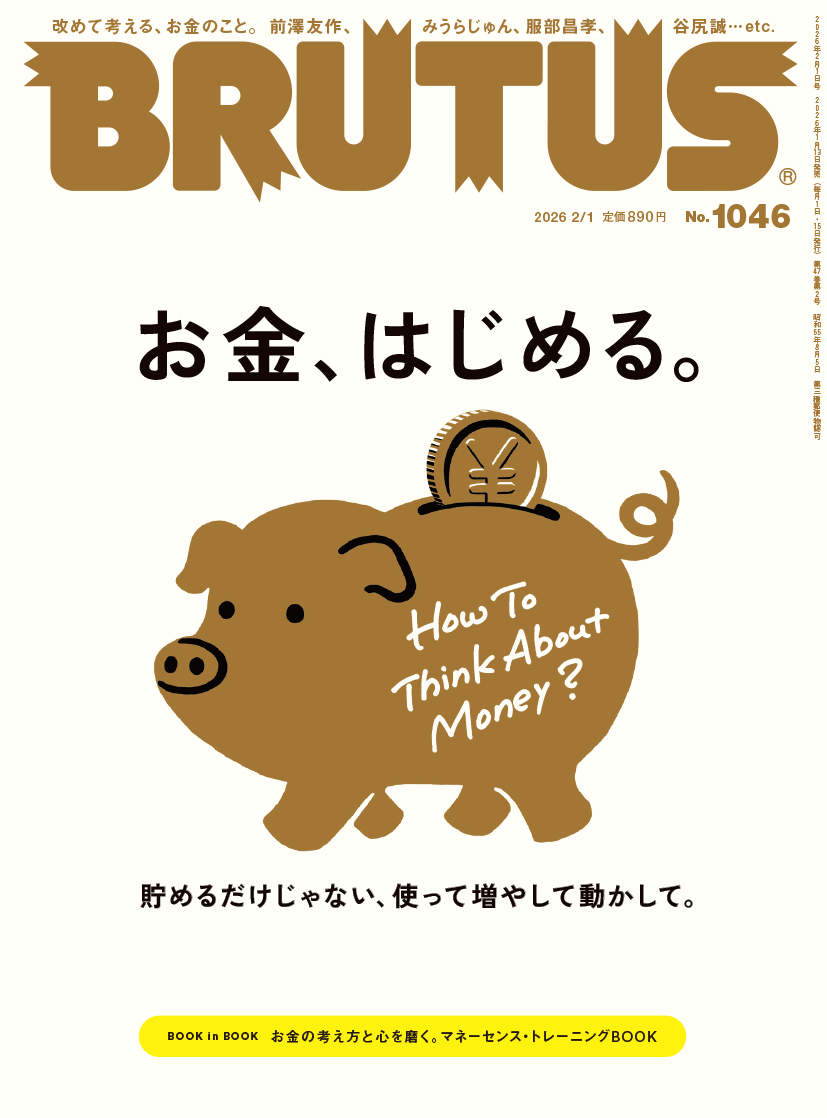“適当に読むこと”から、多くを得る
「ここ数年、家にこもって漫画を描く代わり映えのしない日々が続いているので、環境を変えようと、複数人で使えるシェアハウスのような仕事場を借りようと思い立ちました。善は急げということで1週間で物件を決めて。今は、編集者の友人と学生時代の同級生の2人にもよく使ってもらっています」
数ヵ月ほど前に、新たな仕事の拠点を構えた魚豊さん。入居すると間もなく、リビングの一角にライトグレーの棚を据え、空間と同様に、本棚も友人たちとシェアすることとなった。
「出入りする友人たちも読書好きなので、なんとなくお互いのスペースを決めつつ棚を共有しています。実際には仕事の資料本や漫画など、本は手当たり次第に購入するのですが、それらは自宅に置いておいて、あくまでもここはコンパクトに。主にはそれぞれが近々で読んだ本を置いているので、お互いが今何に興味を持っているかが視覚的にわかるようになっています」


本棚のうち、左端の上下2つのブロックが主に魚豊さんのスペース。大学では西洋哲学を専攻し、かねて関心を寄せる思想や哲学などを扱った人文書を中心に、テクノロジー、経済、アートなどジャンルを横断した多彩な本が40冊ほど並んでいる。
2023年夏から続いた漫画連載が一段落つき、ここ半年は「好きに読書ができる、久々のインプット期間だった」と話す。専門性の高い本を好むため、既に読んだ本に引用されていたり、SNSやメディアを通じて興味を持ったりした本を、ネットで目的買いするのが彼のスタイルだ。
「興味があって手に取るとはいえ、何かを得ようと読むわけでもないんです。むしろ、頭を空っぽにできるのが本の好きな点。映画や漫画は一つ一つの場面を理解できないと気が済まないし、つまらないと思った時点でやめてしまうんですが、本だと退屈でも不思議と淡々とページをめくっていける。それでいて自然と知らないことが入ってくるし、自分なりに思考を巡らすこともできます。ほかのメディアと比べて適当に向き合えるのがいいんですよね」
読書会の課題図書が新鮮な気づきをくれる
初めて漫画を描いたのは13歳の頃。以来「部活もせずに、ひたすら漫画を描いてきた」という魚豊さんが、自分事として関心を寄せるのは、“どうして人は物語を作るのか”との問いだ。
「夢中で続けてきた一方で、なぜ自分を含む作家たちは、現実でないものを描くという、ある種の意味不明な行為をするのかが気になっているんです」
ゆえに、手に取ったあまたの本の中でも、かねて抱く根源的な問いにどこかで触れる作品が心に残る。自ら興味を持って手を伸ばした本のみならず、棚を共有する仲間たちと月1、2回のペースで続ける読書会を機に思いがけず手にした本の中にも、新鮮な気づきをもたらしてくれるものがあった。
「友人が課題図書としてセレクトしてくれた、ミハイル・バフチンの『小説の言葉』は面白かったですね。目から鱗が落ちる思いがしたのは、言葉そのものについての考察です。僕なりに解釈すれば、著者のバフチンは、“言葉とは、過去の積み重ねによってのみならず、未来から逆説的に生まれるものでもあるんだ”と説くんです。小説の中でも現実においても、その後に続く受け取り手のリアクションに制約されて放たれるのが、言葉の本来のあり方なのだ、と。
僕も作家として、無意識的ながらも次の展開やセリフを想定した状態で言葉を書くので、すごく腑に落ちました。と同時に見方を変えれば、相手を意識せず無秩序に言葉が飛び交う今のSNSの言論空間の不毛さも暗に示している。言葉というものの本来の役割を担う作家の存在意義を痛感させられましたし、100年近く前の本ながらも期せずして現代とリンクしていて、心に刺さりましたね」
好奇心を持って読書の幅を広げながら、一冊の中で引っかかった部分を自分なりに拾い、根源的な問いへの考察を続けていく。人の本質をさまざまな形で描き出す、現代的で普遍的な魚豊さんの作品は、彼が読書を通じて自然と繰り返す、こうした思考プロセスの末に生まれるのかもしれない。