初期社会主義
19世紀以降、ヨーロッパでは資本主義が拡大し、弱肉強食化が進みました。その中で生じた矛盾を克服すべく、有象無象によって作られていったのが社会主義という考え方。
こうした背景によって登場した社会主義者たちは、後にアナキストを標榜しばらばらになって戦うバクーニン派と、共産党という党を主体とするマルクス派に分かれていくのですが、初期段階ではごちゃ混ぜでした。
初期社会主義者たちが変えようとしたものの中には、劣悪な労働環境も含まれます。そこでかれらはさまざまな労働運動を展開し、資本家や工場主たちに文句を言っていきます。「賃金を上げてくれ」「労働時間を短くしてくれ」と。しかし、ご存じのように、資本家たちはこちらの言うことなんか聞いてくれない。
じゃあ、どうしたか。みんなで力を合わせて嫌がらせしていくわけですね。そうやってできた“技”が、今にも続くサボタージュやストライキです。時には工場自体を破壊したり。
重要なのは、かれらが“サンディカリズム(組合主義)”を掲げ、組合というものを組織したことです。なぜそれが必要かといえば、ストライキでも何でもみんなでやった方が威力が大きいから。
『革命的サンディカリズム』には、当時のアナキストたちがそうやって労働環境を変えてきた歴史が書かれています。もちろん、負けることも多々ありましたが。
私は勤め先の大学でも、弱小ですけど労働組合に参加し、大学相手にさまざまな申し入れや裁判を仕掛けて要求を呑ませています。その中で労働者としての知恵も醸成されます。組合っていうのは今でも有効で楽しいものです。
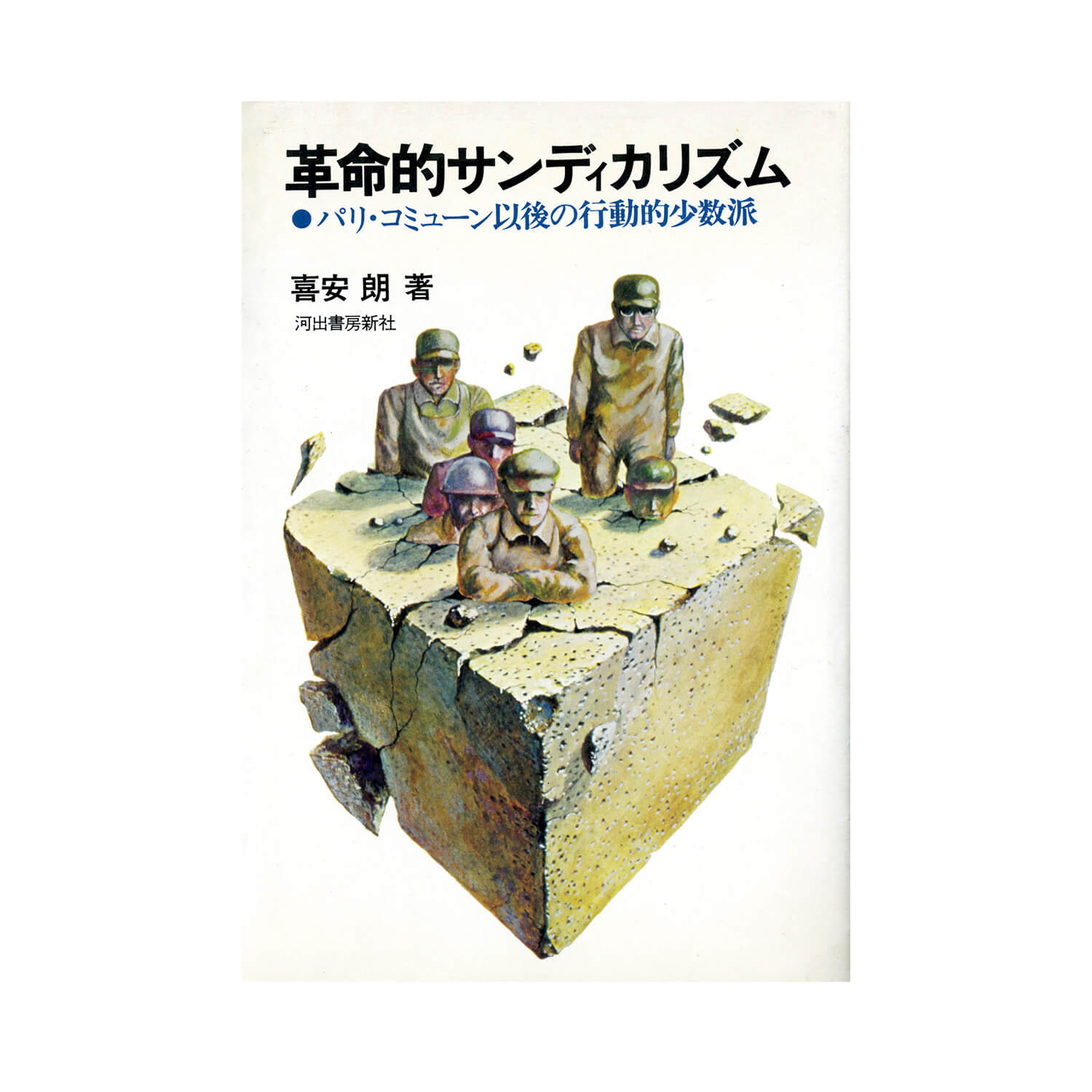
パリ・コミューン以降の労働運動の軌跡を、組合(サンディカリズム)に焦点を絞りつつ綴る。著者によれば、革命的サンディカリズムとは「一九世紀末の労働者の生活や意識によってなり立つ労働の世界に密着しつつ、そこから運動の流れを形成しようとした一連の実践の過程」と定義される。河出書房新社/品切れ
地人論
エリゼ・ルクリュは、19世紀末に活躍したアナキストであり、地理学者だった人。彼は『アナキスト地人論』の中で、世界中の地域の環境を例に取り、どんなトライブがどんな自治空間を作っているかを分析しました。
彼はそうした環境を重視する観点から、労働のあり方についても考えています。例えば、里山地域に住んでいるなら、林業や農業に従事すべきだといった具合に。そうやって場所に依拠した労働によって自分を作り変えて生きていくことの重要性を、彼は訴えた。
とはいえ、コミュニティの同調圧力がひどくて、「こんなところじゃ仕事ができない!」となることもあるでしょう。そういう時は、移動すればいいんです。
ルクリュ自身はそこまで書いていませんが、彼こそは生涯を通じて移動の自由を謳歌した人ですからね。つらい労働環境に身を置き続ける必要なんてありません。
アナキストたちが大事にするのは、自分に合った環境を探す、あるいは作っていくことなのです。
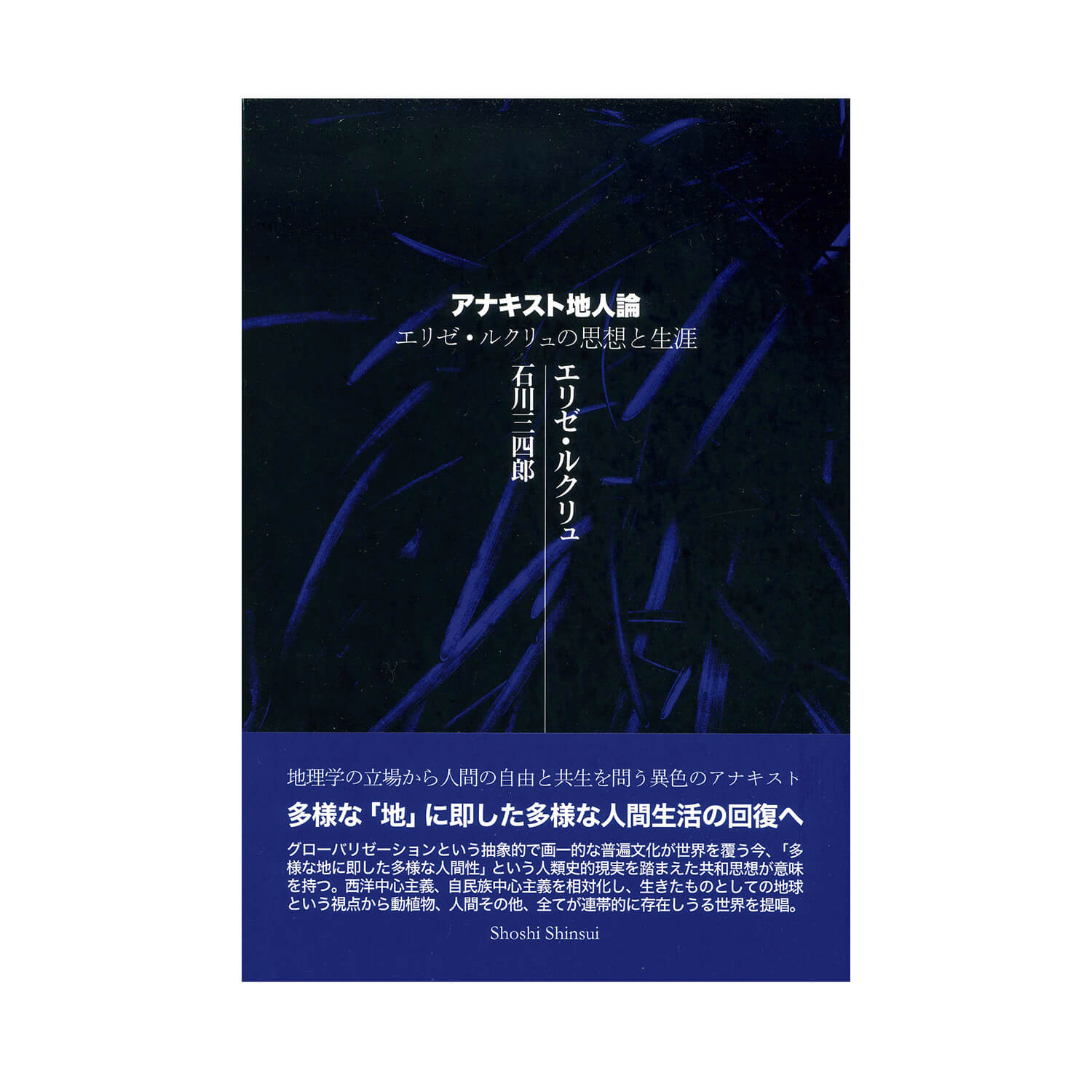
エリゼ・ルクリュが1900年代初頭に執筆した論文集。西洋中心主義、自民族中心主義を相対化し、地球上において、すべての人間や動植物が連帯的に存在できるという世界観を提唱する。労働についても原始時代の人類の営みに端を発し、そこに本来あるべき創造的な可能性が示唆される。書肆心水/3,600円
幕末
近世から近代にかけてヨーロッパの人々は、日本の暮らしをどう見ていたのか。さまざまな文献を通してそれを紹介する『逝きし世の面影』において、アナキスト的に興味深いのは、幕末の日本人労働者たちのあり方。遣日使節団長として来日したスイス人は、職人たちの仕事ぶりを見て驚くんです。
なぜなら、みんなが楽しそうに働いているから。きっとゲラゲラ笑いながら、時々歌を歌ったりしつつ仕事をしていたんでしょう。まさにアナキズム的な働き方を、そうとは意識せぬまま実践していた。これはすごい、と。
当時のヨーロッパでは、既に朝9時から夜5時までみっちり働くことが常態化されていましたから。もちろん、職人にしても仕事場でのヒエラルキーはあったでしょうけど、現場においては楽しさがある。それは現代に置き換えても同じでしょう。
しかも、そうやって適度になまけても納期に間に合ったりする。案外そんなもんなんです。かれらの働きぶりは、そういったことを思い出させてくれます。
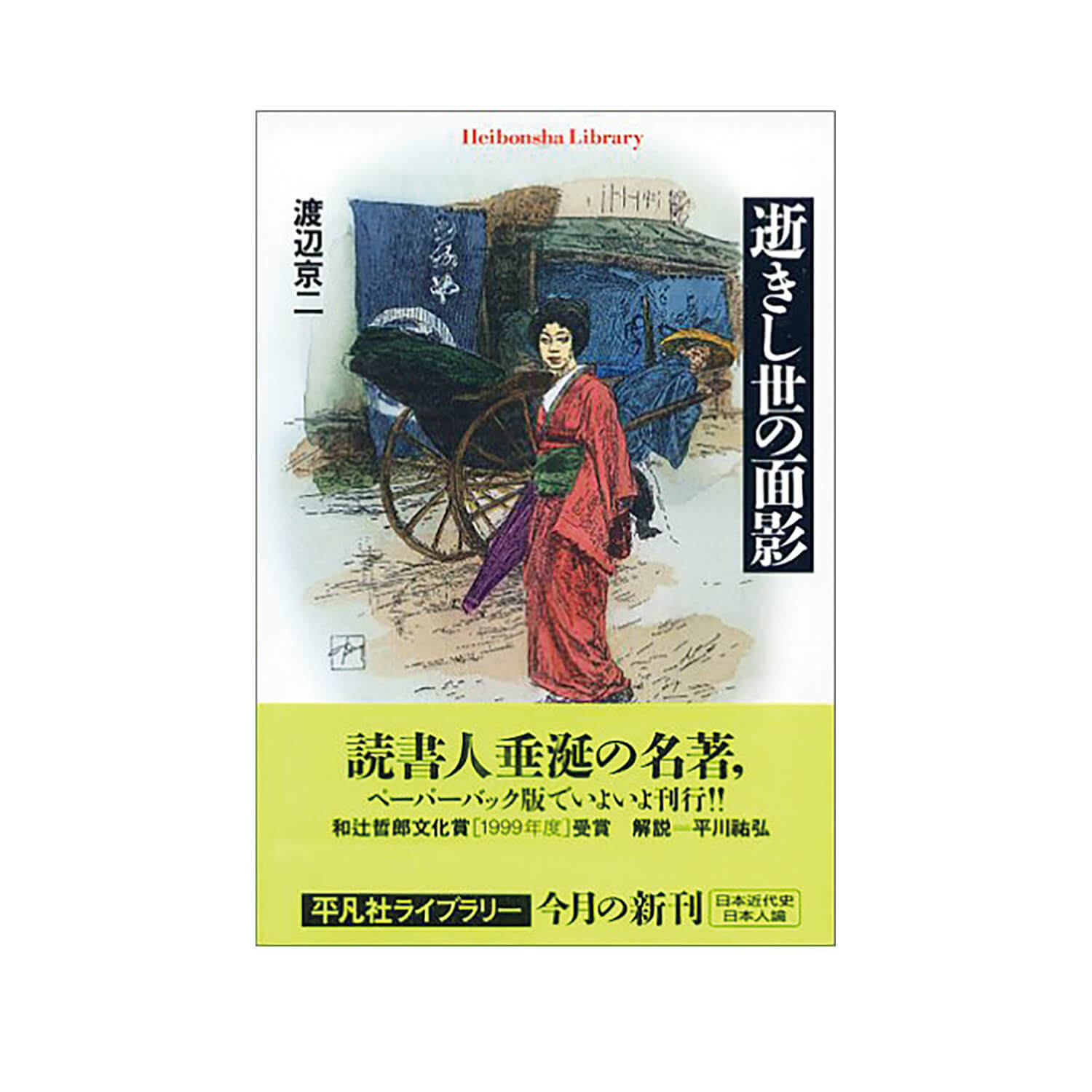
過去に来日した外国人たちの記録を通し、失われた日本の姿を描出。ある外国人は当時の労働者を「概して人々は生活のできる範囲で働き、生活を楽しむためにのみ生きている……労働それ自体が、もっとも純粋で激しい情熱をかき立てる楽しみとなっていた」と記している。2005年刊。平凡社ライブラリー/1,900円















