労働廃絶論
「労働はクソである!」という観点に立ち、ありとあらゆる労働を排除するのが、労働廃絶論という考え方です。現代のアナキスト、ボブ・ブラックが同名著書の中で展開しています。
とはいえ、何かしら生産しないとこの世の中は回らない。そこでブラックが重視するのが、“遊び”というファクターです。
要するに、この世界に労働者ではなく遊び人として参画し、遊ぶことを通して生産をし、賃金を得るべきだと。マルクスの『共産党宣言』の結びは「万国の労働者よ、団結せよ」ですが、こちらは「誰も働くべきではない。万国の労働者……リラックスせよ!」。
ところで、こうした発想自体は19世紀の空想的社会主義者、シャルル・フーリエにも通じると思います。彼は構成員が生産も消費も行う「ファランジュ」という労働者共同体を作り、その生産過程に仕事のストレスを発散させ、エキサイトさせるようなさまざまな仕組みを導入したからです。
例えば、2時間ごとに仕事を交代させるとか。いかにして仕事に遊びの要素を導入するか。これもアナキストにとっては大事なテーマなんです。
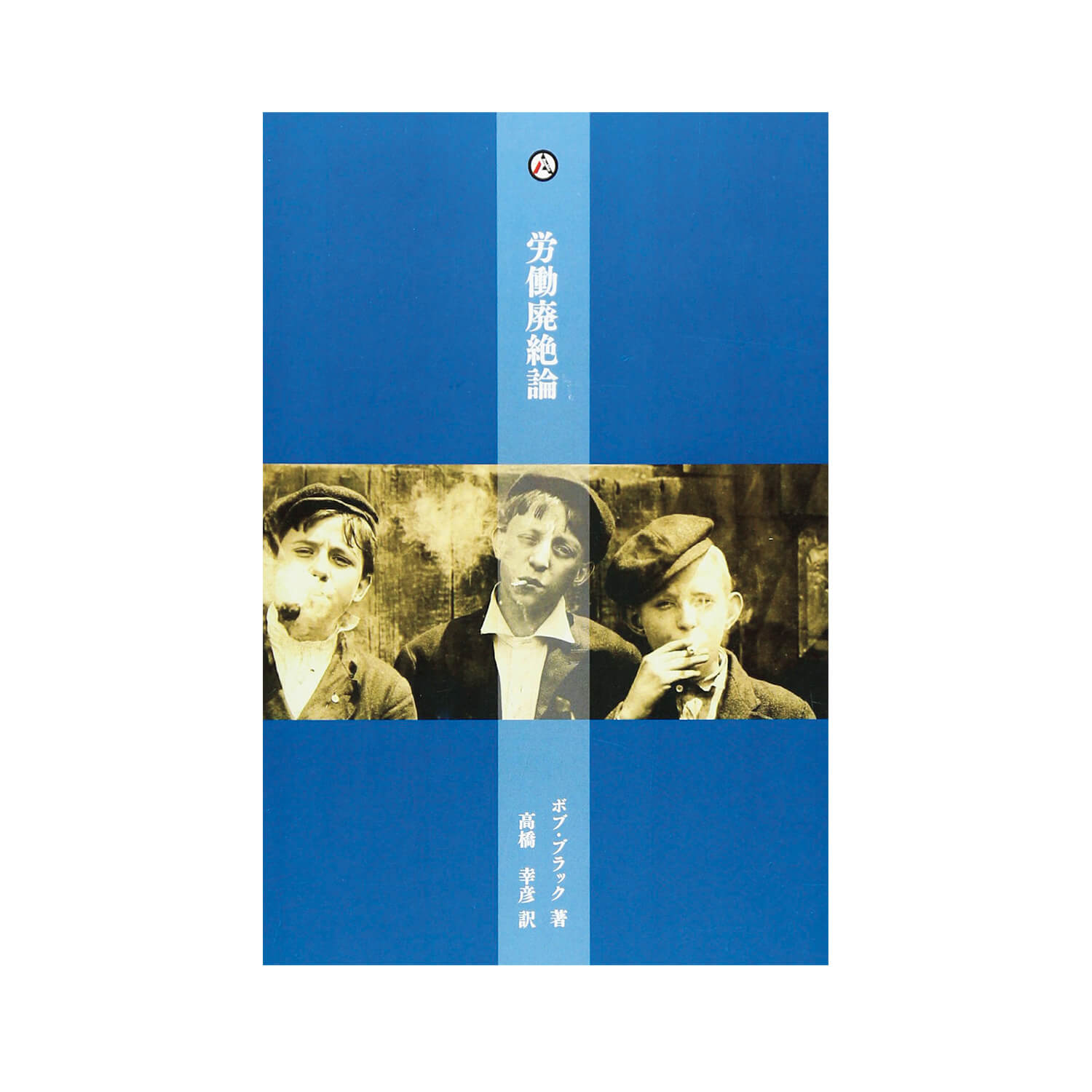
「人は皆、労働をやめるべきである。労働こそが、この世のほとんど全ての不幸の源泉なのである」という過激な文句から始まる檄文。1985年に書かれたそれに代わる生産様式と示される「遊び」は、皆と喜びを分かち合うことの中に共同の冒険があり、能動的な行為であると語られる。『アナキズム叢書』刊行会/品切れ
基盤的共産主義
「各人は能力に応じて働き、各人は必要に応じて受け取る」。これは現在にまで脈々と受け継がれている、アナキストたちの労働論の基盤です。オリジナルはエティエンヌ・モレリが1755年に『自然の規範』で書いた言葉。
ですが、これが社会主義者やアナキストの中で広まって、マルクスが『ゴータ綱領批判』で定式化しました。当時のマルクスはアナキズム的な側面があったんですね。
その後、エンゲルスと出会って、共産党を主体とする国家の奪取に向かっていくんですが。
マルクスが重視したのは「各人は必要に応じて受け取る」という部分。「各人は能力に応じて働き、各人は能力に応じて受け取る」だと、能力がないと見なされた人は搾取されてしまうから駄目なんです。労働者が自ら報酬をいくらもらうか決める必要がある。
それを実現するためにまず必要なのは、資本家とか中間管理職みたいなヒエラルキーをなくすことです。要するに全員が労働者として働くということ。それは「基盤的共産主義」と言い得る、理想的な労働のあり方なんです。
そんなこと可能なの?と思うでしょうか。しかし、2008年のリーマンショックの時、経営危機に陥ったギリシャのある工場でのこんな実話があります。
資本家たちが逃げ出して、労働者だけが残った。そこで組合の人たちが中心となって労働を続け、自分たちで金勘定をした。すると、内部留保や役員報酬がとんでもなく高くて、それを普通に再配分したら労働者の給料が1.5倍くらいになった。
それで労働者たちのやる気が上がり、この工場はどんどん売り上げを伸ばしました。ここで実現したことこそ、「各人は能力に応じて働き、各人は必要に応じて受け取る」というテーゼなんです。
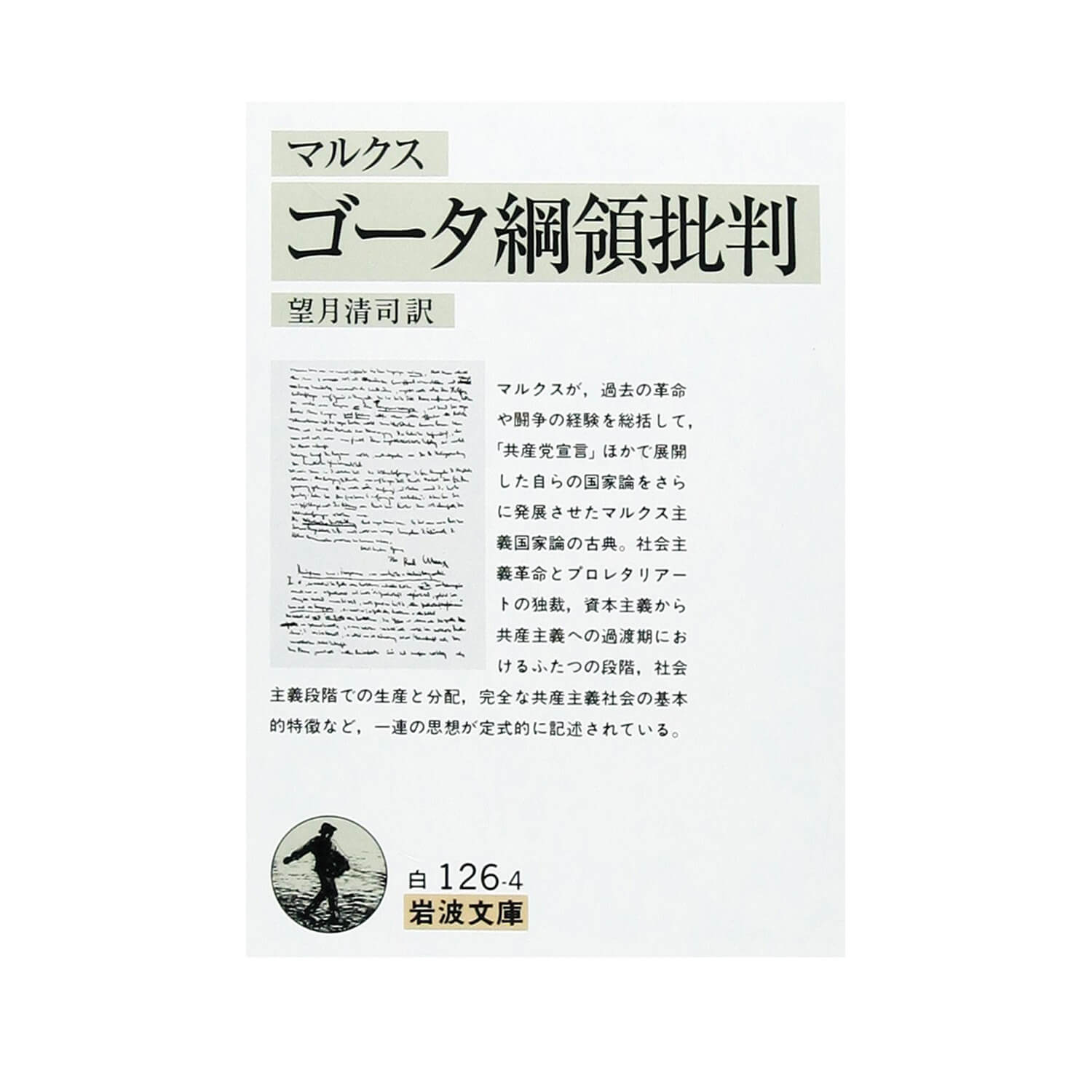
表題作は1875年に書かれた、ドイツ社会主義労働者党の綱領(ゴータ綱領)を批判した文章。かれの革命的戦略が強く示されており、「各人は能力に応じて働き、各人は必要に応じて受け取る」のほか、「プロレタリア独裁」などマルクス思想を理解するうえで重要な概念が数多く登場。岩波文庫/品切れ
ブルシット・ジョブ
デヴィッド・グレーバーによる『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』では、誰もがクソだと感じずにはいられない仕事の事例がたくさん紹介されていて、労働者であれば自分の愚痴を代弁しているかのごとく読めるはずです。
ただ、グレーバーさんは、客観的にこの仕事がクソだとは書きません。あくまでその仕事に従事している人がどう思っているか、つまり主観性というものを重視するんです。
そのうえで、この本を読んで自分のやっていることがブルシット・ジョブだったと気づく人もいるでしょう。そして、「あ、自分の仕事はクソだ」「これからは自分のやりたいことだけをやろう」「いっそ辞めるか」と思って行動を起こす人も多いはずです。
あるいは、組合を組織して資本家たちと交渉するとかね。本書は、そうやって自分の働き方を変えるための端緒になる一冊だと思います。
グレーバーさんは文化人類学者として、いろいろな民族の営みの中にアナキズム的な側面を見出してきた人です。例えば、ある共同体の中では、価値が作られるとそれが絶対視されるけど、次の時代には壊れるということを発見したのもその一つですね。
そこでグレーバーさんは、非常に明るくこう訴えるわけです。
社会には「諸可能性」、要するに、変わる可能性があるから、それを拾い上げて新しい価値を作りましょうと。仕事に関しても同じで、しばらくは変わらないだろうと思いがち。ですが、変化の諸可能性は至るところにあるんです。
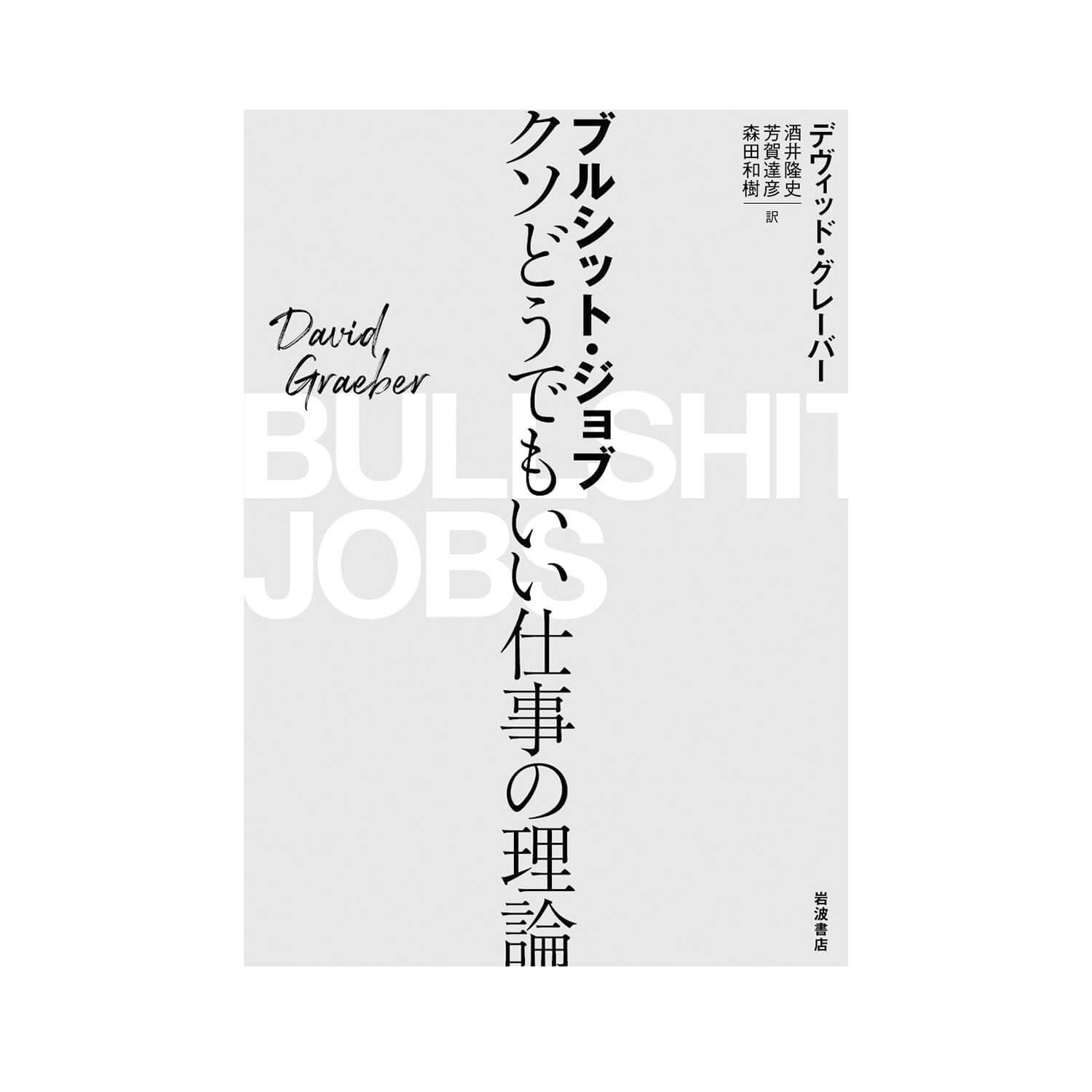
多くの労働が機械に代替されたにもかかわらず、なぜ無駄な仕事が増えるのか。その現象の正体が、資本主義との関係から考察される。またこうした仕事をなくす手段の一つとして、すべての国民に一定の金を支払う、ベーシックインカムという考え方も紹介される。2010年代を代表するアナキズム労働論。岩波書店/3,700円















