ナチュラルワインはカウンターカルチャー?
「大資本の力を持つメジャーがあって、自然派ワインはカウンターカルチャー的な立ち位置だと思うんだよね。そこにすごく惹かれる」(『ウグイス アヒルのビオトーク』マガジンハウス、p.17)。2011年、雑誌『GINZA』で始まった連載をまとめたこの本には、東京・三軒茶屋〈ウグイス〉店主の紺野真によるそんな言葉があります。
初期のロックやヒップホップのように、権威に対してのカウンター、あるいはオルタナティブな運動は、音楽はもちろんファッション、アート、文学など多くのカルチャーの現場で幾度も生まれてきました。
ワインも例外ではなく、既存の体系への反動として生まれた新しいワインがこの20年ほどで台頭しています。この“カウンターカルチャー”がナチュラルワイン・ブーム初期の正体だったのかもしれません。
音楽で言えば、大量生産されるワインは、データがパッケージされたCD。それに対して、ナチュラルワインはライブのようなもの。開けてみなければわからないし、いいときも、今ひとつのときもある。そのライブ感を不安定ゆえにNGと受け取るか、むしろ面白いと取るか。
どちらも良さがあるとして、ライブのない世界は考えられません(そして元来、すべての音楽はライブでした)。目から入る情報としてボトルデザインも、奇抜なラベルやネーミングが多く、いかに既存の枠を壊すかを競い合っているかのようです。このあたりもロックのアルバムジャケットやTシャツ、ヒップホップのグラフィティなどにも似た話です。

自然派ワイン、ビオワイン、ヴァンナチュール……その通称も、どんどん変わってきました。始まりはフランスでも、やがて英語圏への普及が進んだ結果か、現在は「ナチュラルワイン」という用語がスタンダード化してきたため、今回の特集ではこの言葉を使います。
しかし、そもそも「何をもって“自然”なワインか?」という点では、欧州の一部でようやく法律的な定義が始まったものの、世界基準があるとはいえません。
ごく大まかに言えば「有機(かそれに近い)栽培でブドウを育てて、酸化防止剤(=亜硫酸塩、SO2とも)をはじめとする、化学的な添加物や介入をできる限り減らして醸造し、瓶詰めしたワイン」がそう呼ばれるものの、内実や細かい基準はさまざま、プロ10人に聞いても10通りの答えが返ってきかねない、という現状です。
むしろ「ナチュラルか否か」をどこかの権威が決めて線引きすべきではない、という人も多くいます。ただし「オーガニック」がそうであるように、「ナチュラル」もマーケティング的に使われやすいワードであることには注意が必要でしょう。
“酸化防止剤無添加”と謳われていても、原料のブドウはどこでどう作られたか。また「無添加」の代わりに酵母を殺菌する熱処理をしたり、ミクロフィルターで濾過処理したワインをナチュラルと呼ぶプロは、ほぼいません。
この20年の現場と、ブームを担ってきた人
ナチュラルワインは生産者、インポーター、酒販店、飲食店まで、いずれも個人の顔が見える規模感であることが共通します。そのカウンター的な気配と存在感にも惹かれてか、飲み手もどんどんファンを増やしています。
かしこまった店で仰々しく高級ワインを飲むより、顔の見えるカジュアルな店で面白いナチュラルを飲む方が、今は楽しいし気分がいいよね、という新しい価値観が生まれたのが、この20年の大きな変化でしょう。
かつて90年代末に起きたワインブームではボルドーやシャンパーニュが主役で、高級ホテルやフレンチのソムリエが華々しく登場し、シーンを先導してきました。今、街場のカジュアルな飲食店にフィールドは移っています。日本経済の“失われた30年”は飲食店業界も例外ではありません。
個人経営では都心の一等地が難しくなり、賃料が安い裏通りや穴場のエリアに、小さい物件を借りたバルや酒場が次々とオープンしてきました。クラシックで高単価なワインに比べて、バラエティ豊かなアイテムを安く仕入れられ、熟成スペースを要さず、リスト化もせずすぐ客に出せるといった特徴も“小さくて強い”個人店がこうしたワインを扱う流れを後押ししました。

この10年余り、そんな“ストリート”で個人店を始めたオーナーたちと、そこに集った飲み手たちの中心を担ったのが、まさにロスジェネ世代です。スタッフのユニフォームも、スーツやソムリエの正装から、カジュアルなシャツやデニムへと変わりました。
より若い80年代、90年代生まれの世代にとっても、気軽に楽しめるこうしたワインが魅力的に映り、飲酒デビューの最初からファンになったという飲み手も多いようです。
また、飲み手が軸になるイベントも増えています。生産者やインポーターに飲食店まで、顔が見える人々が一堂に会するイベント『フェスティヴァン』は2010年に東京で第1回が開かれて以来、全国に拡散し、シーンに大きな影響を与えてきました。参加者は皆が飲み手となって楽しみつつ、こうしたワインの魅力を広める役割も果たします。
2009年に鎌倉の小さな店から始まり、やはり地方都市にさざなみのように広がった『満月ワインバー』のように、さまざまな小規模イベントも続きました。いずれも、大きなメーカーが仕掛けるプロモーションイベントとはまったく違い、個人レベルで企画、実行される点が共通します。
情報が伝わるのはSNSで、そこには南フランスの生産者から、東京のバーで飲む人まで同じタイムラインに並び、シェアされていきます。ナチュラルワインはマニアのものから、誰でもより気軽に楽しめるようになったのです。
今起きていることと、ワインのこれから
ブームが次に迎えるのは、差別化の時代です。ナチュラルワインも「あれば嬉しい」から「あって当たり前」になりました。インポーターから仕入れた酒を、口上もそのままに卸すだけでは、酒販店の存在感も薄れます。その酒販店から同じ酒を仕入れて自らの言葉で語らず、受け売りで客に注いでいるだけのバーも、やがて個性を失うことでしょう。
仕入れた酒に、いかに自分たちならではの付加価値を付けて売るか。これはいつの世も課題ですが、そこにこそ個々の店主の創造性も発揮される、飲食店というものの楽しさがあります。
単純に同じ酒ならEC全盛の今、安く簡単に買えてすぐ家に届くボトルを飲めばいい。でも、実際に飲み手は「何か」を求めて、飲食店へ行きます。店側は応える「何か」をどう提供できるか。それによって、未来は決まるのかもしれません。
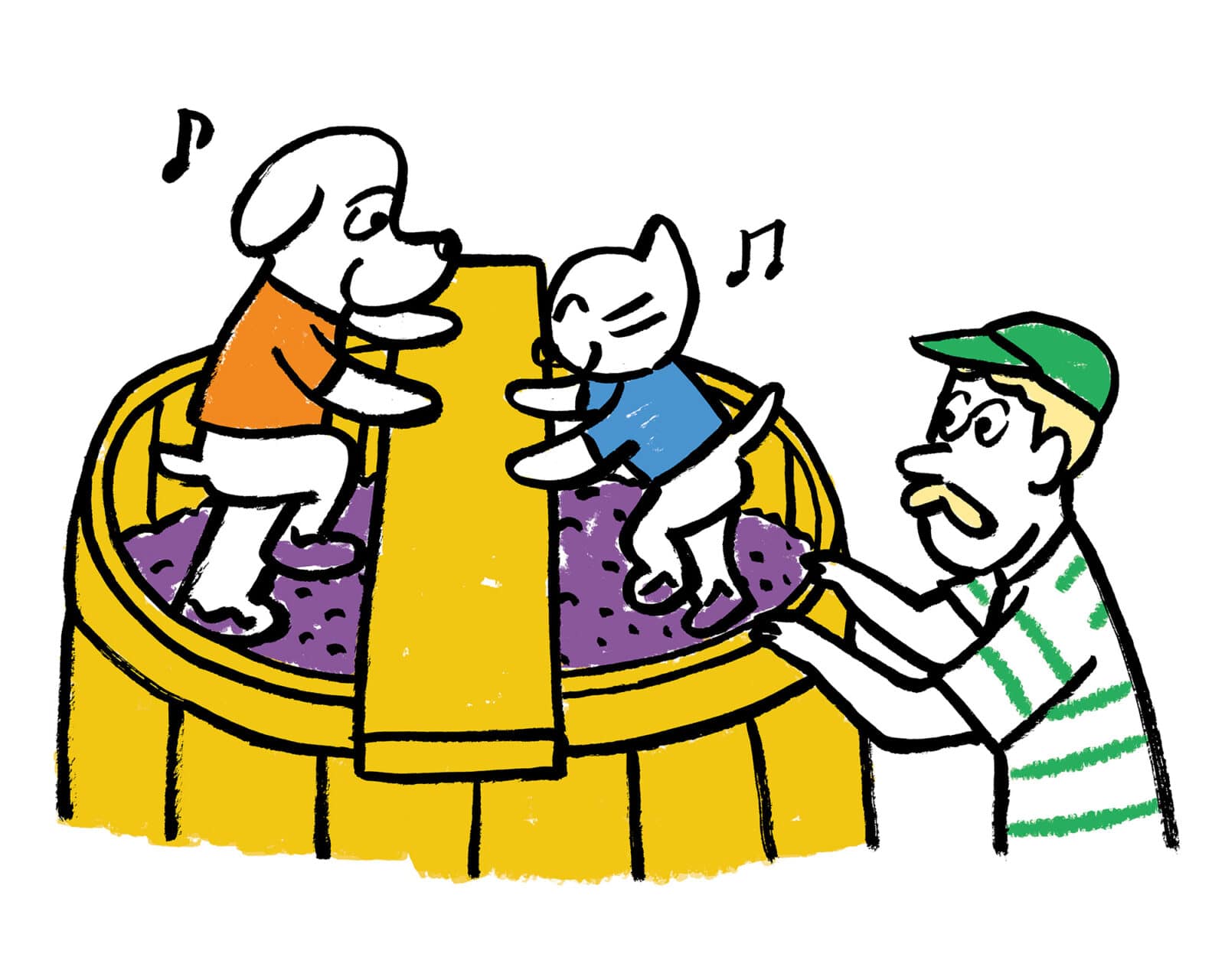
カウンターカルチャーが成功して主流になると、自らが対抗していたはずの“権威”になってしまう──これも繰り返されてきたことで、ナチュラルワインも例外ではありません。ファンに崇められてプレミア化し、造り手も意図しない異常な高額で転売される例も相次いでいます。
一方、星付き高級レストランがこうしたワインをずらりとオンリストする例も増えてきました。カウンターとして生まれたロックやヒップホップが、いつしか成功と富の象徴になったのと似たようなことが、ここでも起き始めています。
これからの世代は、いわばナチュラル・ネイティブ。ガラケー?なにそれという彼ら彼女らにとって、スマホもナチュラルも別に何ら特別ではなく、最初から普通にあるアイテムです。
一方で、クラシックなワインが縁遠くなり、まったく経験していない層も増えています。「権威vs.カウンター」という単なる分断だけでなく、その双方の橋渡しができる存在も、これからのワイン体験を考えるカギになるでしょう。
ワインはもう、考える前に、まず感じよう
この20年は、ライフスタイル全般において、一つ一つのプロダクトの背景を知り、選ぼうとする変化も起きています。“ストーリーがある”“作り手の顔が見える”“エシカル”“サステイナブル”といった言葉が選択のキーワードになり、食の世界でもそうした動きは顕著。
ことにスペシャルティコーヒー、クラフトビール、ナチュラルワイン、という3つは相性が良く、これらを扱う店がいくつかできれば、そこはメディアによって「注目のエリア」になり、タグ付けされるストリートになっていく。まさに街の活性化を測る物差しでもあります。
ブドウ栽培という農業ありきのワインも、今の流れの中にいます。有機栽培を貫くことは、環境への負荷を減らせる一方、病虫害によって収穫量が激減し、その一年の収入を大きく失うリスクもあります。それも覚悟して土地に根ざした造り手の、意思やセンス、ボトルに込められたストーリーが感じられるからこそ、一杯のワインが強い意味を持って体内に入り、味覚以上の記憶として心に残る。
大量生産で規格化されたワインにはない、その「意味」が、非常に説得力を持って飲み手に迫るからこそ、この時代にナチュラルワインはより広く支持されてきたのでしょう。ポイントは、これが一部の現象ではなく、当初の発信源だったパリはもとよりロンドン、NY、東京と、まさに世界中に広まっているムーブメントである、ということ。
かつてのカウンターカルチャーが、名実ともにポップカルチャーとなりつつある今、飲むべきワインとその選び方、楽しみ方はどう変わっているのか。“その先のワイン”に出会う、良いターニングポイントに来ているのかもしれません。

こうした時代になれば、多くの現場でもうワインリストは要りません。信頼できるプロと対話して、一杯が注がれたら、もうグラスはグルグル回さず、飲んで、感じればいい。そうしているうち、ムリに細かいワイン名などを勉強などせずとも、ああこれが誰々か──きっとそんなふうに造り手の名前を一人、最初に覚えるでしょう。ワインの今は、そこから始まります。















