chapter3 「個」こそすべて。モダンな革命戦士たち
ビ・バップを契機に、ジャズはアメリカ固有の文化を代表する音楽ではなく、世界の音楽になりました。これが「モダンジャズ」の始まりです。モダンジャズとは、1960年代後半まで続くジャズの総称です。ビ・バップに加え、メロディアスなハードバップ、より自由なアドリブを可能にしたモードジャズ、クールジャズ、ソウルジャズ、ファンキージャズなどが含まれます。
まず、チャーリー・パーカーの偉大な発明を受け、さまざまなミュージシャンが新しいジャズを繰り広げたのが、1955~58年頃のこと。トランペットのマイルス・デイヴィス、サックスのソニー・ロリンズ、ベーシストのチャールス・ミンガス、サックスのジョン・コルトレーン……彼らビ・バップ第2世代は、演奏スタイルも志向もバラバラでした。題材はもはや何でもよく、重要なのは、自分の個性をどう表現するか。各人がそれぞれのやり方で演奏し、全体でモダンジャズのムーブメントを形成します。
ビ・バップは「アドリブという創造の現在性だけで音楽が成り立っちゃうんだぜ」という可能性を示しましたが、その魅力を引き受けながら、多彩な方向に自身の音楽を発展させていったのがマイルスです。音と音との関係性をクールに切り詰めた彼の演奏は、「クールジャズ」と呼ばれるスタイルの代表となりました。ジュリアード音楽院で学んだこともあり、知識も豊富。スタイルを次々と変えながら創造を続けます。
例えば、1964年にNYのフィルハーモニック・ホールで行われたライブでは、極めて白人的なバラード「My Funny Valentine」と、極めてエモーショナルなブルースを、同じステージで演奏した。この2つはアメリカ大衆音楽の両極ですが、彼はこれら両方を、モダンかつクールに、極めて抽象化された音でもって演奏することができました。
ここでのポイントは、抽象度の高さゆえ、世界中の人に届くものになったということですね。ブルースという民族音楽──つまりアメリカの風土だとか歴史だとかへの理解を前提にした音楽を、自分なりの解釈で個人のものにすることで、普遍性を持つ音楽として提示した。この「個人の音楽にした」ことが重要です。
一方、絵画史に目を向けると、印象派という大ムーブメントから、さまざまなスタイルが派生しました。後期印象派のゴッホやゴーギャン、キュビスムのピカソ、フォービスムを経て抽象的で構築的な表現に向かったマティス……。多様な個性が時代を創る現象は、モダンジャズと重なります。
中でも世界を大きく変えた点で、マイルスと対比したいのはピカソですね。常識だった遠近法を無視し、「自分に見えたように、自分が描きたいように」表現したキュビスムは、絵画史における大革命。表現のスタイルを次々に変えながら、常に新しいものを生み出した点も、2人はよく似ています。
さて、再び話をジャズに戻しましょう。ビ・バップ第2世代のうち、ソロだけで成立させる音楽に突入していくのがコルトレーンです。
ミュージカル『Sound of Music』の中に、リチャード・ロジャースが作った「My Favorite Things」という2分半足らずの曲があるのですが、コルトレーンは、あのヨーロッパの民謡みたいなかわいらしい曲を素材として、1時間以上即興で吹き続けるところまで行っちゃうんです。
わずかなモチーフを基に、ソロの構築力だけでどこまでいけるかという次元に向かっていく。楽曲の再現ではなく、歌的なサウンドからも完全に離れ、もはや原曲が何なのか全く聴き取れないような状態になっていく。極端な表現主義と言ってもいいでしょう。
やれる可能性を全部やってみないと気が済まず、「どうやってやめるのか、タイミングがわからない」と悩んでいたコルトレーンに、マイルスは「マウスピースを口から離せば?」と言ったとか言わなかったとか。たくさんのジャズ・ジャイアントを生んだ「モダン」の時代も、そろそろ終盤に向かいます。

ビ・バップ第2世代の中でも特にモダン度が高かったジョン・コルトレーン。そのテナーサックスはマイルス・デイヴィスにも高く評価されていた。やがて抽象表現の限界に挑むがごとく、ソロの即興のみで成立させる演奏を追求。鮮やかなフォービスム時代を経て、より単純化&デフォルメされた形と色で抽象美術の先駆けとなったマティスを思わせる?
chapter4 フリージャズとポロックの即興最前線
短期間で急激に進化した──それもモダンジャズの大きな特徴です。わずか10年ほどの間に大勢のミュージシャンが登場しましたが、そこには絵画史上の50年と同じくらいのエコールの変化が見られたのです。20世紀生まれの芸術特有のスピードでもって進化したジャズは、やがて同時代の絵画の運動に追いつきます。ゆえに1960年代に入る頃には、同じ肌触りを持つジャズと絵画が登場することになるのです。
たった一つの旋律を基に即興で1時間のソロを吹き続けたというコルトレーンの例は極端ですが、個人の表現が「曲」とは切り離された状態で突き進んでいったのが1960年代です。曲とはメロディとリズムとハーモニーで構成されるもの。ところが極限まで行った「モダン」がどうなるかといえば、元の曲の要素を完全に破壊する、あるいは、その要素を極端に切り縮めて、自身の楽器の音だけを頼りに演奏する。絵画でいうと「描くための題材はいらない。キャンバスと絵具と自分だけあればいい」みたいな状態になっていくのです。
例えばサックス奏者のオーネット・コールマン。彼には、自身を含む8人のミュージシャンによる「FREE JAZZ」というエポックメイキングな曲が存在します。「せーの!」で8人全員がバラバラなことを即興で始める、しかも1曲だけで37分間。
あまりに自由奔放すぎて何がなにやら……な状態なのですが、これは演奏のための枠組みを作らないことによって、その場でのプレーヤーの自由度が極端に高まった結果のサウンドだったのでした。この時から「フリージャズ」と総称される、これまでの既成概念をぶっ飛ばした革新的なジャンルの運動が始まって、ジャズ界に一大センセーションを巻き起こします。
ちなみに演奏したのは、四重奏のバンドを2組合わせた8人編成の、“ダブルカルテット”。ステレオの左右のチャンネルから別々のカルテットの演奏が聞こえるという、斬新なやり方で録音されました。
注目したいのは、この曲を収めた1961年のアルバム『FREE JAZZ』のジャケットに、アメリカの抽象表現主義を代表する画家ジャクソン・ポロックの、「白い光」(1954年)という作品が使われていること。

「音楽はスタイルではなく表現」と語ったオーネット・コールマンは、集団即興演奏による自由すぎるアルバム『FREE JAZZ』で、フリージャズの先駆者となった。ブルーのスーツがお気に入りでモダンアート好き。レコードジャケットに使ったのは抽象表現主義の巨匠ジャクソン・ポロックのアクションペインティング……と、とてもおしゃれだった。
ポロックといえばアクションペインティング。顔料や絵具を紙やキャンバスに垂らしたり、勢いよく叩きつけて飛び散らせたりする技法です。キャンバスの上に表れるのは、絵を描くポロックの身ぶりそのもの。アクションというドキュメントの軌跡をそのまま提示するような作品は、創造の現在性というものが、行き着くところまで行った最終形とも言えるでしょう。
とはいえ、めちゃくちゃに絵具を飛び散らせているように見えるポロックのアクションペインティングも、実は絵具が垂れる位置や量を意識的にコントロールしているのだとか。同様にコールマンの「FREE JAZZ」も、自由奔放な半面、譜面に起こしてみると各人が各人なりの理屈でもって演奏していることが理解できるのです。
実際コールマンは、『FREE JAZZ』の前年にリリースしたアルバム『世紀の転換』のライナーノーツで、「自分の音楽はポロックのようなものなのだ」と綴っています。
そして1970年代。絵画史においてもジャズにおいても、モダンの時代は終わりを迎えます。
抽象化とは本質に還元しようという運動なので、それが十分に達せられた段階で停止せざるを得ません。ここでジャズもいったん歴史の更新を止め、「ポストモダン」と呼ばれるような時代に入っていくのです。
chapter5 そしてジャズはポップスになった
1970年代。「モダン」の時代を終えたジャズは、世界各国へと拡散され、それぞれの国で新たな音楽として発展します。モダンまでのジャズは、アメリカのブラックミュージックとしての運動、つまり民族文化運動でもあったのですが、ここから先は各国独自のアート運動になっていく。
イギリスで、フランスで、西ドイツで、もう一度「ジャズという音楽の発見」が行われ始めるのです。日本では、それはもっぱらフリージャズを経由した形で行われました。コールマンらによって作られた即興のスタイルは、ジャズピアニストの山下洋輔らによって日本独特のフリージャズに発展します。ジャズの多民族化、多文化化と言ってもいいでしょう。
この時代から先のジャズを「ポストモダン」という括りの中に入れてしまってもいいのでは、と僕は思います。絵画史でいうと、例えば抽象表現主義へのアンチテーゼとして、アンディ・ウォーホルに代表されるポップアートが登場しますね。彼らは「画題」を以前とは異なった形で回復させました。
同じようにアメリカのジャズも「題材」を取り戻す。「曲」から離れてハードコアにやってきた人たちが、ファンクやブルースやポップスなど、自分たちがこれまでに発見してきた題材に再び立ち返ります。
1960年代にマイルス・デイヴィスのグループへ参加していたジャズピアニストのハービー・ハンコックは、電子的なサウンドやファンクを取り入れます。グルーヴィで踊れるジェームス・ブラウンのような音楽をジャズと融合させた名盤『Head Hunters』(1973年)は、ジャズファンクという新たなジャンルを開拓。ジャズ好き以外にもファンを広げました。

ハービー・ハンコックはモダンジャズ時代のピアノをショルダーキーボードに持ち替えて、ジャズにエレクトリック・サウンドを導入。フュージョンという新ジャンルに挑んだり、グルーヴィなジャズファンクを確立したりと大活躍。1973年のアルバム『Head Hunters』はジャズ好き以外のファンも獲得。80年代にはヒップホップやDJも取り入れた。
70年代後半に出てきた新たなスターは、ジャズギタリストのパット・メセニー。芸術運動としてのジャズをすべて咀嚼したうえで、誰とも違う音楽を作っています。南部っぽいテイストの曲も即興もノイズもあり。クロスオーバーといわれるそのスタイルは、モダンの拘束から解放された新しいジャズにも思えます。
そして現在。21世紀のジャズは芸術運動ではなく、学校で教える/習うことができるものになったと僕は感じています。ある意味で古典になった。ジャズの理論や技術を習った人が表現をしようとする時、彼らの武器は何なのか。それは即興みたいなものではなく、いろんな時代のいろんなジャンルを取り込んで、自由にリデザインできること。ジャズが今いるのはデザインの領域です。
現在は、ロバート・グラスパーのような若い世代が、20世紀に蓄積されたジャズの技術や考え方と、R&Bやヒップホップといった自分たちの文化を融合させて新しいジャズを生み出している。21世紀のジャズはだから、ポップスなんですね。
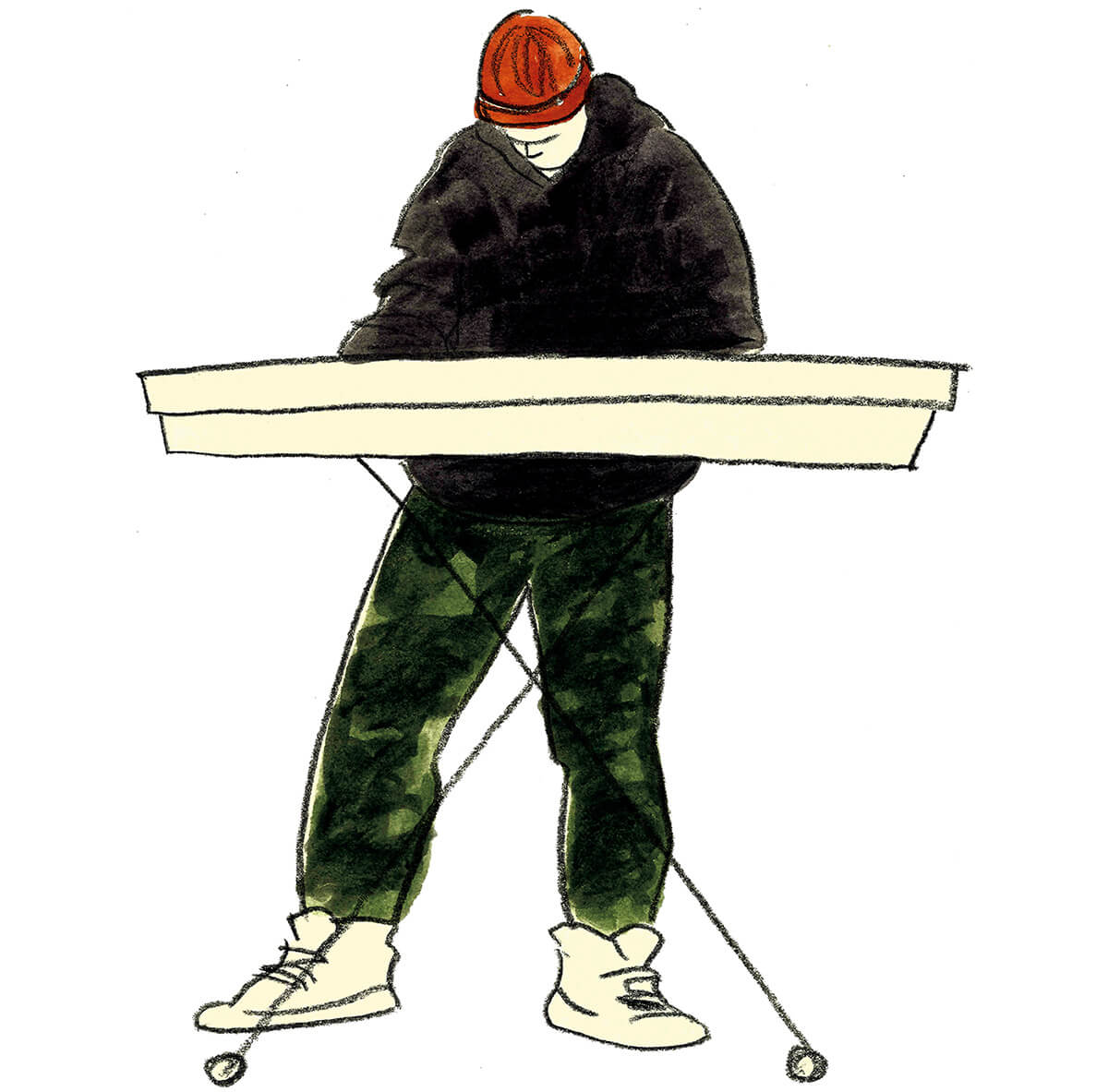
ジャズを学校で教えるようになった現在は、どの時代のどのジャンルからでもジャズを引っ張ってきて、自分なりにリデザインできる時代。ヒップホップやネオソウルなど、時代を象徴するポップミュージックにジャズを融合させるアーティストも多数。ジャズが芸術運動だった時代から、ジャズによってポップスが革新される時代へと進化したのが現在だ。















