脳と体をほぐす、“周波数マッサージ”。
モーリッツ・フォン・オズワルド・トリオの『ヴァーティカル・アセント』(2009年)が発表された時、DJのリカルド・ヴィラロボスがこの作品を“周波数によるマッサージ(原文はFrequency Massages)”と評したんです。脳と心に施術してくれる音楽。
医学にも正式にそういう療法があるみたいですが、一種の音楽ジャンルとして捉えているのが、すごくおもろいと思ったんです。細かく聴けば、複雑なリズムを多用しているんだけど、すごく心地よく響く。打楽器が交差する時に生まれる“揺らぎ”には、マッサージのような効果があるんじゃないかと思う。そんな基準でアルバムを少しずつ集め、その中から10枚選びました。
僕は飛行機などでの移動中、身動きの取れないシチュエーションで徹底的に向き合って聴いています。一般的なマッサージと同様、気持ちが良くて寝落ちしてしまっていることも(笑)。
周波数によるマッサージが、効いているってことでしょうね。

新しいガムランで、最近一番聴いています。インドネシアのグループなのですが、どこかUKのベース・ミュージックのようなエッセンスも加味されていて、面白いですよね。連鎖的な刺激が脳に効いてくるような感じ。効能的には、足つぼマッサージに近い気がします。
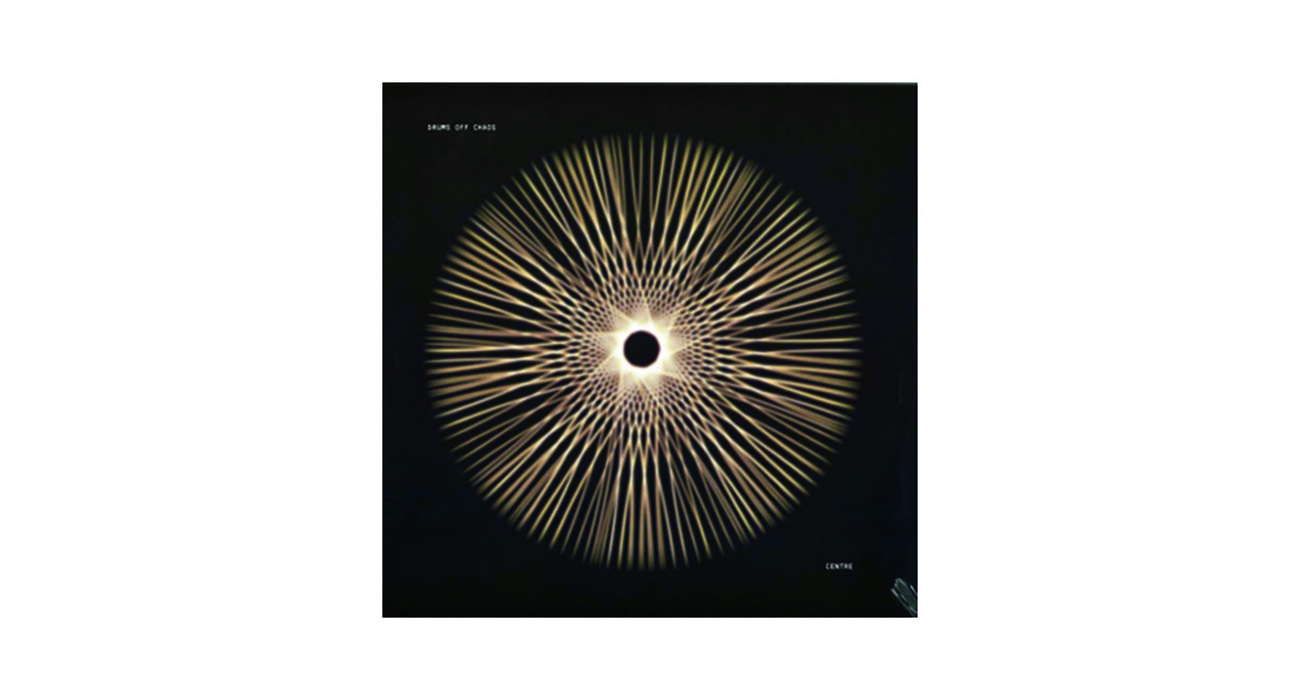
CANのドラマー、ヤキ・リーベツァイトが生前録音した音源を編集したアルバム。ヤキは「ドラマーは粛々と同じリズムを叩くものだ」と発言しており、構成やサウンドデザインが完璧。打楽器奏者の美学が詰まっています。聴いていると、高揚してきますね。
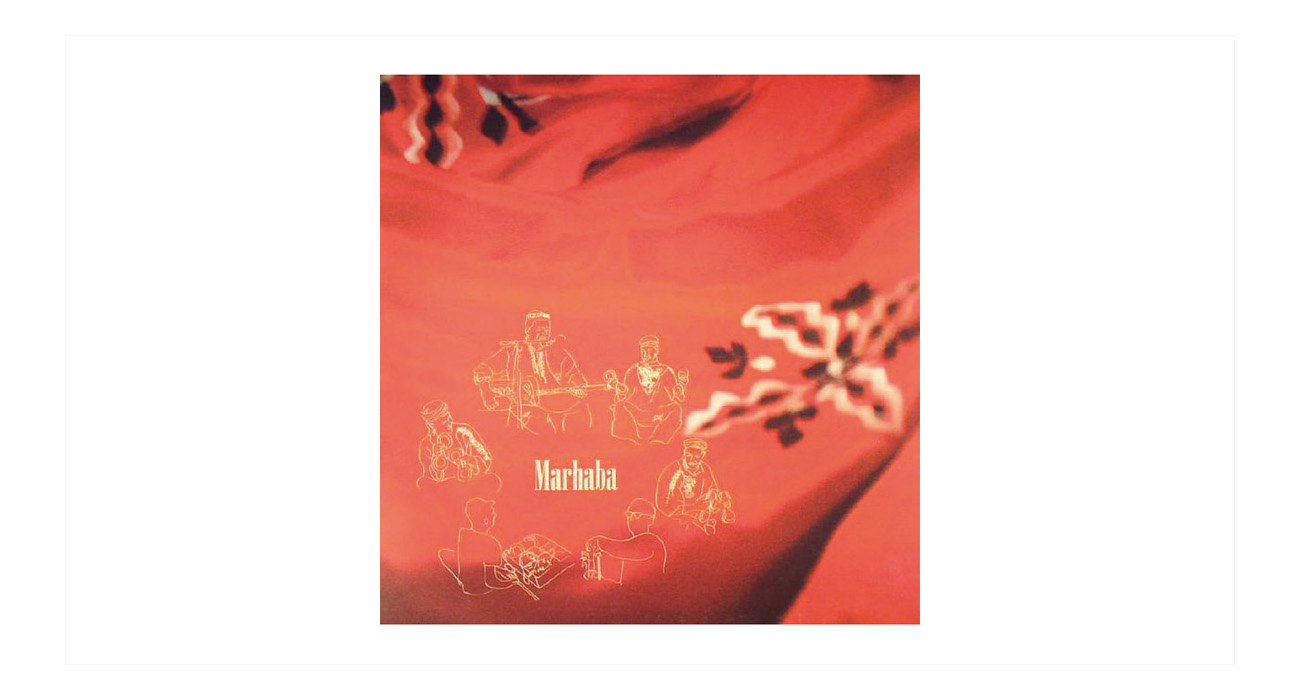
フローティング・ポインツ(以下FP)とジェイムス・ホールデンが、モロッコの民族音楽であるマリーム・マフムド・ガニアと共演。マリームのギンブリという楽器とチャントに、FPは(シンセの)ハンドクラップで対応。

ドイツの音響的なジャズ。これはモーリッツの作品に近い、シンプルだけど複雑なリズムの組み合わさった揺らぎを感じます。エレクトリックピアノやビブラフォンのメロディが乗り、すごく洗練されていますね。ヤン・イェリネックなど、音響ジャズのルーツといわれています。

ケルンの名門〈Kompakt〉の首領、ウォルフガング・ヴォイトが90年代に打ち出した、ポップアンビエントという定義が好きなんです。いわゆるアンビエントとは異なり、イントロのような高揚感をキープするポップアンビエントなんじゃないかと思うんです。ジャケットもいい。
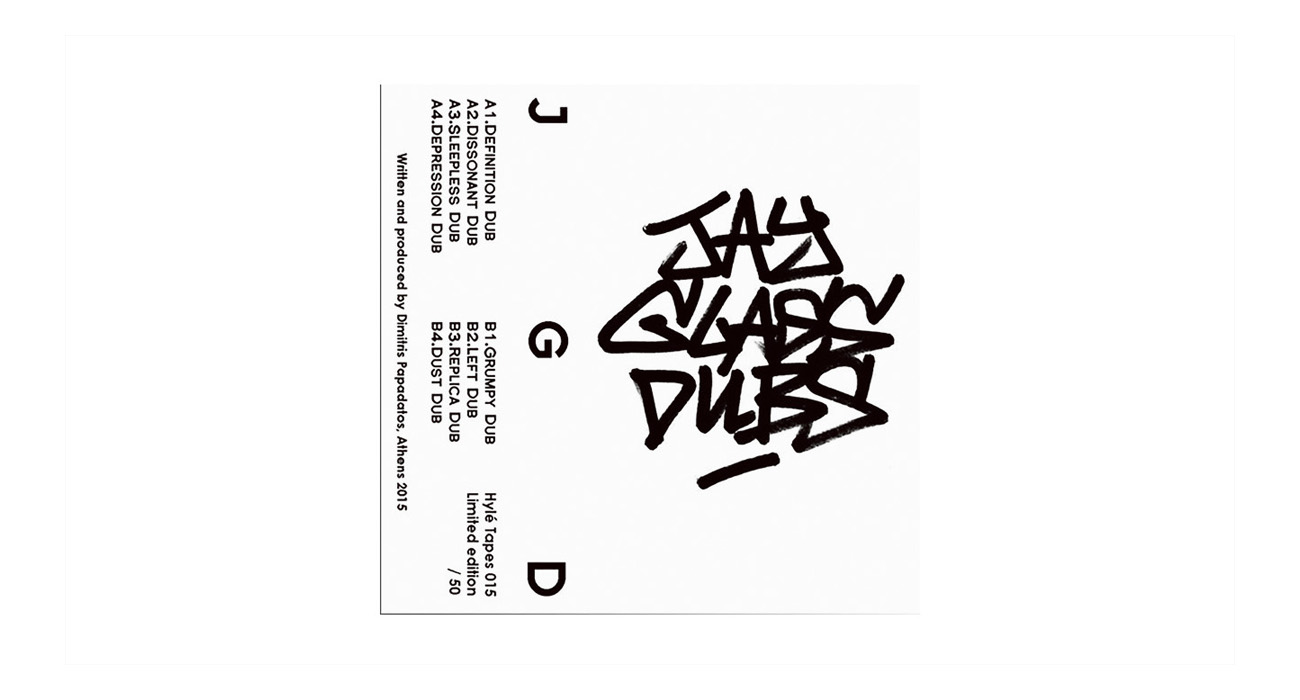
音響的なダブを、よりシェイプアップさせたようなアルバム。シンセの音色に、ディレイなどのエフェクターを、レイヤー的に組み合わせていて、よくできています。リズムレスだけど、人を踊らせるダンスフロア向けな魅力もあるし、どこか官能的なんですよね。
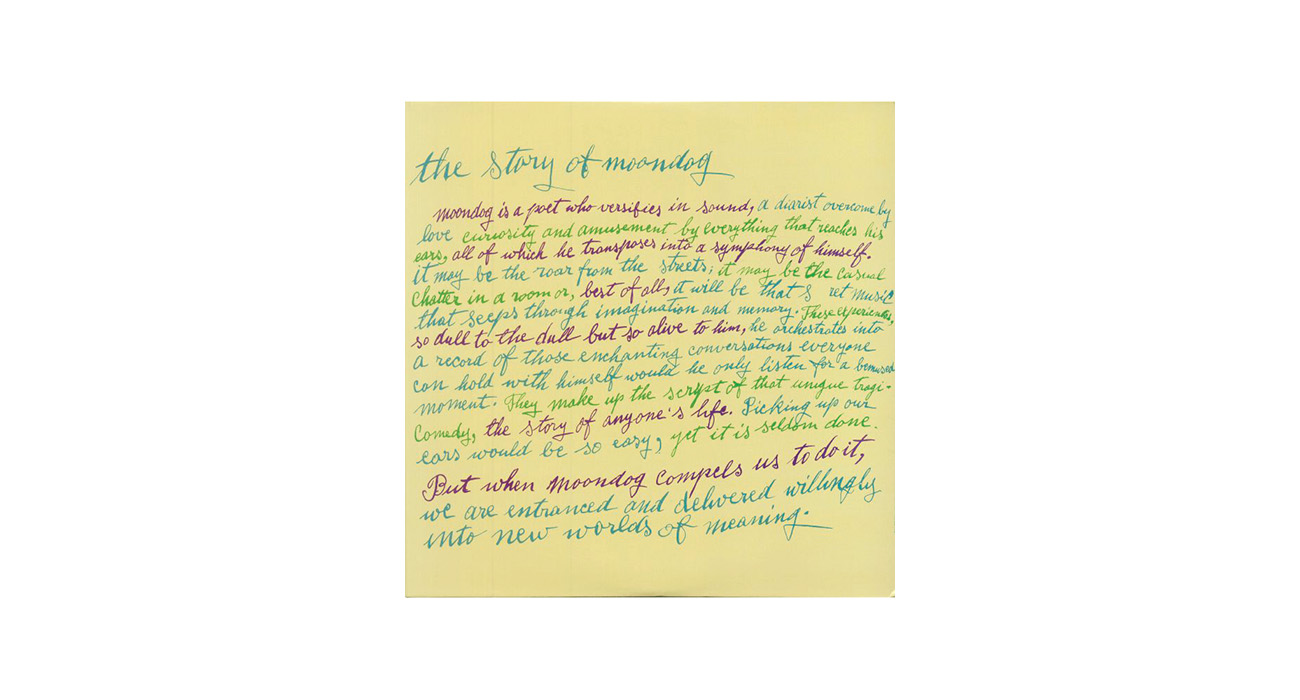
1950年代〈Prestige〉など、ジャズのレーベルから作品を発表している全盲の音楽家。打楽器の演奏家からすると、彼のリズムは発明に近いような拍子らしい。この作品はポコポコした心地よいリズムに、NYの街の音をコラージュ。打楽器と環境音の揺らぎによるアンビエント。
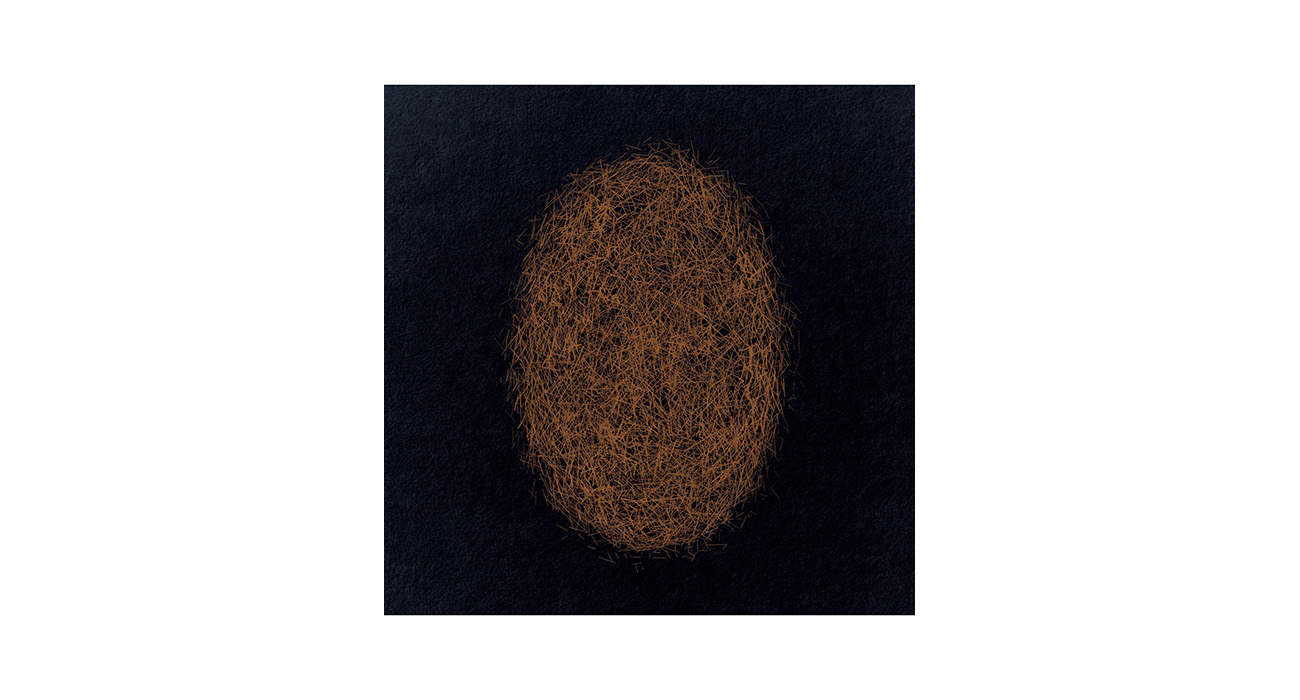
O.P.N.やローレル・ヘイローの作品に参加しているドラマー。このソロ作品も、すごくカッティングエッジかつ、コンテンポラリーです。現代音楽とは違い、実験的で間口が狭いわけではなく、誰にでも門戸が開かれていて、聴きやすいのが魅力的ですね。
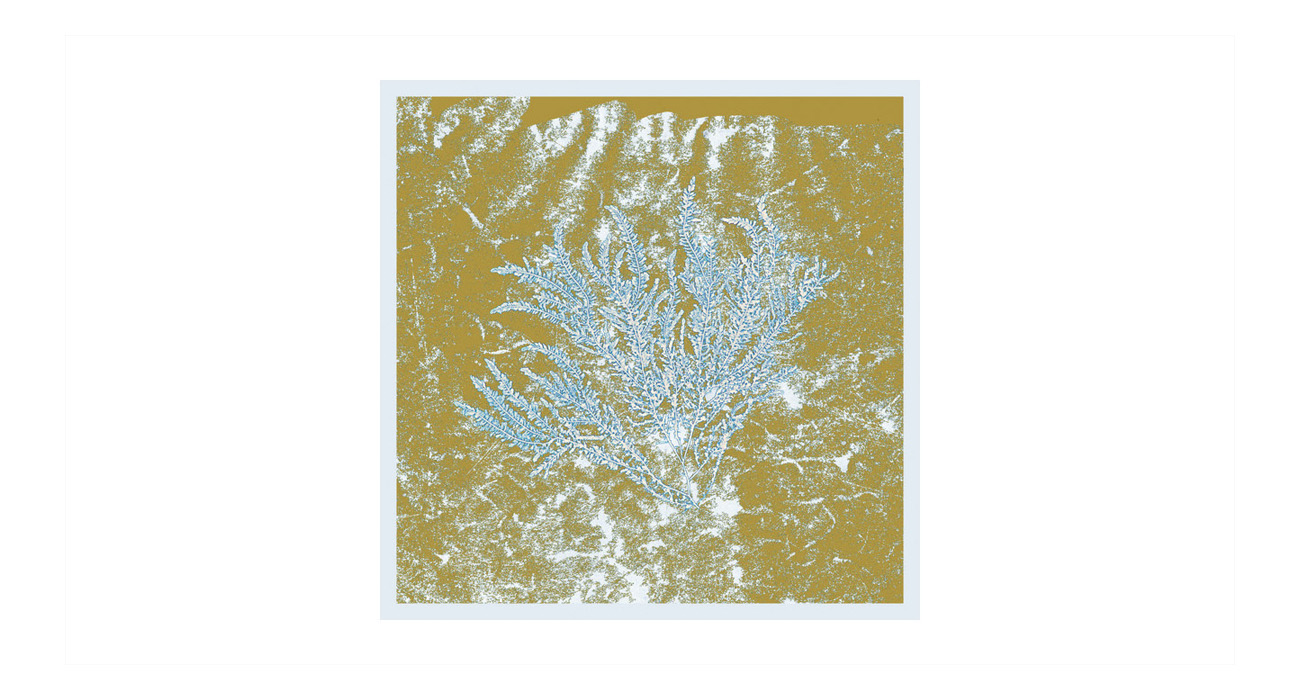
シンセサイザーなど、電子音の波。単純に美しい作品。ビートはほとんど入っていないんだけど、寄せては返すような電子音の波でリズムを形成していて。とにかく心をクリアにしてくれるような効果があります。

モーリッツの名シリーズ「Basic Channel」はダンスミュージックでした。しかし、トリオ編成になってからは、パーカッションなどを取り入れた有機的なアプローチに。一聴すると簡素ですが、実は複雑なリズムで形成されています。トニー・アレンも加わった近年の編成も大好きです。






































