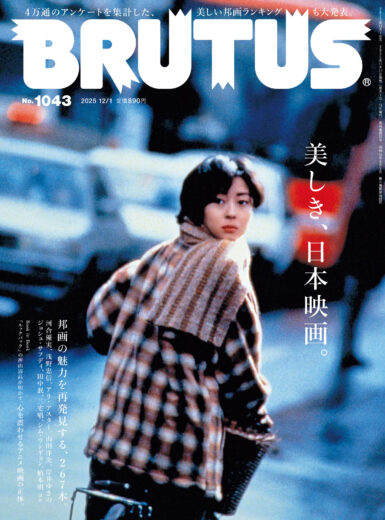文・鍵和田啓介
京都を拠点に活動していた映像作家であり、デザイン集団〈groovisions〉の“デザインしない”メンバーだったミルクマン斉藤が、商業雑誌で映画評論家デビューを飾ったのは、1994年のこと。元バイト仲間であり、京阪神エルマガジン社の雑誌の編集部員だった田中知之(Fantastic Plastic Machine)の仲介がきっかけだ。
彼が属していたのは、当時活況を呈していた渋谷系を、関西において体現する界隈だったという。確かに、本書におけるタランティーノの登場とその余波に興奮し、悪趣味なモンド映画をも面白がる姿勢には、渋谷系的なものが感じられる。
そんな“中の人”ならではの考察も示唆に富み、例えば加藤綾佳監督の『おんなのこきらい』についての「90年代の『渋谷系』以降に意味付けられた“可愛い”という言葉に潜在する客観性や虚構性、あるいは邪悪さや居心地の悪さをおそらく初めて分析的に描いてみせた」という記述には、ハッとさせられた。
しかし、彼の評論家としてのアイデンティティは、やはり「関西人」という点にあったようだ。2010年以降の原稿の近況欄から伝わってくるのは、関西における映画イベントに積極的に登壇していたこと。
もちろん、掲載媒体が関西の情報雑誌だったこともあるだろうが、06年に「なぁんもオモンナイ」と綴られた「関西の映画状況」を変えるべく、孤軍奮闘しているようにも思える。また、そのアイデンティティは、時に評論をも活気づける。
とりわけ、山戸結希監督の『溺れるナイフ』について、「ただ関西人として言っときたいのは、今まで映画化されたどの中上健次作品よりも濃密濃厚に中上健次を感じさせるってことかな」という評言は、流石としか言いようがない。
その意味で、映画評の集成として楽しめるのは言うに及ばず、ある時代の映画と関西をめぐる記録としても興味深い一冊だ。

『1994-2024 ミルクマン斉藤レトロスペクティブ 京阪神エルマガジン社の映画評論集』
映画評のほか、白石和彌をはじめ監督や役者へのインタビュー、生前の著者と親しかった執筆陣のエッセイも収録。付録として言及される膨大な映画をまとめた索引を封入。京阪神エルマガジン社/3,200円。