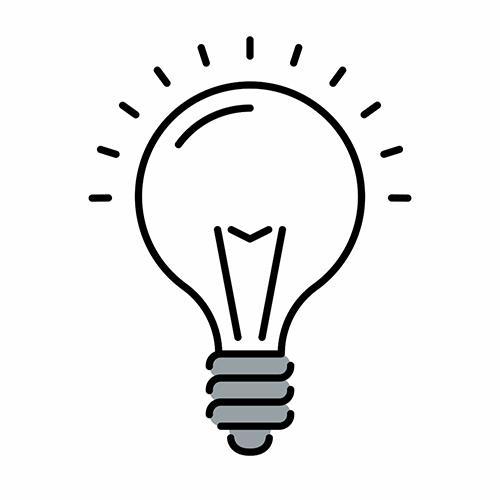教えてくれた人:栗野宏文(ユナイテッドアローズ上級顧問 クリエイティブディレクション担当)
英国の伝統的な価値観と移民のミックスカルチャー
今、ファッションカルチャー界で注目したいのは、イギリスのパブリックスクールカルチャーとカリビアンカルチャー。ブリティッシュスタイル自体はこの何年かずっと続いていますし、カリビアンカルチャーは、来年の春夏以降のヒントになってくると思います。
その視点で言うと、イーヴリン・ウォー原作のイギリス映画『情愛と友情』がおすすめ。第二次世界大戦前後の英国貴族の暮らしがベースになっていて、とにかく衣装が素晴らしい。主人公は中流階級ですが、彼の友人となる男性がベン・ウィショー演ずる領主の息子で、上流階級だけれどボヘミアンなスタイルという異端な存在。
映画の中では英国ならではの伝統的なアッパークラスの学生スタイルを観ることができます。基本は制服、制服ではない時はフェアアイルのセーターや(大学対抗のボートレースで多く着用されたブレザー柄に由来する)レガッタストライプやレガッタジャケット、スクールマフラーを身に着けていて、品の良いおしゃれなんです。
2022年度のLVMH ヤングファッションデザイナープライズのグランプリに選出されたエス・エス・ダーリーは、その英国的なパブリックスクールカルチャーとデイヴィッド・ホックニーをテーマにしていました。彼のインスピレーションソースである英国のトラディショナルなセンスとゲイカルチャーはこれからのファッション潮流に影響してくると思います。

一方で、同じイギリスで今注目されているのが、カリビアンカルチャー。去年から今年の春にかけて、ロンドンのテート・モダンで開催された『Life between Islands』展。イギリスとジャマイカをはじめとするカリブ諸島の文化がいかに影響を与え合ったか、そこからいかにユニークなアートや音楽が生まれてきたかを解き明かす展示で大きな反響を呼びました。
英国の植民地だったことで、移民が行き交い、文化が混じり合う面白さ、そこには独特なカルチャーがあって、植民地としての鬱屈とした感情みたいなものが、逆にクリエイションの中に出てきていると感じます。英国の伝統的なスタイルを含めて、70年代、80年代のレゲエが誕生した頃のリアルなジャマイカの情景が垣間見えるのが、1972年製作の『ハーダー・ゼイ・カム』。
ジャマイカ人のミュージシャン、ジミー・クリフが主演し、全編にレゲエをフィーチャーしています。当時のゲットーの熱気をはじめ、“リアルジャマイカ”を描いたもの。その後、78年に作られた『ロッカーズ』も有名なジャマイカ人アーティストが多数出演していて、共にレゲエ映画のクラシックとして知られています。音楽はとても有名ですが、ファッションもとにかくカラフルでカッコいい。
暑い国なのにスーツを着ているのは、モッズやブリティッシュジャズカルチャーの影響もあるから。両国で音楽とファッションが行ったり来たりする。そういった背景がよくわかって面白いですね。
ちなみに2016年度のLVMH ヤングファッションデザイナープライズにおいてグランプリとなったウェールズ・ボナーは、ブリティッシュジャマイカン。彼女はルーツでもあるカルチャーを取り入れながら、『Life between Islands』のキュレーションや図録にも協力しています。

スウィンギング・ロンドン。振り切ったものが普遍的に
個人的な実感ではファッションの構成要素、いわゆるシルエットやスタイルというのは、80年代までにほぼ出尽くしてしまったと思っています。90年代以降は、それらを合わせたミックスカルチャーとなる。そういう意味ではゼロから生まれた60年代、70年代のファッションは圧倒的に面白かった。
世界の音楽やファッションをリードした、若者たちの文化革命と呼ばれるスウィンギング・ロンドン時代の映画で代表的なのは『ジョアンナ』。ロンドンのアートスクールに通う美大生、ジョアンナの暮らしぶりを通して当時の空気感が手に取るように伝わってきます。
ヒッピーやボヘミアンなスタイルが面白かった頃、僕は、15、16歳の時にこの映画をリアルタイムで観て衝撃を受けました。後で観直した時にわかったことは、イギリスのゲイカルチャーやさまざまな人種が交ざり合っている描写が多かった。
ジョアンナは田舎から出てきて美大に入るんですけど、それはおそらくRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート。2022年の時点で世界一の美術大学といわれる)。一緒に学校に通う友達が黒人だったり、学校の先輩がゲイだったり。ジョアンナが好きになるのも黒人。あの時代を考えると、ものすごく自由な映画だったと思います。
今の〈グッチ〉のデザイナー、アレッサンドロ・ミケーレは、母親がチネチッタ(イタリアの映画撮影所)の衣装係だった。彼は子供の頃からそういう環境にいたこともあって、クリエイションには常に60〜70年代のボヘミアンカルチャーの要素が入っている。ミケーレの〈グッチ〉はまるで『ジョアンナ』の世界だなと常々思っています。

同じスウィンギング・ロンドンを感じるなら、『唇からナイフ』もおすすめです。これも中高生の頃、映画館で観て衝撃的でした。ジョゼフ・ロージーの作品で、アメリカで赤狩りに遭ってイギリスに亡命した社会派監督だけど、女泥棒が主人公という漫画原作をなぜか映画化して。好き勝手やっているような、一見破天荒な作品でもあります。
90年代にリバイバルした時には、モニカ・ヴィッティの美しさも相まって、サブカル的な“おしゃれ映画”とされたけど、それ以上に、当時の人種や性別に対する常識やモラルを考えると、かなり前衛的な作品だったと、今観るとよりそう感じます。『ジョアンナ』も同じく、当時振り切ったものを作ったがゆえに現代では普遍的になった。だからいつ観てもカッコいいし、新しい。そんな作品です。

昔の映画をファッションの視点で観直してみる
1984年の『ゴーストバスターズ』は、ストーリーが楽しいので注目が集まるけれど、実はファッションも面白い。80年代は、NYのデザイナーズブランドが一気に盛り上がった時なんです。ラルフローレン、アレキサンダー・ジュリアン、ジェーン・バーンズ、ジェフリー・バンクスなど。
でもそんなに知られてなかったし、ブーム自体は短期間だったから資料があまりない。だから洋服を研究してる人にはぜひ観てほしい。ツイードのジャケット、チェックのシャツにネクタイ、その上にスポーティなパーカを羽織ったりして。この作品では、NYデザイナーズものを着て動いている人の姿を観ることができるので、ある意味貴重です。当時の空気感も感じられるし、シルエットもよくわかると思います。

僕にとって、映画はずっとファッションの先生でした。昔は映画くらいしか情報がなかったし、基本的に映画館で一度しか観られないから、ものすごく集中してディテールまでチェックしていました。今の自分を作っている元ネタであるともいえます。
現代は配信でもDVDでも何度でも観直すことができるから、いろいろ発見も多いのではないでしょうか。つい最近感じたのは50年代、60年代の日本映画がいいなと。黒澤明の『天国と地獄』で、刑事がみんな真っ白いシャツを着て、カンカン帽みたいな帽子を被ってる。扇子を扇ぎながら、額の汗を拭いながら犯人を追ってるシーンがあって。今観るとカッコいいんですよね。
小津安二郎の作品に出てくる笠智衆の立ち居振る舞いも、欧米の俳優には出せない侘び寂びを感じさせます。以前はわからなかった男のカッコよさを、今はファッションとして観ることができる。そういった昔の映画から得られる現代のファッションとのつながりは、思った以上にたくさんあると実感しています。