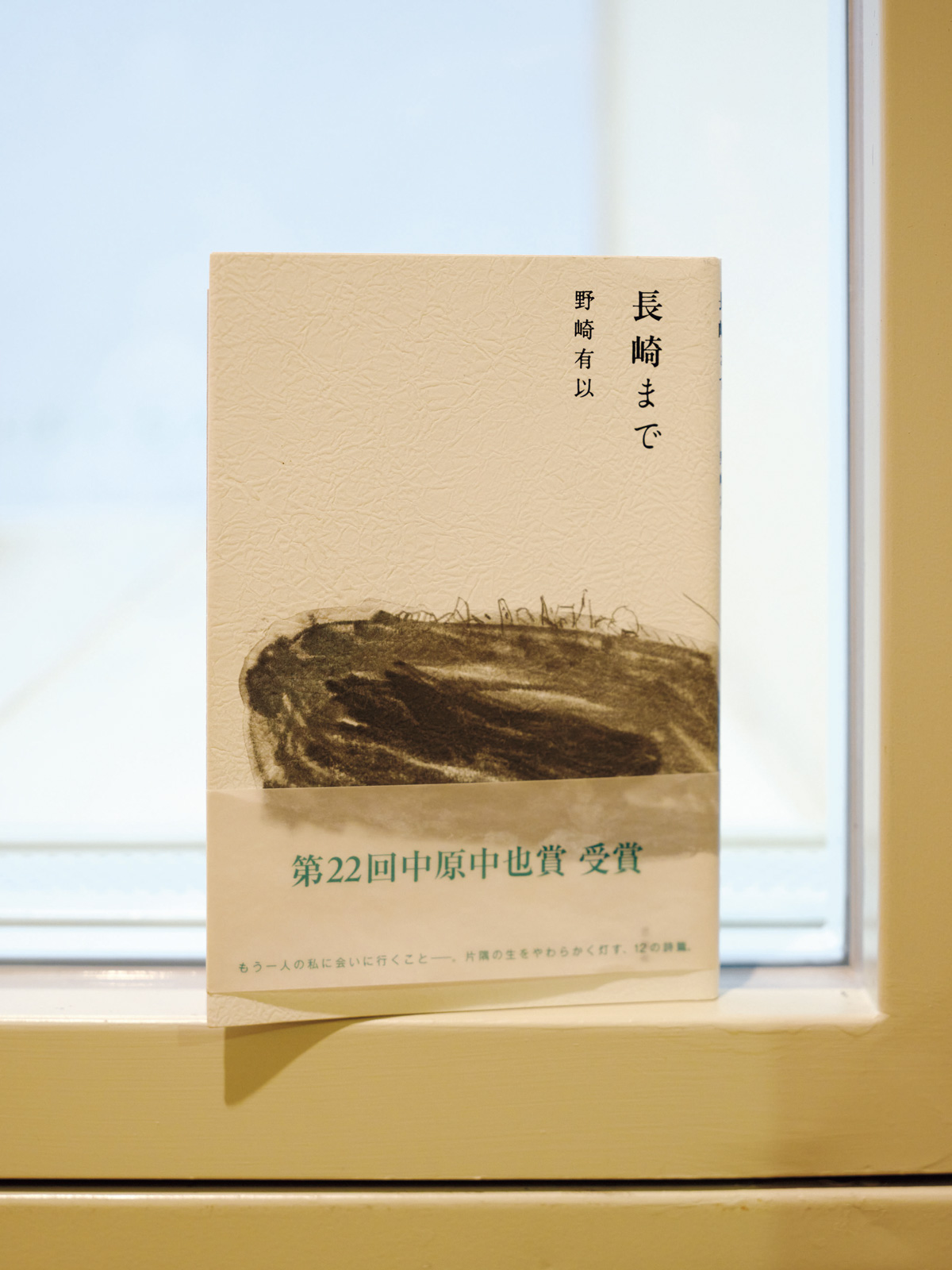本棚から、物語を通じて心の奥深くへ
「普通は本棚って、その人がどう生きてきたかがバシッと反映されてしまうものですよね。僕はそれが嫌で、あえてめちゃくちゃにしているんです。予想ができない不安定な状態であり、際限なくどこまでも広がっていってほしい。自分を映す鏡ではなく、自分だけの宇宙であってほしいんです」

その言葉の通り、曽我部さんの本棚は徹底してランダム。ジャンルも判型も年代も関係なく、本同士が肩を押し合うように無造作に詰め込まれている。
「森鷗外の小説の隣にカンパニー松尾のエッセイがあるような、そのくらいの適当さが心地よいんです。唯一エリアを分けているのは積読本くらい。Amazon経由でも、誰かの紹介でも、目に留まった本は手当たり次第に買うので、読むのが追いつかなくて(笑)。常に20〜30冊はストックがあります」
エッセイにノンフィクション、写真集に音楽本と、並ぶ背表紙からはジャンルの幅広さが窺えるが、中でも最も多いのが小説。骨太な海外文学に純文学、時代物、ミステリー、私小説まで、気になったものは乱読している。

「本音を言えば、基本的にはフィクションだけを読んでいたいくらい。だってインターネットを開けばノンフィクションだらけじゃないですか。でも、誰かが考えたお話は簡単には転がっていない。登場人物の行動や物語の展開に一喜一憂しながら読み進めることで、現実から切り離されて、自分の心の奥深くに潜っていける気がするんです」
例えば2024年に手に取って「これまでの読書体験の中でも究極的なものだった」と語るのが、チリの作家、ロベルト・ボラーニョの『2666』。謎に満ちたドイツ人作家に魅せられた4人の批評家たちが国をまたいで互いに出会い、作家を探しに旅へ出ることから始まる物語。単行本にして上下2段組、850ページ超えの一大長編だ。
「幻の作家を軸にした話の骨格はありつつも、一見関係ない話への脱線や飛躍が随所で繰り返されます。またかすかな繫がりはあれど、部ごとに独立した中編と言ってもいいほど別の物語が展開するんですよね。ただ一貫して登場人物たちは、実在するかわからない作家の存在を常に少しだけ意識しながら、それぞれの現実の中を生きている。今、ここ、という地点と、ここじゃないどこかの中間、あるいはその両方が同時に描かれる物語なんです。そのどことない浮遊感やまどろみに身を委ねる時間は極めて新鮮で、極上でした」
また、SFはかねて曽我部さんが好きなジャンルの一つ。中でもハーラン・エリスンの短編集『死の鳥』の読後感も深く心に残っているのだそう。
「SFというといかにもなロボットが出てくる荒唐無稽なものや、緻密な設定で現代を批判するディストピア小説が思い浮かびますが、本作はどちらにも当てはまらないんです。明らかに近未来を舞台にしたSFですが、音楽で言うとニューヨークパンクを思わす粗削り感と体温が残っている。ゆえに著者が幻視した風景が鮮やかに立ち上がってきて。唯一無二の読書体験でした」
こうして絶えず物語を追いかける彼の原点の一つが聖書だ。両親がカトリック教徒だったことから、幼い頃は毎週日曜日は教会に行くのが習慣だった。ごく自然と触れてきた物語だ。
「教条的な視点はいったん脇に置いて読むと面白くて。例えば旧約聖書のヨブ記は、ヨブという人が散々な目に遭う話。でも彼はそれは神が与えた試練だと耐え続け、明確な着地点もないまま結末を迎える。何もないところに放り出される読後感なんです(笑)。でもこれだけ時代が変わっても、人間の抱える問題は根本的には変わらない。大人になって読み直すと発見が多いですね」

インスピレーションの源泉は携える本がもたらしてくれる
目下、サニーデイ・サービスは全国ツアーを展開中。こうした時期は「絶好の読書機会なんです」と曽我部さん。各地へ赴く前に、まずは本棚の中から旅に携える本を数冊選ぶのが習慣だ。
「喉が心配なので、移動と本番以外の時間はホテルに籠(こ)もるようにしていて。基本的にはずっと本を読んでいます。日常ではどうしても細切れにしか読めないところを、たっぷり時間が取れるのが嬉しいんですよね」
そして本を携えていることの効用は、読書を楽しめることだけにとどまらない。
「本ってお守りのような存在でもあって。その時に読んでいる一冊がインスピレーションをくれるので、過去に読んだ本を旅先に持っていって、好きなページだけを読み返すこともあります。良い本を持ち歩いていると、不思議と良いパフォーマンスができるし、良い曲が書ける気がするんです」。
際限なく広がる本棚の宇宙から、その時々に必要な一冊を手に取る。彼の音楽は、そんな“物語との出会い”の積み重ねによって奏でられていた。