『コウモリの見た夢』
モーシン・ハミッド/著 川上純子/訳
マスメディアには映らない
もう一つの9.11像
2001年9月11日、4機の旅客機がハイジャックされた。そのうち2機がマンハッタンのツインタワーを崩落させた映像は世界中を駆け巡り、繰り返し放送された。
こうして、マスメディアを通して事件映像が繰り返し放送されたその過程こそ、「9.11」という未曽有の1日を生み出し、アメリカの傷こそ世界に共有されるべき特別な傷であるというメッセージが視聴者に刷り込まれていく過程でもあった。
特別な追悼、そして、特別な治療に値するトラウマとしての9.11像に、文学は揺さぶりをかける。『コウモリの見た夢』は、パキスタンとアメリカに引き裂かれながら生きる男の視点を通して、9.11にまつわる凝り固まったイメージをゆっくりとほぐしていった。(矢倉)

『一時帰還』
フィル・クレイ/著 上岡伸雄/訳
兵士たちの生を通して描く
多彩な戦争の姿
2003年3月、イラクが保有する大量破壊兵器に対処するという名目でイラク戦争が始まった。実際には大量破壊兵器など発見されなかったのだが。
アメリカの嘘から始まった戦争を描くフィクションは多彩だ。従軍経験をもとに兵士の心情を辿るケヴィン・パワーズの『イエロー・バード』、メディアが戦争をスペクタクル化するベン・ファウンテンの『ビリー・リンの永遠の一日』、戦争を正当化した知識人へのインタビューという形式をとるドン・デリーロの『ポイント・オメガ』など。
とりわけ、フィル・クレイの『一時帰還』は、短編集ゆえに一層多彩な戦争の姿を浮かび上がらせる。兵士のみに通じる戦場でのコミュニケーションは、兵士の帰国後もなお続いている。(矢倉)

『コズモポリス』
ドン・デリーロ/著 上岡伸雄/訳
リーマンショックを予見した、
投資家ノベル
2008年9月、投資銀行リーマン・ブラザーズ・ホールディングスが経営破綻し、世界規模の経済危機が訪れた。利潤追求の果てなき欲望が招いたリーマンショックを予見したと再評価されたのが『コズモポリス』だ。
28歳にして巨万の富を築いたマンハッタンの投資家エリックは、スクリーン上のデジタルな数字に夢中だが、生身の肉体を持つ妻やボディーガードやリムジン運転手にはさほど関心がない。暗殺予告を受けたにもかかわらず散髪に出かける彼にとって、人生はまるで他人事のようだ。
終盤、路上に累々と裸体が横たわる映画撮影シーンは、抗議デモ(オキュパイ運動)と重ねて読まれるようになった。生命と時の関節は今も外れたままだ。(矢倉)

『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』
ジェスミン・ウォード/著 石川由美子/訳
黒人が直面する問題に
肉迫した南部物語
「文学は21世紀のアメリカをどう描いたのか?」この問いに対して、本書ほど完璧な答えを持つ小説はないだろう。
ブラック・ライヴズ・マター、ハリケーン・カトリーナ、拡大する経済格差、そして不可視化される女性の労働問題 南部に暮らす黒人女性作家として、ジェスミン・ウォードはその苦しみの全てを生きた。
押し潰されそうになりながら、それでも彼女はペンを執り、その悲しみの全てを本書に注ぎ込んだ。悲劇としての奴隷制の過去は、フォークナー直系の語りの技巧によって描かれ、未来は祈りとなり、モリスンが紡いだ遺志は「歌」に託される。
歌え、葬られぬ者たちよ、歌え。時代を超えんとする強靭な意志の翼を持った、21世紀アメリカ文学最高の一冊。(青木)
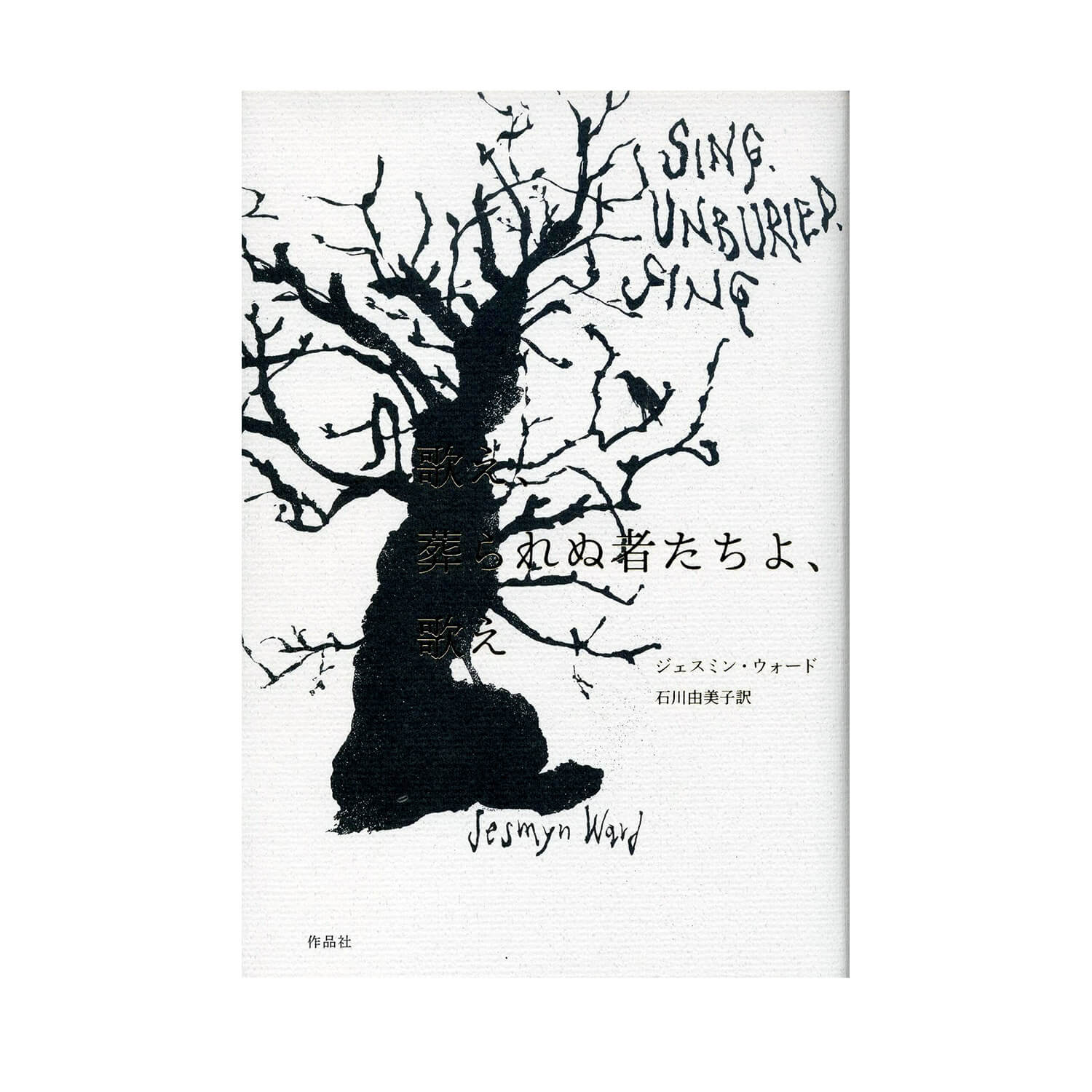
『くたばれインターネット』
ジャレット・コベック/著 浅倉卓弥/訳
SNS利用者をボロクソに批判する
“炎上”小説
ツイッターもフェイスブックもインスタグラムも、はじまりは2000〜2010年代のアメリカ西海岸。SNSはまたたく間に世界中に広がり、人々のライフスタイルを変えた。
SNSは自由と解放をもたらす。アラブの春への貢献が報道されると、そんな声すら上がった。アメリカでも、拡散された動画がBLMに火をつけた。
そんなSNSの負の側面を、アメリカ文学は捉える。デイブ・エガーズの小説『ザ・サークル』はSNSによって監視社会化する世の中を描いた。コベックは炎上とデジタルタトゥーに焦点を当てる。
喜々として個人情報を垂れ流すSNS利用者は、実のところ搾取されている。それを「ボロクソ」に批判するこの小説の声は痛快で、思わずゲラゲラと笑ってしまう。(日野原)

『十二月の十日』
ジョージ・ソーンダーズ/著 岸本佐知子/訳
トランプ的人物も登場⁉する
現代奇譚集
あのツイートっぷり……大統領として問題アリだが、ソーンダーズの小説なら地獄上司として登場しそう。長篇『リンカーンとさまよえる霊魂たち』で死霊のオールナイトアメリカントークを披露した作家は短篇が本領。
情け容赦ない労働環境を珍妙設定テーマパークに落とし込むデビュー以来のお家芸は今回も絶好調。
私たちよりちょっと愚か、ちょっと(というかかなり)不運、ちょっと判断力がマヒ、そして自分の気持ちにちょっと正直な主人公たちが窮状から抜け出せないように、私たちも彼らの脳内にトラップされる。
ディストピア感満載の「センブリカ・ガール日記」は必読。21世紀最も次回作を待ち望まれる作家の「全米を泣かす」センチメンタリズムを最強の岸本訳で。(吉田)
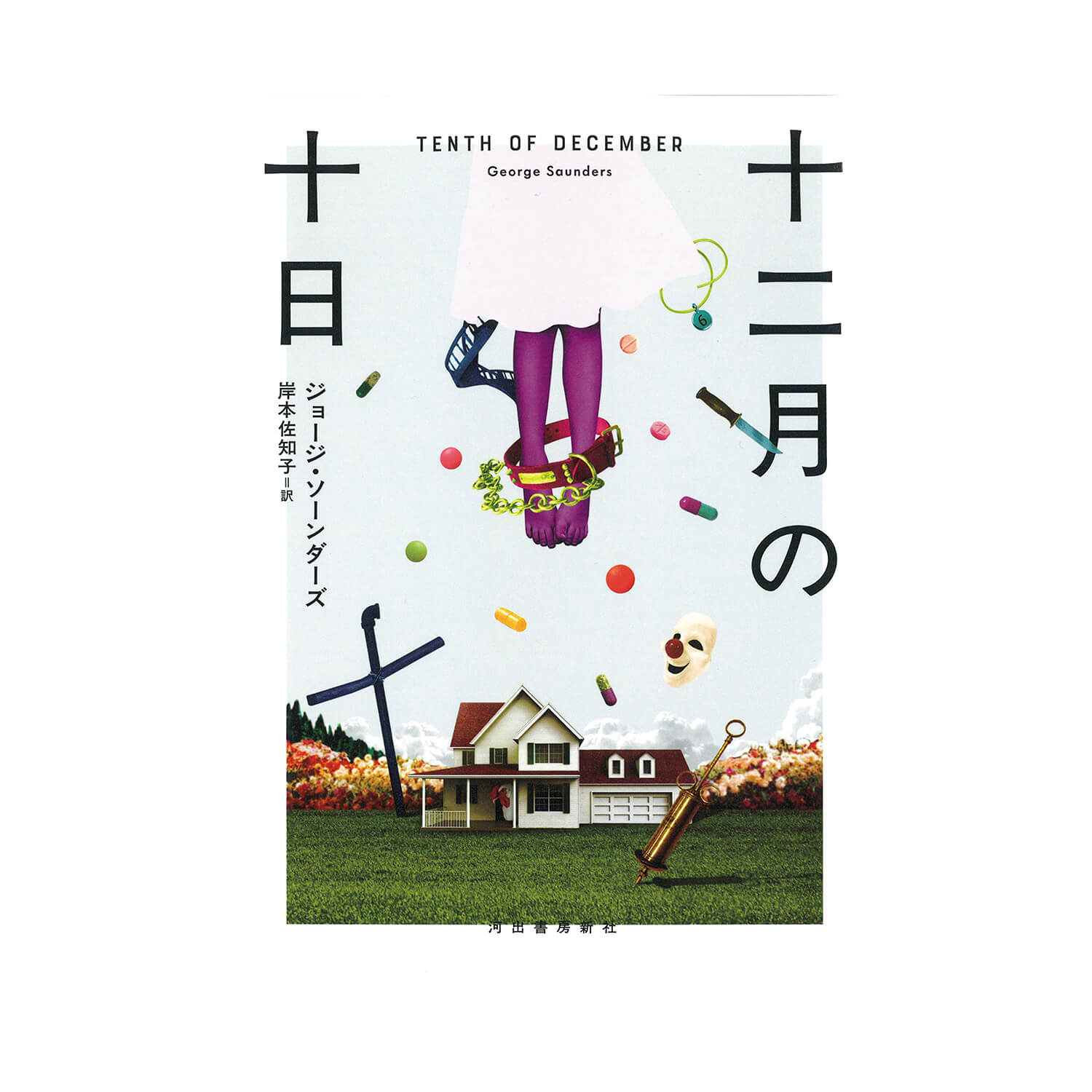
展望:ポストトランプ時代の文学のゆくえ
トランプ政権を象徴する文学は『十二月の十日』のような小説だけにとどまらない。
J・D・ヴァンスの『ヒルビリー・エレジー』(原著2016年、邦訳2017年)は、「忘れられていた白人労働者階級がトランプの躍進を支えた」というノンフィクション風フィクションの代表格だ。
2019年の学会発表で髙村峰生が指摘したように、ヴァンスはオハイオ州のミドルタウンに衰退する工業地帯のイメージを重ね、白人労働者を忘れられた者として演出し、ネガティブな感情の受け皿をつくりあげた。
こうして、アメリカンドリームを描く自伝文化が盛んなアメリカにまた一つ、記念碑的オートフィクションが生まれた。
タナハシ・コーツは、『僕の大統領は黒人だった』(原著2017年、邦訳2020年)のなかで、白人労働者階層を特別視するこのような見立ては、アイデンティティを重視する政治を白人専用にしたうえで白人男性主導の資本主義世界を理想化しているに過ぎないと喝破した。貧乏白人男性の物語には情動を巧みに操る訴求力があったのだ。
人は物語を求め、ときに陰謀論にすがってしまう。それでは、得体の知れない物語以前の何かに出会えないだろうか。
2020年度ノーベル文学賞で注目されたルイーズ・グリュックの詩や、人々が停電によって一切の電子的喧騒から遮断されるドン・デリーロの『沈黙 (The Silence)』(2020年、未邦訳)のように、凝り固まった物語以前の音韻や沈黙のなかから個人の生活を見つめ直す文学は、深い傷と分断を抱えたアメリカに静かな導きをもたらしてくれるだろう。(矢倉)





































