断片的な声に流されず、主体的に情報に向き合うために
全国の学校や自治体、美術館などで哲学対話を続けるかたわら、エッセイの執筆やラジオ番組への出演、さらには市民メディア「Choose Life Project」の運営にも携わるなど、時代のオピニオンリーダーとしても活動の幅を広げている永井玲衣さん。以前から、本やWEBメディア、SNSなど幅広いツールを使って日々情報を得てきた中で、特に意識的に新聞というメディアに触れるようになったのはここ数年のことだという。
「時事的な目線が必要な仕事が増えたことも理由の一つですが、SNSが席巻する中で、もう少し主体的にメディアや情報と向き合いたいと思うようになったことも影響しています。
例えばTwitterでは、ウクライナの凄惨な写真の次に、猫の可愛い動画が流れてきたり、美味しそうなラーメンの写真と政治的な発言とが隣り合っていたりしますよね。“個人の声を拾う”という意味では有用なツールですが、受動的な形で極めて断片的な情報が無尽蔵に流れ去っていくことに、少し怖さを感じたんです。自分は今、どんな時代を生きていて、どういう属性なのか。どの地点から目の前の出来事や事象を見ているのかという、自分の現在地を俯瞰的に把握したいとの思いから、新聞を手に取るようになりました」

日頃触れているのは、特定の一紙ではなく複数の新聞。全国紙のみならず時に機関紙も読み、媒体ごとに取り上げる情報や、その切り取り方の違いを味わうというところは、俯瞰性を見据える永井さんならではだ。
「例えば日本経済新聞はとにかくデータに強くて、私はもちろん、周りの研究者たちも頼りにしている媒体です。一方で、社会面に力を入れているものもあれば、国際欄が充実しているものもある。各紙の強みに注目しながら読み進めるのがすごく面白いんです。
さらに新聞は、あらゆるトピックを公平に扱いながらも、必ずそれぞれに“観点”があるところが面白いなと。一見、どんな思想や立場にも根ざさずにありのままの事実を伝えるものが良いメディアだと思われがちですが、一方で、本質的に偏りのない中立な情報は存在し得ないとも言われますよね。どんな情報にも、新聞社、あるいはその記事を書いた記者による解釈が含まれていて、そこにはなにかしらの姿勢や態度が表れている。同じデータを扱うにしても、どの数字を大きく取り上げるのか、どんな見出しを立てるのかによって、新聞ごとに差が出ます。どういう問いを持った上でそれらの記事が書かれているのかという点に考えを巡らすのも楽しいですね」
ずらりと並ぶ見出しが、社会の複雑性を視覚化してくれる
電子版であれ紙であれ、永井さんなりの新聞の読み方は、まず見出しを目で追いながら、全体を一通りさらうこと。多忙な毎日の中で、さらにいくつかの新聞に目を通そうとすると、当然ながらすべてを隅々まで読み込むことは難しい。だがむしろ、記事をずらりと一覧で眺めることにこそ、新聞の醍醐味があるという。
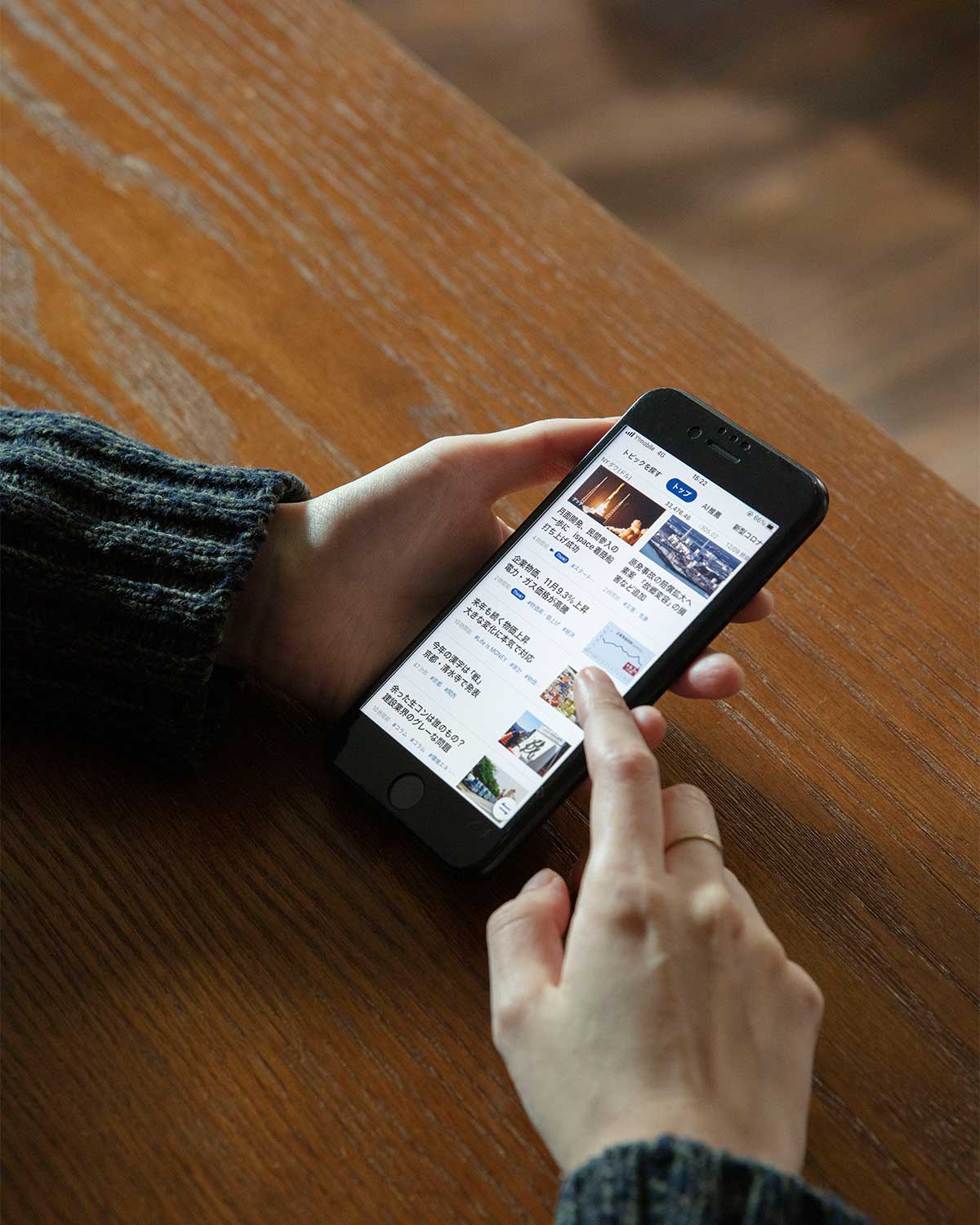
「眺めているだけで、今、世界ではこれだけ多くの出来事が起こっているんだという事実が視覚的に迫ってきます。無理に単純化することなく、この世はこんなにも複雑なんだということを、手放さずに見せてくれる。それを味わえるのが醍醐味だなと思います。自分にはまだこんなにも知らないことがあるのかと圧倒されるし、分からないことにもっとのみ込まれたい、とある意味ワクワクもするんです(笑)」
そして見出しを追っていった後は、目に留まった記事を読み込んでいく。その中には、自分が知る由もなかった、世界の裏側の小さな、けれども確かな情報が転がっていることもある。
「最近私が関心を寄せているは、世界の同性婚にまつわる動きや、社会の不均衡に対して各地でどんなアクションが起こっているのか。狙ってキャッチしようとしても、SNSでは、自分が思い浮かぶようなキーワードからしか検索ができないし、本では、何らかのワンイシューに対して深掘りすることはできても、リアルタイムの幅広い情報を得ることは難しい。
そんな中で新聞は、どうしても受け身にならざるを得ないような細かな情報を、取材力を駆使して引っ張ってきてくれるんですよね。例えば、スコットランドで『生理の貧困』解消のために、生理用品無償化の法案が議会で承認されたことや、アメリカの大手新聞社ニューヨーク・タイムズの労働組合が40年ぶりにストライキを起こしたといった情報も、新聞を眺めていたからこそ得られたもの。知らず知らずのうちに自分の幅を広げてくれるのは、新聞ならではですね」
新聞もまた、「他者」であり、対話相手である

「さらっと読み飛ばしたような記事でも、ああ、そういえば……と思い出して振り返って、考えるタネにすることもあります」と永井さん。受け身にならざるを得ないような幅広い情報を、独自の観点を持って伝える新聞は、毎日の情報収集のみならず、永井さんが哲学的な目線で物事を考える上で、あるいはそれを文章を書く上で、適宜立ち戻る道標としても機能している。
「後から記事を探すときは、検索機能がある電子版はやっぱり重宝しますね。日本経済新聞からは、確かなデータを根拠として引っ張ってくることも多いです。新聞に載る情報って、時事性が高くて日々流れ去っていくものでありながら、絶版になって読めなくなってしまうこともある本や雑誌と異なり、時代を表す情報としてアーカイブされていくものでもあるところも面白いなと。“刹那で永遠”という、両義性を持つ不思議なメディアだなとつくづく感じます」
SNSを通じて、誰もが簡単にデータを用いて発信ができ、誰もが批評家になれる時代だからこそ、後世に残す時代の情報を伝える矜持を持つ新聞社の専門性と責任感がなおさら際立つのだと永井さんは話す。そしてそれは、彼女がライフワークのように続けている「考える」ことにも作用している。
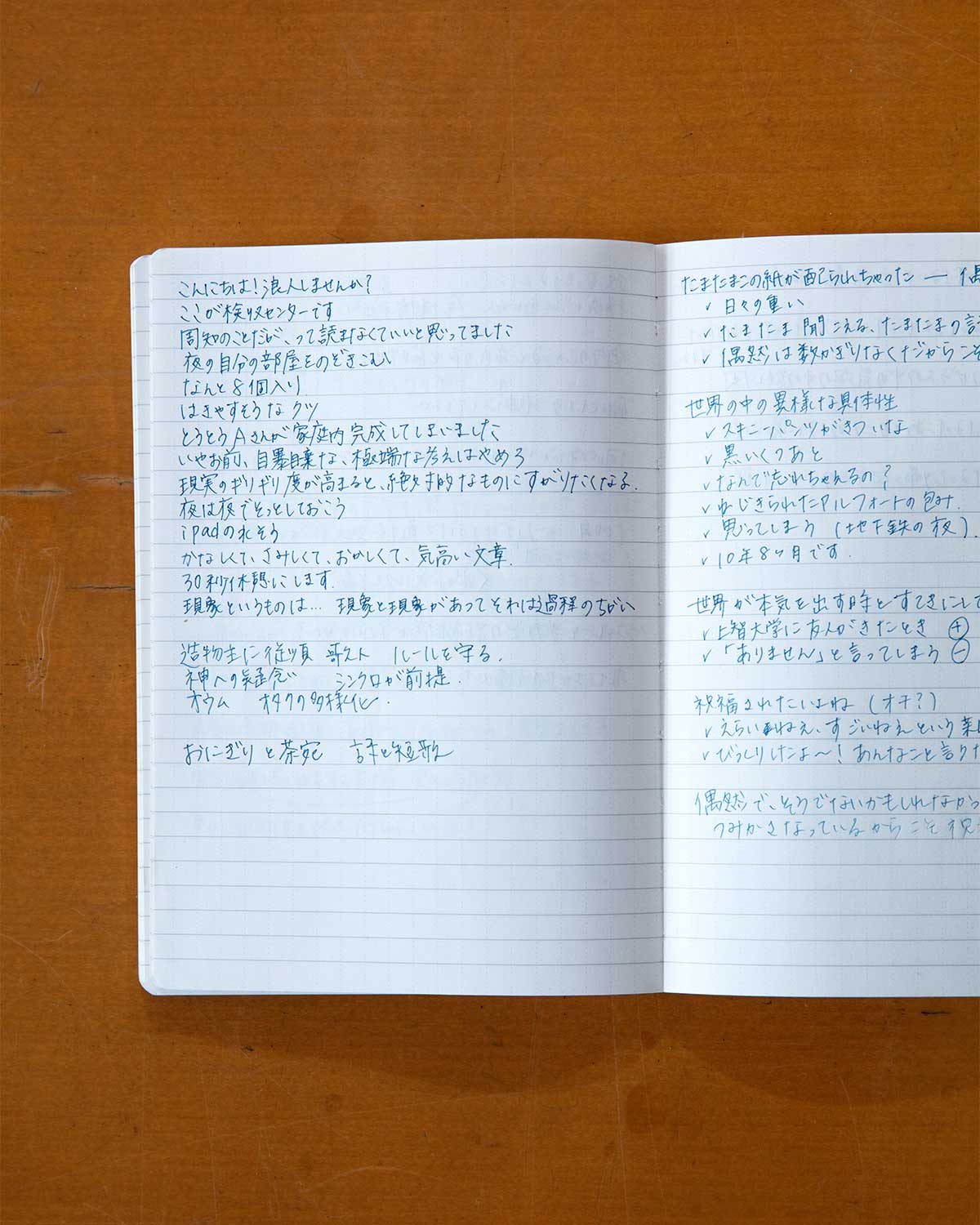
「考えるってなんとなく、一人で完結する孤独な作業と捉えられがちですが、本来は“他なるもの”が導入されて初めて突き動かされるもの。他者がいないと成し得ないことなんだと、私自身哲学対話の回を重ねるごとに実感します。
その点、新聞も自分にとって、対話相手となりうる他者だと思っています。それを書いている記者との対話であるし、その記者が浮かび上がらせた現実との対話である。一方的に情報を受け取るだけのツールとしてではなく、新聞から投げかけられた視点を受けて考え、そこからさらにまた別の記事を選び取って読んでいく、といったように、共に対話を深める相手として考え直してもいいんじゃないでしょうか。
情報は、電子データのようにマテリアル的なものにも思われますが、実際にはそれを書いた人がいて、その人と自分は同じ社会に生きている。その共同性をいかに手放さずに読んで、自分の考えを深めるきっかけにできるかは、むしろ読み手側が試されていることなのかもしれないですね」
変化の早い時代に流されることなく自分の足で立ち続けるためには、考え続けることが必要。そして考えるきっかけをくれるのは、いつだって他者の視点。新聞に触れて思いがけない情報や視点と出会うことが、社会を、あるいは自分自身を本質的に理解することとも繋がるのかもしれない。












