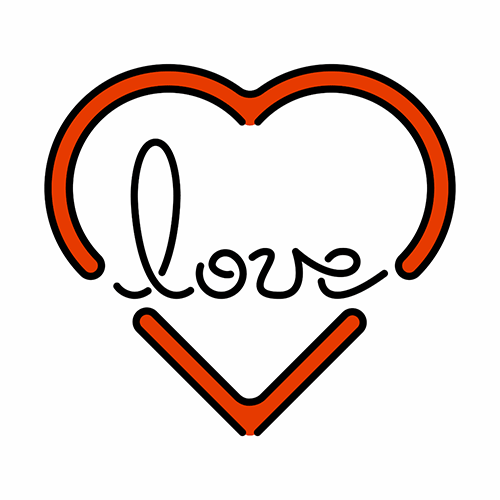落語のなかの恋
恋愛っていうものは、昔から日本にあったんですかね?だって二葉亭四迷は「I love you」という言葉をうまく表す日本語を考え抜いて、「あなたとならば死んでもいい」って訳したっていいますよ。男と女は親の決めた相手と一緒になるわけで、いわゆる自由恋愛でもなかった。恋や愛っていうより情でしょう。だから落語には夫婦の情を描いたものはいくらでもあるけど、恋を扱うものはほとんどない。
そういうふうに江戸の時代に純粋な恋物語ってのが珍しかったからこそ、『紺屋(こうや)高尾』という噺があるんだと思います。染物職人の久蔵って男が、吉原の花魁(おいらん)のトップもトップ、高尾太夫(だゆう)に一目惚れしちゃう。ところが3000人の遊女たちの最高位の花魁ですから、“大名道具”と呼ばれるほどで、身分のある人や、恐ろしくお金を持っている豪商としかつきあわない。久蔵なんて手の届きようもない存在です。
外国のおとぎ話には、お姫様と一般人の男の恋なんてものがよくあるけれど、吉原の場合、なんとしても遊女たちですからね、お金を支払います。金銭を介した疑似恋愛なんですよね。『紺屋高尾』はその疑似恋愛の場から純愛が生まれていくのが面白いんだけど。
吉原に独特だったのが、花魁たちに拒否権があるってことですね。きれいなだけではもちろんダメで、きちんと教育をされていて、教養もあり、簡単には男と寝ない。だから、お金を払って行くのに嫌われて何にもできないなんてこともあるわけです(笑)。
江戸には圧倒的に男が多かったから、吉原のような場所がないと困っちゃうんですよね。だから、今考えるよりずっと吉原は市民権を得ていた。振られちゃったり、会ってくれなかったり。男たちは、この吉原という場所で、セックスだけじゃなくて、恋は思い通りにはならないってことを学ぶんですよね。かつ、思い通りにならなくても怒らないってことも。それを端的に表すのが「粋」と「野暮」って言葉です。
金を出しているのに女が来ないって文句を言うと、野暮なことを言うもんじゃないと、店だけじゃなくて女からも罵(ののし)られる。「おととい来やがれ!」って女に言われて「おとといも来てらぁ!」なんて(笑)。女たちにしたって、客の男を惹きつけておくためには、最初に寝ちゃっても、そのあとに惚れさせなきゃいけない。だからそこから情を通い合わせていくんです。
寝る寝ないではなくて、コミュニケーションに長(た)けていないと“疑似”でも恋はうまくいかないわけ。吉原ではなく、仲人があって親の決めた人と一緒になるような場合でも、男と女がきちんと出会うのは婚礼の日が初めてのようなものでしょ。そこから情を通じて2人の距離が近づいていく。
今、“草食系”が増えたって言うけどさ、セックスにこだわらないってところだけを見ると、江戸の頃と違和感ないと思うんですよね。相手との距離をコミュニケーションで埋めてくってことをしない、どこか引いたところが周囲の人間を不安にさせるもんだから、“草食系”なんて名前で呼ぶだけなんじゃないですかね。
現代ってインターネットで世界が小さくなったとか複雑になったとかって言いますけど、俺の目には、進歩しているようで江戸の頃とあまり変わってないように映るんです。昔は小さな町内なんだけど、そこに食べ物屋があって銭湯があって寄席があって、って世界の全部が揃ってたんだから。お上が頼れない。銀行も頼れない。こりゃあ町内なり家族なりがしっかりするしかないぞってさ。今、俺らはちょうど同じようなことを経験しているわけでしょう?
だからちょっと舵を切って、江戸の頃に学んでみるのもいいのかもしれませんよね。「恋」っていうより「情」。ぐずぐず言ってないでまずしちゃえ、と(笑)。極端なことを言うようだけど、だってそこから恋愛に移行していけるんだから。もめたり、うまくいったり、怒られたり、別れるのが大変だったり……ってさ、そういうことを10年続けりゃ、あんた根多(ねた)増えるよ、恋愛のオーソリティって呼ばれるよっていう。
落語の根本にある、“喜ばせたい”という気持ち
落語と恋ということでもう少し言うと、落語家の師弟関係も疑似恋愛なんですよね。それも思いの通じない恋。この人の芸を教わりたい、でもただ教えてくれっていうんだから、教えたくなるような空気を作らないといけない。つまり、師匠(立川談志)を喜ばせないといけない。
そうして師匠のことが本当に好きになってくると、「喜ばせないといけない」が「喜ばせたい」になって、師匠が喜んでいるのが幸せになってくる。これは実は教育で、相手を喜ばせることってのが、落語のコミュニケーションの根本なんですよね。
修業時代に師匠がよくこう言ってたんですよ。「どこへでも行って、そこで私はあなたがこんなに好きなんですって伝えてこい。そうすりゃ人は振り向いてくれるから」って。いろんなところへ行くようになって、それはやっぱりその通りなんですけど、相手の体調や心情によって伝わらないことはある。
で、本当に好きだと思うなら、自分の伝えたいことを二の次、三の次にしてでも、「こういう伝え方をするとこの人は喜ぶだろうな」と考える場面も出てきたんですよね。相手に喜ばれる、成就するってことを是とするならば、自分を脇に置いておくことも必要になるわけだから、ここまで尽くす意味があるのか?って自問自答したりもする。
でも、それと背中合わせで、相手の喜びが自分の喜びとイコールになる時ってのがあるんですよ。もしかするとこれが惚れるってことなのかもしれない、とも思いますね。

「ごろっと横になって天井見たら、天井の節穴から高尾があっしに向かってほほえみかけるんす。
『紺屋高尾』より
何見ても高尾にしか見えなくなっちゃったんです。
夜寝ようと思って眼ぇ閉じたって、あの目が合ったときの高尾の笑ってくれた顔が忘れられなくて……」
古典落語『紺屋高尾』のあらすじ
神田の紺屋(染物屋)に勤める職人、久蔵は、親方も一目置くほどの真面目で純粋な青年。それがある日、吉原の花魁道中を目にし、高尾太夫のあまりの美しさに惚れ込んでしまう。身分違いの恋で叶うべくもないと呆れる親方だが、思い詰める久蔵に、15両貯めれば会わせてやると請け合う。寝食を忘れて仕事に励み、3年ののち、当時は途方もない大金であった15両を上回る給金を貯め上げた久蔵。周囲のとりなしでいよいよ高尾に会えることになるが……。