高校の先輩の話をしようと思う。名古屋で精神科医をしている先輩だ。彼が高校を卒業する直前、一緒に葬式に行った。そこでの奇妙な体験は特に処理されることがないまま、僕の中にしまわれている。水野さんと話してからだろうか、そういう記憶にアクセスしやすい身体になったのかもしれない。
同級生が死んだのだ。彼の同級生で、僕から見たら先輩ということになる。死因は交通事故だった。でも、2年ほど引きこもっていたから、自殺だという噂も出ていた。でも実際に彼女が死んでいるということが妙に生々しくて、事故死だとしても自ら死を選んだとしても、どうでもいいことに思えた。葬式の最中、僕が先輩にそれを耳打ちすると、彼もゆっくりと頷いた。
焼香の列に並ぶ。薄いビニール傘から落ちる水滴が玄関前に置かれたマットに楕円をいくつか作る。受付の脇で名前を書き終えると、筆ペンのキャップを閉める音がやけに大きく響いた。受付で香典袋を渡すとき、先輩が小声で「字、うまい」と言った。借り物の黒い革靴はかかとが余って、歩くたびに中で踵が一拍遅れた。
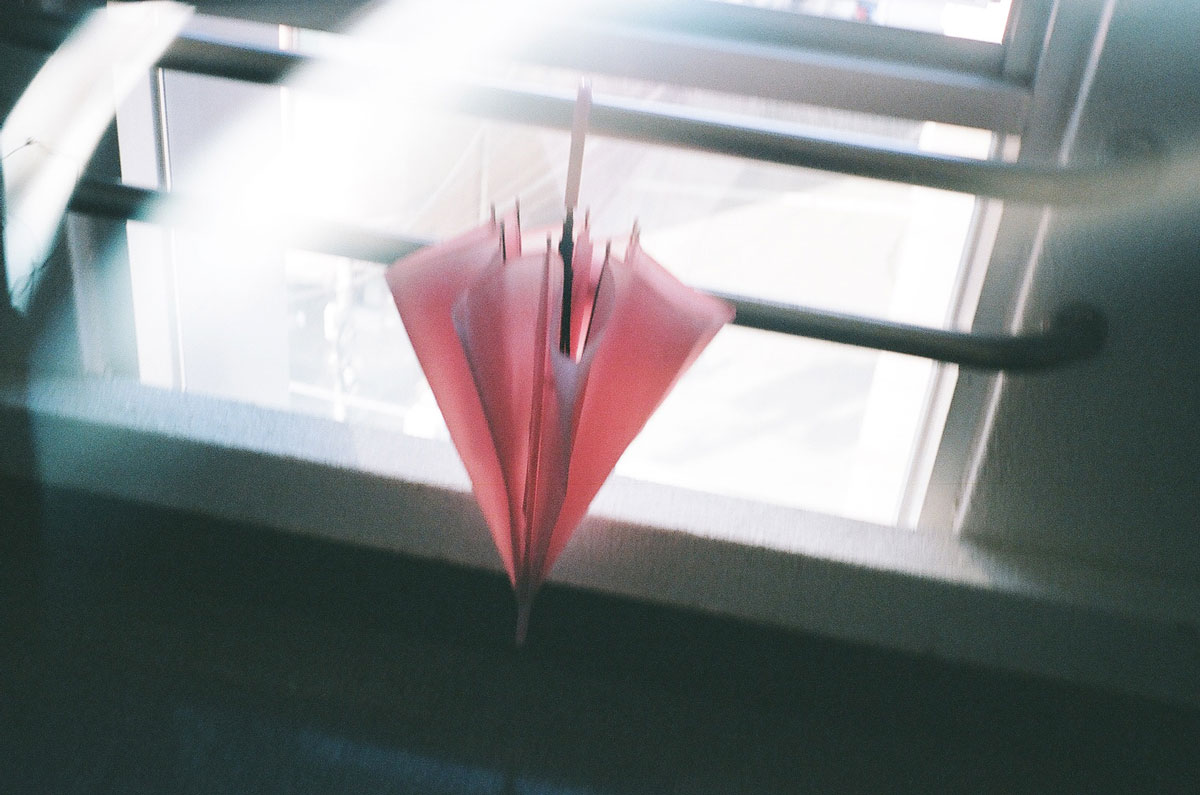
故人が若いケースの場合、葬式は独特な静けさを持つ。遺影は卒業アルバムの流用だった。それを見て、「事故か自殺か、どっちでもいいね」と先輩は改めて僕に囁いた。焼香の順番がいよいよ近づいたとき、彼はポケットからミントタブレットを取り出した。二粒、白い点が光を反射して小さく光った。ほのかな匂い。
その夜のことを、名古屋の喫茶店で十五年ぶりに会った先輩と話した。杖の先がテーブルの脚にふれて、かすかに音がした。「あの時から、たぶん決めていたんですよね」と先輩は言った。
「人が余白から追い出される瞬間の話を、仕事にしていくって」
何か業務連絡をするかのように淡々と続けた。「ほぼ他人と言ってもいいような人が死んで、そう思うのは自分でも不思議な気持ちでした」それを聞きながら僕はミントの匂いを思い出していた。僕は笑って、でもすぐ笑えなくなって、「診断名はつくんですか、今振り返ると」と聞いた。
「もちろん、今でもそれはわからないです。自殺だと仮定して、何個か便宜上は名称は与えられるけど、軽率に病名をつけると違うものになる。だから、ただ覚えておく」
葬式に話を戻す。焼香に並ぶ。脳内でシミュレーションする。ほとんど経験がなかったから、作業の順番を頭の中で箇条書きにして並べる。読経が始まってから、天井の四角いスピーカーが一度だけ小さく「……上り線、渋滞のため……」と鳴った。一秒に満たないくらいの、やすりで擦ったような薄い声だった。すぐに経の声が上書きして、目の前の黒い背中が何事もなかったみたいに前に進んだ。
上り線。渋滞。それに僕が少なからず動揺したのは、それが彼女の声に聞こえたからだ。先輩が僕の袖を軽くつまんで、「聞いた?」と口だけで言って、自分で首を縦に振った。彼女の印象的な掠れた声。猫じゃらしを指でつまんで引っ張ったときみたいなしゃがれた声。しばらくの間耳にしてなかったけど、不思議と耳に残った。
試しにドキュメンタリーにフィクションを挿入してみた。あくまで手始めにくらいのもので、水野さんに送る「プロトタイプ」みたいなものだ。僕は気づいたら、水野さんの試みに興味を持ってしまっていたみたいだ。いや、正確にいうと違うかもしれない。実際にそれを試してみることで、そしてそれを水野さんがどう思うかに興味を持っている。この連載に興味を持っているのか、水野さんという人間に興味を持っているのか、その領域は不可分でマーブル模様のように広がっていく。葬式のときに足元に広がっていた水たまりを思い出す。黒い靴が上で跳ねるたびに、合体や離別を繰り返す。
引きこもっていた先輩が亡くなったのは本当だ。死因が分からなかったのも本当の話だ。ただ、それは僕が詳細を知ろうとしなかっただけで。「ただ、それは僕が詳細を知ろうとしなかっただけで」という一文を打ったところで、指が止まった。
なぜ僕は知らなかったんだろう。高校時代に親交のある先輩が亡くなったことは極めてセンセーショナルだったはずで、詳細を知ろうとしなくても(なんなら懸命に耳を塞いだとしても)その情報は飛び込んできてしまった気がする。自殺ではなかった、と思う。10年そこらしか経っていないのに、すでに記憶は曖昧だ。でも自殺とは聞いたことがなかった。交通事故だ。でも、センター試験の前日のことだったから、もしかしたら自殺なのかもしれない、と僕は心の中で一人呟いたのだ。
水野さんの言う通りなのかもしれない。書き手である僕ですら曖昧なのだ。これこそが「虚構が現実として立ち上がる感覚」なのだろうか。まあそれは僕が思い出しながら綴っているからそう思うだけかもしれないが。
実際には精神科医の先輩とは一緒に葬式には行っていない。ひとりで行った。天気は覚えていない。覚えていないということは雨ではなかったのかもしれない。自殺ではないといいなと思った。センター試験のニュースに、これから続いていく人生と暴力的でシステマチックな資本主義社会を突きつけられ、ふらふらと道を歩いていたときに轢かれてしまったのだろうか。そんなことを考えていた。彼女の名前は覚えている。ただ仮名だとしてもなんだか名付けることはできなかった。プライバシー的な理由ではない(精神科医の先輩はそうなわけだけど)。僕の記憶に肉付けしていく作業をしていると、頭の芯が収縮していくような感覚に襲われる。そう、端的に彼女の死はとても悲しいものだった。
天井の四角いスピーカーが一度だけ小さく「……上り線、渋滞のため……」と鳴った。ここは全くのフィクションだ。ここで彼女の声が聞こえるということが、この記憶をフィクションにするうえで必要に思えた。「必要に思えた」という言葉が、画面の上で少しだけ浮いている。必要。誰にとって。僕にとって。読者にとって。水野さんにとって。あるいは、彼女にとって。
水野さんに送るためのプロトタイプ、と僕は書いた。プロトタイプという言葉は便利で、まだ責任を負わなくていい感じがある。試作品。未完成。だから、失敗してもいい。そうやって僕は、彼女の声を天井から落とした。















