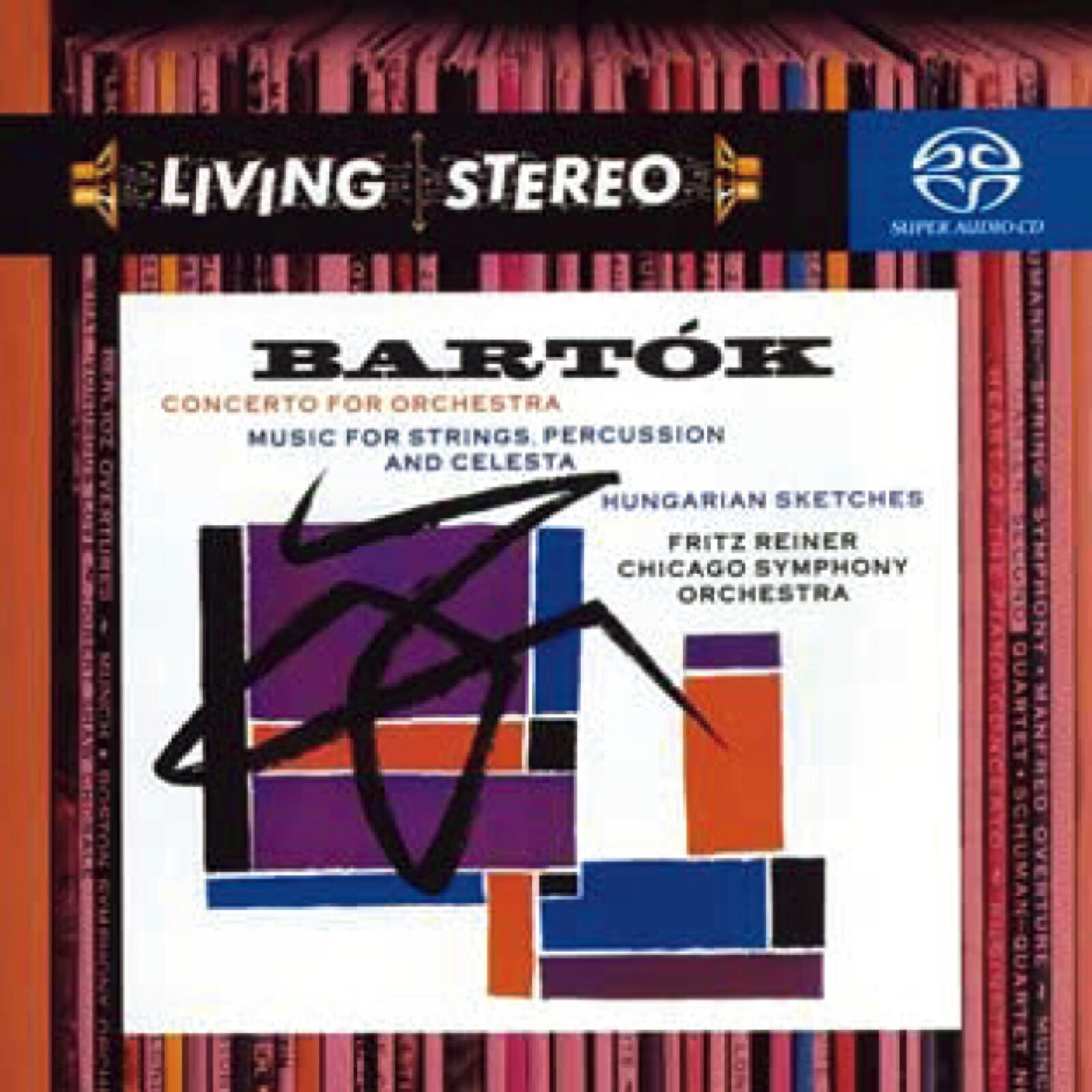心を掴まれた、
ラヴェルの超絶技巧曲に含まれたさりげないユーモア
幼少期からピアノ曲は聴いていましたが、いわゆる広義でのクラシックを聴き始めたのは社会人になってからですし、全く聴かない時期もありました。聴き慣れるとBGM化してしまう音楽。最近キチンと「聴いて」ないな、と思った時に聴き直す3曲です。
1は、小学6年の時に聴いて、その独創的なメロディの数々、実在する絵から着想したという物語仕立ての構成に驚き、圧倒されました。弾けもしないのに楽譜を買ってもらいましたが、私の小さな手ではもちろん無理でした。
2は、社会人になってから、たまたまテレビで聴いて全身が震えるほど感激。超絶技巧を要する曲ですが、さりげなく含まれるユーモアにもぐっときます。
3は、学生時代に管楽器を吹いていたんですが、全く自分が「吹いて」などいなかったと思い知らされた曲。普通、オーケストラは楽器を聴き分けられますが、シカゴ交響楽団は、音があり得ない完成度で溶け合う、異次元レベルの演奏です。
1. 「展覧会の絵」/ムソルグスキー
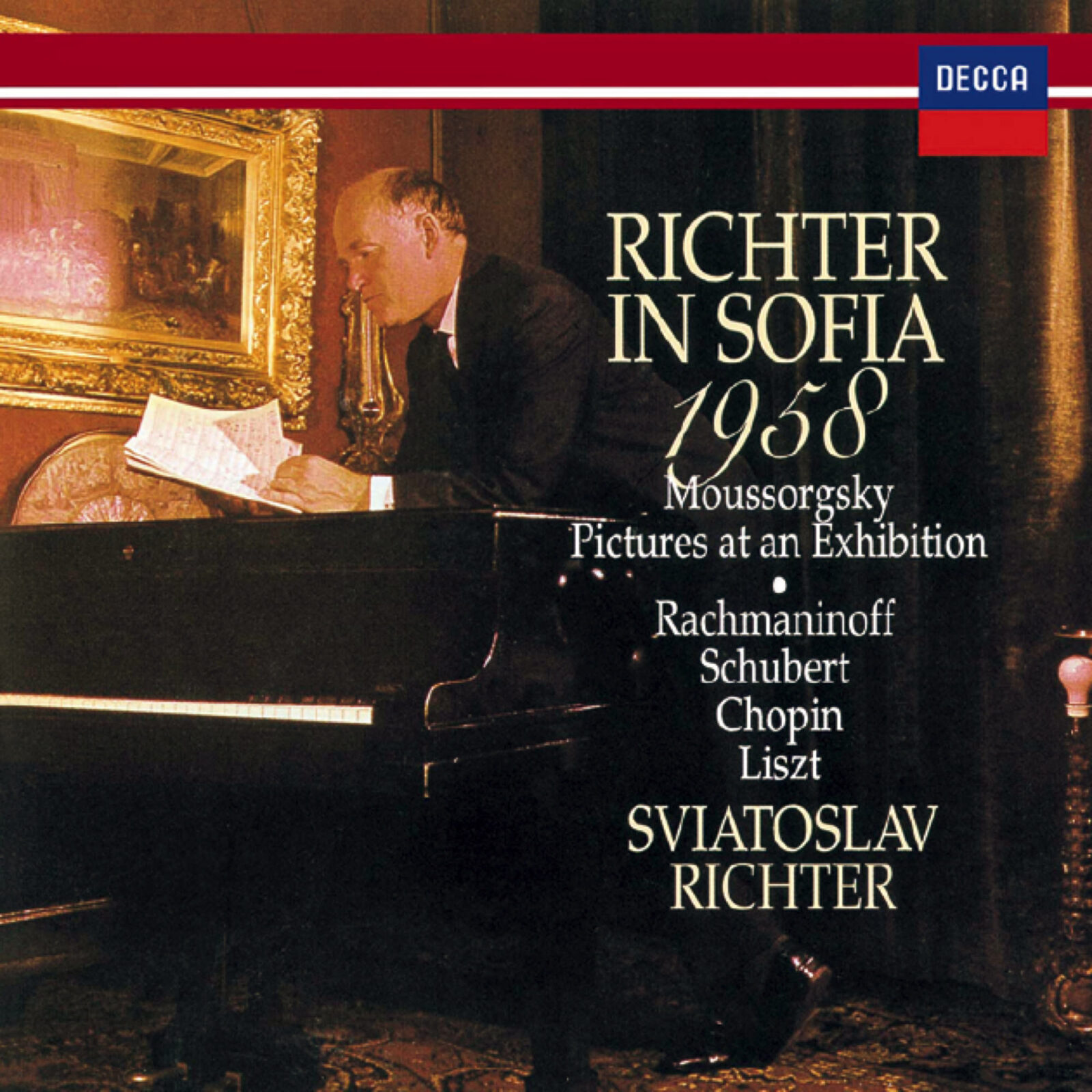
2. 「ツィガーヌ」/ラヴェル

3. 「管弦楽のための協奏曲 Sz.116」/バルトーク