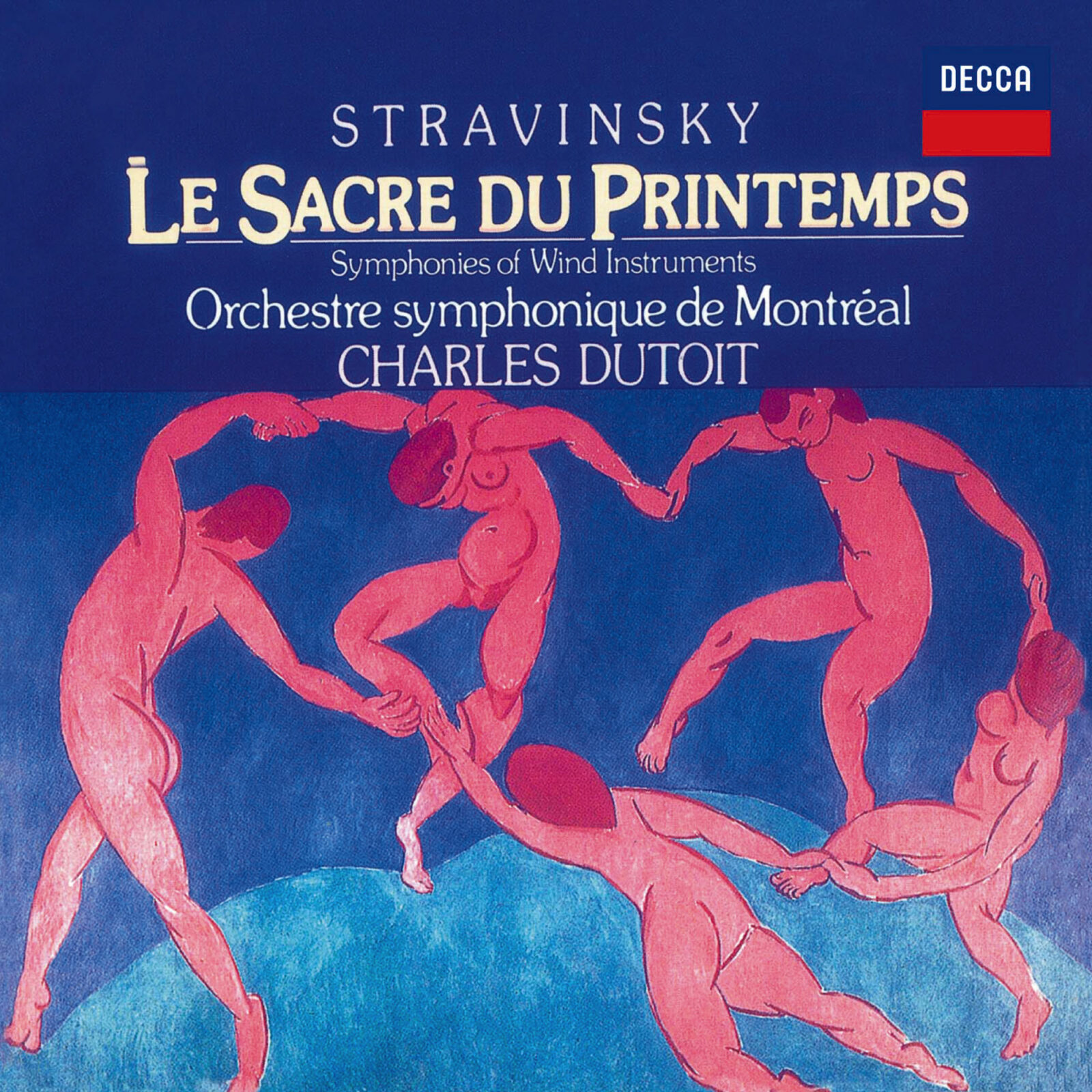サンプリングも炎上商法も?
始まりはクラシック音楽にあった!
クラシックってとっつきにくいですが、ちまたで流れるポップスの源流を辿るとクラシックに行き着くことが多いんです。1は、「現代音楽って変でしょ?」という文脈で紹介されがちな「無音」の曲。けれども、楽器音や歌声を構成したものだけが音楽ではないと示した画期的な作品で、ミュジーク・コンクレートの概念と同期しながらサンプリング文化に影響を与えました。
2は同じモチーフを840回繰り返すピアノ曲。サティは生活空間を彩るための音楽=「家具の音楽」を初めて提唱した人物でもあり、本作も「聴き流す音楽」として設計されていたなら、Lo-Fi Hip-Hopの、そして、同一構造の繰り返しとしてはミニマルミュージックの源流かも?
3は格式ある「バレエ」でありながらも、そのアバンギャルドさにパリでの初演は大混乱。バレエ団はこの炎上を予測し、客席にサクラを仕込んでいたとの噂も。「炎上商法」の原点もクラシックにありました(笑)。
1. 「4分33秒」/ジョン・ケージ
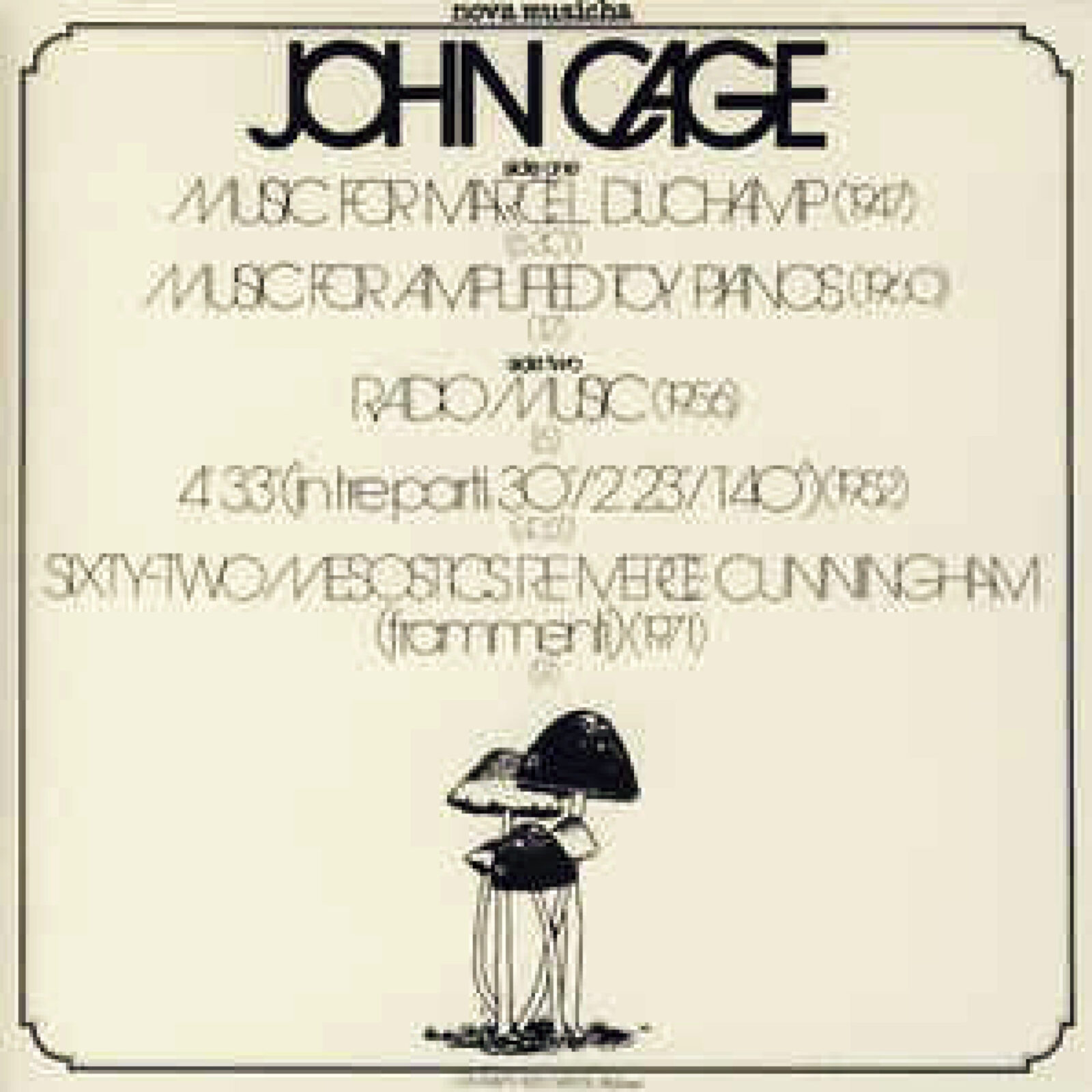
2. 「ヴェクサシオン」/サティ
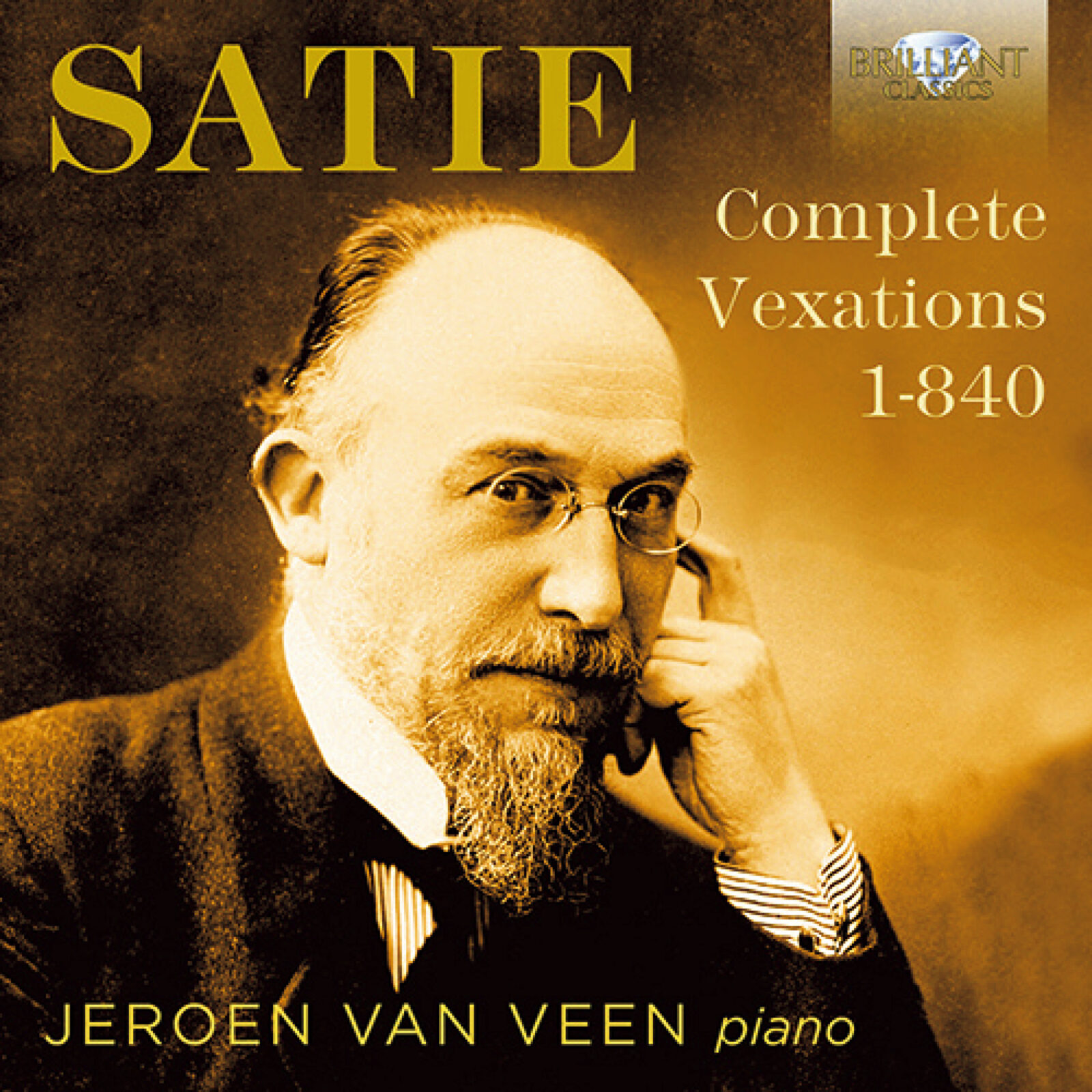
3. 「春の祭典」/ストラヴィンスキー