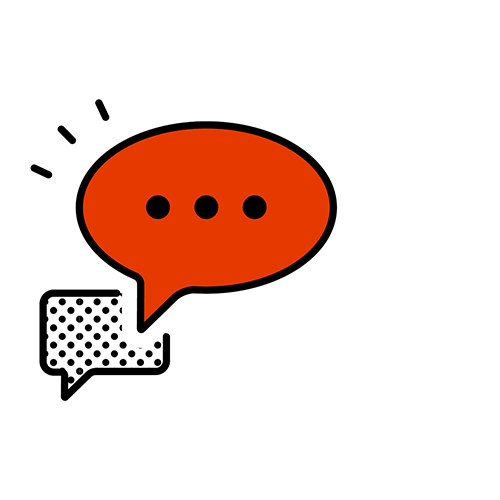今年、小説を本屋さんで買った人いますか?
去年、都内の某大学に、「SNS時代の作家」という大掴みなテーマの授業に、ゲストとして呼ばれた。八十人の大学生の前に立ち、教授の「ではよろしくお願いします」というこれまた大掴みなフリで、授業は始まった。
始まったはいいが、僕はまさかのノープランだったので、いきなり無言になってしまう。すると、助け舟を出すように、一番前に座っていた女性が挙手をし、僕に質問をしてくれた。「小説家って食べていけるんですか?」と。
一瞬笑いが起き、教室はすぐに静まりかえった。「えっと、今年、小説かエッセイを本屋さんで買った人いらっしゃいますか?手を挙げてもらっていいですか」と質問をしてみた。先ほどよりもさらに静まりかえる教室。教授がたまりかねて、「おいおい、お前らマスコミ志望だよな~」と笑いながら、「すいません、本当」と僕に謝る。
そのとき、教室の一番後ろに座っていた女性が恐る恐る手を挙げた。「あの、漫画なんですけど、小説が原作だった場合、小説にカウントされますか?」と質問する。遠足時の「バナナはお菓子に入りますか?」に匹敵する質問だった。
「それは漫画ですね」と僕は即答する。「あ、そうですよね……」。彼女はそう言って、押し黙った。そして誰もいなくなった。いや、教室には八十人いた。いるにはいたが、誰も小説もエッセイも買っていない八十人だった。今日、ゲストで僕が来ると決まっていた場合、なんとなくでも興味があったら、一冊や二冊、読んでみようかと思うものじゃないだろうか?高望みしすぎだろうか?
「小説家で食べていくのは、これくらい大変です」と僕は、質問をしてくれた女性に回答した。そしてまた温度が下がったんじゃないかと思うほどの静けさが、教室を支配する。
その空気を払拭するかのように、「すいませーん!」と教室の隅の席に座っていた赤い髪の男性が手を挙げてくれた。僕はすがるように「はい、なんでしょう?」と満面の作り笑いで訊く。「YOASOBIに会ったことありますか?」と男性が発すると、今日一番の笑いが教室に起きる。教授が「静かにしろ、静かに」と場を鎮めようとする。僕は「ないです」とだけ短く答えた。男性が、「会ったらサインもらってくださ~い」と言う。もう一度爆笑が起きた。
その日の夜、僕は新宿の某飲み屋にいた。知人の作家と担当の編集者の三人でウダウダと日頃の鬱憤も肴にハイボールを飲んでいた。昼間あった大学での出来事をよっぽど最初に言おうかと思ったが、どうにも酒が不味くなりそうで言いそびれてしまう。
酔いが少々回ってきたところで、編集者がおもむろにとある文芸誌を鞄から取り出し、「この雑誌のこの小説読みました?つまんなかったな~」と、とある作家の文芸誌に寄稿した小説の内容がいかにダメだったかを話し始める。重ねるように、知人の作家が「この作家を載せなきゃいけないなんて、この雑誌もヤキが回ったな」と揶揄する。
その言葉を聞いて僕は心臓あたりがズキンとした。僕も最初に文芸誌に載ったとき、ツイッターのリプライで「お前が載ってるから買うのやめた。あの文芸誌も底が抜けたな」と、ほぼ同じ言葉でディスられたことがあった。どこかの夜に、どこかの酒場で、きっと僕もそうやってディスられていたことだろう。
さらに編集者は最近僕が載った文芸誌を鞄から取り出し、あからさまに煽てるように、「まず目次!このラインナップに、この級数で名前が載ってることが、まず素晴らしいです!」と僕を持ち上げる。
僕はとりあえずの「ありがとうございます」をテーブルに置くように発してみた。そのとき脳裏にはクッキリと、「えっと、今年、小説かエッセイを本屋さんで買った人いらっしゃいますか?手を挙げてもらっていいですか」と質問をしたあとの、静まり返った教室の光景が浮かんでいた。