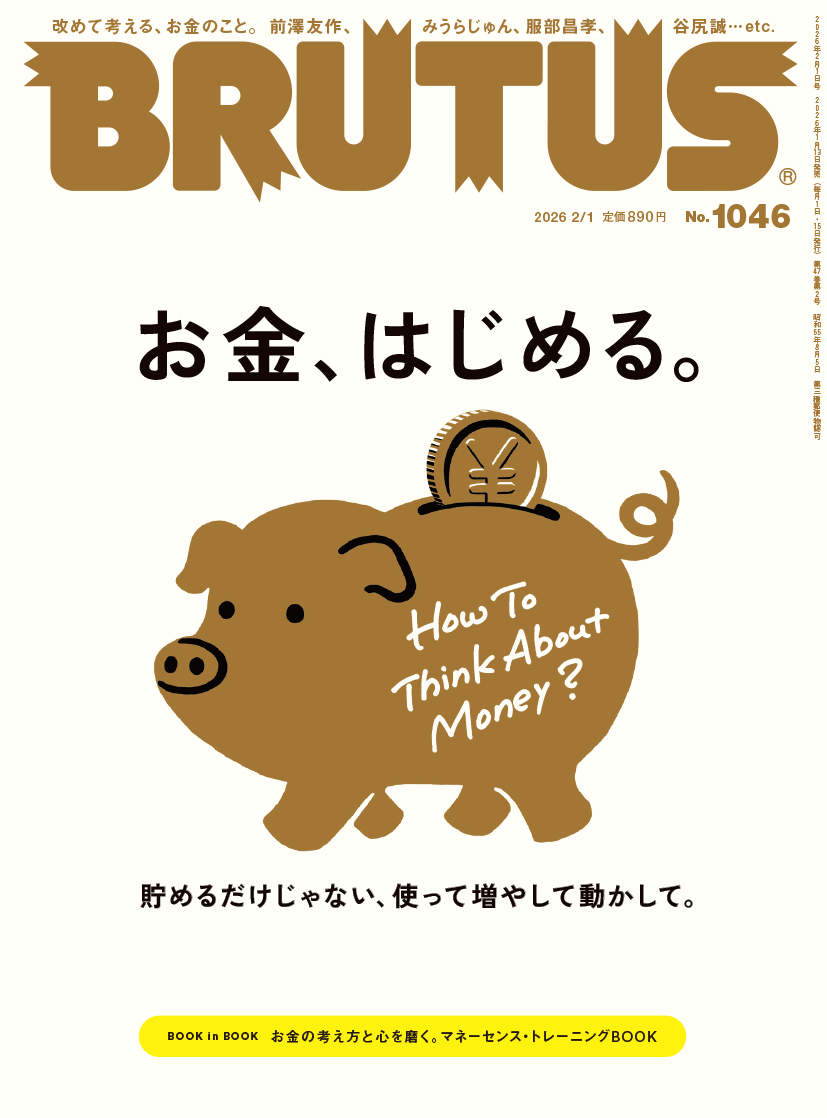ミルクマン斉藤とは何者なのか?
『1994-2024 ミルクマン斉藤レトロスペクティブ 京阪神エルマガジン社の映画評論集』が話題だ。書店の映画本のコーナーでもひときわ目を引くピンクの装丁、束(厚さ)も3cmはあろうかという存在感。いや、中身も外観に負けていない。ページによっては、目を凝らさないと読めないほどの小さな文字からなる圧倒的な情報量、600ページものボリュームの映画本。
この本は、昨年惜しくも他界したミルクマン斉藤が、エルマガジン社発行の『Meets Regional』『SAVVY』『月刊誌Lmagazine』に残した膨大な原稿をまとめたものだ。
生前のミルクマンを知る人なら、それが彼の人となりにどこか重なるイメージを持つかもしれない。
トークイベントで登壇する際のあのド派手なピンクのビッグスーツ。そして、一度話し始めるや、終了時間がくるまで、澱みなく延々と続く博覧強記(狂気?)のマシンガントーク。
それはミルクマンの名前を一躍有名にした、今や伝説となった1990年代の〈ピチカート・ファイヴ〉のライブにおけるVJも同様。曲に合わせて縦横無尽に繰り出される古今東西の映画のシーンのカットアップ。ポップにして過剰、過剰にしてポップ。それこそが、ミルクマンの身上だった。
そのVJをミルクマンとともに担当した〈groovisions〉の伊藤弘に、当時のことや、ミルクマンについて話を聞いた。
はじまりは京都の〈メトロ〉で
同じ1963年生まれで卯年というミルクマンと伊藤が出会ったのは1992年。
場所は京都。二人を結びつけたのは、ある映像作品だ。
「当時、自分は京都の大学で助手をしていたんだけど、一方で、〈メトロ〉のようなクラブで音楽イベントをやっていたんですよね。その頃はまだVJはしていなくて、DJだけやっていたかもしれない。その〈メトロ〉で、少し前に知り合っていた田中はん(FPMことDJの田中知之)と松山さん(ヘアサロン〈Romanza〉の店主・松山禎弘)が〈sound : impossible〉というチーム名で音楽イベントを立ち上げたんですけど、そこに遊びに行って知り合ったのが斉藤さん(ミルクマン)でした。
斉藤さんは、その頃すでに、いろんな映画をカットアップして繋いだ素材を作っていました。そのとき、二人で盛り上がったのが、イームズの短編映画『パワーズ・オブ・テン』だったんです。この人とは、何か合うなと思いましたね」
そして、二人は協働してVJを行うようになる。きっかけとなったのは、大阪で開催されたイベントだった。
「それから、田中はんの企画で、心斎橋のオオバコでイベントをやることになったんです。そこで、いよいよ斉藤さんとVJをやることになって。例の斉藤さんの作った映画のカットアップ素材の合間に、僕がコンピュータで作ったタイトルとかクレジットのモーション・グラフィックを入れるようなスタイルで。動くタイポグラフィのような映像は、その頃から制作していたんです。大学の機材を使いまくって(笑)、二人ともソール・バスが好きだったから、あんなイメージで作っていました」
そのイベントにゲストで出演していたのが、〈ピチカート・ファィヴ〉の小西康陽。
小西との出会いが、二人のその後の運命を決める。
そして〈groovisions〉の誕生
「小西さんが僕らのVJを観て気に入ってくれたみたいなんですよ。それでお声が掛かって、93年から〈ピチカート〉のライブのVJを担当することになったんです。それから結局、2001年の解散まで毎年やっていましたね。
途中からは〈groovisions〉の名義で活動するようになりました。その名付け親も小西さん。後に、僕の教え子たちもデザイナーとして加わって、97年に拠点を東京に移すんですけど、関西に残った斉藤さんがメンバーとして居続けたのは、〈ピチカート〉のVJがあったからですね。そう、斉藤さんは、田中はんのグループだったはずなのに、なし崩し的にこちら側のチームに移籍する結果になってしまった(笑)」
〈ピチカート〉の演奏と連動した〈groovisions〉による、まさにグルーヴィーでクールな映像は、当時観るものの度肝を抜いた。
その頃から、他のアーティストのライブやクラブイベントでもVJは増えていたが、特に、斉藤が編集した映像は、映画に対する該博な知識がなければできないもので、他の追随を許さなかった。
斉藤は、〈ピチカート〉の仕事と並行して、映画評論家としても活動するようになる。
底知れぬ映画への知識とエネルギー
「斉藤さんの映画の知識は、とにかく底が知れないというか。まあ、究極の『オタク』ともいえるんですけど(笑)、後年、うちの事務所が京都に出した〈三三屋〉という店で、斉藤さんに映画についてのトークライブをやってもらうようになるんですけど、放っておくと、4時間も5時間も平気で喋り続けてしまう(笑)、そんなとめどない過剰なところが、斉藤さん個人や作品にもあった。〈ピチカート〉の映像なんかはそのいい例だったと思います。
一度、田中はんとも話したことがあったんですけど斉藤さんの映像は凄まじいけど、そのままだと収まりきらないというか収拾がつかなくなるんじゃないかって。だからこそ“フレーミング”や“パッケージング”が必要で、そこが奇跡的にうまくいったのがピチカートの仕事だと思っています。カッコよくもお洒落にも見えてくるというか・・・・それは、映像やトークもだけど、彼の書く文章にも言えるんじゃないかな」
残念ながら、今その当時のVJを再現することは難しいが、ミルクマンの映画に対する知識や熱量は、今回の本でも十分感じることができるはずだ。
「この本も凄いボリュームだし、情報も詰まりまくっている。本気で読みこなそうと思うと覚悟が要りますよね。生半可な知識では対抗できない。でも、斉藤さんのトークと一緒で、ちょっと話を聞く分には、オモロい関西のおっちゃんの話を聞いているみたいなところがあったりもする(笑)。
僕らは今回カバー周りしかやってないんだけど、本の中身にもそんな風に入ってもらえるように、ミルクマンのあのピンクのスーツのようなポップなデザインにしたんです。本屋の映画本コーナーだと、ひときわ存在感も出るしね。だから、中身は、読みたいところから気軽にパラパラ読んでいったら良いんじゃないかな。もちろん、腕に覚えのある人は、斉藤さんの映画沼にずぶずぶハマっていってほしいですね(笑)」