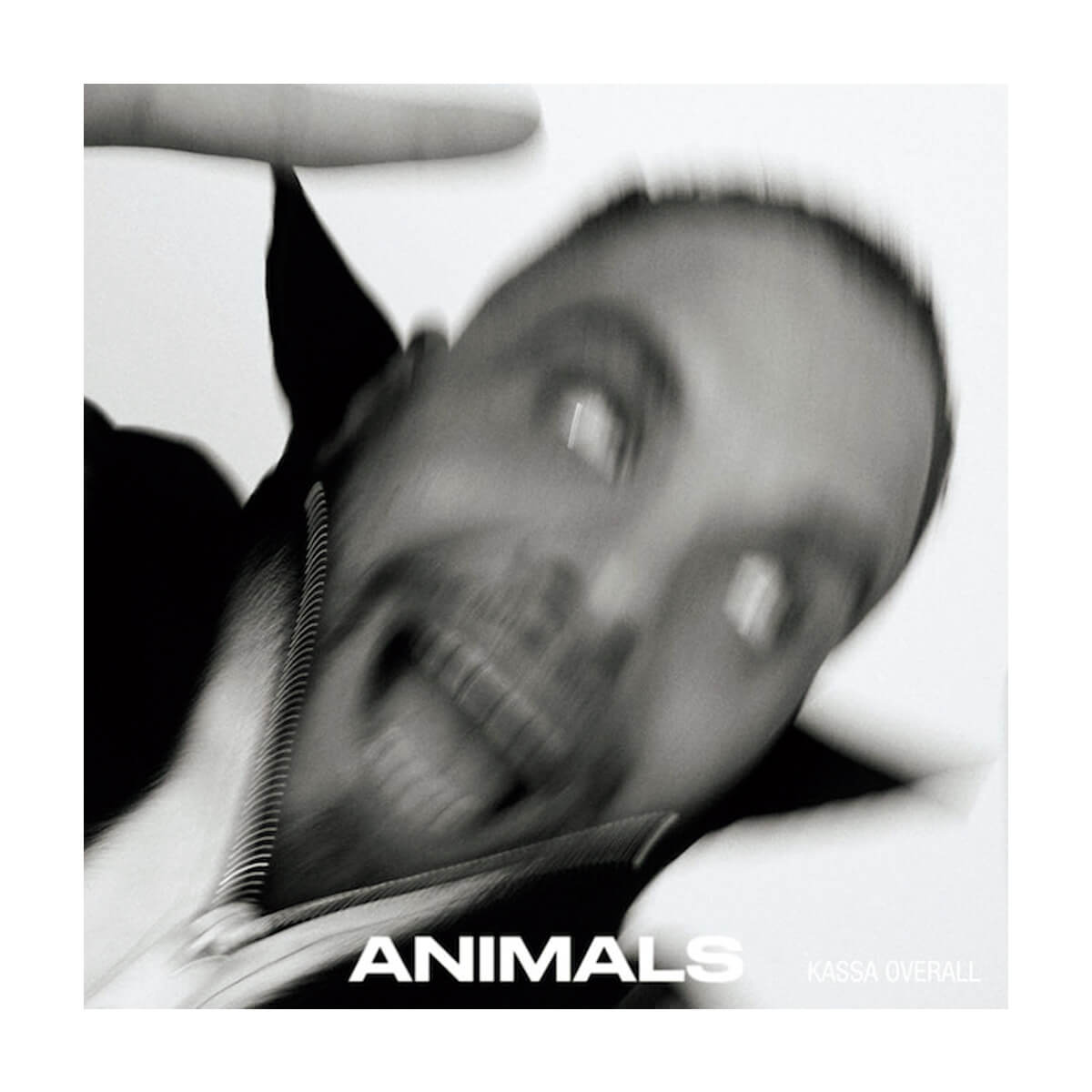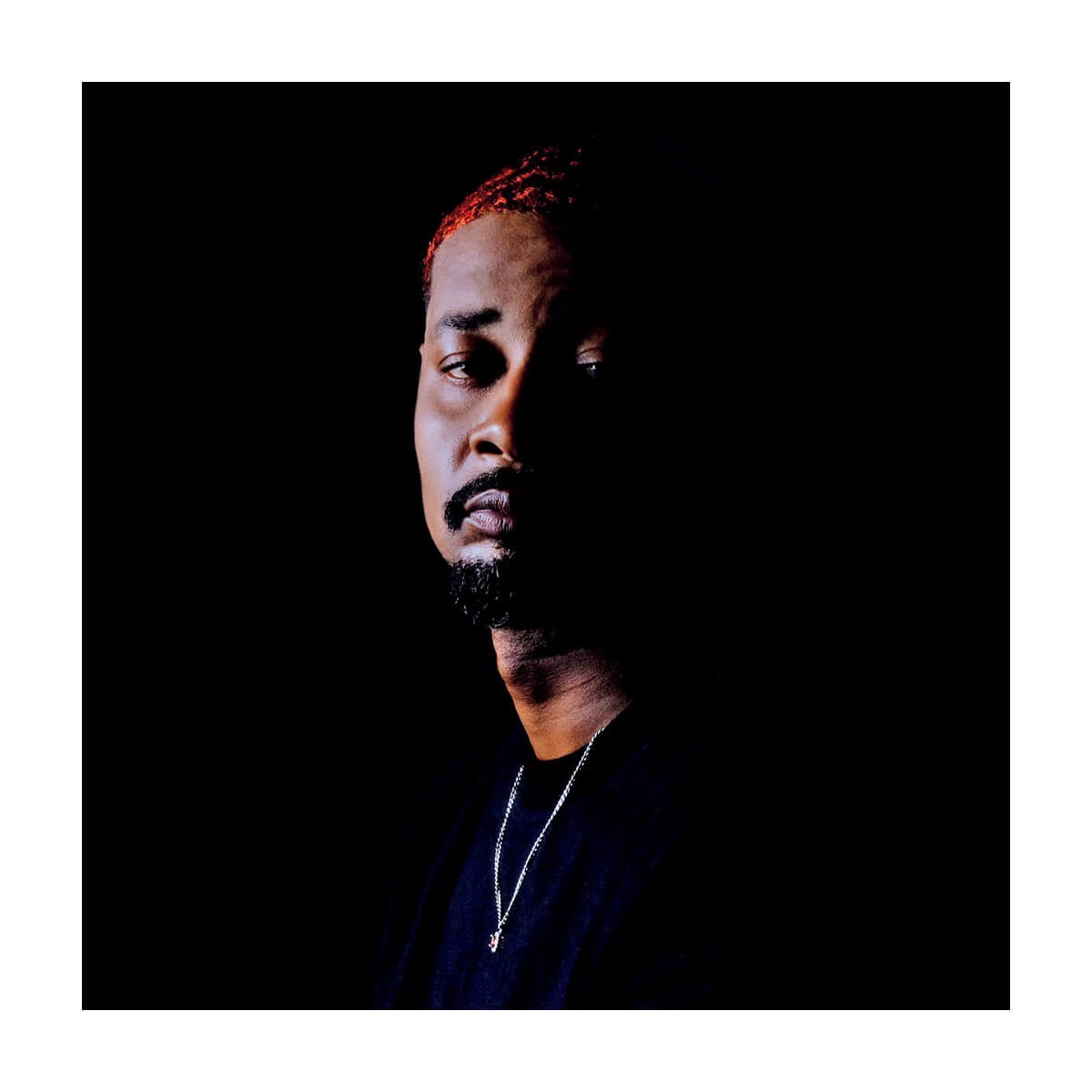新作『Neon Chapter』で、生演奏とテクノロジーを融合させ、新たな表現の領域に突入したピアニストのBIGYUKI。そんな求道的な姿勢に、テクノロジーと音楽を発展させてきた真鍋大度も共鳴している。
真鍋大度
古くはエレクトリック楽器を導入したマイルス・デイヴィス『Bitches Brew』(1970年)などをはじめ、シンセサイザーとスクラッチが印象的なハービー・ハンコックの「Rockit」(83年)など。ジャズミュージシャンは、新しいテクノロジーを取り入れますよね。
BIGYUKI
自分にとって、ジャズは血と汗のにおいがある肉体的な音楽。同時に、音楽家は常に表現の幅を広げることを考えている。肉体性を維持しながらも、やっぱり新しい技術は気になっちゃうんですよね。
真鍋
現在、AI技術の処理のスピードが、どんどん速くなっていて、2014年はリアルタイム生成AI元年といわれています。これまで1分くらいかかっていたAIの処理が昨年末に0.1秒以下になりました。そして、今後面白くなりそうなのが、リアルタイムの先読み。
例えば、僕が少し話したら、続きはAIがしゃべってくれるような。YUKIさんがワンフレーズ弾くと、AIが先読みして続きを演奏してくれるシステムとか。ただし、それが面白い音楽になるかは、今のところ別の話ですけど。
YUKI
実は2022年に、エンジニア兼音楽家の徳井直生さんが開発したAIプラグイン「Neutone」と共演したんですよ。オレがステージで演奏を始めると、AIが事前のデータからトラックを生成し、生演奏とセッションする形でライブが進んでいったんです。口ずさんでいたビートが、エグいリズムに生まれ変わって(笑)。純粋に“こんな音楽、聴いたことがない”と思っちゃった。
真鍋
「Neutone」は、ドラムのリズムをピアノの音へ変換できたりして、面白いですよね。
未発達のテクノロジーから新しい音楽が生まれてくる
真鍋
ツールとしての利便性が上がると同時に、クリエイティブとは離れていくと思うんです。みんなが同じ方向を向きすぎると、独創性のレベルは下がるような気がして。
YUKI
コンピューターのプラグインも、ヴィンテージ楽器みたいに「前世代の方が良かった」とか(笑)。
真鍋
現在6世代目の画像生成AI「Midjourney」は、2世代目の方が面白いですからね。黎明期のテクノロジー楽器ほど、ユーザーが制作側の意図しない使い方をした結果、新しい音楽が生まれたりして。
YUKI
僕らの共通点の一つでもあるヒップホップの進化の過程でも、そんな事件がありますよね。
真鍋
J・ディラなんか、一般的なサンプラーを使っているけど、リズムの補正機能を使わずに打楽器を演奏するようにサンプラーを叩いた結果、もつれたビートが生まれ、徐々に定番化した。最初に出てきた時は、変わったグルーヴだなぁと思いましたが。DJのフォロワーが出てくるのは当然だけど、ジャズの演奏家まで、あの演奏方法を真似する人がいる。面白い現象ですね。
YUKI
そのもつれたようなビートの揺らぎが、違和感がありながらも、新鮮で気持ちのいいリズムとして受け入れられた。それをディラ周辺のミュージシャンたちが発展させ、新しいボキャブラリーになった。
真鍋
学者や評論家も魅せられたから、分析したんでしょう。学術的に体系化して、いつの間にかセオリーになったりするから面白い。
2人のライブで共演が決定。必要なのは技術?即興?
真鍋
YUKIさんが単独で演奏されるエレクトリックセットを聴きました。共通のバックグラウンドとして、ヒップホップの文脈が入ったら、面白いと思う。
YUKI
まずは、共通ルールを決めましょうか。テクノロジーの導入方法や、生演奏の割合など。それだけ決めれば、出たとこ勝負の方がハッピーアクシデントが起こりそう。
真鍋
あとは感覚の共有。ノサッジ・シングとの制作時など、一緒にレコードを聴いたり、話したりする時間の方が重要だったと思う。
YUKI
わかる!Qティップのスタジオへ行った時も、制作同様、一緒に映画を観たり、話したりする時間の方が長かったから(笑)。
真鍋
ヒップホップ好きには、たまらない話です(笑)。
それぞれが挑んできた音楽とテクノロジー


2人が考えたジャズの未来を感じさせる曲