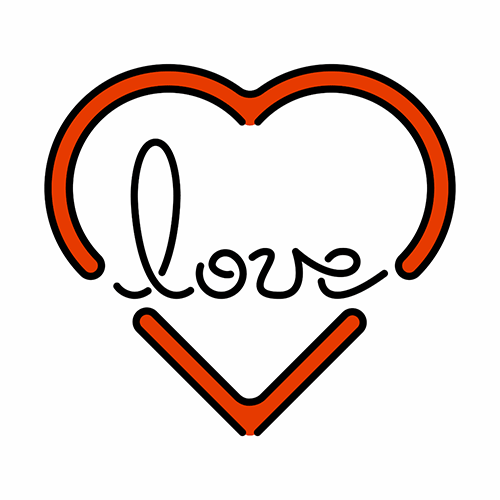澁澤龍彥
愛欲においては、
正常と異常の区別などない。
どんな“趣味”も
非難されてはならない。
澁澤龍彥は、日本人の恋愛における性を解放した人物と言えるかもしれない。「性本能は、単に繁殖や性交のためにあるのではない」と説き、どんなフェティシズムも容認すべきだと意見を吐く。性のあり方が、「人の数ほど多くの型がある」という言葉は、恋愛にも言える。「正常であるということは、同時に精神の貧困を示すこと」という哲学者の言葉を用いて、恋愛と性におけるあらゆる可能性を肯定する。
伊丹十三
「あたしのこと好き?」と
聞かれたら、
ありのままの気持ちを答える。
「さあ」とか、「普通」とか。
「女と話をするのは苦手である」から始まるエッセイには、男女の会話への嘆き節が書かれている。魅惑的にと一生懸命に語りかける女性が紋切り型へと陥って、「あたしのこと好き?」という、かの有名なセリフを吐く。取り繕うことなく素直に答える。「さあ」「普通」と答えていると、「ねえ、あたしのことまだ普通?」と聞かれるようになるという。「普通?」と聞かれたら「いいや。別に」と答えればいい。
坂口安吾
恋は幻なんていう真実は、
忘れてしまえ。
恋愛は、人生の花なのだから。
「ほんとうのことというものは、ほんとうすぎるから、私はきらいだ」と記した安吾。恋愛は所詮、「必ず亡び、さめるものだ」という「ほんとう」のことを、大人たちは知っている。けれど、どんなに「恋愛がバカげて」いても、「愚かな一生において、バカは最も尊いもの」。恋は幻という真実を忘れ、バカになれと説く。なぜなら「恋愛は、人生の花であり」「いかに退屈であろうとも、このほかに花はない」から。
吉行淳之介
何倍も収入が多い女性でも
すべて自分で払うこと。
吉行淳之介のようなモテ作家も、「男が払う」という常識を守っていた。いや、当たり前とされる作法を守るからこそ、モテる男だったのか。女優・宮城まり子と逢瀬を重ねた際、あるとき金がなくなってしまう。仕方なく金を借りるとき、いそいそと財布を開けて札束を渡そうとする女優から、1枚だけ紙幣を借りて、残りは彼女に戻した。男の作法は、仕方なく破るときに、その本性が透けて見えるのだろう。
山口瞳
急に別れてはいけない。
相手の女が、
すこしずつ悟るように。
師である文学者・高橋義孝の言葉を引いて、女との別れ方の作法について山口瞳は言う。少しずつ離れることによって「相手の誇りや虚栄心を傷つけない」ことが必要だと。さもなくば「女は簡単に死ぬ」あるいは「簡単に殺す」と。「女はこわい。特に美女はこわい」からこそ、女性から嫌いになったと思い込ませるような別れ方が望ましい。そして「ふりむかず、逡巡することなく」別れるのが、エチケット。
池波正太郎
浮気は、あくまで
浮気でとどめること。
30前に結婚し、40代で妻のほかに女ができることが少なくないという前提で、池波先生は浮気について語る。問題は、浮気相手が恋人になり、「女房に張り合う」こと。だから「もし浮気のテクニックというものがあるとするなら、それは、『あくまで浮気にとどめる……』ということ」。浮気が本気になり、男が苦しむ。すると当然、仕事にも影響してくる。いつの時代も「男の運を落とすのは、女」なのか。
北方謙三
“一応の恋”は何千回とあるが、
“ほんとうの恋”は、
三度か四度。悩むなら
“ほんとうの恋”で悩め。
伝説の人生相談には多くの恋愛に関する悩みが寄せられたが、その返答は毎回、一刀両断。なぜなら、ほとんどが“一応の恋”に関する質問だから。「好きになった。それが恋ではない」。その先にある“ほんとうの恋”は、自分で感じ、心を震わせるもの。人生に3度か4度だけの“ほんとうの恋”に出会ったとき、初めて人生を賭して悩み抜け。それが、モテない男に「ソープへ行け!」と答える男の真意だった。
野坂昭如
男女の色ごとについて
とやかくいうのは
もう止めようじゃないか。
女にモテないという自覚を持つ野坂昭如だが、女性に対するガッツは失っていない。男のだらしなさを問うたエッセイでは、「一夫一婦制の中に収まりかえってなけりゃ人間じゃないみたいな、風潮は文化を衰退せしめる」と記している。もう「とやかくいうのは止めようじゃないか」。誰の目も気にすることなく、自由に恋愛すればいい。ちなみに、このエッセイのタイトルは、「老いてなお色」。さすがの貫禄。