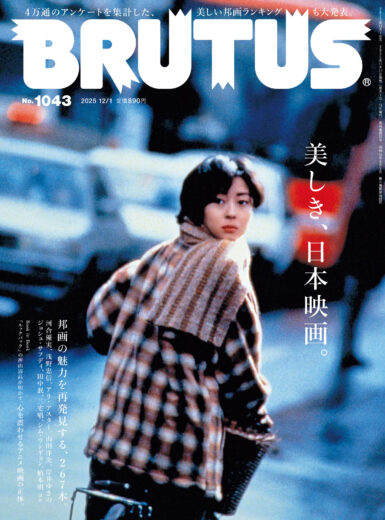無償の思いやりで助け合う。強い絆が描かれた「愛って、ケア」な映画20選
近年注目されるケアという概念は、今最も重要な愛のカタチの一つと言えるだろう。介護、共助、連帯……。自助自立を求める社会からこぼれ落ちた者たちが、あらゆる“違い”を乗り越えて、無償の思いやりによって助け合う。そんな強い絆が描かれた物語。
illustration: Yoshimi Hatori / text: Keisuke Kagiwada
実は身分を超えたケアの連携も描いていた名作西部劇
8人の男女が駅馬車に乗り合わせる。旅の途中で産気づいた妊婦にまず手を貸すのは、乗客から白眼視されていた娼婦だ。これを合図に、男たちは酒浸りの医者にコーヒーを飲ませて出産を手助けさせる。西部劇の傑作として知られる本作は、愛あるケアも描いているのだ。
ホームレスたちが築く、博愛主義的コミュニティ
ひょんなことからホームレスたちのコミュニティに身を寄せることになったトトは、激しい突風によってそこが全壊してもへこたれない。住人たちと笑顔で協力し合いながら以前よりも暮らしやすい住環境を築き、あらゆる人を受け入れる彼は、間違いなく博愛主義者だ。
諦めずに注がれた愛情が、不可能を可能にする
目が見えず耳が聞こえず言葉も話せないヘレン・ケラーと、彼女に言葉を教えようと尽力するサリヴァン先生をめぐる、有名な実話を基にした一作。ヘレンが指文字を理解する瞬間、諦めずに愛情を持ってケアすれば、不可能が可能になることもあるのだと思い知るだろう。
慈愛が恋心に変わる時、恐ろしい悲劇が起こる
南北戦争末期の南部。自給自足の暮らしを行う男子禁制の女学院に、北軍の負傷兵ジョンがやってくる。敵ながら看護することにした学院の女たちだったが、いつしか彼女たちの心に芽生えた男としてのジョンへの淡い恋慕が、惨劇を招く。ケア=愛は時に恐ろしい。
ケア労働がもたらす、息子とのかけがえない時間
子育てをはじめとするケア労働は、長らく女たちに任されてきた。本作はそれを妻が放棄したことで、初めて息子と真剣に向き合うことになる夫の物語。慣れないケア労働に苦戦する彼はしかし、それがいかに息子とのかけがえのない時間であるかも思い知るのだった。
戦争が終わる時、兵隊は敵を生かすためにこそ動く
第二次世界大戦下において、ドイツ軍と激戦を繰り広げるアメリカ軍の軍曹は、終戦を知った瞬間、瀕死の重傷を負った敵兵を、仲間とのチームワークによって助けようとする。国家の命令で人殺しをさせられる軍人も、職務から解放されれば愛を知る一人の人間なのだ。
自分らしく生きることを可能にする、女たちの友情
専業主婦のテルマは、夫の束縛から逃れて親友のルイーズとドライブに出かけるが、ある事件が起こり警察から追われる身に。天真爛漫なルイーズの力添えにより、「女性らしさ」の檻から解放され“本当の自分”に目覚めるテルマ。2人の友情の根底にあるのも愛あるケアだ。
差別や偏見を超えて築かれる、男たちの「兄弟愛」
HIVに感染した同性愛者のベケットは、病への偏見から職場を解雇される。職場に対して裁判を起こす彼に手を貸すのは、同性愛に差別的だった黒人弁護士だ。フィラデルフィアはギリシャ語で「兄弟愛」の意味。2人の関係を表現するのに、これほどふさわしい言葉もない。
2人の少年が弱点を補い合いながら“より強い1”になる
学習障害を抱える大柄の少年マックスと、難病を患う天才児ケヴィンが出会い、意気投合。マックスがケヴィンを肩車し、さまざまな場所へ出かける冒険の日々が始まる。弱点を補い合いながら苦難を乗り越える2人は、1+1が2ではなく“より強い1”なのだと示している。
世界をよくするためには、ケアの数珠つなぎが必要だ
「親切にされたら、別の3人に親切行為をする」。「もし君たちが世界を変えたいと思ったら、何をする?」という授業の課題で、一人の少年が提案したのは、そんなケアの数珠つなぎ的なアイデア。その愛のバトンは、彼の知らぬ間に受け継がれ、世界を少しだけ優しくする。
共に生きるだけではなく、別れを選ぶこともまた愛
大学生の恒夫が愛した女性は、足が不自由なジョゼ。恒夫が引きこもりがちな彼女を、スケートボードを装着した乳母車で外の世界へと連れ出すシーンは抜群に美しい。そんな2人が別れるのは、ジョゼが彼の負担になるのを恐れたから。共に生きるだけが愛ではないのだ。
見捨てられた高齢女性たちのシスターフッド
70歳になったカユは雪山に“姥(うば)捨て”されるが、死を意識した瞬間、彼女を救う者が現れる。実はその雪山には、これまで捨てられてきた老婆たちの共立共助の村が築かれていたのだ。一致団結して凶暴なヒグマと格闘するその姿は、凡百のシスターフッド映画を凌駕する迫力。
介護する夫を通して、愛の一筋縄ではいかなさを問う
ある日突然、年老いた音楽家の妻が発作を起こし、車椅子生活を余儀なくされる。認知症まで発症してしまい、彼女は死すら望むように。それでもなお精いっぱいの愛情を注いで自宅介護する夫が、最後に下す決断は果たして愛なのか?答えは観客の側に委ねられている。
津波の被害者たちが形成する「災害ユートピア」とは?
大規模災害が起こると、一時的に博愛的な共同体が形成されることがある。スマトラ島沖地震による津波に巻き込まれた人々を描く本作で散見される、自分もまた被災者なのにほかの被災者に手を貸す姿は、「災害ユートピア」とも呼ばれるこの現象を見事に描写している。
法律では定義することのできない、ある家族愛の形
同性愛カップルのルディとポールは、育児放棄されたダウン症の少年マルコを監護者として引き取る。しかし、家族のような絆を築く3人の前に立ちはだかるのは、法律の壁。ラストで怒りを露わにするルディが訴えるのは、法律によって愛が制限されることの愚かしさだ。
持たざる者たちの愛ある連帯が、世界を大きく動かす
サッチャー政権下の英国で、炭鉱労働者のストを同性愛者の団体が援助した実話を描く。炭鉱の代表が口にするこの言葉は、ケアの愛についての多くを物語る。「自分よりはるかに巨大な敵と闘っている時に、どこかで見知らぬ友が応援してると知るのは最高の気分です」
「みんな“普通”じゃない」からこそ助け合いが必要だ
難病のため変形した顔を持つオギーは学校でイジメに遭うが、家族や友人のサポートにより前向きになれる。しかし、そんな彼らも悩みを抱え、オギーに癒やされている。オギーがラストで得る気づきは、助け合いを考えるうえで重要だ。「みんな“普通”じゃない」
恋愛感情を超越した思いやりを「渡世の義理」と呼ぶ
「なぜ俺を助けるんだ」。運命のいたずらによって結ばれなかった男女の17年を綴る本作の終盤、車椅子に乗って現れた男は、介護してくれる女にこう問う。対する女の答えが不器用ながら伝えようとするのは、もはや恋心を超越した愛だ。いわく、「渡世の義理」よ。
「メハル」とはアイルランドに伝わる助け合い精神だ
誰かを助けることで自分も救われる。こうした助け合いの精神をアイルランド語で「メハル」と呼ぶ。アイルランドを舞台に、DV夫から娘を連れて逃げた女性が、役立たずな公共的支援に痺れを切らし、隣人たちの協力を得て自ら家を作る本作が描くのも、そんな隣人愛だ。
血縁がなくても家族としか表現できない関係がある
移民としてベルギーで暮らすロキタとトリは、姉弟のように振る舞っているものの、実は血がつながっていない。しかし、自分よりも相手を優先し、危険も辞さずにケアし合う2人の姿は、家族という運命共同体において、血のつながりよりも大切なことがあると教えてくれる。