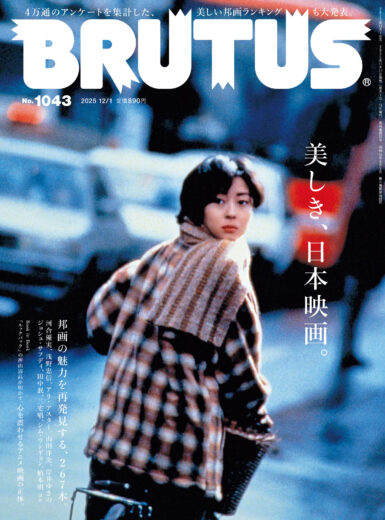人を殺してしまう人と、何があっても人を殺さない人の間にある“線”について想像してみます。それはかすかに震えるくらい細い糸なのか、それとも、台風の夜に急に牙をむく多摩川のように、渡ろうとすればあっけなく呑み込まれる断絶なのか。
夕方のニュースを見ながら考える。「カッとなって殺した」という報道が多い。「カッとなる」という短い言葉に、現場の温度も匂いも、ほとんど含まれていない。想像してみる。どうにも、カッとなって殺す、その様子は像を結ばない。
カッとなることのリアリティ
では、試しにカッとなって殺す、ということにリアリティを持たせるにはどうすればいいのか検討してみたい。それは、自分の中に静かに沈殿している記憶と、ゆっくりすり合わせていく作業だ。触れるたびに濁りが舞い上がる。マドラーでかき混ぜるように、底に溜まっているものを揺らすと、形にならない何かだけが、あとから浮いてくる。見覚えがない断片とともに。一度、深く息を吸い込んでみましょう。
小学校の頃の記憶を辿る。ひとりの女の子の輪郭だけが浮かんでくる。名前は思い出せません。でも、彼女がいつも薄い黄色のパーカーを着ていたことと、袖の部分が日焼けして色あせていたことは、はっきりと覚えています。今どきの言葉でいうところの「放置子」だったのだろう。そんな言葉は当時なかったけれど。育児放棄というほどではないにせよ、親の視線が彼女に届いていないことは、子どもでもわかった。学校が終わってから所在なさげに時間を過ごしていた。
彼女は若い女性の先生に懐いていて、放課後教室で長々と話しかけていた。特定の話題で盛り上がっているというより、とにかく先生を引き止めることが主な目的になっていて、会話の中身はほとんど空っぽだった。昨日食べたお菓子の話や、家の前を通った犬の話。あのゲームが欲しい。あそこに行ってみたい。先生は短く返事をしていた。そこには若干の気だるさが含まれていた。先生ならばもっと相手にしてあげてもいいのではないか、と思った。小学生の僕は、先生という存在をほとんど「聖職」のようにも感じていたから。
今ならわかる、あの若い先生はただ鬱陶しかったのだ。サービス残業の時間に、自分の体力を削られていると感じていたのだろう。でも、億劫だという気持ちを隠しきることができない(隠そうという気概も感じない)先生の若さを、なぜか僕も不愉快に感じていた。北欧猫のように「愛してほしい」という気持ちを全面に出して先生にまとわりつく彼女の声は、放物線を描いて教室から廊下へと届いていた。なんだろう、僕は彼女のことを、ずっと哀れだと思っていた。
彼女は分かりやすく“問題児”な一面もあった。授業中に立ち歩き、先生が叱っても、無言で飛び跳ねる。教室の床が鳴って、獣の声のように広がる。いま私立高校で教師として勤めている友人から聞いたことだが、学級崩壊というのは、ひとりの問題児を起点に起こることが多いらしい。未成熟な子どもは過敏に影響を受け、水面に波紋が広がるように、あっさりと教室は壊れていくそうだ。
でも、あのころ教室で飛び跳ねる彼女にはその影響力を持っていなかった。そう、彼女は模倣品だったのだと思う。飛び跳ねるときも、机を蹴るときも、本当に腹を立てているようには見えなかった。足が床を叩く音。でも、彼女の目の奥は静かだった。跳ねるたびに、髪が遅れて揺れた。髪は油分を含んでいて、髪の毛は常に束になって動いていた。その揺れは、舞台の稽古のようにも見えた。本物の怒りにしか人はついていかないのか。彼女の様子よりも、冷ややかな周りの眼差しの方が強く残っている。子どもの目は、大人のそれよりも詳らかで厳しい。
彼女のことを僕は好きでも嫌いでもなかった。クラスメイトたちは彼女に悪口をぶつけ、陰口も言った。ただ、悪口を言うことすらも、彼女が無理やり作っている物語に乗せられてしまっているようで、それが嫌だったのかもしれない。彼女の息は臭かった。なんかそういうどうでもいいことを覚えている。
その日、僕は喪服を着ていた。黒いズボンに白いシャツ、ネクタイまで締められて。周りの子どもたちのカラフルな服のなかで、異物として浮いていた。学校終わりにそのまま親が迎えにきて、葬式に行くという段取りになっていた。親戚の葬式だった。子どもは知らない人の葬式に行かないといけないことがあるんだな、大人になりたいな、葬式を選べるから、と思っていたけど、大人の方がいく葬式は選べない。それは大人にならないとわからなかった。子どもの僕と現在の僕は、連綿と続いているようでもあり、断絶してもいる。彼女は僕の格好を見て聞いてきた。
「なんでそんな格好しているの?」
僕は短く「葬式がある」と答えた。彼女の方をみると、口を少し開けたまま、舌で上の歯の裏を押していた。押すたびに、舌先が小さくのぞく。そのとき、黒目の奥がゆっくり動いたのを見た気がした。首をかしげて言った。
「死んじゃったの?」
そう、とだけ答えると、彼女は小さく息を吸い込んでから言った。
「それ、逆セックスだね」
語尾が軽く跳ねて、それに合わせるように机の天板に爪をコツコツと当てていた。僕は意味を聞こうとしたが、彼女は答えず、筆箱の中身をすべて机に並べ、また一つずつ戻していった。消しゴムをしまうときだけ、わずかに笑ったように見えた。その笑いは音を持たず、口元だけが遅れて動いていた。
その言葉の意味を理解するのに時間がかかった。セックス=生命を作り出す行為で、死ぬことがセックスの逆。保健の授業で学んだばかりの単語。禁忌のように封じられていたものを、改変して机に置かれた。胸の奥に錆びた釘が落ちて抜けなくなった。視界が揺れた。
あのとき、彼女はこの世にマイナスしか生まない存在だと思った。セックスという禁忌の単語を裏返しにして持ち出したときの、彼女の無邪気とも無感覚とも言える声音。そして、怒りとも諦めともつかない、殺意に似た感情を手にしていることに気づく。そのあと、彼女の声は耳の奥でしばらく反響していた。逆セックス。

次の日、窓外を眺めながら(彼女はしばしばそうしていた)「旅立ちの日に」を口ずさむ黄色い背中が近くに見えた。白い光の中に。強く押せば倒れるような距離感だった。でも、押すことはなかった。押さないという選択をしたことも忘れていた。
リアリティというのは、きっとそういう感覚のことなのだろう。理由も意味も、後から説明できなくても、確かにそこに触れたときの重みだけは消えない。フェイクだとか真実だとか、境界を決める以前に、その重みがあるかどうかだけでものごとは僕の中で生き残る。
「『カッとなって殺す』のリアリティ」に対する僕の中のひとつの答えは、「無自覚に見下していた人物から、舐められたと感じるような行動をされたあとに(一瞬虚を突かれて間があり)沸き立つ感情」ということになる。
フェイクドキュメンタリーを作るときも、こういう過去の記憶の重みを探している気がする。整合性よりも、釘のように胸に残る音や、背中を押すかどうかを迷う一瞬や、意味のわからない言葉の温度。それらが静かに積み重なり、形を持ったとき、フィクションはゆっくりと現実の輪郭を帯びる。
読者の皆さんの「カッとなって殺す」のリアリティもぜひ聞いてみたいです。皆さんの声は(もちろん)聞こえないですが、対話をするように、この連載を読んでいただけるととても嬉しいです。