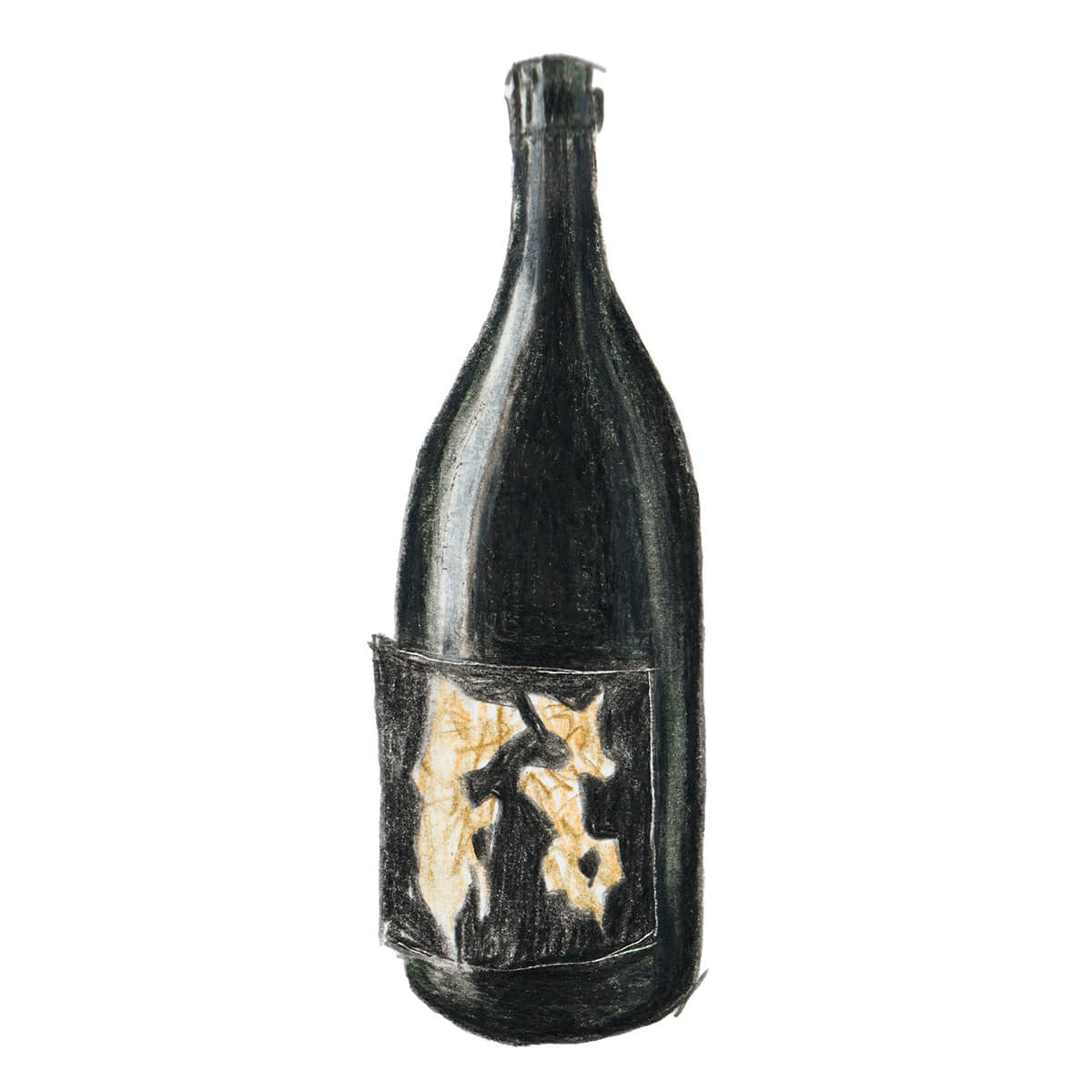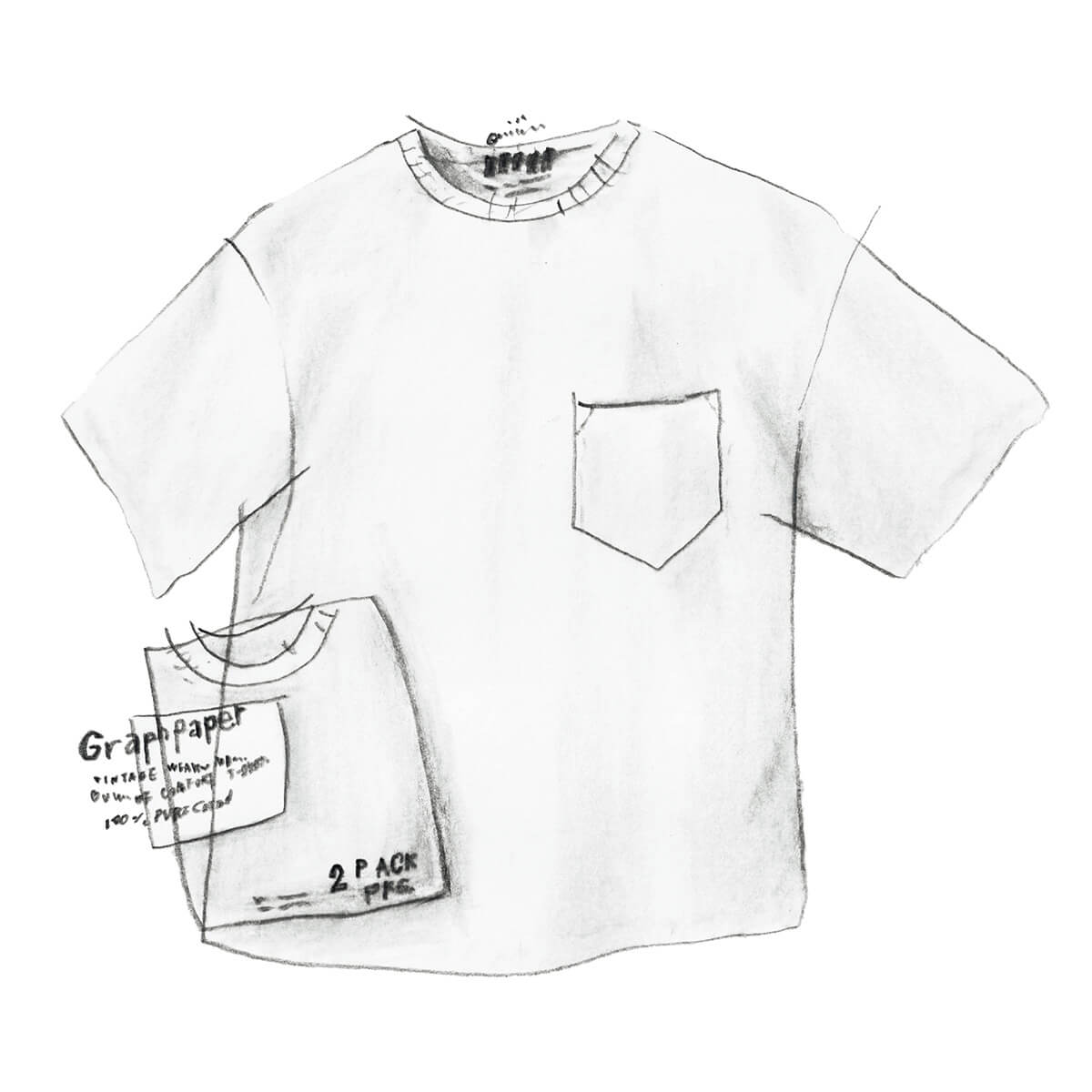センスとは、その人にしか作れない造形を追求できる力
宙吹きの技法で、透明度の高いガラスの作品を作っている蠣﨑(かきざき)マコトさん。アートのように印象的なガラスの照明や、底に“角”がある直線的なワイングラスなど、「まだ世の中にないもの」を生み出し続けているガラス作家だ。
そんな蠣﨑さんがものの良し悪しを見極めるときの基準にしているのが「その人にしかできないもの」であるかどうか。
「奇を衒(てら)うという話ではありません。例えばほかの人が作ろうとしても難しくてできなかった形を、研究を重ね技術を磨いて実現した。そういうものにセンスを感じます」
陶芸家では抽象画のような景色を宿す作風で知られる田淵太郎。香川の山奥に自力で窯を築いた田淵は、窯の炎や降り注ぐ灰によって白磁の表面に変化を生む、独自の「窯変(ようへん)白磁」に辿り着いた。
「こういう形や景色を生み出したい、と思い描く理想があり、それを実現するために誰とも似ていない技法に挑んでいるんです。岐阜県の打田翠さんが作る器も唯一無二。手びねりとは思えないほどすっきりした仕上がりでありながら、手びねりだから表現できる柔らかな線や丸いふくらみを感じさせる。相反する形が両立しています」
さまざまな作風に挑戦するのではなく、一つのことを真摯に追求し続ける姿勢にも共感する。「木工作家の松村亮平さんが手がける〈ANTIPOEME〉もそう。1本脚のテーブルやフレームの細い椅子など、すっきり見せるギリギリを攻めているにもかかわらず、技術の高さによってまったく危うさを感じさせないのが素敵です」
蠣﨑さんはまた、背景に作り手の意志を感じるものにも惹かれると話す。フランス〈レ・フレール・スーリエ〉のナチュラルワインと出会って驚いたのは、ぼろきれの写真を使ったエチケットだ。
「そのぼろきれは、造り手のスーリエ兄弟が、コットンの下着を畑に埋めて数ヵ月後に掘り出したもの。“何十年も農薬を使っていないウチの畑には、こんなに微生物がいる”という証しなんです」
こういうセンスを身につけるためには、発信することが大切だと蠣﨑さんは言う。自分の中にあるものを選んで練ってアウトプットすることで、考えや言葉も洗練され、センスが構築される。
「発信とは世の中に見てもらうこと。僕で言えば、新作を作り企画展を開くことですね。さまざまなセンスを持つ人に見られ、時に厳しい声を聞くことで、気づかされることがあるし、世の中にないものが作れるようになるんです」