「『MOTHER4』は出てほしいよっていう気持ちは、僕の中にもあるんです」
糸井
せっかく岩田さんに会うんだったら、『MOTHER4』の話をしたらどうですかって、うちの事務所の永田くんが言うんだよ。
岩田
(笑)。
永田
すいません。
糸井
でね、もちろん僕は言ったんだよ。「いや、キミも知ってるように『MOTHER4』は出ないよ」って。そしたら、「糸井さんがいまの言葉として改めて“出ない”って言うだけでもファンはうれしいです」って言うからさ。
岩田
ファンとしての提案ですね。
永田
すいません。
糸井
まったく!忙しい社長2人をつかまえて、この話をしろ、なんて指示するわけだからね!
永田
すいません。
糸井
不愉快だ!帰る!
永田
いま来たばっかりですよ。
岩田
ははははは。
糸井
で、真面目な話ですけどね、その話を聞いて、あ、そういえばって思ったんですよ。あの、最近『MOTHER』というゲームを出してよかったなって、しみじみ思うようになってきたんです。
岩田
はい。
糸井
僕は『MOTHER4』は出さないし、『MOTHER』はもう終わってるんです。だけど3つの『MOTHER』を出した自分に対しては、いまごろになって感謝し始めているんですよ。だから、岩田さんと会って、その気持ちについて話してみようかなって。
もちろん岩田さんは、ゲームを出すとか出さないとかいうことに関して責任のある立場にいるから、無理に何かの返事をする必要はないです。ただ、あのゲームについて、いまの気持ちで改めて2人で話せたら、『MOTHER4』は出ないんですか?っていうファンからの真っすぐな質問に対して、いまの答え方ができるかもしれないと思って。
岩田
わかりました。糸井さんのその気持ちの変化について、もう少し詳しく教えてもらえますか?
糸井
はい。あの、昔から「僕は『MOTHER』で育った」って言ってくれる人、多いでしょう。
岩田
すごく多いですね。
糸井
うん。で、ありがたいなぁと思ってたんだけど、最近ね、ありがたいっていうだけじゃなくて、そういう子たちのことを好きになってる自分に気づいたんですよ。
岩田
あー、面白いですね。「ありがたい」と「好き」は、近いかもしれないけど違いますよね。
糸井
違うんですよ。ありがたいと思うっていうのは、やっぱり、どんな表現も製品も全部そうだと思うけど、最後の最後はお客さんに仕上げてもらうわけじゃないですか。歯磨き粉だって、最後にお客さんがそれで磨いてくれるから終われるわけでね。だから、ゲームをやってくれたっていうだけで、もう、「ありがたい」わけです。
岩田
そうですよね。ゲームを遊ぶのって、実はものすごくエネルギーを消耗する仕事なので、そのものすごいエネルギーを費やすに値すると認めていただいたということに対して、まず、「なんとありがたいことか」と思いますよね。
糸井
そうそう。だから、いわば、僕がやりかけの仕事をそこに置いといたら、その後を……。
岩田
残りを完結させてくれた。
糸井
うん。バトンを持って走っていってくれた。で、駅伝やリレーと違って、いろんな方向に走っていいから面白いんです。山ん中走ってもいいし、湖まで行ってもいい。走るのって楽しいぞって声を出してもいいし、黙って走って、走る楽しさを心の中で噛み締めてもいい。いずれにしても、それは、バトンを渡したおじさんにはできないことなんですよ。しかも、その走りがまだ続いてる、なんてこともあるわけで。
岩田
こんなに時間が経っているのに。普通に考えれば、当時経験したことの大半は忘れられてしまっておかしくないのに、いまだにあのゲームのことを思い出して、語ってくれる。それに対して、ありがたいを超えて、その人のことを愛しく思えてくるという。
糸井
そうですね。あとね、あの『MOTHER』というゲームが、僕じゃなくて、他人が作ったゲームとしてあるとするじゃない?そうするとね、僕はきっと、あの感じが大好きだろうと思うのよ。
岩田
はい(笑)。
糸井
きっと、遊び手として大好きで、あれを好きだったというやつと会いたいと思うと思うんだよ。
岩田
あああ、なるほど。糸井さんは、そもそも、『MOTHER』というゲームの企画を任天堂に持ち込まれた時、作ってみたかったんですか。それとも、作ったもので遊んでみたかったんですか。
糸井
作ったもので遊んでみたかったに決まってるじゃないですか。
岩田
ここが糸井さんらしさの原点ですよ(笑)。例えば宮本(『マリオ』の生みの親である宮本茂)さんに同じことを聞いても、「遊んでみたかった」とは絶対言わない。そこには私、自信があります。
糸井
そうだろうなぁ。だって、宮本さんと僕は別の職業だもん。
岩田
別の職業の人だからこそ、糸井さんが『MOTHER』の企画を持ち込んだ時、宮本さんは新しさに感動する一方で、決定的に足らないものがあるということも感じられたんでしょうね。
糸井
そうですね。だから、それをシビアに指摘された時、僕は打ちのめされたんですよ。僕は自分が遊んでみたかったエキスに関してはたっぷり注ぎ込める自信があるけど、それ以外のことについては考えられないからね。でも、そうかといってセリフだけを担当すればいいかというと、それは絶対違うんだよ。
岩田
そうですね。
糸井
『MOTHER』というのは、ゲームじゃなくてシナリオなんだという言い方をする人がいるんです。でもそうじゃなくて、ゲームの形をしていないとあのシナリオは面白くないんだよ。そもそもそういうふうに作ってあるから。言葉だけじゃ面白くないし、遊び手としての僕が時々言ってる無茶なアイデアと絡み合って、ゲームになってるわけでね。
例えば、『2』の地底国で、主人公たちの姿をすごく小さくすることで世界の大きさを表現する、なんてことは、僕が現場で言い出してるわけなんですよ。で、そういうことを言い続けていると、今度はほかの人からもそういう企画が出るようになる。『MOTHER』って、そういう無茶の連鎖でできているようなところがあって。
岩田
そうですね。だから、例えば糸井さんが自宅からシナリオをメールで送ってくるだけでは、ああはならない。
糸井
絶対ならないんです。仕事場で、「なんか普通だなぁ」って言い続けてるからこそ、『3』の海底の酸素補給機みたいなものが生まれてくるわけで。
岩田
酸素補給機というと……。
永田
海底を進むイベントがあって、息が続かなくなるから、酸素を補給しなきゃいけないんですけど、その酸素補給機がなぜかオカマの人魚で、その人魚から口移しで酸素をもらうことになるんです。
岩田
ははははは。そうでした。
糸井
散々ボツを出したあとにそういう「ずるい!」みたいなものが出てくると、うれしいんだよ。
岩田
苦しめば苦しむほどユニークなものが生まれて、それこそが忘れられずに、ずっと残っていく。
糸井
残る。必ず残る。だから、ビッグアイデアっていうのは苦しみのあとに出てくるんですよね。で、そういうことを受け止めて、ニッコニコしてくれる遊び手がいると、僕にとっては鏡に思えるんですよ。その笑顔は自分の笑顔なんですよ。同じ遊び手として、その喜びは僕の喜びだよって思うから、お前、いいやつだなっていうか、好きだなって思うんです。
岩田
なるほど。
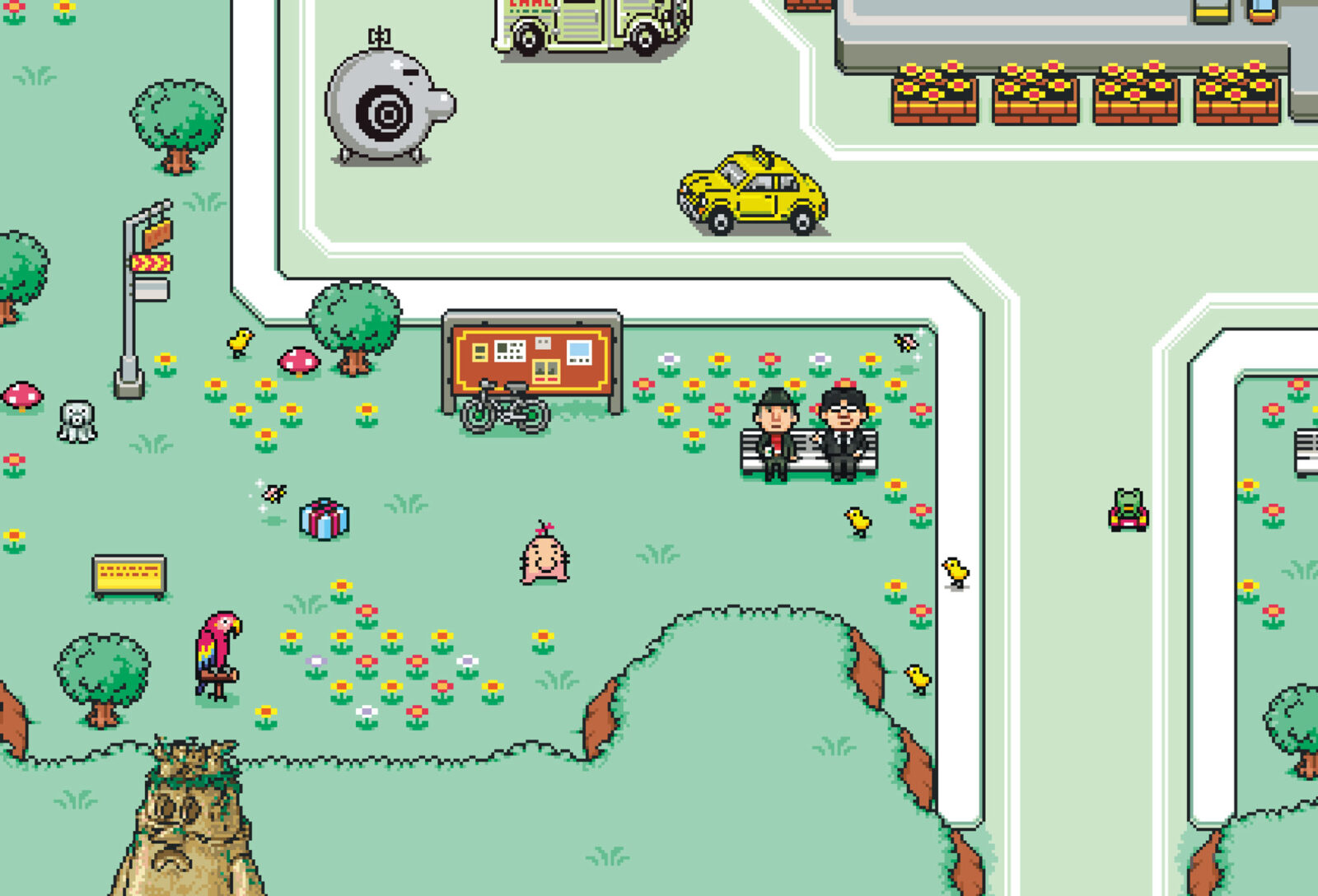
永田
岩田さんにお伺いしたいんですけど、いま言ったような「ユニークなもの」が、ゲームを作っている場からは出にくいというのは、なぜなんでしょうか?
岩田
やっぱりゲームをずっと作っている人って、ゲームを作る上での定石というものをたくさん経験するんですね。こういう時はこうするとうまくいくぞっていうことを、経験が多い人ほどたくさん知ってるわけです。で、その人たちは、目の前に解決しなきゃいけない問題があるとすると、まず、「こうやると解決できる」という手口が一つ見えてしまう、という場合、明らかに自分で解決できる手口が見えているのにそれ以外の手口を考えるっていうのは、実は相当難しいことで。
永田
うーん、なるほど。
岩田
例えば、同じ絵で2種類の見え方をする「だまし絵」ってありますよね。あれと同じで、1種類が先に見えてしまうと、ほかの絵がどうしても見えなくなってしまう。だから、なまじ解法が見えるだけに、変なことができない。
永田
それは、手を抜いたり、努力してないわけじゃなくて。
岩田
じゃなくて、ある答えをいったん見つけてしまうと頭の中でその回路がつながってうまく動いてしまうので、それ以外のもっといい方法、あるいは「変な」方法が見えなくなるんですよ。それはゲームで育ち、ゲームに詳しくて、ゲームを作りながらたくさんの問題を解決してきた人ほど、そういう状態に陥りやすいと思います。そして、その解決方法が定石であればあるほど、すでに過去に見たことがあるものだから、お客さんにとっては驚きがない。つまり、解決はするけど、普通。
糸井
知ってることなんだよね。
永田
はぁー。『MOTHER』以外に、『MOTHER』のようなゲームが生まれづらい理由が、一つわかった気がします。
岩田
だって、ゲームを作る人には、タコけしマシンは考えられないですよ。
糸井
ああ(笑)。タコけしマシンは、よく例に出されるね。
岩田
だって、それを言っちゃあおしまいでしょっていう。
永田
ご存じない方のために解説すると、道をタコが塞いでるんですよね。で、そこを通らないと、次の場所に行けないんです。
糸井
だってさ、タコで塞いでること自体が苦し紛れだからね。石で塞ぐのよ、普通は。
永田
うん(笑)。
岩田
うん(笑)。
糸井
でも、石じゃ面白くないからタコで塞いだの。で、それをどうやったら……。
岩田
どうやったら消せるのかっていう話ですよね(笑)。
永田
え~、どうやってそのタコを消すんでしたっけ?
糸井
タコけしマシンを使うんだ。
岩田
ははははは。
永田
ははははは。
糸井
タコけしマシンがあれば、世界のタコは全部消えてしまう。で、道を塞いでるタコを消したあと、どっかで売ってるタコ焼きの中のタコもなくなってるんだよ。「なんだこれ、タコが入ってないじゃないか」っていうところも、押さえてなきゃいけない。確か実際にそこまでは書かなかったけどね。そういうことを考えるのが、僕の趣味なんだよ。
岩田
よくわかります。
糸井
で、そういう僕の趣味は、変だったり笑わせたりっていうだけじゃなくてね。こっちの方が、いま、ゲームを作ってる人の中にない要素かもしれないけど、僕には、人を切なくさせたいっていう気持ちがけっこう強くあるんだよ。笑わせたいもあるし、喜ばせたいもあるんだけど、ちょっとどうしたらいいかわからない気持ちにさせてみたいっていう欲求が、これはゲームに限らず、いろんな仕事をする時に必ずあるんです。
岩田
それは、感動させたいでも泣かせたいでもなくて。
糸井
そう。「切なくさせたい」。
岩田
「切なくさせたい」っていう狙いで作られているものは、私は、ほぼほかに知らないです。
永田
そうですね。
糸井
それは僕のテーマみたいなものだから。『MOTHER』のセリフって、僕は全部、一文字一文字、しゃべって作るんです。それを誰かにタイピングしてもらって、しゃべった後で文字として目で確認する。『MOTHER3』の時は、永田くんと戸田(昭吾)くんにずっといてもらって、2人に最初のお客さんになってもらった。
で、僕は2人を切なくさせるために、ずっとワナを張ってるんです。笑わせたり、くだらないことを言ったり、カッコいいですねっていうセリフを作ったりね。で、その中に、どうだろう、48個の中に1個ぐらい「切ない」を入れるんです。で、2人に「どう?」って聞くわけ。
岩田
ああ(笑)。
永田
覚えています、その感じは。「どう?」って聞かれるとね、困るんです、僕も戸田さんも。だから、「いいから続けて」みたいな、ぶっきらぼうな返事をする。
糸井
そう。「切ない」がほんとにバーンと決まった時は、2人とも僕を邪険にするんだ(笑)。
岩田
もう物語を味わうモードになってるから、人間・糸井重里への敬意が消えていくんですね。
永田
そうです、そうです(笑)。
糸井
だって、その48個のうちの1個の「切ない」をやりたいがために、笑わせたりくだらないことを仕込んだりしているともいえるわけだからね。だから、シナリオだけでもダメだし、タコけしマシンだけでもダメなんだ。全部があって、本当に時々、脇役のちょっとしたセリフの中にでもいいから「切ない」がないと。
岩田
『MOTHER』にはならない。
糸井
そう。だから、普通のゲームの中にはあんまりないかもしれない。ピクサーの映画の中なんかにはちょっとあるんだよ。
岩田
ああ、ピクサーには確かに「切ない」がありますね。
永田
ピクサーの作品の中には、ポーキーがいますよ。
糸井
そうなんだよ。例えばプロレスとか見ててもね、ヒールの方が切ないし、クリエイティブなんだよ。ベビーフェイスは頓知がないんだよ。カウボーイがカウボーイハットを脱ぎました、みたいなことばっかりでさ。
岩田
はははははは。
永田
はははははは。
糸井
それに比べると、ヒールの方はさ、次から次にしょうもないことをやるじゃないか。毒霧を吹いたり、サーベルをなめたりさ。そっちの方が、見に行く理由なんだよ。
そこのところをね、『MOTHER』のファンは知らず知らずに気づいて愛してくれてる。うがった見方じゃなくて。だから、すごく普通の子から「ポーキーが好きでした」なんて言われると、たまんないですよね。

岩田
改めて、どうして『MOTHER』は、こんなに人の心に強く残ったと思いますか?
糸井
本気だからじゃないですか、僕が。
永田
でも、みんな本気ですよ。
糸井
いや、その本気と一緒にしないで(笑)。
岩田
でも、本気でゲームを作ってる人はたくさんいるんですよ。全員とは言わない。確かに全員とは言いません。でも、本気で作ってる人はほかに何人もいるのに、残り方というか、刺さり方がここまで特別なのはなぜか。
いま糸井さんがおっしゃった「切なさ」を表現した稀有なゲームであるというのは、一つの大きな要因ですが、それだけでは説明できない気がします。『MOTHER』の魅力って、要素を分解するだけでは語り尽くせない感じがあって。
糸井
ああ……。要素ではないところに、静かに流れているのは、子供のことですね。結局、うちの子はあのゲームをやらなかったんですけど、あれははっきりと、子供への手紙なんです。離婚中で、しょっちゅう会えなかった頃の、自分の子供への手紙。
岩田
なぜお父さんは、主人公と電話でつながっているのか。携帯電話のない時代ですからね。
永田
パパはいつも、冒険する主人公を、遠くから見ている。
糸井
そういうことだよね(笑)。
岩田
あと「2時間パパ」ですよ。
糸井
そうそう、それがあった。
永田
ゲームのプレーが2時間を超えると、パパから電話がかかってくるんですよね。「そろそろ休んだらどうか」って。
岩田
そういう仕様を入れるって聞いた時、私は仰天したんです。「何を考えてるんだ」って。だってせっかくゲームに夢中になってる人に、「休んだらどうか」って。
永田
でも、Wiiで岩田さんは同じような仕様を入れましたよね。
岩田
そうなんです(笑)。「2時間パパ」を入れようっていう糸井さんの考えは、どこかで私に乗り移って、Wiiに同じ方向性の仕様が入るんです。
永田
どのゲームをどれだけ遊んだか、というプレー時間が記録されるんですよね。しかも消せない。あの仕様は親からの視線ですよね。
糸井
だから、岩田さんも遊び手なんだよ、『MOTHER』の。
岩田
そうかもしれません(笑)。
永田
『MOTHER』は、タイトルが示すように、親から子への視線がずっと感じられるように思います。
岩田
「2時間パパ」も含めて、子供たちへのメッセージが。
糸井
うん。保護者からのものだよね。手も口も出さずに、遠くから、ただ見ている。それはある意味で親の理想の姿だと思う。
『長くつ下のピッピ』っていう物語が僕は好きでね、ピッピにはお父さんがいないんだ。船乗りなんだけど、行方がわからないというところから始まるの。でも、ピッピは力持ちで元気なんだ。お父さんがいないっていう悲しい物語に読み手を耽溺させるんじゃなくて、いないっていうことをただの事実として捉えていて、物語はどんどん進んでいく。そういうもんなんじゃないかな、実際もさ。だから、『MOTHER』の話に戻ると、『3』までの動機はあったんだなっていう気がするね。いまはもう、子供も大きくなっちゃったから。
永田
『MOTHER4』は……。
糸井
出てほしいよっていう気持ちは、僕の中にもあるんです。僕がやる必要がなくても、そういう気持ちはある。でももう、遠くから見てなきゃいけない子供はいないからね。もし『4』があるなら、お客さんになりたいな。
永田
逆に言うと、自分じゃない人たちで作ってもらっても。
糸井
うん。例えば、いいセリフのある芝居見てる時って、『4』だよ。本人にそのつもりなくても。僕が「このセリフ、たまんないね」って言ってる時は、作家の作った世界を僕が遊び手として完成させてるともいえるわけだからね。『MOTHER』をみんなが完成させてくれたようにさ。
だから、そういうゲームがあちこちにあればいいじゃない。ゲームの形じゃなくてもさ。ゲームの形でやりたいんです、って人はやってみれば。で、『血みどろ沼の逆襲』とかいう名前で作り始めて、「これはどう考えても『MOTHER4』っていう名前がいいんですけど」ってなったら、もしかしたら僕は「じゃあ、主人公に赤い帽子でも被せてリュック背負わせたらどうかね」って言うかもしれない。
岩田
どこかに鼻の大きい変な言葉をしゃべる人でも出してみたらどうかね、って(笑)。
糸井
そうそうそう(笑)。
永田
そしたら、セリフの一つくらい書かないでもないとか(笑)。
糸井
カメオ出演じゃなくて、カメオセリフね(笑)。だから、なんだろう、「君がやればいいのに」っていう人が現れることが一番嬉しいよね、きっとね。
岩田
実際に手を挙げる人が出てしまいそうな(笑)。
永田
岩田さんが、なにか質問を受けざるを得ない場所で、ひょいと手を挙げた人が、「『MOTHER4』は出るんでしょうか?」って言ったら、どうなさいますか?
岩田
いま、そう聞かれたら?
糸井
なんかの説明会とかでね。
岩田
……。
永田
……。
糸井
……。
岩田
……前の制作体制と同じ形で『MOTHER』が新作として生まれることはもうないと思いますと。
永田
……はい。
糸井
全部入ってますね、いまの岩田さんの言葉の中に。
岩田
ええ。
糸井
さすがです。だからね、最初に言った『MOTHER』を好きな人を好きになってきてるってことと同じ意味なんだけど、カッコよく言えばさ、「キミたちが生きてること自体が『MOTHER4』だよ」って、ほんとに思うんだよ。今日もしょうもないことを考えたり今日も切なかったり、今日も笑ったりしてる、そういうことがあのフィールドでやりたかったんだもん。……いい?これで。
永田
十分です、十分です。じゃあ、締めの言葉を。
糸井
ぽてんしゃる!
永田
ありがとうございました。
岩田
(笑)。

HER』をめぐる不思議な縁にしみじみ感謝。















