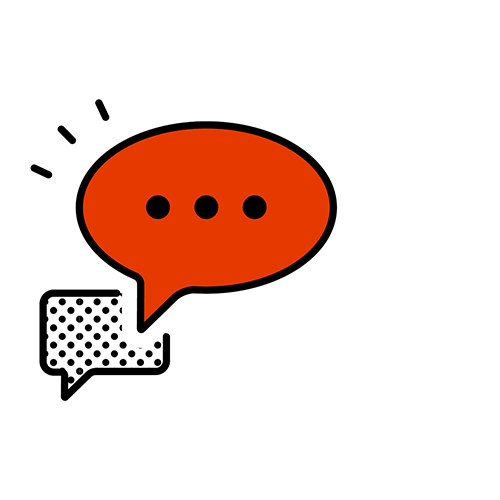まずはBTSの「Dynamite」のMVから
まずは近年の世界的大ヒット作である、BTSの「Dynamite」のMVから始めましょう。ドーナツに関連するところでは、メンバーが全員集合するのがドーナツ屋の店先。屋根に巨大なドーナツがのっかっているのは、ロサンゼルスの有名店〈ランディーズ・ドーナツ〉のオマージュでしょう。
この前のシーンでは、レコードショップ(そういえばEP盤のことをドーナツ盤と言います)、そして冒頭はティーンエイジャーの部屋から始まります。その室内にはビートルズの『アビイ・ロード』や、デヴィッド・ボウイの『ジギー・スターダスト』などのポスターが。音楽的にとても大切なポイントですが、一番最後に話すことにします。さらに、本作のもう一つの特徴は全編に貫かれた明るいパステルカラー。
この色彩に屋根の上のドーナツと来れば、思い出すのは『マーズ・アタック!』です。火星の侵略から地球を救う少年はドーナツショップの店員で、そのお店は〈ランディーズ〉を模しているとしか思えません。
どんどんつながる、
ドーナツムービーの系譜
〈ランディーズ〉そのものが登場するのは『アイアンマン2』。ロバート・ダウニー・Jr.演じるトニー・スタークが屋上の巨大ドーナツに座りドーナツを食べるシーンはインパクトがある。さらに面白いのはこれに続くシーン。トニー・スタークとサミュエル・L・ジャクソン演じるフューリーが店内で話し合うのですが、実はこの〈ランディーズ〉はテイクアウト専門店。映画のためだけに作ったセットなのです。
なぜこんなことをしているかといえば、おそらく映画『パルプ・フィクション』のオマージュ。サミュエル・L・ジャクソンが出演したシーンをいじってるんですね。ちなみに、この作品にもドーナツが登場します。ギャングから逃亡中のブルース・ウィリス演じるボクサーが、車の運転中にたまたま組織のボスを見つける。このボスが抱えるピンクのボックスの中身がドーナツなのです。特に西海岸ではドーナツのボックスといえばピンク色。
それを教えてくれたのはリドリー・スコット製作総指揮のドキュメンタリー映画『ドーナツキング』でした。カンボジアからアメリカに渡り、ドーナツチェーン〈クリスティーズ〉を成功させた男の半生を描く本作で、それまで一般的に使われてきた白色から仕入れ値が安いピンク色にしたというエピソードが。ごくざっくり言えば、西はピンクのカンボジア系、東は白の〈ダンキンドーナツ〉系に分けられます。
ドーナツブームの起源は、
1950年代のロードサイドに
また、西海岸の特徴に〈ランディーズ〉をはじめとする、巨大ドーナツをのせたバカバカしい建築スタイルがあります。そのきっかけの一つはハイウェイができたこと。象徴的なのは、州同士を結ぶインターステート・ハイウェイで、本格的に整備が進んだのは1956年から。
道沿いに建築物を建てられないから、遠くへアピールできるよう目立つためだけの要素がプラスされていったんですね。こうしたなかでロードサイドカルチャーが育ちました。特に発展したものの一つにドーナツショップがあるのです。
そんな状況をいち早く書いたのがウラジーミル・ナボコフ。40年代後半にアメリカ中を車で巡った経験は、小説『ロリータ』に色濃く反映されています。主人公の中年の文学者が少女を連れて、ナボコフ同様旅をするなかで、ロードサイドの変な建築や看板を眺める描写が。
時代を下って90年代初頭にはドラマ『ツイン・ピークス』。チェリーパイの印象も強いけれど、会議室にずらっと並ぶドーナツは、謎が謎を呼ぶ本作らしく、ミステリアスな存在でした。その後、10年もしないうちに公開された『ブギーナイツ』には庶民的なドーナツショップが登場。銃撃戦という思わぬ出来事が、そこで勃発するんです。その意外性を演出するのに、“日常にあるドーナツショップ”という舞台はうってつけでした。
日本では、家庭の味から
ミスドとダンキンの時代へ
日本ではどうか?そのターニングポイントは70年代初頭でした。70年に〈ダンキンドーナツ〉が、翌71年に〈ミスタードーナツ〉が日本にオープン。以来、アメリカンカルチャーとして浸透していきます。しかし、これ以前のドーナツ観は全く違ったもので、いわば家庭の味でした。
歴史を追えば、明治時代、1903年に連載された村井弦斎の小説『食道楽』に「ドウナツ」が、26年に婦人之友社編の『家庭で出来る和洋菓子』に「ドーナツ」のレシピが登場します。
そして、70年代以前のドーナツ観を端的に示すのが「ドレミの歌」。「ドはドーナツのド」でお馴染みですが、これは歌手のペギー葉山が翻案した歌詞で、もとの詞は「Doe, a deer」。ドーナツにしたのは、彼女にとって大切な母の味だったから。戦時中の疎開先で母親を思うときに手作りドーナツを頭に浮かべたと言います。
この状況がガラッと変わるのが70年代。これ以降のドーナツ・カルチャーを見てみると、まず思いつくのは村上春樹さんの一連の作品。82年発表の『羊をめぐる冒険』ではドーナツの穴は空白か、存在か、と哲学的に捉える一幕も。この時期の村上さん自身、ファッションからライフスタイルまでなにもかもアメリカで貫いていたから、ドーナツがモチーフとして登場するのにもうなずける。
98年には菊地成孔さんが小説「ミスタードーナツのシュトックハウゼン」を発表しています。これがすごく面白くて、1953年のNYのミスドを舞台にエルヴィス・プレスリーと現代音楽家のカールハインツ・シュトックハウゼンがニアミスする、という話。なのですが、現実には起こり得ないんですね。そもそも53年にミスドは存在しないし、エルヴィスはデビュー前でシュトックハウゼンはおそらくNYにいない、という具合にあり得ない架空の3つの出来事を重ねた嘘の小説なんです。
そして、嘘のような本当の話、ではないけれどミスドは24時間営業していたときもありました。94年に発表された吉本ばななさんの小説『ハチ公の最後の恋人』では家出した少女が真夜中のミスドでコーヒーを飲んでいるし、僕自身、90年代にクラブで遊んだあと始発までの時間を過ごすのはデニーズやミスドでした。
個人的によく通っていたのは今はなき渋谷の公園通り店。山下達郎さんの「ドーナツ・ソング」のなかにも登場します。シンプルな歌詞の繰り返しで、節回しが変わり、最後は歌詞がなくなっていく、というロックンロールらしさ全開の一曲。達郎さんはファンクやソウルなど、ブラックミュージックへのリスペクトがある。
ここで冒頭に戻ると、ボウイもビートルズも憧れのブラックミュージックを自分たちなりに解釈し続けた人たちですよね。そんな彼らをリスペクトしながら、BTSもまたブラックミュージックをやっていた。このように、ドーナツをめぐるカルチャーは、その形の通りに無限ループするように思えます。