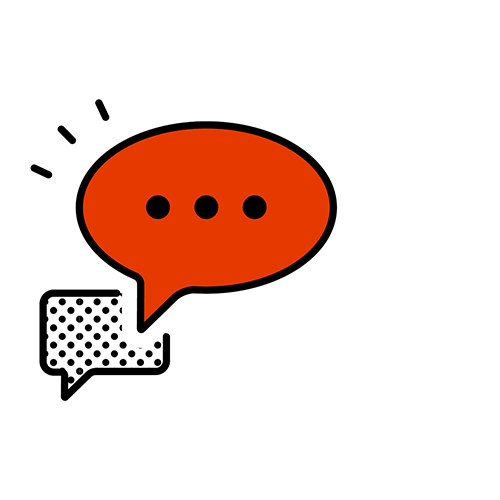拡張される展示
観客が石岡瑛子との対峙に没入できる、
“もう一つの展覧会場”。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、第3波を迎えていた2020年11月14日、東京都現代美術館で開幕したのが、『石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか』展(*1)だ。「Go To トラベル」も12月には停止、明けて1月7日には2回目の緊急事態宣言が首都圏に発令され、11都府県へと拡大、3月21日まで継続される中で会期終了(21年2月14日)という、最悪の状況下での開催となった。
展覧会のオンライン化はコロナ以前、90年代からさまざまなかたちで試行されてきたが、この時期、県境をまたぐ移動を抑制された人々のために、多くの美術館・博物館が、一斉に動画やVRを用いたオンライン展示に取り組み始めた。
そこで脚光を浴びたのが、「4K3D360度対応の独自カメラでの撮影と、3Dモデルを作成・配信まで一貫して行えるクラウドサービス」(*2)だ。『石岡瑛子』展も会期終了後の21年8月24日から22年3月31日まで、360度VR+ハイライト映像が公開されたが、実はこのコンテンツでは、デファクトスタンダードのサービスを使っていない。
「当時は美術館に限らず、“行きたいのに行けない”というコメントが、それこそ1分に1回Twitterに投稿されるような状況でした。展覧会は実空間あってのもので、私自身はオンライン展示には懐疑的でしたが、いち早くVRの展覧会をはじめた海外の事例で、解説の情報を画像に直接埋め込むなど、カタログの延長のような取り組みには興味がありました。
一方、コロナ禍以前から本業の傍ら、画像のVR化に取り組んできた写真家チームをご紹介いただく機会もありました。もともと記録動画は制作していたのですが、その方たちからも、空気感や音も含めて、その空間をより十全に再現したいのであれば、映像の方が適している、VRと映像は対で見せるべきだと言われました。
また、彼らと話し合う中で、既存のサービスではデータ自体は特定の企業が所有し、サブスクリプション制でプラットフォームを利用する形式のため、美術館自身がアーカイブの主体になれないなど、問題があることもわかってきました」と、担当学芸員(当時。22年から東京都美術館)の藪前知子さん。
そればかりでなく、広告や映画といった領域で活躍したアートディレクターの回顧展であるため、ポスターなどの平面作品だけでなく、映像や音楽まで含む展示をオンラインへ拡張しようとすると、著作権の処理が限りなく煩雑になっていく(*3)。それでも石岡展のオンラインコンテンツは、足を運べずにいた遠方のファンや、混雑した会場とは異なる体験を楽しんだ観客まで、多くの視聴者から高い評価を得た。

「“もの”の展覧会ではなく、情報の展覧会だったと思っています。石岡瑛子という人を情報として解体し、その生涯を空間的に可視化する展示、とでもいうのでしょうか。コロナのせいで作品を借りることができず、複製品を展示せざるを得なかった部分もあるのですが、意外と誰も気にしていなかったことも含め、オンライン展示との相性は非常によかった。
とはいえ情報だけではなく、その情報をいかに体感してもらうかということで、会場では石岡さんの声を使い、彼女の気配のようなものを感じられるようにしました。それがVRの没入感と相まって、親密な体験になった、混雑した会場とは違って一人で石岡さんと向き合えたという感想をいただく結果につながりました」
インスタレーションが、実空間からオンライン上の仮想空間へと拡張されることで、ファッションやデザイン、パフォーマンス、音楽など、領域横断的な志向を持つ作家の全体像が体験できる。藪前さんは今、リアルな展示の補助、代替手段ではない、テクノロジーが拓きつつある可能性の沃野に注目している。