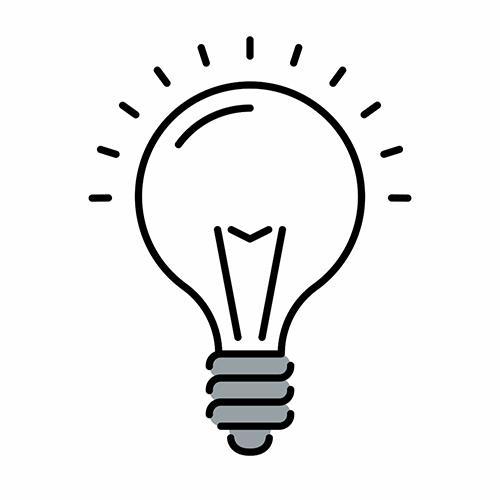江戸の魚食
江戸後期の儒学者、寺門静軒が天保2(1831)年に著した『江戸繁昌記』の中に、「鮮魚を嗜(たしな)み、常に言ふ、“三日肉食せざれば、骨皆離る”と」というくだりがあります。つまり江戸庶民は「3日魚を食べなければ骨がバラバラになる」と口癖のように言っていたほどの魚食いだという意味です。
この頃には漁業と流通が安定し、日本橋や芝の魚市場の周辺の町には天秤棒を担いだ魚売りが毎朝やってきて、客の前で魚をさばいていました。一方、両国や上野をはじめとした繁華街などには、料理屋や屋台が出て寿司や天ぷらも食べられました。
このように庶民がこぞって魚を食べるようになったのは江戸中期以後のことで、その変化の大きな要因は、江戸の町が百万都市に成長し、消費経済の主体が武士階級から町人へと移っていったことにあります。江戸時代に武家社会の経済基盤となったのは米であり、全国から年貢米が集まる江戸では商人を通じて市中に米が出回り、町人たちも米がたらふく食えた。
だからこそ、市中には食べ物屋が溢れ、グルメの文化が生まれました。つまり、江戸の料理は公家や武家から生まれたものでなく、庶民生活から生まれた食文化であるということです。

江戸っ子たちの気風の一つとして、「宵越しの金は持たない」というのが知られています。「江戸の華」と呼ばれたほど火事が日常茶飯事で、江戸全体が焼けてしまうことすらあった当時、資産を焼失してしまうことも珍しくなく、庶民の蓄財意識は低かったようです。そんな時代、「一日に千両の落ち所」と言われたように、一日千両ものお金が動く場所が江戸市中に3ヵ所ありました。それが芝居町(歌舞伎小屋)と吉原(遊郭)、そして魚河岸です。
魚市場が現在の築地に移ったのは大正12(1923)年の関東大震災がきっかけですが、それ以前には日本橋北詰、現在の三越と中央通りを隔てたあたりにありました。日本橋魚河岸の活況は多くの錦絵などに描かれており、江戸の商いが窺えます。雑踏を極める通りで、仲買たちが魚を陳列している戸板状の台は「板舟」と呼ばれるもの。
一枚ごとに販売権が付帯しており、有力問屋はこの板を何枚も持ち仲買に貸していました。向こう鉢巻きに腹掛け、尻切れ半纏(はんてん)を片肌脱いだ、いかにも江戸っ子らしい風情の小売りの魚屋をはじめ、買出人たちの姿も見えます。
魚河岸の有力問屋は歌舞伎や浮世絵、相撲など江戸文化のパトロンとなり、河岸の若い衆は「いき」や「はり」に男を磨く侠気のやからとして、江戸っ子の見本でもありました。今でも使われる「鯔背(いなせ)」という言葉は、河岸の若者の間で流行した髪形が語源で、イナ(ボラ)の背の形に似ていることから、「鯔背銀杏(いちょう)」と呼ばれたもの。そこから転じて、粋で勇み肌の者を「いなせ」と呼ぶようになりました。

「よく脂ののった魚」は江戸っ子に好まれなかった
当時の江戸湾は環境も良く、魚の宝庫でした。沿岸や河川で獲(と)れるのはクロダイ、カレイ、コチ、スズキ、キス、アイナメ、サヨリ、コノシロ、アナゴ、タコ、イカ、エビ、カニ、ハマグリ、ウナギなど、内海ではタイ、イシモチ、イサキ、サバ、ブリ、サワラ、アジ、イワシ、サンマ、マグロ、アンコウなど。
クジラやカツオ、サケ、タラのように地方から搬送されてくる魚もあり、当時から魚河岸では実に多種多様な魚が手に入りました。とはいえ、もちろん違いもあります。例えば、今では高級魚の代名詞として人気のマグロ。これはかつては下魚(げざかな)扱いでした。
その理由は、氷もない時代、遠隔地から運ばれて鮮度落ちするので、塩マグロなんて代物が出回っていたから。しかし江戸後期に江戸近海でよく獲れたことをきっかけに、マグロの刺し身が広まりました。ただし、トロを喜んで食べるようになるのは昭和に入ってからの話です。江戸っ子は魚にもさっぱりとした味を求め、脂身を嫌った。脂は特に傷みやすいですしね。当然、「脂ののった魚」という表現もなかったんでしょう。

西から入ってきた魚食を洗練させ、文化にまで高めた
現在でもよく使われる「江戸前」という言葉ですが、これは江戸時代にはウナギのことを指すのが一般的でした。ウナギは潮入りの隅田川河口や深川を漁場としたので、ご当地ものを「江戸前」と呼んで売り出しました。そのほかの地域で獲れたウナギは「江戸後」と呼んで嫌うくらいに、江戸の人々はプライドを持っていたといわれます。
江戸文化といっても、実際に江戸で始まったものは少なく、先進的なものはたいてい西からやってきたものでした。ウナギ料理や天ぷらももともとは関西にあったし、関東の味覚に欠かせない濃口醤油も、銚子に定住した紀州の漁民が売り出したものです。
とはいえ、それらを洗練させ、文化の域にまで高めたのは、やはり江戸庶民の精神文化があってこそ。文政年間(1818〜30)になってやっと登場した「にぎり寿司」は、江戸前の海から獲れたての魚介を使い、その場で握ってくれるもので、客を待たせないのが好まれ、江戸の人々は毎日のように屋台に足を運びました。さっさと食って、長居はしないのが江戸っ子流。庶民の生活から生まれた江戸の魚食文化は、現代にまで受け継がれています。