上出遼平
どんな経緯でドキュメンタリー映画の世界に足を踏み入れることになったんですか?
原一男
私は地元・山口で夜間の定時制高校に通っていて、昼間は働いていたんですが、3年生のときに先生が朝日新聞山口支局のバイトを世話してくれたんですよ。記者が撮ってきた写真を現像して本社に電送するという仕事です。
そんな中、若い記者たちが私を面白がって「一緒に写真撮り行かないか」って誘ってくれて、私が撮った写真が結構採用されましたね。それでフォトジャーナリストになろうと上京して東京綜合写真専門学校に入学したんです。
上出
最初はフォトジャーナリスト志望だったんですね。
原
そうなんです。そこに通いながら、最初に被写体として出会ったのが、脳性麻痺障害者の方たちでした。結局、学校は1年でやめちゃったんですけど、以後4、5年は障害者の養護学校で働いたりしながら、彼らの写真を撮るということをやっていました。
その写真の展覧会を1969年に〈銀座ニコンサロン〉でやらせてもらったとき、たまたま今のカミさんで私の作品のプロデューサーでもある小林佐智子が観に来ていて、「一緒に映画を作らないか?」って誘われたんです。
それで当時はドキュメンタリーの時代でしたから、じゃあ、1作目はドキュメンタリーを作ろうということで撮ったのが『さようならCP』。だから、彼女と出会わなければ映画は作ってません。
脳性麻痺の患者たちに
教えてもらった“教養”
上出
『さようならCP』も脳性麻痺の障害者がテーマですが、なぜ障害者という被写体に興味を?
原
山口では一度も脳性麻痺の人に会ったことがなかったんです。だから、初めて見たときはショックが大きくて、これらの人たちを、どう見るのか?を早急に自分の中で整理して、見方を確立しないと、とても写真を撮ることはできませんでした。
それで障害者=脳性麻痺の人たちがどういう問題提起を孕んでいるのかを勉強しようと、脳性麻痺者の施設を、カメラを持ってほっつき歩いたんです。私にとって幸運だったことは、大人の障害者の施設に行くと、その施設を開設した人が、社会を改革しないと彼らの問題は解決しないということを、障害者問題に無知だった私に優しく教えてくれたこと。
脳性麻痺者だけのコミューンを実践している人もまた自分で革命家を名乗っている人で、脳性麻痺者たちだけで革命を起こそうと考えていて、その人の革命理論を丁寧に教えてくれる。私たちの社会はいかにあるべきかなどという、大学で学ぶレベルの内容を、私に教えてくれたんです。
社会とは何か?というような問題意識を全く持っていなかった私にはそれらが新鮮で、真綿に水が染み込むように意識に染み込んでいったんです。
もう一点、当時は全共闘運動をはじめ、黒人たちの運動、チェ・ゲバラなどの思想がどんどん日本に入ってきている時代。
例えば、「Black is beautiful」という思想を知ったとき、社会的には何もできないとされていた脳性麻痺者たちの肉体にも適用されるんじゃないか?と考えてみた。そんなふうに学んだ理論をもっと深く研究するような意味合いで作ったのが、『さようならCP』。
教養というべきことを私に教えてくれたのは、脳性麻痺の人々との関わりなんだと、今も思っているんです。
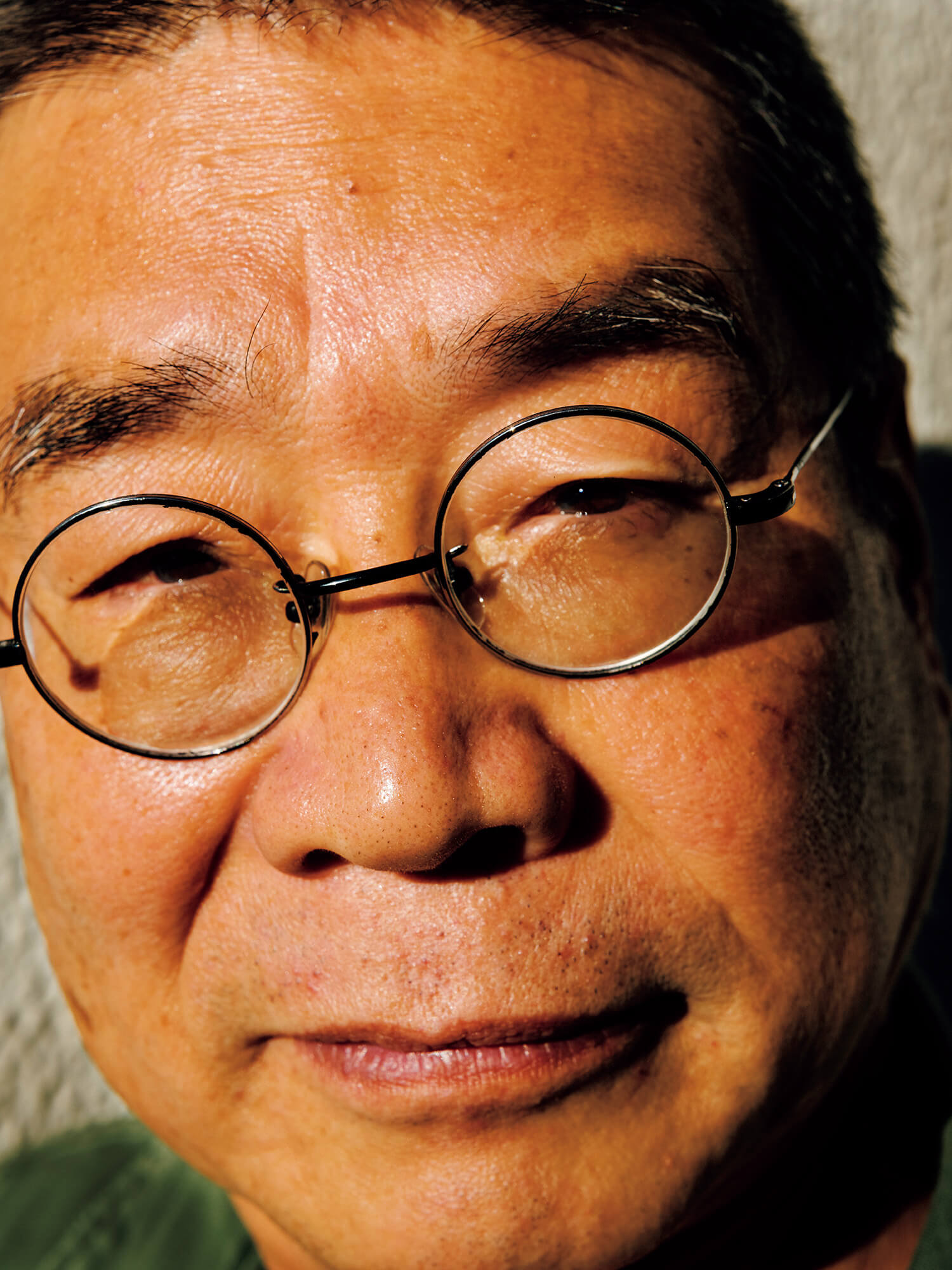
上出
原監督は『水俣曼荼羅』を含め今も自分でカメラも回していますが、なぜなんですか?
原
写真家出身なので、自分でカメラを回すことを前提に、カメラワークのスタイルから作品に入っていく傾向があるんですよ。自分でカメラを回せる人間にとって、どれだけ素晴らしい映像でも誰かが撮ったものには納得できないところがあるでしょ?
『水俣曼荼羅』でもスキューバダイビングを習って、水中撮影をしたりしていますが、自分がカメラマンなので、自分の手で撮影しないと納得できないんですよね。
上出
水俣湾の埋め立て地の護岸を水中から撮影したシーンですね。
原
私は子供の頃に中耳炎をやっているので、医者に言われたんですよ。「潜っちゃいけません」って。でも、練習も含めて100回近く潜っているんで、今では片耳が完全に聞こえなくなりました。
ドキュメンタリーっていうのは、そうやって肉体を酷使しないと作品として成立しないところがある。
上出
完全同意です。僕も『ハイパーハードボイルドグルメリポート』でケニアのゴミ山に行った後、公害型の喘息になりました。大袈裟なマスクをしていてはそこに住んでいる青年と向き合えなかったから。
『水俣曼荼羅』の撮影は15年かかったそうですが最初からそんなにかかると思っていました?
原
水俣病問題って100年近く解決してないわけですよ。だから、地元の運動も熱気のピークは過ぎているし、一般人には「もう終わったでしょ?」とすら思われている。そういう中で取材に行っても、なかなか撮らせてもらえない状況でした。
第3部でかつて惚れた男たちと再会してくれた患者の坂本しのぶさんの場合、撮らせてもらうチャンスを3年くらい待ちました。そうやって気づいたら15年経っていたんです。
上出
取材対象者との交渉にそこまで時間をかけられるのは映画ならではですよね。長くても3ヵ月くらいしか準備期間がないテレビとは全然違います。

原
でもね、どんなに仲良くなってもやっぱりタブーってあるんですよ。結局、坂本さんは誰とも恋は成就しなかったんだけど、もし相手が受け入れたとしたら、その次は性の問題が出てきますよね。
水俣病っていうのは、脳にメチル水銀が入って五感神経の細胞がダメージを受ける。五感っていうのは味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚なんですが、もう一つ、性の感覚っていうのが絶対ある。個人的にその問題が気にはなっていますが、最後まで聞けませんでした。
上出
『水俣曼荼羅』は6時間以上あります。水俣病の問題を周知したいんだったら、2時間以内に収めた方が観る人は増えるかもしれない。それでもこの長尺を選択したのはなぜですか?
原
私はドキュメンタリーを始めて50年経つんですが、一貫して変わってないなと思うのは、権力者へ喧嘩を売る人にカメラを向けているということ。
ただ、『ゆきゆきて、神軍』の奥崎謙三さんのように、個人で喧嘩を売る人っていうのは、昭和という時代にしか存在し得ないと気づいたんです。今の時代だったら……。
上出
炎上して白い目で見られて終わり?
原
そうなんです(笑)。
そう考えたとき、権力に向かう怒りを自覚的にエネルギーに変換するという生き方を見つけた民衆にフォーカスを合わせるしかないなと。
『水俣曼荼羅』にもそんな意識があります。ところが、民衆は感情の沸点が低い。そこにこそ庶民の問題が潜んでいるわけですが、その沸点は低いがゆえに丁寧に描かないとよく伝わらないんですよ。
それと、感情を抑えるタイプの人を1人描いても映画として持たないから群像劇にせざるを得ない。
上出
それで6時間になったと。
原
そうですね。ただ、そこには民主主義という価値観が体現されているとも思っていますが。あとね、なんで権力に喧嘩を売る人たちにこだわるのかというと、自分自身が社会の最下層の出身だから。
ドキュメンタリーって相手にカメラを向けながら、同時に「俺って何なんだろう?」って内省する要素が必ずあるじゃないですか。その延長で作品を作ってきたという思いがあるんです。






































