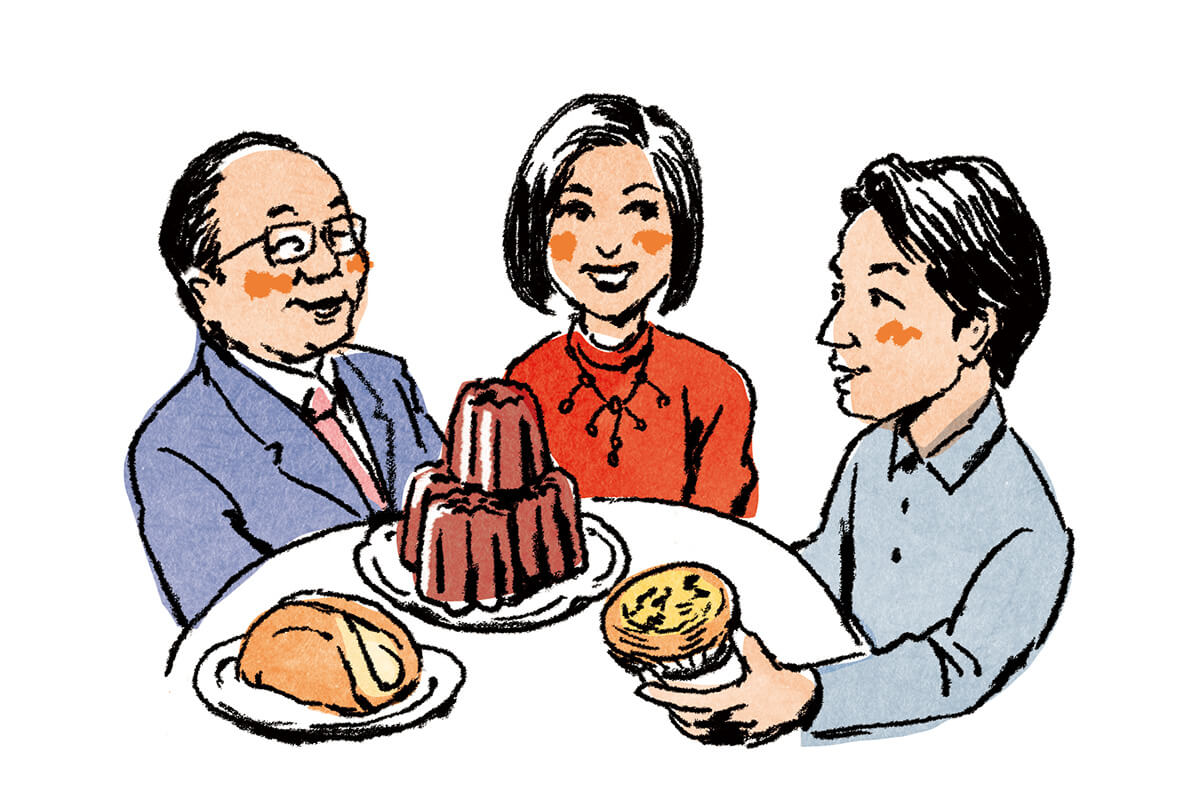カスタードの専門家
吉田菊次郎(ブールミッシュ代表、西洋菓子研究家)
大森由紀子(フランス菓子、料理研究家)
林周作(郷土菓子研究社代表)

卵、牛乳、砂糖をベースにした生地を、加熱して作るお菓子のこと。この3つの材料を合わせて蒸し焼きにしたのがプリン。主に卵黄を使い、小麦粉などを加えて炊いたのが、カスタードクリーム。ここにバターを足せば、カヌレの材料になる。
大森由紀子
カスタードのお菓子というと、卵、特に卵黄と牛乳と砂糖を使ったものを指すのかな?
林周作
僕もそう思います。
吉田菊次郎
そこにバニラビーンズや洋酒で風味をつけてソースにしたり、多少の小麦粉やコーンスターチを入れて、とろみをつけたりね。小麦粉をもっと入れれば、ソースがクリームに変わってくる。
大森
基本は、卵と牛乳と砂糖。そこから、牛乳が生クリームに変わったり、バターが加わったりして、いろいろなお菓子に枝分かれしていく。
吉田
その代表格が、日本でいうカスタードクリーム。小麦粉を加えて作るクレーム・パティシエールでしょ。でも、昔の文献を見るとね、最初は、いまのような甘いクリーム状のものじゃなかったの。
林
いつ頃のことですか?
吉田
1655年に書かれた『ル・パティシエ・フランセ』という本に、その作り方が出ているんだけど、材料は、牛乳と全卵と小麦粉とバターと塩。砂糖が入っていない。
大森
そのまま再現すると、プルプルの生地になるのかしら。
吉田
クリームというより、ルーのような、硬くて甘くない生地になっちゃう。なぜ、これが、パティシエールと呼ばれていたかというと、当時、パティシエという言葉は、パテ=生地を作る人のことで、製菓職人のことを指していなかったの。
大森
菓子を作る人は、ウーブリエ=ウーブリを作る人って呼ばれていたんですよ。ウーブリっていうのは、クレープと似たような生地を、鉄板で挟んで焼いた、ワッフルの前身といわれているお菓子です。
吉田
じゃあ、いつ頃砂糖が入ったのかというと、そこから先の文献がしばらくないんだよ。次に記述が出てくるのは、1800年代の前半。アントナン・カレームの著書まで待たなくちゃいけない。
大森
カレームは、近代フランス菓子を発展させた菓子職人であり、料理人で、お菓子や料理の文献をたくさん残しているんですよ。
カスタードクリームは、フランス生まれじゃない?
吉田
その間、世界がどうなっていたかというと、世は大航海時代。ポルトガルとスペインが、どんどん外に出ていった時期でしょ。この2つの国はさ、卵黄が大好きで、卵黄をとっても大切にしていたの。日本にも、ポルトガルから伝わった鶏卵素麺があるじゃない⁉
林
卵の糸という名前の、フィオス・デ・オヴォスですね。タイにも、アヒルの卵で作る同じようなお菓子が伝わっています。
吉田
スペインもそうでしょ?
林
卵黄と砂糖だけで作られた一口菓子は多いですね。イェマス・デ・サンタクララ(サンタクララ修道院の卵黄菓子)という、卵黄とシロップだけで作る、ふわふわした食感のお菓子もありました。
大森
カタルーニャのあたりも、卵黄菓子の世界ですよね。ジョエル・ロブションが考案したクレーム・ブリュレのもとになったクレマ・カタラーナも、カタルーニャの郷土菓子。
林
クレーム・ブリュレは蒸し焼きにするんですが、これはもっと素朴で、鍋で炊きます。この時、オレンジやレモンの皮、シナモンを入れて風味づけするのが特徴ですね。
大森
ポルトガルも、リスボンに行くと、カスタードを包んだお菓子が、本当にたくさん。有名なところでは、エッグタルトとして知られているパステル・デ・ナタがある。

吉田
リスボンのベレンにさ、その有名なお店があるじゃない?
林
1837年創業のカーサ・パスティス・デ・ベレンですね。パステル・デ・ナタは、18世紀以前に隣接するジェロニモス修道院で生まれたといわれていて、そのオリジナルのレシピでいまも作っている、観光客にも人気のお店です。
吉田
だからね、これは僕の個人的な意見だけど、いまのクレーム・パティシエールを作ったのは、フランス人じゃなくて、ポルトガル人じゃないかと思っているの。フランスから入ってきた硬いクレーム・パティシエールに砂糖を入れてクリーム状にしたのは。すでに、1700年代には、できていたと思うよ。
大森
私もそう思います。ただ、ここで、一つ疑問が湧いてくるんですよ、余った卵白はどこへ行っちゃったのか、という。実は、もともとは卵白が必要で、卵黄を使ったお菓子は、その副産物として発展していったという話があって……。
林
僕も聞いたことがあります。ボルドーで、赤ワインの澱を取るのに大量の卵白を使っていて、余った卵黄から、郷土菓子のカヌレが生まれたという話。
大森
修道院で修道士が僧服を糊付けするのに卵白を使っていて、その残りの卵黄でたくさんの修道院菓子が生まれたという説もありますよね。余り物でお菓子を作ってみたら、それが世の人々の好みに合っちゃったっていうことかもしれないですね。
吉田
いずれにしても、そのためにはたくさんの鶏卵が必要でしょ?16世紀になって、多産系の鶏が出てきたという背景があって、お菓子の世界が一気に華やいでいくの。

最初はプディングに、粉チーズをかけていた?
大森
プリンは、フランスでもポルトガルでもなく、珍しくイギリスで生まれたお菓子ですね。
吉田
そのプリンの誕生も、大航海時代と関係しているんだよ。1585年からスペインとイギリスの間で英西戦争が始まるでしょ。結局、英海軍提督だったフランシス・ドレイクが長期戦に持ち込んで、スペインの無敵艦隊を破っちゃうんだけど。長期戦になると、船に積んだ食料がどんどん足りなくなってくるの。
で、小麦粉の余ったの、フルーツやナッツの余ったの、卵なんかを“ええぃ、混ぜちゃえ”っていって、全部混ぜて、蒸し焼きにしたのが、プディング、つまりプリンの始まり。当初は、粉チーズなんかもかけていたらしい。
林
イギリスでレストランに入ると、メニューにプディングの項目があって、肉料理も並んでいたりしますが、その名残なのかもしれませんね。
吉田
それが陸に上がって、一般の家庭にも広がると、材料がどんどんシンプルになっていって、ライスだけのプディングや、卵の原液だけのカスタードプディングができた。
大森
イギリスには、デザートをプディングって書いてあるレストランもありますよね。
吉田
じゃあ、そのカスタードプリンは、いつ頃、日本に伝わったのか。はっきりしたことはわからないんだけど、おそらく幕末にはあったんじゃないかと思う。その頃、すでにイギリス人が経営するホテルなんかがあったからね。
大森
日本の文献には、いつ頃、出てくるんですか?
吉田
1872(明治5)年に仮名垣魯文が書いた『西洋料理通』という本に初めて出てくるんだけど、ここにはすでにライス・ポッディング……プディングのことね、干柿ポッディング、生姜(しょうが)ポッディング、蜜柑(みかん)ポッディングが記されている。
大森
へぇ、明治5年に、すでにそんなにいろいろなプリンが作られていたんですか。
吉田
ただ、まだまだ一般的じゃなかったと思うよ。この後、1889(明治22)年に、岡本純(半渓)って人が書いた『和洋菓子製法独案内』にね……、ちなみに、この本で初めて“和菓子”“洋菓子”という言葉が出てくるんだけれども、そこにボイルカスターケーキというのがあるの。作り方を見ると、カスタードプリンみたいなものなんだよ。
大森
この頃にはもう、クレーム・パティシエールも伝わっていますよね、きっと。
吉田
おそらく、日本で初めてクレーム・パティシエールを作ったのは、サムエル・ペールだと思うよ。
大森
ペール家は兄弟4人が来日。代わる代わる、文明開花の日本にフランス菓子を伝えました。
吉田
母国では、少なくとも2世紀も前にできていたものを、作らなかったわけはないでしょうから。そして、そこで修業をした村上光保の〈村上開新堂〉らが作り始めた。〈米津凮月堂〉の2代目職長だった門林彌太郎は、1896(明治29)年にシュークリームもエクレアも作っていたよ。なんで知っているかというと、私の母方の祖父にあたる人なの。
林
クリームパンが、そのシュークリームから生まれたという話は有名ですよね。あまりのおいしさに感動した〈中村屋〉の創業者夫妻が、あんこの代わりにクリームを入れたらどうだろうと、1904(明治37)年に考案したという。
吉田
カスタードを詰めた〈凮月堂〉のクリームワッフルなんかもそうだよね。それでね、日本のブリア・サヴァランといわれる食通、村井弦斎が、1903(明治36)年に書いた『食道楽』には、プリンもシュークリームも出てくるの。
カスタードプデン、珈琲プデン、ジャミ(ジャム)プデン、米のプデンなんかが出てくるし、同じ年に出た『洋食のおけいこ』っていう家庭用に書かれた料理本にも、チョコレートプッジングの作り方が載っているから、家庭にも広がり始めたんだろうね。
大森
でも、この時代に、プリンやシュークリームを食べていたのは、きっと、お金持ちの、ごく限られた人たちだったと思いますよ。庶民は、まだまだお饅頭や大福ですよ。
吉田
でもさ、これだけバリエーションが書かれているんだから、日本人が昔からプリン好きだったというのは、よくわかるよね。

日本人だけじゃない。世界に広がるプリン人気
林
プリンは世界各地にあって、いろいろな国で食べましたけど、印象に残っているのは、クロアチアのロジャータ。ロザリンというバラのリキュールや、マラスキーノ、ラム酒なんかが入ったプリンで……。
大森
食感はどんな感じなの?
林
日本の硬いプリンのような感じでしょうか。クロアチアは結構、カスタード菓子があるんですよ。カスタードとメレンゲを合わせたクリームを、パイ生地で挟んだクレーム・シュニッタというお菓子は、いちばん人気がありました。
大森
ポーランドにも、これに似たクレムフカっていう、やっぱりパイ生地でカスタードクリームを挟んだ伝統菓子がありますよ。
林
ただ、中東のあたりは、プリンはもとより、カスタード菓子自体があまりなくて、次にプリンに出会ったのは、インドのゴア。牛乳の代わりに、ココナッツミルクを使った生地を、薄く流し込んでは焼き色をつけ……、という作業を繰り返して作るベビンカというお菓子。焼きプリンのミルクレープのような感じで、これはおいしかったですね。
大森
へぇ、結構、手間がかかりそうだね。でも、食べてみたい。
林
アジアはココナッツミルクを使ったカスタード菓子が多い。タイは、カボチャに入ったココナッツプリンが有名ですが、甘いもち米にココナッツで炊いたカスタードがのるお菓子もありますし。インドネシアには、ココナッツミルクのカスタードとココナッツの果肉を合わせた生地を型に流して焼くお菓子もありました。
大森
カスタード菓子は、本当に世界中にありますよね。フランスの国民的なカスタード菓子といったら、なんといってもフランですよ。卵、牛乳、砂糖、小麦粉で作った生地を、焼いて作るお菓子。家庭菓子だから、もともとは容器に流して焼いていたんだけど、パティシエが持ち運びできるように、タルト生地に流し込んで焼くようになった。
吉田
そこにサクランボを入れて焼いたのが、クラフティね。
大森
材料の牛乳を生クリームに替えたり、バターを入れて風味を良くしてツヤツヤにしたりと、それぞれ工夫をして作っている。ただ、なんでかなぁ、日本人には、あんまり好まれないんだよね。
林
軟らかい食感が好きなので、あの硬さに馴染めないんじゃないかな。
大森
いま、フランスでは、お菓子がブームで、パティシエがスターなんですよ。そんな彼らが、こぞって作っているのが、このフラン。大きなサイズのものを作ったり、チョコレート味だったり……。〈MORI YOSHIDA〉も、フランのコンテストで優勝していますから、日本でも、もうちょっと注目されてもいいんじゃないかな。
世界と日本のカスタードまとめ
・クレーム・パティシエールは、最初、甘いクリームではなかった。
・カスタードを甘くし、世界に広めたのは大航海時代のポルトガル人説。
・修道院で大量に余った卵黄から、カスタードのお菓子が生まれた。
・プディングは、食料不足に陥った戦争の船上、苦肉の策で生まれた。
・明治初期の日本では、すでに何種類ものプリンが作られていた。