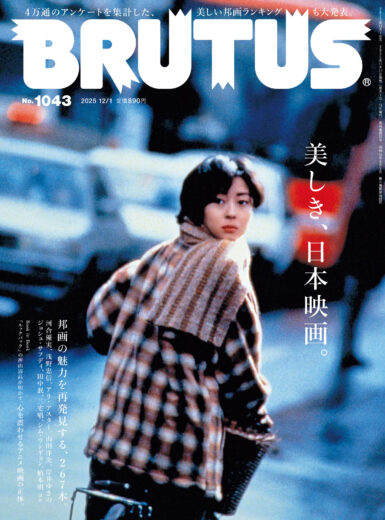TOKYO COFFEE FESTIVAL
新時代のコーヒーカルチャーを支える草分け的存在
2015年、ブルーボトルコーヒーが日本に上陸し、サードウェーブコーヒーといった言葉が知られるようになってきた頃。現在も運営に携わる竹内剛宏(たかひろ)さんらは「サードウェーブコーヒーをブームで終わらせたくない。実際に飲んで奥深さを体験できる場を作りたい」と、ファーマーズマーケットに企画を打診、東京コーヒーフェスティバルは誕生した。
実績のないフェスながら、当時立ち上げに携わっていたポール・バセット出身の大槻祐二さんの尽力で、フグレン、グリッチコーヒー、オニバスコーヒーなど注目店の出店が実現。第1回から話題のイベントとなった。一方で、大盛況がゆえに来場者の行列問題が発生、特定の店舗に客が偏るように。そこで着目したのが“情報”だ。
「行列ができると、みんなそこに注目してさらに行列が生まれてしまうので、事前にウェブで各店舗の紹介を載せるようにしました。そうすれば“みんなが並んでいるから並ぶ”のではなく、“自分の飲みたいコーヒー”を選べますから」。現地でもチケット購入者向けにZINEを配布、並びながら読める仕組みを作った。
さらに出店者側にも働きかけた。「イベント出店に慣れていない方も多かったので、作り置きができる態勢や必要な人員の数だったりを伝えていきました」。出店者と来場者、双方のコーヒー体験をより良いものにできるようイベントを成長させていった。
このフェスの特徴は、全国のコーヒー店が一堂に会するところ。2024年5月の開催では京都のアバウトアスをはじめ半数以上が東京以外からの出店だった。
また、2019年には世界の都市の一つを取り上げ、その土地の注目のショップを招く「ゲストシティ」企画にも着手。メルボルンやポートランドといったコーヒーゆかりの地からショップが来日。新型コロナを経て、2024年5月、久々に香港や台北からの出店も実現した。
常に幅広い視野でコーヒーカルチャーの今をフェスに反映させる彼ら。ファーマーズマーケットの拝原(はいばら)宏高さんは今後の展望について、「前々回のテーマが“ジャズ喫茶”、前回が“independent”。今、この業界の作り手を担っているのって、ジャズ喫茶世代の方々のちょうど孫くらいだと思うんです。彼らがそれぞれ自分たちの作りたい世界観を自由に作っていくことが豊かな日本のコーヒー文化を作ることにつながると思うので、そこをサポートできるフェスでありたいですね」と意気込む。

History
2015年9月・第1回 TOKYO COFFEE FESTIVAL開催
映画『ア・フィルム・アバウト・コーヒー』の上映など間口を広げる取り組みを行う。
2019年4月・初ゲストシティ メルボルン
パトリシア・コーヒー・ブリュワーズをはじめ現地のコーヒーショップ、ロースターを招致。
2023年10月・新型コロナ後初開催
「ジャズ喫茶」をテーマに掲げ、その文化にインスパイアされた世代の新提案の場を提供。
2024年5月・5年ぶりの海外枠復活
アアアアアア豆焙所(台北)などアジア各地のショップが集結。当日会場は大盛況となる。
2024年10月・第14回開催予定
テーマは「Can Tokyo lead Independent Craft Coffee Roasters in the World?」。
JAPAN COFFEE FESTIVAL
地方の魅力をコーヒーとともに発信、次なる夢は海外
奈良・興福寺や鳥取砂丘コナン空港、福岡・宇美八幡宮など、一風変わった場所でイベントを行うジャパンコーヒーフェスティバル。
代表の川久保彬雅(あきまさ)さんが団体を発足したきっかけは、前職時代に有志で参加した音楽フェスだった。「音楽で人と人の出会いが生まれていくことに感動して。コーヒーでもそんな場所を作れるんじゃないかと思ったんです」
開催初期から出店店舗はプロ・アマ・知名度問わず。「コーヒーって情報ありきな側面が強いと思うんですが、やっぱり味覚で楽しんでほしい。だから自分の足で店舗を探します」。当初から集客に成功した一方、収益は赤字。混雑で店と客側が会話しづらい状態にも歯がゆさを感じた。
2017年、南海電鉄からの依頼で、高野山付近の駅を会場にしたフェスを企画。普段は人影もまばらな駅周辺に、当日は多くの人が訪れた。「地元の人が“こんなに人が来てくれるんか”とすごく喜んでくれたんです。お客さんも土地の素晴らしさに感動していて。地方活性に興味が湧きました」。駅舎等を間借りし設営費も削減。資金面も改善された。

その後いろいろな地方自治体からも依頼が舞い込み、石川・金沢や兵庫・宝塚などでも開催。その際、一番重視しているのがテーマ設定だ。例えば滋賀県・長浜市木之本町でのテーマは“水”。
住民が今も地下水を活用していることに着目し、各店舗がコーヒーを淹(い)れる際にその水を使用すると、クオリティが格段に上昇。地元民も地下水の魅力を認識する契機となった。「日本の地方は素晴らしいものを持っていても気づいていないことが多い。気づいて活気を持ったら地域は勝手に活性化するはずです。そのきっかけをフェスで作れたらなって」
そして今、もう一つ注力するのが海外。2024年バンコクでフェスを初めて主催したが、課題を感じる部分もあった。それでも「僕は日本のコーヒーが世界で一番すげえと思ってるんです」と今後への意欲を見せる。その理由は、過去にフランスやドイツのイベントに出店した時のこと。ハンドドリップをしていると「何してるの?」と聞かれ、海外では一杯ずつ手でコーヒーを淹れる姿が珍しく映るのだと驚いた。
まさに地下水の魅力に気づいていなかった木之本町同様、自分たちの美点に気づいていない状況が国単位で起きている。「日本は圧倒的にコーヒー最先端国。自分にはこの文化を世界に発信する義務があると思っています」
History
2016年10月・第1回 大阪・中崎町ホールで開催
大学生有志で出店していた3人がのちに東京・蔵前にカフェ〈Lonich,〉を開店した縁も。
2017年6月・第5回 和歌山・南海高野線8駅で開催
橋本駅から高野山駅まで、周辺の住民20人の場所にイベント開催日は1,000人以上が訪れた。
2018年5月・第9回 福岡・宇美八幡宮で開催
地方自治体から初依頼。住民説明会なども行い、自治体と協業するやりがいを知る。
2023年9月・アジアンコーヒーフェスティバルin南海参加
初めて韓国でイベントの企画・運営に参加。大学生ら若い世代に声をかけ、10団体を招致。
2024年2月・第56回 タイ・バンコクで開催
ついに海外で初主催。西日本を中心に12店舗とともに、3日間イベントを行った。