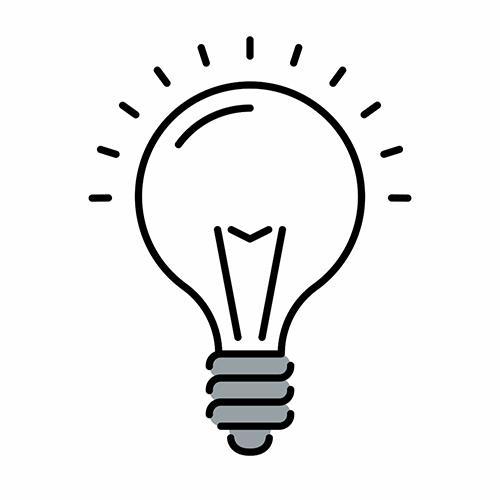昨今のアートシーンは?
岩渕貞哉
アート界で注目の出来事といえば、まずは現代美術の国際展『ドクメンタ』でしょうか。ドイツのカッセルで5年に1度開かれていますが、15回目になる今年、インドネシアのルアンルパ(1)がディレクターに選ばれた。
アジア人というのも、10人超のアートコレクティブでのディレクションも初めてで、話題になりましたね。テーマとして掲げられた「ルンブン」はインドネシア語で「米倉」を意味していて、余った穀物を預けて足りなくなった時に共有する場所。彼らは作品中心ではなく、知識を持ち寄って必要な人とシェアしようとした。
個人の作家性よりも、いろんな立場の人たちと集まって会話を交わしたり、違う価値観をすり合わせたりということ自体を目的としたんです。それは、アーティストがスターキュレーターに呼ばれて代表作を発表するという、これまでの大型国際展とは全く別のものでした。
山峰潤也
かつてあった「選ぶ側」と「選ばれる側」というような、圧倒的なヒエラルキーがある社会構造から、いい加減脱却するぞということの表れとしても衝撃的でした。ここ数年、ブラック・ライブズ・マターや#MeToo運動による人種や女性、コロナ禍からの自然や環境の問題へのエンパワーメントの流れもあり、そうした作品を集めて紹介する動きが多い中で、ルアンルパは芸術祭自体を一つのコミュニティを作る装置にした。
「事」が起こっている場所としてドクメンタを使用したというのが、決定的に大きかったですね。彼らは、私たちを西洋的な美術の価値観に押し込めることを拒否するという前提で、“No art, Make friends(アートではなく、友達を作ろう)”という理念を掲げたんです。
もともとアートは、価値の象徴を作るという世界ですが、そうしたモニュメントではなく、その後に残る関係性を作り出すというやり方をした。それは世界的に見ても、ゲームチェンジャー的な大事件だったと思いますね。
岩渕
開幕直後に反ユダヤ主義の問題が浮上して、ドイツのメディアが沸騰したりもしましたが、現場自体はすごくピースフルで、これまでと全く違う新しい体験ができたようです。
山峰
ある意味ドクメンタと真逆で、もう一つの潮流と言えるのが『ヴェネチア・ビエンナーレ』ですね。今年は、女性アーティストたちが作り上げた彫刻やテキスタイルの作品など、かけてきた時間や思いの込められた身体的な作品を数多く見せていた。体験として、とてもリッチでした。
岩渕
メイン展示部門で金獅子賞を獲得したアフリカ系アメリカ人の彫刻家シモン・リー(2)の作品も、マイノリティや差別などの問題を扱い、ひときわ目を引くものでしたよね。
アート表現は人間以外の
事象と切り離せないものに
山峰
手前味噌ですが、昨年秋から今年の頭にかけて〈国立台湾美術館〉で、コロナ以降の社会を考える展覧会をキュレーションしたんです。タイトルは、レヴィ=ストロースが『悲しき熱帯』に書いた一節「The World Began without the Human Race and It Will End without It(世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう)」。
コロナ禍は世界が人間中心主義に陥っていたという、自然環境に対する「搾取の状況」を気づかせました。ならば人間は、文明やエコロジーとどう向き合い、どう共生できるのか。ナフタリンが気化して結晶ができる宮永愛子(3)の彫刻など、人工的なものと自然とが一体化して成立する作品や、宮島達男のLEDカウンター、避難マニュアルをモチーフにしたナイル・ケティングの作品などを展示しました。
岩渕
これまでアートは、人間が作り出したものの中でどう価値があるのか、あくまで人間社会の問題として考えてきました。でも、人間なしの世界でアートはどう成立するのか。
Chim↑Pom from Smappa!Groupが発案したプロジェクトとして2015年から開催されている『Don't Follow the Wind』は、福島第一原発の帰還困難区域内で行われていて見ることができないという、想像力が試されるものでした。が、今年ようやく避難指示が徐々に解除されて、一部の作品が見られるようになりました。
人と自然との関係が変わりつつある現在、こうして人間以外の事象を含めてものを作るという試みも目立ってきています。美術史だけではなく、人類学や生物学などの知識や経験とともに、表現を考えていかなければならない現代を象徴する展覧会です。
山峰
北海道白老町での芸術祭『ROOTS&ARTS SHIRAOI』を通して、自然からインスピレーションを受けながら制作活動を続けてきた鈴木ヒラク(4)も、その自然観を、新しいアートの文脈でいかに作品化していくか、どんな価値をもう一度伝えることができるのかを模索している段階にいると思います。
ストリートアートなど都会のカルチャーから影響を受けてきた彼が、他方でそういう事柄と結びついて探求しているというのは興味深いです。
岩渕
生物とともに作品を作るという方法で表現している人もいますね。AKI INOMATA(5)も、作家性を一部手放しているアーティストの一人。
ビーバーに角材を渡して、ビーバーがかじったものを彫刻作品として発表したり、ヤドカリが快適に棲める家を3Dプリンターで作ったり、動物たちとの共作を通して、人間以外のものの世界をどう想像し共存するかを、実際の制作の中で実践しています。
山峰
韓国出身のアニカ・イ(6)は、生物の発達の仕方をモチーフに、培養された皮膚を使ってモニュメントを作ったり、動植物の動きを考察して彫刻を作ったりしていますね。2016年にはヒューゴ・ボス賞を取りました。
岩渕
香りなど、視覚以外の五感に訴える作品が面白いですよね。
帰還困難区域で展示されていた作品が公開になった
アジア、アフリカからも、
世界規模の作家が誕生
山峰
国際的なアートの文脈で言うと、アイヌの伝統歌を歌うマレウレウのメンバーでもあるマユンキキ(7)が、2020年の『シドニー・ビエンナーレ』に選ばれたり、注目されなかった存在がエンパワーメントの流れもあって再評価されています。
80年代生まれのアーティストも活躍していますね。近年、アフリカンアートの流れも強く感じますね。アフリカ系だとイブラヒム・マハマ(8)でしょうか。ガーナの地域に溢れているごみや路上生活者の人が使っているものを集めてきて作品化したりしています。
アジアでは、タイのアピチャッポン・ウィーラセタクンが有名ですが、バンコクとNYを拠点に活動しているコラクリット・アルナーノンチャイ(9)が、エネルギッシュなクラブシーンと、もともとの宗教観や自然観と結びついたネオアジア的な表現で、次世代のアーティストとして注目されています。
イスラム圏だと、1983年生まれのソフィア・アル・マリア(10)。イスラム社会における女性のあり方を強く打ち出して、世界中で評価されています。
岩渕
グローバリズムや資本主義によって地球が危機に瀕している背景には、植民地化による搾取があります。その中で等閑視されてきた人々の尊厳を取り戻すことが、今の時代、表現を考えるうえで無視できない視点になります。
日本もやや遅れてはいるけれども、新しい動きはあります。彫刻家で評論家でもある小田原のどか(11)は、モニュメントとしての彫刻の問題を考えていて、長崎の原爆の記念碑や、奴隷労働など植民地からの搾取によって成功したことで建立された銅像の引き倒しを取り上げています。
彫刻が公共的な空間に鎮座する土台となる制度自体を問い直している。そして、それは彫刻の問題だけではなく、ジェンダーや教育など美術における権力の勾配の再考を促す活動にまで広がっています。
山峰
人権運動とデジタルアーキテクチャーを合わせて、非人道的な状況に置かれている人たちや報道をリークし、真実を暴き出す活動をしているフォレンジック・アーキテクチャー(12)も、ゲームチェンジャーですね。
リーダーのエヤル・ワイズマンは建築家でイスラエル人です。彼はインターネット上にある画像データを解析することで、例えば、市民が上げたSNSに映っている噴煙がどこで上がっているのか、どこで爆撃が起きたのかなどを明らかにし、非人道的な攻撃が行われているということを訴えたりしています。
岩渕
人種的な衝突による死亡事件を3D映像で再現して、当局の発表とは異なる事実を明るみに出したりと、調査報道に近い活動もありますね。
山峰
コンテクスチュアルな話をしていくと、どうしても表現としての感覚的な話がしづらくなるんですが、アイドルをモチーフに、体が醜く壊れながらも永遠に歌い踊り続ける作品を作るジョーダン・ウォルフソン(13)の作品も、破壊的でやばいですよね。まるでアイドル(偶像)という虚像が再生産され続けて、劣化していくような感覚を覚えます。
岩渕
ポストヒューマンの流れにあるアーティストですよね。人間は、もはや機械と一体化していて、その定義や輪郭自体が変わってきている。そうした問題を扱っています。
山峰
セシル・B・エヴァンス(14)も、デジタル社会における死や、実態を離れた噂やイメージが膨らんでいく社会の不条理を描いています。亡くなってしまった人気俳優をドラマの継続のために、CGを使って蘇らせようとした出来事をモチーフにしたこともあります。
別の作品では、人間とAIが電脳空間で友達のように生きている、その社会の中で、AIで作られたアイドルが殺されるという事件が起こる。進化した社会における死や作られたキャラクター像を考える作品を作っています。