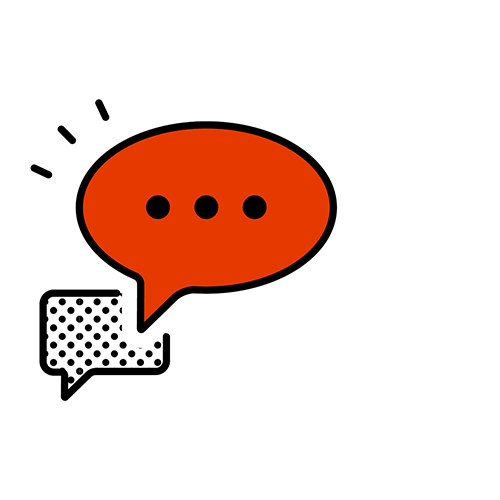ディスコの聖地パラダイスガラージで使われていたヴィンテージのロータリーミキサーから、イギリス製やフランス製のハンドメイドのものまで、DJ用の機材に溢れた部屋、この場所こそがルイ・ヴィトン メンズ アーティスティック・ディレクターに就任し、今年の夏にファーストコレクションを発表すると世界をあっと言わせたヴァージル・アブローのスタジオだ。ジャンルレスな活動を同時多発的に発信しあらゆるカルチャーに影響を与える時代の寵児となった彼の、新たな基地。
「Apple Musicの自分の番組もここでやってるんだ。ミックスも録れるし、なんでもかけられる。移ってきてまず手をつけたのがスタジオだけど、まだ30%くらいだよ。家具はマックス・ラムのものをロンドンから持ってきた。仕事が始まってすぐに家を探し始めて、最近やっとパリに住むようになったんだ。この街に来るようになって9年くらい経つけど、長くにわたってホテル暮らしというのはおかしなもので、ようやくここで働いている実感が湧いてきた。ただ自分の作品を見せる場所というのではなくてね。なぜなら帰る家があるのだから。
もちろん、まだシカゴがベースだから、行ったり来たりだけど、パリに滞在する時間はどんどん長くなってる。FaceTimeも多用するし、新しいエコシステムで働いてもいるけれど、実際に手をかけなければならないことが増えたからね。けれど、ここ24時間の間に、僕はパリからロンドンに行って、いまココにいる。パリに住むことで僕はヨーロッパでのハブを持てたんだ。今年の最初の週、僕は大西洋を5回は飛んだよ。6、7時間は毎回機上で過ごすスーツケースの人生だったけど、ようやく家とオフィスが整ってきたってこと。ルイ・ヴィトンでの平均的な一日の過ごし方?ミステリーだろう?(笑)
僕はマルチタスクに働いて、1日に24時間分以上のことをこなす。ルイ・ヴィトンのオフィスにいるときは大抵、9時には出社して夜9時まで、12時間は働く。皮肉なことに、コレクションを実際に生み出す瞬間というのはオフィス外なんだけどね。まずコンセプトについて考えるんだ。どんな物語を自分が伝えたいかということをね。大体は旅の途中で考える。そんな時間こそインスピレーションを得やすいんだ。オフィスにいるときは、ミーティングしたり指示をするため。僕と一緒にクリエイティブを手がけるチームはだいたい30〜35人。それぞれの部署のトップもここには含まれていて、常に直接やりとりをするのはその中でも8人くらいかな。もちろんこのチームの外にはよりたくさんの人たちが関わっているんだけどね」
退屈な人間にならないように、別の視点を意識しながら動き続ける。
アーティスティック・ディレクターという、メゾンでは頂点の一つである地位についたヴァージル。しかし、自らをマルチタスク人間と呼ぶように、その仕事ぶりは一向にスローダウンする気配がない。移動を繰り返し、ルイ・ヴィトン以外の様々なプロジェクトにも取り組み、夜はあらゆるクラブでDJをし、キッズたちを熱狂させる。その驚異的なワークレートはどこか意図的なものなのだろうか?
「一つのことだけをやっていたら退屈な人間になると思うんだ。たくさんのことを同時に手がけながらハードに働くのは、それを僕が恐れているからだと思う。自分が手がける作品たちに対する仕事の倫理観というのは、とてもパーソナルなものなんだ。ルイ・ヴィトンで働くことで、いままでとは異なる舞台で自分の作品を表現できる。素晴らしい機会を与えられたのだから、もちろん優先事項だよ。でも、同時にこの仕事には別の視点も必要とされるんだ。そして僕はそれをほかのプロジェクトから得るんだよ。IKEAとルイ・ヴィトンのために同じ日に働くということは、僕にまた別の視点と、考えるきっかけを与えてくれる。その両者は陰陽であり、どちらも大切なことなんだ。
例えば、DJだって僕にとって重要なことなんだ。旅をしながらサブカルチャーとコネクトし続けるということは、カルチャーがどこで発生し存在するかを理解させてくれるし、そこにちゃんと根差していくことができる。ただ車で走り回り、高級なレストランで食事して、ファンシーなパーティに行くだけじゃ駄目なんだよ。ちょうど、マラケシュのフェスティバルでDJをしてきたんだけど、まるでクリエイティブなマインドのための、ジムみたいなものだよ。ダッシュを繰り返し、バーベルを持ち上げるように、3分で曲を選んで、その曲が終わればまた次を選んでかけなきゃいけない。自分の頭を創造的な方向へと向けてくれるんだ。だから、世界中でプレーしなくちゃいけないし、場所が変われば違う反応を示す客に対しても共鳴しなければダメだ。
それこそ17歳の頃から、僕はいつも何かを作りたいと思っていた。ファッションなのかアートなのか音楽なのか定かではなかったけれど。だから振り返ると、ものを作り続けてきたからこそ、いいキャリアを持ち得ているんだと思う。大人になったいまの僕は17歳の頃に望んでいた姿の完成形と言えるね。その発端は大学かもしれない。僕は建築、それもモダニズムについて学んだ。
1950年代の“インターナショナルスタイル”は、一つのビルをデザインすれば、世界中どこでも実現可能となるもの。提唱したミース・ファン・デル・ローエは母校イリノイ工科大学の有名なクラウンホールを設計しただけでなく、カリキュラムそのものもデザインしたんだ。だから2000年当時でも、50年前に彼が造り上げた建築をどのように考えるべきかを教えていた。実はローエについてよく知らなかったけれど、“なんてラディカルなんだ”って思ったよ。それでも学生の頃は建築だけとか一つのことしかやらない人が多くて退屈だった。
僕にはマイケル・ロックという師と呼べる人がいた。グラフィックアーティストで、彼からTシャツ作りのノウハウを学んだ。僕はラップのコンサートに行き、DJをして、木工所に行って家具を作り、そしてPC教室でTシャツを作ったり、ルーペ・フィアスコと一緒にカレッジラジオで番組をやったり……。あらゆることに手を出した。それをいまも続けている感じかな」
何をやるにも、2回目が難しいんだ。真価を問われることはわかってる。
キャリアを一つ一つ、選んで段階的に取り組むのではなく、好きなものを同時に手がけ突き進む。ルイ・ヴィトンがこのファッションの大変革期における革命者としてヴァージルを指名した理由はそのアグレッシブな人柄にあるのかもしれない。そしてその望み通りのセンセーションをファーストコレクションは引き起こした。そしていまヴァージルは世界中が注目するセカンドコレクションに取り組んでいる。宴の後の、より真価を問われるセカンドに。
「そういうことだよ(笑)。音楽でもアートでもそうだが、セカンドは一番難しいんだ。そのための時間が持てないからね。正直に言うと、ショーが終わるまで僕はルイ・ヴィトンらしい語り口というものを深く考えてはいなかった。とにかく時間が足りなかったんだ。ショーの後に、クリエイティブチームと一緒にキャンペーンについてアイデアを出し合ったんだ。その結果“いまのルイ・ヴィトンのメンズウェアとは何か”というよりむしろ、“どうやってメンズウェアに至ったか”ということに考えが行き着いた。
カルチャー的に言えば、ジェンダーの意味やそこに至った経緯を考えるのに、いまほど完璧な時はないだろう?男対女、何が違いを生むのかとかね。僕にとってのキャンペーンが前提とするのは、メンズウェアより幼少期や少年期から思春期や成人についてだ。僕らはただファンシーなイメージのマーケティングをして、服を売るという時代には生きてはいない。過去5年の間に何かが変わったんだ。だから“男を作り上げる土台であるティーンの時代にフォーカスしよう!”、そう感じたんだよ。次のコレクションはもしかしたら、メンズウェアらしくないかもしれないしね。僕が男のためのウェアをいまさら定義する必要もないと思うんだ。それより過去の5年、10年、15年を振り返るようなものになるよ。
カート・コバーンのデニムにネルシャツという美しさに心惹かれる理由は、それがファッションとしてじゃなくて、単に音楽のアウトプットとして着られたものだったから。コレクションのデザインの源も僕の過去から来るもので、90年代や2000年代を振り返り、いまにないものを作る。それを考えるには、ランウェイ用のルック30体を作るよりはるかに長い時間がかかる。いまは、“このでかい広告キャンペーンに注目してくれよ!”的な時代の終わりにいるんだと思う。僕がやろうとしているのはもっとニッチで、小さなスケールの、想像を膨らませるようなイメージだね。“もし興味あるなら見に来なよ”くらいの、決してマス向けではないものなんだ」

歴史上の新しいムーブメントは、何かの反動として生まれてきた。
これからのファッションはどこへ向かうのか?そしてルイ・ヴィトンにおいて何を成し遂げたいと思っているのか?聞かれ飽きたであろう質問に、ヴァージルはゆっくりと、そして自信ありげに答えてくれた。
「建築の話に戻るけど、僕がそこで学んだのは、“特に素晴らしいムーブメントというのは現状に対する反動として生まれた”ということだ。それこそが進化であり、アートの歴史だろう。モダニズムはヨーロッパにおける産業革命から反動的に生まれて世界に広がった、新しい素材や美のことだよ。そういう考えをファッションに取り入れ、いまあるファッションから違う語り口を考えようとしている。
僕が生きてきた世界から見れば、手渡しで広がるTシャツはどんなラグジュアリーブランドのタグ付きの服より価値があった。もしそれが僕の心にあるのならば、そしてまだ体制にアンチであるならば、ルイ・ヴィトンで働きながら、同時にそういうTシャツを作るということになる。僕は常にどちらか一つを選ぶのではなく、両方の考えをいつも同時に持ってきた。だから僕はどうしたらルイ・ヴィトンを外の世界で起きていることに合うように調整できるか?ということに対して、いままでとは違った形でコミュニケーションをとっていかなければならないと信じているんだ」

イメージは、僕のバイブをそのまま伝えるものじゃないと。
「スタジオにはクールな服を作るためにいるけど、モノを作ること自体はそんなに難しいことじゃない。そして、このレベルの世界になれば、服を作ること自体が一番難しかったらダメだ。ただ、キャンペーンは違う。イメージやその動きは僕のバイブを、そのまま伝えるものじゃなきゃいけない。そうすれば人々がこのブランドの、ロゴの、店の裏にいる僕という人間を認識できるだろう?“あのオフィスからラジオをやっているやつの服か!”“あいつはストリート上がりで、どこから発想を得たかわかるぞ”となるだろう?
ルイ・ヴィトンは車と比較するとわかりやすい。イタリアのスポーツカーのエンジンのようだ。それに歴史も経験も段違いだ。例えばオフ−ホワイトだと、チームをゼロから作り上げた。僕のハンドメイドといっていい。どこかが壊れたら、どうすれば直せるか完全に理解している。ただ、ルイ・ヴィトンは違う。ブランドが始まったのが1854年だ、はるかに長い物語があるんだ。それと会話するということだよ。ルイ・ヴィトンではいまのカルチャーにおけるロゴの意味や、それがどこから来たかを理解して語るんだ。
楽しいけれど、頭の中でははっきりほかとは区別しているよ。たくさんの人に“まったく、お前は一体、何百のことを手がけてるんだ”と聞かれるが、それを成し得るのにどれだけの労力がかかるかを誰も理解できていない。普通に考えて、世界中を飛び回れば、目覚ましをかけて、起きて、出発するの繰り返しだ。僕がいちばん聞かれるのは“一体、どうやってこなしているんだ?”っていう質問。確かに十分には寝ていないね(笑)。人には限界があるんだろうが、僕の場合やると決めたら、ただやるんだ。そうすれば1日に6つはやり遂げられる。よくキッズたちに“それは簡単なの?”と聞かれるが、答えはこう。“簡単ではないけど可能”だということだよ。もちろんたくさんのことをやれば時間が常に足りないし、それを言い訳にもできない。けれど、人生は速く、短いんだ。
あと一つ、僕は完全主義者であろうとすることはやめた。あらゆる意味においてね。僕がファッションをこの規模で始める前、人は“ちょっとスローダウンして、いま作ってるTシャツで満足しなよ”と言いに来た。それこそが服を作り、ランウェイ用のドレスを作るモチベーションになったよ。それは僕がやりたかったことなのだから。できることしかやらない方がはるかに安全だ。でもね、僕は自分がやっていることに心地よく感じた瞬間こそ、“逆をやろう、より難しい道を行こう”と思うんだ」

インタビュー後記
世界中を飛び回るヴァージル、いろんな街で一緒になるが彼はただのクリエイターでもセレブリティでもない。常に時代を見据え、思考し、思いついたことはすぐiPhoneにメモし、そのままテキストで指示を飛ばす姿を何度も目撃してきた。一つの夢のために他を犠牲にするという考えは彼の頭には存在しない。好きなことは同時にすべてやり、そのそれぞれが密接にリンクしてヴァージルの世界を作り上げているのだ。古いディスコのレコードで一緒に踊り、巨大な箱で最新のエレクトリックミュージックでキッズを虜にし、建築とグラフィティとファッションの話を同レベルに語れる男。ルイ・ヴィトンと未来を作る男。これからがつまらないわけがない。
(本文ともに、野村訓市)