「その10トン・トラックが目の前を走り抜けた時は、衝撃だったんですよ。これは何なんだと。それから、そのトラックの持ち主を探し求めたんです」と語るのは、写真家の志賀理江子。10月11日から日本橋のアーティゾン美術館で開催される展覧会「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着」(2026年1月12日まで開催)の準備の真っ只中の志賀は、その天啓のような体験を語り出す。まるでトラックが彼女を異世界に導いてくれたかのように。
1980年愛知県生まれの志賀理江子は、日本のアート写真のメイン・ストリートをまさに爆走トラックのように突き進む。ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ・アンド・デザインを卒業し、ロンドンの公営団地の住民を被写体とした『Lilly』、仙台とオーストラリアで撮影された『CANARY』の2冊の写真集で2008年に第33回木村伊兵衛写真賞を受賞。美術館での展示も「螺旋海岸」(せんだいメディアテーク 2012–13年)、「カナリア」(Foam写真美術館 アムステルダム 2013年)、「ブラインドデート」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 2017年)、「ヒューマン・スプリング」(東京都写真美術館 2019年)と30代で公立美術館での個展を立て続けに開催。
今回の「ジャム・セッション」は、石橋財団コレクションと現代のアーティストとの共演により、美術の新たな可能性を探るシリーズの第6回。沖縄と東北という異なる土地に根ざし、歴史や記憶に向き合ってきた山城知佳子と志賀理江子を迎えて、複雑で困難な現実に対するまなざしと、芸術の力を再考する場を創出することを意図している。

志賀は今回の展示のために「なぬもかぬも」と題した長文のドキュメンタリーのテキストが収められた冊子を制作した。その「なぬもかぬも」とは、志賀が住む宮城県石巻市で彼女が偶然目撃した一種のデコトラが題材となっている。そのフロントガラスに巨大な大きさで「なぬもかぬも」――宮城県の方言で「なんでもかんでも」の意味――と書かれた大型トラックが目の前を走り抜けた衝撃から、志賀はそのトラックの主を追い求め、それにより、東北のトラックドライバーの実態、東北の震災復興の「見えてこない」状況などをより深掘りすることになる。このドキュメンタリーは、まるで探偵小説のようにスリリングなシーク&ファインドが描かれており、そこで志賀はそのデコトラをメタファーとして、世界の「見えないもの」に導かれていく。
志賀は「なぬもかぬも」の中でこう記す。「私の中にも、社会の中にも、消えることのない依存の道。『道』はWAY、『やり方』でもある。目の前にあるのに見えない、ということを『なぬもかぬも』号は、風土の中に自らの車体でもって挑発する。『なぬもかぬも』号が走れば、世界は幾つにも分裂し、その裂け目を覗け、と私の目前に迫ってくる。『なぬもかぬも』があれほど強烈だったのは、風景を引き裂き走っていたからだ。その姿は忘れ難い残像を私に残した」
この「目の前にあるのに見えない」ものを可視化させる行為、それこそが志賀が一貫して追求していることに思える。「見える/見えない」ということをテーマとして大きな反響を呼んだ丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の「ブラインドデート」展もそうだが、彼女の写真作品は、志賀の言葉を借りると、普段我々が目にしない「世界の裂け目を覗け」と言わんばかりの迫力で観る者に迫ってくるのだ。
今回の展示では、巨大なターポリンにプリントされた作品群の空間の中で、観客は異空間を体験するような展示になるという。ターポリンとは、布にポリ塩化ビニールをコーティングした合成樹脂素材で、主に屋外の掲示、横断幕などに使われる。2024年の横浜トリエンナーレでの志賀の展示も巨大ターポリンを使った展示だったが、通常の写真プリントによる展示よりも巨大ターポリンの方が「私の性格に合っている」と志賀はいう。

今回は、映画のスクリーンに近いサイズのターポリンの壁の連なりに、志賀の新作イメージが物語的に展開されるものになる。それも多くが夜間撮影で、人々が役を演じているようなもの。それはまるで映画のような、さらにいえばホラー映画のような仕上がりになる。
「今回の写真作品制作で、演出なしに撮ったものは一枚もないんじゃないかなと思います。撮影現場に来てもらった人たちも、全員で演じるというか。例えば、新作で巨大な太いロープを用いて、それを一回海の中に沈めて、それから自分たちで引き上げるというシーンを撮った時などは、引き上げる人たちに、『この太いロープは、へその緒だと仮定してて、だからこれをみんなで全力で引っ張って、今から生まれてくる命を全員で呼んで迎えるような気持ちでやってみたい、つまり、全員が産婆の役ね』という演出をしたんです。撮影現場に見えないイメージをインバイトする、招くような感じです」
志賀は2008年に宮城県に移住し、2011年の東日本大震災の津波で自宅もアトリエも流失するという被害を受けた。以後、震災とその後の「復興」を大きなテーマとし、さらにその風土と歴史の捉え直しを試みている。彼女の映画の演出のような撮影手法は、彼女ならではのリアルとの向き合い方と言えるだろう。
「被写体となってくれる方々に演じてもらうことでより世界に向き合えるように思えることがあると思います。人々が思いっきり演じることで何かが変容して、新たなイメージが立ち現れるまでやるという感じです。だから、ホラー映画を演出しているというよりは、『私たちの体の中に一体何があるのか?』というのを見ようとしているんです」
アーティゾン美術館の学芸員である内海潤也は、志賀の社会性の強い表現を展示する意義をこう語る。
「志賀さんは震災以降の社会に潜む『見えないようにしているもの』をすくい上げ、写真や言葉、空間構成を通じて多方向の解釈を可能にする物語を立ち上げてきました。それは『そこにかつてあった』ものを写すという写真の性質を広げる営為でもあります。アルゴリズムに象徴されるように均質化しやすい現代社会にあって、このように社会の奥底に潜む揺らぎを捉え続ける姿勢は稀有です。その提示は、アーティゾン美術館が掲げる『創造の体感』を来館者に届けることにも直結すると考えています」
東北の、日本の、そして世界の「見えない」リアルを強烈かつスペクタクルに可視化する。それが志賀理江子の揺らぎない方法論だ。「自分が予想すらできないイメージ、光景に出会うために、私はその風景や現場に対して働きかけている感じなんです、人々が演じているとか演出されているというよりは。私は世界に対して働きかけて、世界が何をレスポンスしてくれるか。そのレスポンスが写真に写りますようにと念じている感じですね」。
アーティゾン美術館の内海は志賀にこう期待する。「志賀さんは写真を出発点にしながらも、言葉や音、インスタレーションを表現に取り入れ、作品やアートの枠を常に拡張してきました。そのスケールや方法は回を重ねるごとに深化し、触れる人に新たな体験と、自ら立ち止まって考えるための契機やイメージを生み出しています。今後もその姿勢を続けていただくこと自体に大きな意義があると思います。個人的には、レクチャーやパフォーマンス作品をさらに拝見したいです」
そのような期待に応えるかのように、志賀の作品はますます映像的、映画的かつ物語的になってきている。今回の展示作品は、そのスケールや風土性も相まって、志賀理江子による東北の新しい視覚的民話のようだ。実際に映像の作品も作っているが、それでも彼女はあえて写真にこだわりたいという。
「例えば何かを思い出す時に、すごく写真的な時はないですか?何か想起する時は、続けて3〜4秒くらいのイメージが多くて、1分ぐらいの映像をありありと頭の中で見るみたいなことはあんまりない気がするんです。やっぱり私が一番身近にずっとやってきた写真というものは、ひとつの呼吸で見ることができる。自分が手がけた写真を見て、それから私の中に映像的なものが生まれるみたいな。そういう行為を私は好きなんだと思いますね。今回は『写真の表現で何ができるんだろう?』ということを追求している感じはありますね。さらには『写真を能動的に見るとはどういうことか?』という追求だとも思っているんです」
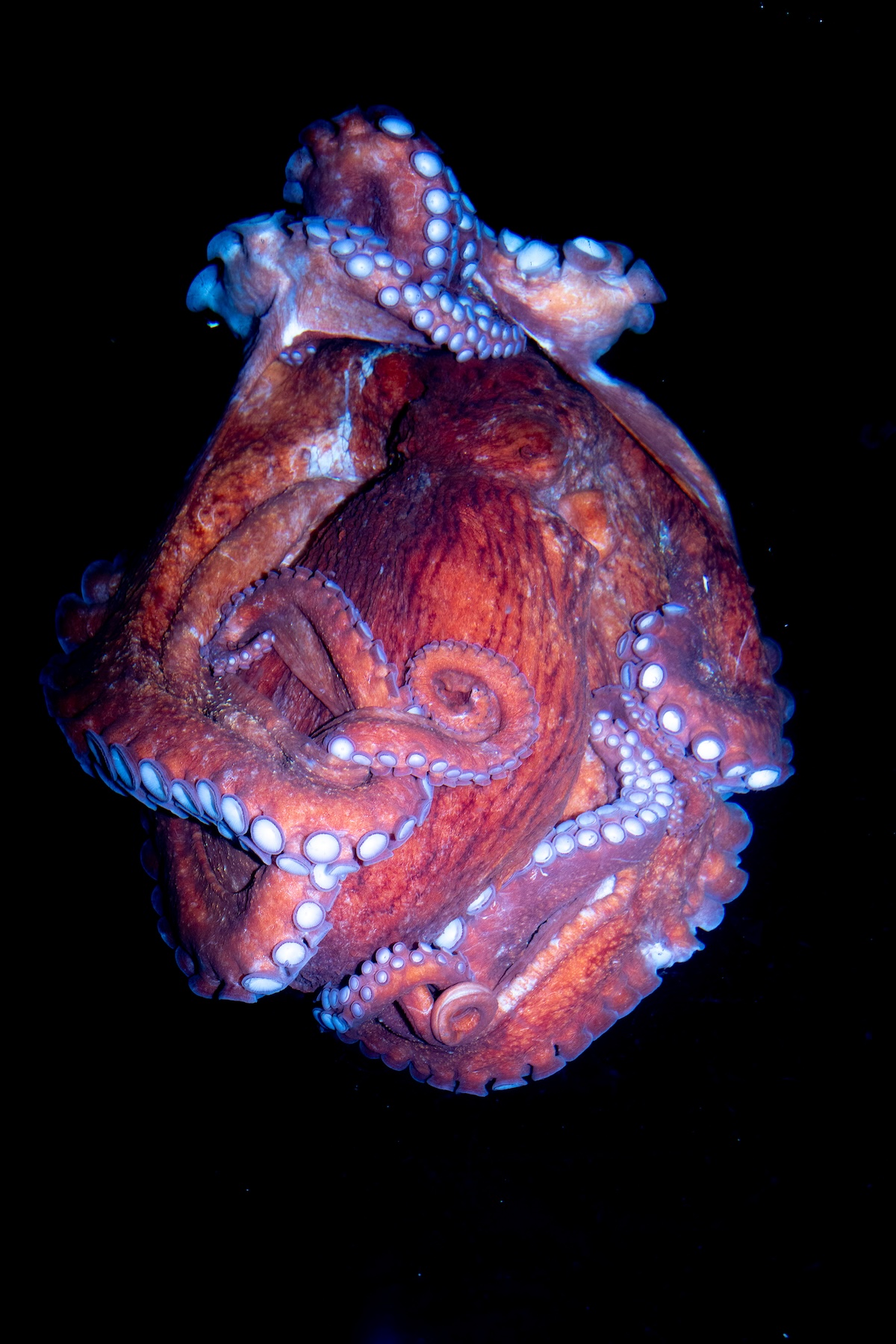
今月の流行写真 TOP10
-
10:『旅と日々』監督:三宅唱
つげ義春原作。女性映画監督の淡々とした創作の日々とその劇中劇を描く。自然の描写が見事で物語というより映像詩のような仕上がり。
10:『旅と日々』監督:三宅唱
つげ義春原作。女性映画監督の淡々とした創作の日々とその劇中劇を描く。自然の描写が見事で物語というより映像詩のような仕上がり。
https://www.bitters.co.jp/tabitohibi/ -
9:Vittoria Ceretti by Carlijn Jacobs for VOGUE Italia July 2025
イタリアが誇るスーパーモデル、ヴィットリア・チェレッティをカーリン・ジェイコブズがモロ80’s調に仕上げる。
9:Vittoria Ceretti by Carlijn Jacobs for VOGUE Italia July 2025
イタリアが誇るスーパーモデル、ヴィットリア・チェレッティをカーリン・ジェイコブズがモロ80’s調に仕上げる。
https://www.vogue.it/article/vittoria-ceretti-intervista-cover-vogue-italia-luglio-2025 -
8:Rachel Brosnahan by Jackie Kursel for Interview Summer Issue 2025
米テレビドラマ俳優のレイチェル・ブロズナハンをNY在住の若手ジャッキー・カーセルがキャンプな演出で撮る。

8:Rachel Brosnahan by Jackie Kursel for Interview Summer Issue 2025
米テレビドラマ俳優のレイチェル・ブロズナハンをNY在住の若手ジャッキー・カーセルがキャンプな演出で撮る。
https://www.interviewmagazine.com/film/rachel-brosnahan-gets-amanda-seyfried-ready-for-superman-summer -
7:『キムズビデオ』監督:アシュレイ・セイビン、デイヴィッド・レッドモン
NYの名物ビデオレンタル店の奇想天外な顛末とそのコレクションの奪還を試みたドキュメンタリーの枠を超えた一本は、映画好きなら誰もが心揺さぶられる。

7:『キムズビデオ』監督:アシュレイ・セイビン、デイヴィッド・レッドモン
NYの名物ビデオレンタル店の奇想天外な顛末とそのコレクションの奪還を試みたドキュメンタリーの枠を超えた一本は、映画好きなら誰もが心揺さぶられる。
https://kims-video.com -
6: Nick Haymes写真展「DANCING ON THE FAULT LINE」@新宿Photographers’ gallery
米クィア活動家を題材とした同名ドキュメンタリー写真集の展示。ニック・ヘイムズは写真家としても写真集編集者としても次なる段階へ移行しつつある。

6: Nick Haymes写真展「DANCING ON THE FAULT LINE」@新宿Photographers’ gallery米クィア活動家を題材とした同名ドキュメンタリー写真集の展示。ニック・ヘイムズは写真家としても写真集編集者としても次なる段階へ移行しつつある。
https://pg-web.net/exhibition/nick-haymes-202509/ -
5:“ANOK” by Mario Sorrenti for VOGUE France Aug. 2025
黒人モデルのアノック・ヤイを徹底的にオブジェ的に捉えたマリオ・ソレンティの造形美。
5:“ANOK” by Mario Sorrenti for VOGUE France Aug. 2025
黒人モデルのアノック・ヤイを徹底的にオブジェ的に捉えたマリオ・ソレンティの造形美。
https://www.vogue.fr/article/interview-anok-yai-mannequin-cover-vogue-france-aout-2025 -
4: 『愛はステロイド』監督:ローズ・グラス
80年代後期の米郊外を舞台にレズの女性と両刀の筋肉女が犯罪に巻き込まれるB級映画だが、A24ならではのツイストが効きまくりジャンル映画を超えた怪作。

4:『愛はステロイド』監督:ローズ・グラス
80年代後期の米郊外を舞台にレズの女性と両刀の筋肉女が犯罪に巻き込まれるB級映画だが、A24ならではのツイストが効きまくりジャンル映画を超えた怪作。
https://a24jp.com/films/loveliesbleeding/ -
3:Emma Stone by Jamie Hawkesworth for VOGUE US Sep. 2025
俳優エマ・ストーンをジェイミー・ホークスワースが彼の絵画的世界に引き摺り込む。

3:Emma Stone by Jamie Hawkesworth for VOGUE US Sep. 2025
俳優エマ・ストーンをジェイミー・ホークスワースが彼の絵画的世界に引き摺り込む。
https://www.vogue.com/article/emma-stone-september-cover-2025-interview -
2:『アイム・スティル・ヒア』監督:ウォルター・サレス
遅ればせながら拝見。ブラジルの名匠サレスによるブラジルの軍事政権下のある家族の悲劇を静謐なリアリズムで描く。70年代映画のようなカメラが秀逸。

2:『アイム・スティル・ヒア』監督:ウォルター・サレス
遅ればせながら拝見。ブラジルの名匠サレスによるブラジルの軍事政権下のある家族の悲劇を静謐なリアリズムで描く。70年代映画のようなカメラが秀逸。
https://klockworx.com/movies/imstillhere/ -
1:Bruce Weber “My Education”(Taschen)
ブルース・ウェーバーの564ページにも及ぶ集大成本。セレクト、デザイン、紙と印刷も見事で写真集の金字塔的仕上がり。
1:Bruce Weber “My Education”(Taschen)
ブルース・ウェーバーの564ページにも及ぶ集大成本。セレクト、デザイン、紙と印刷も見事で写真集の金字塔的仕上がり。
https://www.taschen.com/en/books/photography/08182/bruce-weber-my-education/


















