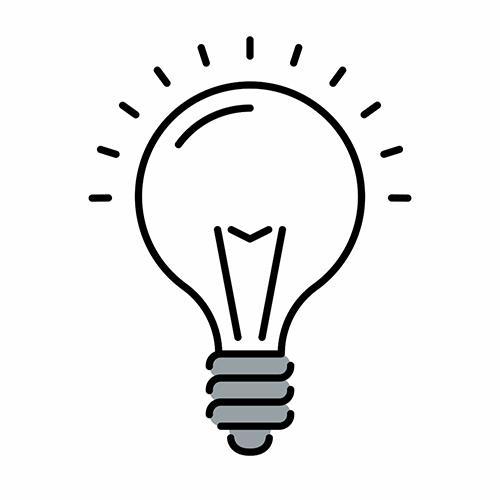宮入法廣(のりひろ)さんの工房は通常の土間ではなく、伝統にとらわれず、合理性を重んじた師匠の隅谷正峯がそうしていたのと同じ、耐火レンガ敷き。長野県・東御市内を見晴らす自宅のリビングで、宮入さんが手がけた数多くの刀(試作を含む)を手に取ってみながら話を聞いた。

BRUTUS
ここまで取材して、かえってわからなくなってきてしまったのですが、何より知りたいのは「いい刀ってなんだ?」ということ。
宮入法廣
まず姿形が洗練されていること。それから地鉄が冴えていること。これは流派ごとにいろいろな特徴があり、見どころも異なりますが、晴れ渡った秋の満月と春の朧月くらいの差があります。そして3番目が刃文で、やはり多彩な個性がある。この3つが揃って初めて、名刀と言えるのではないでしょうか。
山中俊治
いずれにしても、鑑賞が主体ということですね。切れ味などではなく。
宮入
切れ味うんぬんを言い出すようになるのは、江戸時代以降のこと。刀を実用しなくなった時代だからこそ、付加価値を付けて高く売るために、そんなことを言い出したのでは。
山中
実際に刀を使っていた時代は、わざわざそんなことは言わないか。
宮入
まして名刀、格の高い刀は、いざとなれば使うにせよ、基本的に「持っているもの」ですから。
山中
では「用の美」ではなかった?
宮入
本来武器として作られたものですが、その中に出来のいい、名刀と呼ばれて家に代々伝えられるような刀がある。その一方で、ただ道具として刀の形をしていて、刃が入っていればいい、という考えで作られたものもある。2通りに考えなくてはいけないと思います。
山中
挙げていただいた3つの条件と武器としての機能は、まったく関係ないのですか?
宮入
必ずしもそうではないと思います。例えば鎌倉時代に備前で活動した長船長光や、京都の来国俊など、当初は非常に華やかな乱刃を焼いていました。ところが元寇以降は直刃になっていく。
その理由を考えた時、例えばモンゴル軍との戦闘中に刀が折れるようなことが頻発し、それを改善するために施した工夫があるとして、刃文の変化がそうした機能面での工夫と関係していてもおかしくはありません。
山中
実際使ってみると、考えた通りにはいかない、と。
BRUTUS
宮入さんがお仕事の中で、正倉院の刀子や稲荷山古墳の鉄剣など、古刀の復元を積極的に手がけているのは、そうした古刀期の技術を深く知りたいからですか?
宮入
そうですね。基本的な技術がわからなければ、どうしようもありません。我々がいままで教わってきた技術は新々刀(復古刀を目指した水心子正秀以降、廃刀令まで)のもので、それ以前の古刀に迫ろうと思えば、もう一歩前に出るしかない。
正倉院の刀子を復元した時にも、ちょっとしたヒントがありました。自分はまだ作風が確立していませんから、こうした知識や技術を応用して、これから自分なりの方向性を見つけていきたいと思っています。
孤高の巨匠、隅谷正峯に弟子入り。
山中
宮入さんはどうやって刀鍛冶の技術を学んできたのですか?
宮入
うちは江戸時代末期からの刀匠の家で、父の宮入清宗も刀匠、伯父の宮入行平は人間国宝でした。ただ僕は少し変わっていて、途中からまったく流儀の違う隅谷正峯先生の下へ行ってしまった。
隅谷先生は独学で技術を身につけてきた方で、一門の縛りはないから受け入れてくれました。それでも伯父や、当時刀剣界の御意見番だった先生が存命であれば、叶わなかったかもしれません。
山中
宮入さん自身は現代に生きる方ですから、最近の科学、技術の進歩の中で新たにわかってきたことについて、それはそれとして理解されると思います。そうした科学的事実がわかっていなかった時代と、わかってしまった後の時代で、日本刀の作り方は変わってきたのでしょうか。
宮入
いま僕らが使っている技術は、鎌倉時代までに完成されてしまっている。基本的にそれを踏襲しているだけで、変化はないと思います。
山中
なるほど、では近代科学は、過去の技術がどのようなものであるかを紐解いただけであって、新しいやり方が生まれたわけではない、と。
宮入
はい、現代の言葉や解説に当てはめていくだけです。
山中
制作のための道具、設備についてはいかがですか。
宮入
変わりません(笑)。強いて挙げるなら、金箔を打ち延ばすハンマーを改良した機械ハンマーが、大正時代に導入されたことが、最大のイノベーションです。
かつて、この打ち延ばしの工程には複数の人手を必要としましたが、現在は機械ハンマーのおかげで、一から十まで1人でできるようになりました。原材料の品質もより安定しているでしょうし、そういう意味では、品質の安定したものを作れるよう、進化してはいるのです。
ですがその過程で失われたものもある。例えば雅味、自然味は、薄れていると思います。現代ではまず安定したもの、完成されたものを作ることが第一義ですから、過去の不安定な技術は残りません。
山中
現代の我々が、抗いがたい魅力を感じる古刀を、そうあらしめているものが何かといったら、不安定な技術ゆえの味わいかもしれない、ということですね。
宮入
そうです。だから完全なもの、疵や欠点、破綻が何一つないものばかりを求めていてはいけないような気がしています。疵や破綻を景色として見るくらいの感覚でなければ、古刀の地鉄は恐らく再現できません。実際、古刀は多少の破綻があっても通用しているわけですし、そういう感覚を許容した方が、面白い作品ができるのではないでしょうか。
技術を極めてからやっとスタートラインに立てる。
山中
だから刀はプロダクトではなく、「アート」なんですね。こうして宮入さんのお話を伺っていると、刀についての哲学を非常に明解に語っているように思えます。にもかかわらず、ご自分の作風がまだ確立していない、というのは、どういうことなのでしょう。
宮入
うーん、形に表れるとしか言いようがないですね。僕らがどこで個性を出すかと考えた時、形状については決まっていて、変更の余地がありません。そうなると個性を表現できるポイントは、地鉄か刃文に絞られますが、そこで何をするのか。
例えば僕が師事した隅谷先生は、生前から「隅谷丁子(刃文)」と呼ばれる、個性ある作風を出しておられました。あるいは、古い時代の地鉄や、映り(備前刀の特徴で、地に白く影のように見える)の表現を追求するにしても、技術の掘り起こしを納得のいくまでしてからでないと、スタートラインに立てない。
それでも最近ようやく、そろそろスタートラインに立てるかな、と思えるようになってきたところです。
山中
失礼ですが、今おいくつでいらっしゃいますか。
宮入
62歳です(笑)。
山中
62歳で今がスタートライン。素晴らしい!
映りの再現に成功した、正宗賞受賞の短刀。
宮入氏は長年備前刀の映りを独自に研究しているが、2010年、重要文化財に指定される備前景光の短刀の、特徴的な乱れ映りを忠実に再現することに成功。14年ぶりとなる正宗賞を受賞した、平造の短刀。富山・森記念秋水美術館蔵。