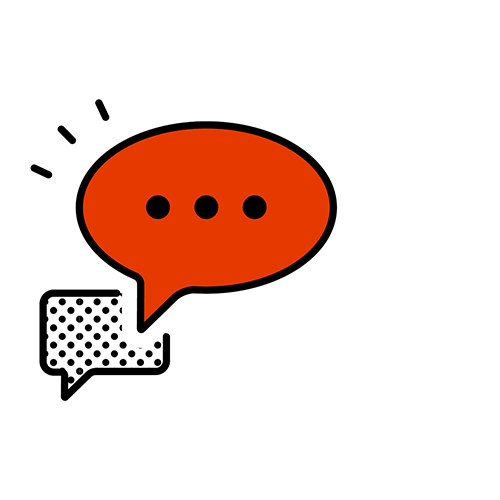中川がいけばなの世界に登場したのは、太平洋戦争後に興った所謂いけばなブームの潮流の最中であった。戦後の経済成長の下、人々は死の香りを消し去るかのように様々な余暇に興じるようになった。いけばなもまた隆盛期を迎えたが、只々美しいだけの飾り物になった。
古くから続くいけばなの流派はめまぐるしく変わる時代の中、伝統を維持することに固執し、新しく生まれた流派は伝統という枷から解き放たれた自由な花を模索した。そんな価値観の揺らぎに中川幸夫という人の花が突き刺さった。
いけばなの史実を紐解くとその発祥は室町時代、足利義政の美学が結晶した東山文化からだという。虚飾を払い、清浄な心鎮まる空間が生まれた時代はまた血で血を洗う戦乱の時代でもあった。ハレとケが背中合わせの狭間に産まれた初めてのいけばなの様式は立花と呼ばれた。
30歳の頃、一門下生として立華の伝承流派・池坊を学んだ中川。そして流派を離れ、己の花をいけはじめる。目指したのは「花」は切られ、殺されるからこそ「生け花」へと生まれ変わるという原点回帰だった。「型は教えられても血は教えられない」と語った中川は生涯弟子をとらなかった。
花は死に対して無抵抗である。花はただ自らの運命を人の手に委ねる。おそらく中川は、手の中でひんやりとする花の温度の向こうに自分と同じく血の通ういのちを感じ、それを何とか引きずり出して見せようとしていたのではないか。
4,500本のチューリップの花弁は流れるはずのない赤い血を流し、情緒を排した花の肉塊へと変貌する。一見濃厚な死を感じさせる作品は実のところ命の臨界点、死の間際の花の煌めきなのだ。
文・片桐功敦 ●花道みささぎ流家元