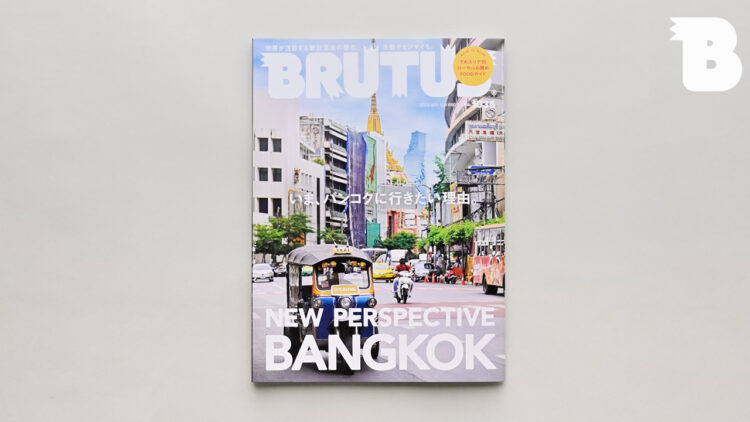1.セリフの描き方で異質さを演出する
アニメと比べたときの漫画の弱点は、キャラクターの声が“音”として読者に伝わらないところです。その言葉を発しているときの声の強度やテンションは、読者の想像力に頼るしかありません。そこでイメージの補助になるのがフォントとフキダシの形です。
ほとんどの場合、同じ作品・ページの中でも複数のフォントが使い分けられています。とりわけ演劇や映画などの“芝居”を題材にした作品ではこれが顕著。『崖際のワルツ』の表題作では、演じると大声の棒読みになってしまう主人公のセリフが禍々しい手書きの文字と枠で表されている。キャラクターの個性が一目で伝わってきます。

著:椎名うみ/2017年発売/講談社
高校演劇を舞台にした表題作の「崖際のワルツ」。主人公の西園寺華は新入部員の初顔合わせで強烈な大根役者ぶりがあらわになり周囲に笑われてしまうが、そこに個性を見出した同級生の五反田律とペアを組むことに。2人が15分寸劇の課題で『白雪姫』を披露すると、抑制の効いた律の芝居と棒読みの華が意外性のある掛け合いを生み出していく。「漫画にはアンチックと呼ばれるフォントがよく使われますが、本作は数種類の書体で芝居の質感を伝えています」
他方で、『映像研には手を出すな!』では、背景に合わせてフキダシにパースをつけることで立体的な空間を強調することに成功しています。フォントやフキダシの描き方一つで、キャラクターや世界観の異質さを演出できるんです。

著:大童澄瞳/2016年〜連載中/小学館
第3話、〈映像研〉を結成して部室を確保した浅草みどり、金森さやか、水崎ツバメの3人は、アニメを作る際に必要な机を手に入れるため芝浜高校の倉庫へ。川や風車があるダンジョンのような空間に降り立つ。「大童さんは、背景を描き込むためにフキダシにパースをつけて面積を小さくしたと言っていて、その発明が結果的にこの作品に合った3次元的な空間表現に寄与しているんですよね」
2.コマ割りの変化で物語にリズムを生む
コマ割りは漫画家にとって最も重要なスキルだと思います。優れた漫画は、物語や感情の流れをコマ割りで表現するのが抜群にうまい。漫画の基本構成とされているのは、1ページを3段に割った「3段組」。これをベースにしつつ、物語展開や感情の動きに合わせて、斜めに線を入れた変形ゴマや見開きが使用されます。
こうしたイレギュラーなコマ割りは華がありつつも、使いすぎるとメリハリが出なくなってしまうので注意が必要です。『狭い世界のアイデンティティー』では、登場人物の疲弊した心情と同期した単調なコマ運びが続くなか、“怒り”の感情を起点にしてコマが変化していく。リズムの変調が可視化されていて、コマ割りのお手本のような場面です。


著:押切蓮介/2016〜20年連載/講談社
漫画業界を舞台に、漫画家同士が殴り合いで優劣を決める抗争に発展していく。第22話、登場人物の押切蓮介と清野とおるが酒を酌み交わすなか、ウェブ漫画家が茶々を入れてくる場面。「漫画業界を描いた漫画」という視点を生かし、コマ割りの変化がメタ的に言及されている。「紙媒体を否定する相手に怒りが湧き、斜めゴマが登場するシーンの迫力がすごい。“見どころ”が明確です」
3.専門性の高い場面をリアクションで実況する
囲碁漫画の『ヒカルの碁』。囲碁といった専門的な知識が必要になる競技は、ルールを知らない人からすれば登場人物たちの強さが伝わりづらいと思います。ただ、この作品では対戦相手や脇役のリアクションを丁寧に描くことによって、そのプレーがいかに特殊かを伝えている。スポーツ番組における実況・解説のような役割を果たしています。

原作:ほったゆみ/漫画:小畑健/1998〜2003年連載/集英社
天才囲碁棋士の霊に取り憑(つ)かれた主人公の進藤ヒカルが神の一手を極める姿を描く。第164局(話)、日本代表を決める北斗杯予選決勝でヒカルと対戦した社(やしろ)清春は、初手を5の五に打つ。「20巻で登場した新キャラの社が見せた奇抜な一手。“とんでもないやつが現れた”と読者にわからせる鮮やかな描写です」
4.シリアスな展開を軽妙なギャグで支える
いわゆるギャグ漫画ではない作品で、ギャグが効果的に使われている場合があります。重厚なテーマであるがゆえに緊張感が張り詰めている物語を、随所に挟まれた“コマ単位で笑えるギャグ描写”によって支えるという手法です。
通称『チー付与』もその事例の一つ。シリアスな場面にあえて間の抜けたコマを配置することで、読者に次のページをめくってもらう原動力を与えています。

漫画:業務用餅/原作:六志麻あさ/キャラクター原案:kisui/2022年〜連載中/講談社
魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内のすべての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。「感動的で骨太なストーリーの間にギャグが挟まれていて、もはや前者はフリになっているような作品。読み進めていくとこのシリアスと笑いが混ざった世界にどんどんハマっていきます」
5.フリオチで心情の変化を強調する
物語の核心やあるメッセージを伝えるために、漫画家たちは「フリオチ」の技法を使うことがあります。フリオチとは、フリの段階で物語の展開を予想させたうえで、それを裏切るような結末(オチ)を用意すること。フリオチがうまくいくパターンでは、フリとオチの間に“変化”があるんです。その変化は3種類あると考えていて、状況・心情・評価が挙げられます。
例えば、勇気を持てなかった主人公が紆余曲折を経て敵に挑むことを決心するといったストーリー展開では“心情の変化”によるフリオチが効果的に使われています。ストレートに話を進めるのではなく、否定からの肯定といった変化を経由することで、メッセージに強度を持たせることができる。
また、読者はより深く物語に感情移入することができるんです。そうしたフリオチのうまさが光っているのが『チ。』。オチに説得力を持たせたい場面で、途中のフリがきれいに作用しています。


著:魚豊/2020〜22年連載/小学館
地動説を証明することに自らの信念と命を懸けた者たちの物語。第16話、地動説を研究するバデーニは、協力者を探す過程でヨレンタに出会う。「バデーニは最初、ヨレンタを切り捨てられる存在として軽んじていたけれど、地動説の話をする中でやがて研究者として認めるに至る。ここには状況・心情・評価の3つの変化が同時に訪れていて、鮮やかなフリオチで物語を加速させています」