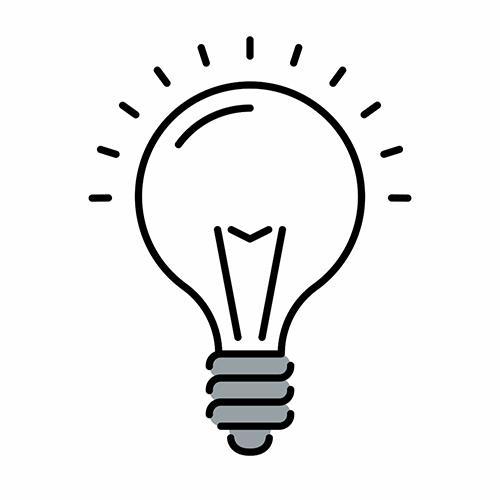好奇心こそが
最強のリテラシーを育てる。
2022年度から全国の高校で導入される新科目「情報Ⅰ・Ⅱ」は、情報リテラシーやプログラミングを学ぶために作られたものだ。
この教科が必修科目として指定されたことは、「情報を処理する技術」が現代の人々にとって必要不可欠なことを示唆しているだろう。真偽の不確かなニュースに溢れた社会で惑わされず生きるために、私たちは情報との関係性をどうデザインしていけばよいのだろうか?
情報処理学会誌の編集長を務め情報学の動向に詳しい東京大学教授・稲見昌彦さんは「好奇心」にヒントがあると語る。
「インターネット以前は頑張らないと目当ての情報が見つけられませんでしたが、今や処理し切れないほど多くのデータに私たちは囲まれています。それを整理するために人は検索エンジンやレコメンドエンジンを進化させ、好きなものを好きなだけ見られる環境を生み出してきました。
しかし、同時に自分の見たいものしか見ず、同質的なコミュニティから生まれたフェイクニュースや陰謀論が社会を分断しているのも事実です。そんな、いわゆるフィルターバブルと呼ばれる状態から脱するためには、自分の現在の好みに流されず好奇心を持って自分の認知の外側に広がる世界を想像しなければいけません。
これからは異なるコミュニティを渡り歩きながら、本来つながっていない情報を各自がつなげていくことが重要だと思います。
今はDeepLのような翻訳エンジンが高度に発達しているので言語の壁もかなり低くなっていて、国境を越えてつながりやすくなっていますから。“貿易”を行うように、領域を超えた交流を意識的に行う必要があります。
そのためにはただ違うコミュニティに行けばいいわけではなくて、かつてフランシスコ・ザビエルが日本の文化に合わせながらキリスト教を広めていったように、コミュニティ同士の共通項を模索しながら働きかけていく意識が有効になるでしょう」
*
稲見さんの言う通り、私たちはともすると自分の興味のある世界に閉じこもってしまいがちだ。他方で、未知の世界に踏み出すことが重要だと言われても、真偽の判断がつかないニュースに溢れている世界にあっては自分の知らないものをどう信じればいいのかわからなくなることも多いだろう。
「信頼をどう構築するかは重要な問題です。ブロックチェーンのように多くの人が計算競争に参加し信頼性を担保する技術も開発が進んでいますが、そもそも私たちは古来、他人から信用されるためにエネルギーをかけてきたともいえる。
かつて布に価値があるとされていたのはそれを生産するために労働力が必要だったからですし、書籍や論文は校正や査読を通じて多くの人の労力が割かれているからこそ信頼に足るソースとなっている。あるいはビジネスパーソンは人から信頼されるためにスーツを着たりネクタイを締めたり服装にコストをかける。信頼性とそこに割かれたエネルギーの多寡は相関していると考えます」
自分が目にしているテキストやニュースそのものではなく、それが作られた背景まで想像すること─視野を広げてみることで世界の見え方も変わるが、誤った情報が急速に広がり社会を混乱させる「インフォデミック」と呼ばれるような状況にあっては、技術だけで危険な情報を淘汰することも難しい。
「反ワクチン運動や陰謀論を少なからぬ人が支持している状況を踏まえると、システムで正確性を証明するだけでは限界がありそうです。人を閉ざされたコミュニティの外に連れ出すためには、論理的に説得するだけでなく感情に訴えかける必要があるのだと思います。
情報という言葉はえてして非人間的なイメージを持たれることが多いですが、“情”という字が使われているように実は身体性を持った人間的なもの。
もちろん感情をうまくコントロールすることでファシズムのように危険な体制が生まれてきたことには注意が必要ですが、心が動かされなければ人は動かないとも思います」
*
稲見さんが語るように、情報とは数値やデータのようにスタティックなものではなくもっと有機的で揺れ動くものなのだろう。現に歴史を振り返ってみても、人間や社会が変化していくにつれ情報のあり方やそれを扱う技術も変わっていったと稲見さんは続ける。
「例えばコンピューターの登場によって漢字が簡素化する流れがほぼ止まったと言われますし、さらに絵文字は新しい文字の誕生ともいえる。
Slackでユーザーがオリジナルスタンプを大量に作っているのも新たな文字文化なのかもしれません。そもそも現代のデジタルメディアは視聴覚しか扱えていない。
触覚や味覚などほかの感覚を扱えるようになれば、人間とコンピューターとの関係はさらに変わっていくでしょう。これまでスポーツのトレーナーや介護士は言語化しにくい身体運動をどうにか言葉で説明しようと試みていましたが、扱える感覚の情報が増えれば言葉を介さずに動きを伝えられるようになりますよね。
最近は音声メディアが注目されていますが、将来的には“動き”のSNSが生まれる可能性だってある。匂いや手触りのように身体的なものこそが大切になっていくのかもしれません」
私たちはしばしばアナログとデジタルを区別し、前者の方が豊かでかけがえのないものだと考えてしまうが、必ずしも両者は切り離されているわけではない。さまざまなサービスやデバイスが開発されるにつれ、人間の扱える情報はどんどん広がろうとしている。
「かつて研究に行き詰まった私の恩師は、気分転換のためにフィレンツェの丘から街を眺めていたらふと新たなアイデアが思い浮かんだらしいのですが、今やGoogle EarthとVRグラスがあれば恩師が見たのとほとんど同じ景色を見られるようになりました。
異文化・異言語学習においては現地に行かないと本当に身につかないといわれますが、Googleストリートビューのようなサービスによってバーチャルに現地を訪れると視覚的には近い体験ができるようになりつつある。
触覚や嗅覚、味覚、そしてその場でのやりとりも扱えるようになれば、さらに体験は変わっていくんじゃないでしょうか」

コンピューターやインターネット、AIなどテクノロジーの発展に従って、日々私たちと情報の関係性は変化している。だからこそ、これからは好奇心のような人間性や身体性を生かすべく主体的に情報と向き合い、それを活用していくことが重要になっていくのだろう。
「プログラミングの必修化が話題になっていますが、単にさまざまなプログラム言語を使えるようになることだけが重要なわけではありません。
パーソナルコンピューターの父と呼ばれる科学者、アラン・ケイがかつて“コンピューターはアイデアを奏でる楽器である”と語ったように、一人一人が頭の中に浮かんだイメージを表現できるようになることが大事なんですよね。
表現方法は文章でもいいし、音楽でもいい。プログラムやVRスケッチでもいいと思います。好奇心を育て、個々人の表現を支援していく手段を増やし、さまざまな情報の扱い方を身につけること。
それはこれからの社会を生きるための新たなリテラシーになるのだと思います」