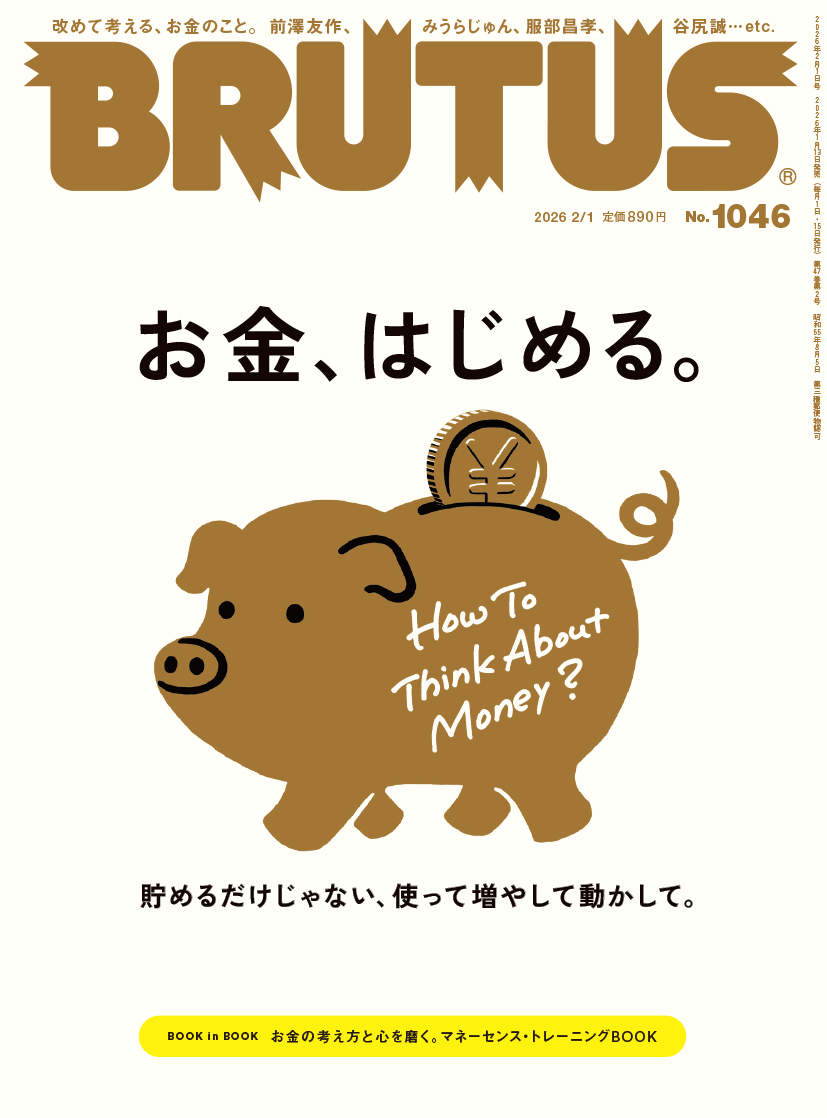「ヒプノシス」というデザイン集団をご存じだろうか。仮にその名は知らなくても、ピンク・フロイドの「牛」とか「プリズム」のジャケットと言えば、知らない人はほとんどいないはずだ。
ヒプノシスとは、ストーム・トーガソンとオーブリー・パウエルが立ち上げ、1970年代を中心にイギリスを拠点に活躍した、主にロックミュージャンのレコードのジャケットをデザインする集団で、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、ポール・マッカートニーなど、数多くのビッグネームの作品を手がけた。実は、松任谷由実の『昨晩お会いしましょう』や『VOYAGER』などのジャケットもヒプノシスによるものだ。

ヒプノシスのデザインは、表ジャケにアーティスト名やタイトルを入れないなど、それまでのレコードのカバーアートの概念を覆すもので、そのアイデア、斬新さ、奇抜さ、ユーモアなど、レコードのデザインをアートの域に高めるものだった。
そんなヒプノシスの活動の全貌を、当時の関係者などの証言を交えながら伝えるドキュメンタリー映画『ヒプノシス レコードジャケットの美学』が、公開された。そこで、昨年韓国で開催された展覧会も観に行かれたという編集者の岡本仁さんに、ヒプノシスのクリエイティブの魅力について語ってもらった。まずは、ヒプノシスとの出合いから。

「ヒプノシスが手掛けたもので最初に買ったレコードは、ピンク・フロイドの『原子心母』だったと思います。実は、音を聴いたのはずっと後年で、牛のジャケットと日本語のタイトルに惹かれて買ったんですよね。いわゆるジャケ買いです。それくらいインパクトが強かった。スコーンと突き抜けた良さがあって。(マルセル・)デュシャンの便器(『泉』)じゃないですけど、何でもないありふれたものが、こうしてレコードのジャケットになったときの衝撃。まさにアートだと思いました」
ただ、その時点では、まだヒプノシスの名前は認識していなかったと言う。

「次は、XTCの『ゴー2』じゃなかったかな。『これはレコードジャケットです』から始まるテキストの羅列。さらに、『このデザインは、レコードを売るためのものである』とか何とか。こんなことやっていいんだとびっくりしました。そのときに初めて、ヒプノシスの名前を意識したような気がします。いや、レッド・ツェッペリンの『聖なる館』のときだったかな。
それからは意識するようになって、ヒプノシスの作品を集めた洋書も買いました。ただ、80年代に入ると、ニューウェーブとか、音楽のモードの変化もあったのか、あまり彼らの仕事を見なくなったんですよね。そんなときだったんです、ゴドレイ&クレームの「クライ」のPVを見たのは。モーフィングで、ある人の顔が別の人の顔に徐々に変わっていくあの映像。これもヒプノシスがやっていたんです。彼らは、いつのまにかジャケットのデザインから映像にシフトしていて、やはり時代に先駆けたことをやっていた」

そんな岡本さんが、久しぶりにヒプノシスを思い出したのが、昨年のソウルでの展覧会のときだったという。
「現地の人に教えてもらってやっていることを知ったのですが、これは見なきゃと思って。ソチョン(西村)のグラウンドシーソーというギャラリーでやっていたのですが、これが素晴らしかった。入ると、すぐに例のXTCの『ゴー2』のジャケットを拡大したものが展示されていて。
もちろん、彼らが手がけた作品は各アーティストごとの部屋に分けて展示していて、アザー・バージョンなんかも見られるんです。さらに、映画にも出てくるヒプノシスの事務所やスタジオの雰囲気なんかも一部再現されてわかるようになっていて。他の展覧会もそうなんですが、韓国のキュレーターは見せ方や楽しませ方がうまい。だから、ヒプノシスを知らない若い人たちでも楽しめるようになっている。日本でもぜひやってほしいですね」
そして、昨年のその展示に引き続いて、今年『ヒプノシス レコードジャケットの美学』が観られることになったのは、個人的にも本当にラッキーだったという岡本さんに、この映画の見どころを聞いた。

「いや、本当に面白かったです。ピンク・フロイドの『炎~あなたがここにいてほしい』の燃える男とか、『アニマルズ』の空飛ぶ豚とか、その舞台裏のエピソードとかももちろん面白いですし、関係者たちが、ヒプノシスのメンバーたちに対して語る毀誉褒貶ぶりも凄まじい(笑)。
あと、80年代を象徴するデザイナーのピーター・サヴィル(ジョイ・ディヴィジョンの『アンノウン・プレジャーズ』のデザインなどで有名)や、90年代のオアシスのノエル・ギャラガーのコメントが入ることによって、単なる礼賛じゃなく、現代の視点で客観的に捉え直しているところも良いなと思いました。
それにしても、10ccの『ルック・ヒア?』みたいに、わざわざハワイまで行って海で羊を撮影したり、そこまでお金や時間をかけておいて写真を小さくデザインしたり、あのバカバカしいユーモアは、今のコスパとかタイパを重んじる社会の中では呆れられるかもしれないけど、だからこそ、この時代を知らない若い人にも観てほしいですね」