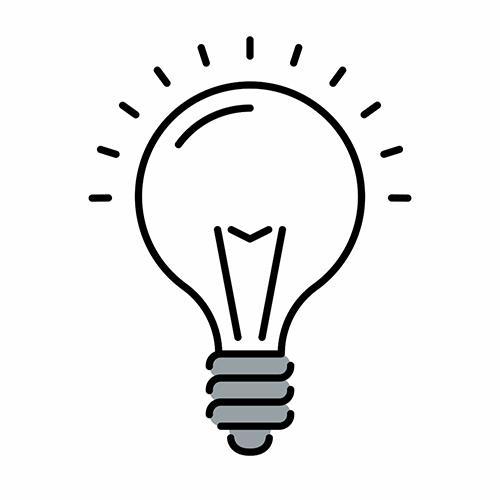話を聞いた人:荒木浩之(クボタ研究開発本部次世代技術研究ユニット)、佐藤光泰(野村アグリプランニング&アドバイザリー調査部長)
1:オフィスで働く、ネオ農家
農作業のフルリモート化が実現すると、農家の姿もがらりと変わる。職場は都会のオフィスビルで、目の前には複数のモニターがずらり。農作物の生育状況や農業ロボットの動作を確認しつつ、AIが推測した収穫時期や収量に基づいて、商品を販売する手はずを整える。長年の経験がなくても、各種ロボットやAI、loTを活用できるため、1年目から安定した収量を確保し、利益を出せる。他業種からの転職組も増え、若者の就農も目立ってくるだろう。
「世界的に見ても、農業関係のスタートアップ企業は増えています。人口増加や天候異変などで、今後、農作物の需給は逼迫するでしょう。もっと農業は見直されてもいいし、ビジネスチャンスは広がっています」(野村アグリプランニング&アドバイザリー調査部長・佐藤光泰さん)
2:産直ECとドローンで流通が変わる
近年、生産者と消費者を直接結びつける産直ECが増加している。
「コロナ禍の影響もあって、生鮮食品の産直ECはかなりの伸びを示しています。消費者が全国の生産者と直接やりとりしながら旬の食べ物を買える『ポケットマルシェ』や、オンライン直売所『食べチョク』など、生産者の顔が見えて、安心できる食品を買いたいというニーズは今後も高まっていくでしょう」(佐藤さん)
将来的には消費者が好むものを生産者側が提案してくれる可能性もあるという。
「その人の味覚の好みを科学的に測定した“ベロメーター”で、好きな野菜や体に必要な野菜などを割り出し、希望価格帯などを設定しておけば、産直ECの生産者側から“あなた好みの酸味の強いトマトを提供できます”“お好みの味や栄養素の野菜をお近くの植物工場で作ります”とオファーしてくれるようになるかも」(佐藤さん)
商品の輸送手段やコストは課題だが、地産地消の流れが加速すると予想される。
「食品を輸送すると、フードマイレージがかかります。フードマイレージとは、輸入した食料の重さ×生産地から消費者の食卓に並ぶまでの輸送の距離で算出した数字。数字が大きいほど、輸送にかかる燃料や二酸化炭素排出量も多くなるため、地球環境に良くない、という考え方が広まっているのです。輸送距離を短くするために、最寄りの植物工場や田畑で収穫した新鮮なものをドローンなどで自宅に配送するのが主流になるのでは」(佐藤さん)

3:植物工場では、葉物以外も生産可能に
今も日本や世界各地で植物工場が稼働しているが、栽培しているのはレタスやベビーリーフ、ルッコラ、ホウレン草などの葉物野菜が主流となっている。未来の工場では、果樹や米など、私たちの暮らしに必要なその他の農作物も作れるようになるのだろうか?
「商業ベースに乗っているのが葉物野菜というだけで、実は、今でも技術的には作れるんです。また、フードマイレージへの意識が高まることによって、遠方から輸送するものに高い税金がかかるなどビジネス環境が変わる可能性が高く、遅かれ早かれ、コスト面の問題をクリアして葉物野菜以外のものを作ることになるのではないでしょうか」(佐藤さん)
4:高品質の農作物を、海外で作る
近年、日本の高級な野菜や果物が海外で人気を集めている。現地の高級スーパーなどで、シャインマスカットやブランドイチゴが高級品として並べられているのだ。現在は冷蔵コンテナを使って空輸で、なるべく鮮度を保ったまま現地に送っているが、未来では生産拠点ごと海外に移し、生育環境が異なる現地でも、日本と同等の農作物を作るのが当たり前になる。
「これもフードマイレージの関係で、日本からの輸送がビジネス的に難しくなるからです。栽培技術や植物工場が進化すれば、日本と環境が異なる場所でも、日本と同じように高品質の農作物を作れるようになるはずです」(佐藤さん)
既に、2017年にニューヨーク近郊で日本品種のイチゴを生産する植物工場を稼働させ、世界で初めて植物工場で高級イチゴの量産化に成功した日本人もいる。
「アメリカのイチゴは硬くて甘味もなく、おいしくない。そこで、コンサルタント出身の古賀大貴さんがOishii Farmを立ち上げ、高級イチゴの安定生産を実現させました。現在創業4年ですが、すでにトヨタなどから55億円の資金調達を行っています」(佐藤さん)
今まで、日本国内で高い技術を持っていても海外には無縁という農家が多かった。技術が進歩すれば、日本から鮮度を気にしながら高いコストをかけて輸出しなくても、自分の農作物に興味を持ってくれそうなマーケットのすぐそばで、日本と同じような環境を整えて農作物を栽培し、現地で販売するのも夢物語ではない。農業ビジネスの新しい展開ともいえる。
「日本で作った“メイド・イン・ジャパン”ではなく、日本人が作った“メイド・バイ・ジャパニーズ”という言葉があります。もともと日本の植物工場が世界から注目を集めるきっかけになったのは、千葉大学のスタートアップ企業、株式会社みらいが、南極の昭和基地に作った植物工場なんです。あんなに厳しい環境の南極でも作物を育てることができるのですから、世界のどこでも、できるようになるはずです」(佐藤さん)