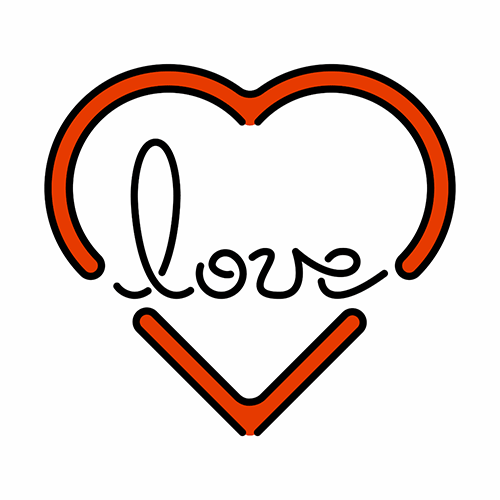ドリス・ヴァン・ノッテンのコレクションのDNAとして、毎シーズン必ず発表される美しい刺繡のアイテム。なぜ表現方法として刺繡にこだわるのか、本人へのインタビューからその秘密を探った。
「そもそも私が刺繡に惹かれるようになったのは、厳格な母の影響が大きいと思います。レースと刺繡が大好きで、特別な日には必ずテーブルを美しく飾り、毎回違うクロスと、中央にはレースの布。決まって話してくれたのが、その装飾品について。“このレースはベルギーのどこから来たのよ”とか“刺繡の編み目が細かすぎて修道女たちは虫眼鏡を掛けて製作しているの”など。職人の手から生み出されたものに、人(母)は愛情を注ぐことを幼いながらに痛感させられたエピソードでした」
曽祖父はテーラーを営み、それを引き継いだ祖父はメンズのプレタポルテの第1号店を開き、父はデザイナーズブランドを扱うブティックを開店。3代にわたり服飾を生業とする家系に生まれたドリスがファッションに興味を抱くのはごく自然な流れだったのだろう。
「アントワープ王立美術アカデミーのデザイン科では、卒業制作に没頭したことを鮮明に覚えています。振り返ってみると実験的なコレクションでした。蛇革のコートやシルクのイブニングドレス。ほかにもリネンを多用した服や、激しい刺繍やレースを施したアイテムを制作した記憶があります」
頭の中にある創造性を最も表現できる手段。
自身の名を冠したブランドを立ち上げて、今年で30年目。
「毎シーズン必ず用いる刺繡には、どれもインスピレーションの出発点があります。2015−16年の秋冬シーズンは、中国の少数民族“ミャオ族”の伝統衣装に着想を得ました。洋服に刺繡された横縞の模様が、消防士が着るユニフォームのテープに見えたんです。ある文献を調べると、昔の日本では、火消し(江戸時代の消防士)が藍染めの服を着ていた史実があった。だからデニム生地を組み合わせてみよう、と発想しました。
その過程で絶対にやらないのはミャオ族がいる現地を訪れたり、オリジナルをそのままコピーすること。できるだけ頭の中で旅をイメージしながら色々な要素をミックスして、独自の創作に変える。それが最も重要で、自分らしいことなのです」
イメージを具現化する生産背景にも驚くべきストーリーがある。
「私がインドを訪れ始めた頃、ファッションではまだ現地で生産している人がいなかった、と記憶しています。コルカタは色鮮やかな織物を伝統とする地域。そこで母がコレクションしていた刺繡が蘇ってきたのです。私はすぐさまそこを取りしきる人と契約を結び、技術指導をしつつ、仕事を依頼してきました。
村にコテージが点在し、一つのコテージに3〜5人の職人が集まって作業をする。これをコテージインダストリーと呼んでいます。やりとりが始まって26年が経ち、インドとアントワープのアトリエを行き来するスタッフを立て、滞りなく作業を進めています。
今では村やコテージ単位で服が完成するシステムが構築され、次の世代へ継承していく産業として、数千人が働いています。彼らに支えられて私の服がある。毎シーズン、何かしら刺繡を用いることで、私は職人としての彼らの生活を支えていきたい。良いパートナーシップが組めています」
巨大な企業グループに属さないインディペンデントなブランドが、ここまでの事業を継続している事実は、もっと評価されていいのかもしれない。また、ランウェイで見せたコレクションピースがすべて商品化され、店頭に並ぶというのも独特。ドリスの洋服に対するアプローチは常に明確なのだ。
「私はファッションを作ろうとするのではなく、美しい服を作ろうと常に考えています。それは親しみやすく、個人の気分や体にできるだけ合っているもの。だからランウェイのインパクトだけを狙ってデザインされすぎた服は作らない。だからといってニュートラルなものにも興味がありません。どこかにストレンジな要素がなくてはならない。そこで私は刺繡を用いるのです。服をブローチで飾るように、直接エッセンスを施せるから。また買った人が自分らしく味つけできる余白を残すデザインを心がけます。決して洋服が人を支配するような“個性”が前に出たものであってはならない。だから、私の服だけで全身固めるのは面白くありません。むしろほかの服と組み合わせて楽しんでほしい」
職人の手を渡り、着る人のもとに届くドリス・ヴァン・ノッテンの刺繡は、洋服への深い愛に包まれ、私たちの心を摑んで離さない。