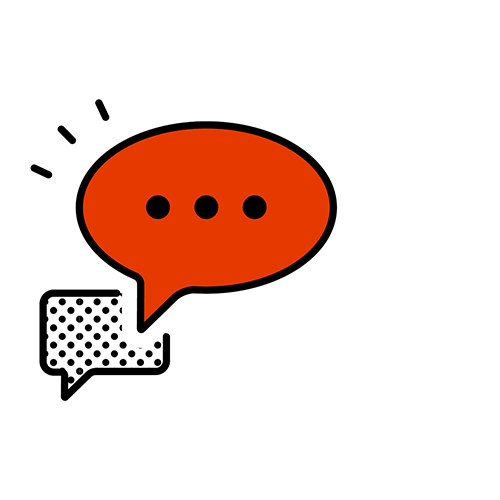BRUTUS
トランプ氏当選のドタバタの顛末は、まさに『東海道戦争』でメディアに煽られて戦争を起こしてしまう民衆の姿とも被るのですが、今回のアメリカ大統領選を筒井さんはどんなふうにご覧になっていましたか。
筒井康隆
それこそ彼の当選は僕の書いた小説みたいだ、なんていうのはツイッターなんかでも今、よく言われているね。面白がって遊び半分の泡沫候補として出てきたはいいけれども、実際に当選してしまったら大変だから、できるだけみんなに嫌われるようメチャメチャな発言をしていたのに、逆にそれで人気が出て、とうとう大統領になってしまった。
で、当の本人がいちばん困っているっていう。だけどまあ、それだけじゃ小説にならんよね。
B
今から半世紀前、1965年に書かれた『48億の妄想』の中でもすでに、テレビが人々の価値観をすべて左右してしまう姿が描かれていました。
筒井
いわゆる「ドッキリ」と呼ばれる企画のテレビ番組はかなり昔からあったんですが、あれを見た時に、このままではドッキリなんだか本当なんだかわからなくなるような、フィクションと現実の違いがわからなくなるような時代がもうじき来るなと確信したんです。最初に思いついて書いたもんだから、その後いっぱい盗作されちゃった。
例えばウディ・アレンも『ローマでアモーレ』で同じことやってるんだよ。まあウディ・アレンだから許すけどさ(笑)。ほかにも怪しいのはいろいろとあるね。
B
筒井さんがとっくに課題として出していた状況を、読者の側が今になってようやくリアリティを持って考え始めたのかな、という印象も受けます。
筒井
それは、みんな僕の小説がずっと昔書かれたものだと知っているからこそ、予言が当たったなんて思って驚くわけ。でも当時のSFは未来を予見する競争みたいな感じだった。それが実現するかどうかわからないまま、とにかく我先にと書いていただけなんです。
例えばヒューゴー・ガーンズバックなんか、90年前の作品だけど、我々日本のSF作家がそういうことを書いていた時代にすでにほとんどの科学技術を予見していた、なんて騒がれていました。そんなの、今の時代から眺めたら大したことじゃないんですよ。ハード面だけ見れば、ここまで発達するだろうという予測はわりと簡単にできるんです。
その一方で、社会学的な予測というのが難しかったりする。世の中は当然変わってくるし、それによって読者も変わってくるし、作品の読まれ方も変わってくるからね。
B
逆に世の中がツツイ化することで書きづらさはありますか?
筒井
というより、僕はもう『モナドの領域』以来、書くことがなくなっちゃったわけですよ。
B
昨年刊行された『モナドの領域』は「わが最高傑作にして、おそらくは最後の長篇」と銘打たれていましたが、本当にこれまでの筒井作品のエッセンスがすべて詰まっていますよね。河川敷で女性の片腕が見つかるというショッキングな場面から、人々がニュースに群がる様子、そこから神や哲学の問題につながって、さらにはメタフィクションの核心にも触れている。
筒井
そうなんだよ。だから今は何事が起ころうと、それを小説にしようとは思わないですね。そもそも新しい小説のアイデアが浮かばなくなってしまった。昔はよく映画を観たりしてましたけど、今はもうニュースを観てる方が面白いもんね。
映画なんか大体パターンが決まりきっているから、最初の10分ほど観たら最後がどうなるかわかってしまう。そりゃ50年も60年も書き続けて読み続けて観続けていれば、たいていのものはすでに描かれたことだってわかってきますよ。
B
それはご自身だけじゃなく、文学全体がそうなっていると感じられるということでしょうか?
筒井
ほかの人のことはわかりません。でも僕は今、谷崎潤一郎賞と山田風太郎賞の選考委員を務めさせていただいているんですが、その候補作さえ読んでおけば、幸いなことに純文学とエンターテインメントの最先端をばっちり押さえられるんですよ。それらの作品を読んでいる限りでは、今は純文学よりもエンタメの方が力があるし、ずっと面白くなってきている。
純文学は実験性の袋小路に嵌まり込んでいる印象ですね。これ以上どうしようもなくなっている感じ。ただ、純文学の中でもエンタメ志向の人もいるわけで。それこそ僕なんか、純文学雑誌に書いているけれど基本はエンタメですからね。同じような作家はほかにも何人かいて、彼らがまた純文学の選考委員とエンタメの選考委員の両方を受け持ったりしている。そういうごちゃごちゃしたところから今後すごい人が出てきそうな気はします。
純文学とエンタメの定義自体もあまり意味がなくなっているし、今はもうそうした垣根はありませんね。むしろことさら分けない方が良い作品が出てくると思います。例えば舞城王太郎とかね。彼が出てきた時はびっくりしました。
小説とはそもそも
不謹慎なものである。
B
発狂した文房具たちと鼬が戦争を繰り広げる『虚航船団』は、文学的な実験とエンタメ要素を目いっぱい詰め込んだ最大の問題作と称されることも多いですが、あの作品はどのような発想から生まれたのでしょうか。
筒井
あれを書いた時はジョセフ・ヘラーの『キャッチ=22』みたいな戦争文学がたくさん出てきた時代だった。中でも僕がいちばん傑作だと思うのは、ノーマン・メイラーの『裸者と死者』。ほかにセリーヌなんかもあるけれどね。そういうものを現代的にできないものかと思って書いたんです。
B
筒井作品を読んでいると、自分の認識が転倒するような危うさを感じます。筒井さんの目から見て、「危ない」と感じる作品はありますか?
筒井
僕はほかの人の書いた小説を読んで危ないと思ったことはないですね。唯一、読者として気をつけないといけないなと思うのは「泣かせる小説」。あの取り扱いはちょっと危ないなと思う。
例えば、僕の書いた小説を読んで泣いてしまった、なんていう反応はよくあるんですよ。だけど作家であるこちらはもちろんそのつもりで書いているわけです。泣かすつもりでいろいろと策を練って、うまくできた時は最後に自分でニヤッと笑うわけだよ。
そんな不埒なものにおめおめと泣かされている状況はちょっとヤバいよね。よく、泣きながら書いた、なんていう人がいるけど、ありゃ嘘だよ。自分が泣いていたら泣かせるものなんか書けない。
B
世の中全体がフィクションに対して、極端に耐性がなくなってきているのでしょうか。
筒井
それはあると思います。例えば昔もパソコン通信上で諍いはあったけれど、そこで悪口を言われたからって自殺する人はいなかったように思うな。今はみんなLINEとかフェイスブックだとかでそういういじめみたいなことが起きるんだろうけど、そもそもあんなのはパソコンやスマートフォンの電源を切れば消えてしまう世界。早くみんなそれに気がつけばいいのに。
B
例えば『大いなる助走』では、実在とおぼしき作家を登場させつつ、直木賞選考のドタバタを通じて当時の文壇の体質を思いきり揶揄されていますが、作品への反応がトラブルに発展したりすることはなかったんでしょうか。
筒井
僕自身が何かされたわけじゃないけれど、編集部に怒鳴り込んできた人がいたという話は聞きました。なんでも、いちばん分厚い唇の人だったらしい(笑)。
あれは世間的には、僕が3回直木賞候補になって落とされた腹立ちまぎれで書いた、っていうことになっているんだよね。だからこんなことを書いて筒井は干されるんじゃないかって心配してくれた人もいたけど、ぜんぜん大したことなかったですよ。
作家の色川武大が文壇バーで飲んでいた時に、当時直木賞の選考委員だった源氏鶏太がやってきて、ちょうど『大いなる助走』の話になったらしいんだよ。源氏鶏太は、自分がモデルとされる人物が作中で惨殺されるもんだから、「あの小説はねえ……」なんて苦々しくしゃべっているのに、色川さんはそんなこと気がつかないで「面白い!」って絶賛していたらしくて。あとで聞いて腹抱えて笑ったなあ。
ただ、「ベトナム観光公社」(泥沼化していたベトナム戦争をパロディにした短編)を書いた時はさすがに身内からも文句を言う人が出ましたね。正義の味方みたいな人がいてさ。「書いていいものと悪いものがあるんじゃないか」っていう言い方されましたけど。
B
そういう場合はどのような切り返しをされるんですか?
筒井
そりゃ「書いて悪いものなんか何一つない」ですよ。
B
小説に関しては、ということでしょうか?
筒井
いや、小説じゃなくて、現実に起こり得ることだもの。

B
代表されるように、どんどん自分たちの現実を覆い隠して狭めているような傾向もあります。例えば震災などの災害があった時に、誰かがSNS上に旅行やパーティなどの楽しげな写真などをアップすると、たちまち炎上するという。
筒井
その言葉、最近よく聞くから、いったいどういうことなのかなと思ってたんだけどさ。ああ、不幸な人がいるのに自分は幸せなことばかり書きやがって、ということか。なんだ、つまんないの(笑)。
みんなそんなこと本気で言ってるの?そりゃ震災そのものを「面白い、面白い」なんて言っていたら不謹慎だけど、もしそうやって書かれた不謹慎なものが本当に面白ければ、別に書いてもいいんだよ。ただ、「不謹慎だ」と謗られることさえ覚悟しておけばね。でも、小説っていうのはそもそも不謹慎なものなんです。
「七瀬です」と言って
家に押しかける人々。
B
「不謹慎」であり続けることは、時代によっては困難もありますか?
筒井
難しいというか、場合によっては殺される時もあるよね。そういう意味でいちばん怖かったのは、「色眼鏡の狂詩曲」(カルチャーギャップを通じて日中戦争や憲法九条を茶化した短編)かな。どうせSFだし誰も読まないだろうと思って書いたんだけど、あれは今自分で読んでもヤバいなと思う。
あとは「首長ティンブクの尊厳」(北朝鮮をパロディ化した短編)。韓国の出版社から、あれをハングルに翻訳したいと言われた時は、さすがにちょっと待ってくれって言いましたよ。だって、そんなことしたら彼らも読めちゃうからさ(笑)。これは命がないぞと思ってね。
B
実際に脅迫の手紙が届いたり、電話がかかってきたりすることは?
筒井
いくらでもありますよ。「堕地獄仏法」や「末世法華経」(いずれも“総花学会”と“恍瞑党”が支配する世界が舞台)を書いていた時なんかもう、あちらの学会から「破折する~!」なんて言われました(笑)。
B
書いている時点でそういう反応が返ってくることも予想されていたことと思いますが、その時は怖くはなかったんですか?
筒井
ええ。反応があった方が面白いと思っていたし、それで被る被害なんて大したことないと思っていた。とはいえ当時の常識で考えて、まさか本当に公明党が政権を取るとは思っていなかったけどね。
B
1993年にマスコミの用語自主規制に抗議して、断筆宣言をされてから20年以上が経ちましたが、当時はどういった状況だったのでしょう。
筒井
あの時は僕が書いた小説の内容に対してというよりも、むしろ断筆したことに対していろんな嫌がらせを受けました。でも僕に言わせれば、抗議をしてきた団体の言い分ばっかり載せて、僕の言い分をぜんぜん載せてくれなかったマスコミが悪い。だからマスコミに対して反旗を翻したわけです。
例えば、ずいぶん昔に世田谷で祖母を殺して自殺してしまった少年のニュースが話題になったけど、彼は僕の小説のファンだったらしい。もちろんそんなこと聞いても「名誉なことです」なんて決して言わないですよ。そのへんの常識はあります。とはいえそれは、本来ならすべての小説が持ち得る毒が作用した結果だろうと思っています。
B
毒性の強い作品といえば、例えばジャンとヴィンという名の宇宙生命体が人間の体を借りてドタバタのスプラッタ劇を繰り広げる短編「トラブル」が思い浮かびます。
筒井
ちょうどあれを書いた時代に〈JUN〉と〈VAN〉という男性ファッションの二大勢力が争っていたんですよ。あの頃は僕も一生懸命ストライプを着ていました(笑)。『平凡パンチ』の表紙がみんなそうだったからね。
あの作品では残酷展示会というのをやりたかったんですよ。どこまでやれるか、という試み。一種のアブストラクトみたいなものです。よく通っていたバーに文学好きのママがいて、僕の作品もぜんぶ読んでいてくれたんだけど、あの作品を読んでいた時だけは途中から自分でもわかるくらいサーッと顔色が変わって読むのやめちゃったって言っていたね。それ聞いて「ああ、俺はもう、そこまで描けたのなら満足だ」って思った。
だから『時をかける少女』が僕の代表作になったら困るんですよ。こないだ街頭で「この人知ってる!」って言いながら若いヤツらが寄ってきてさ。「どういう作品がありますか?」なんて聞いてくるから、いろいろ題名を挙げてみたんだけど、みんな知らないって言うんだよ。そこで『時をかける少女』の名前を出したらいっぺんに盛り上がってね。こりゃヤバいなと思ってさ。あんな無害なものが代表作じゃ困る。
ついでに言えば、あれは小説じゃなくてアニメが本家だと思っている人もいっぱいいるからね(笑)。
B
筒井作品の毒に当てられて、実際に自分の中の何かが揺らいでしまったという読者の話を耳にすることはありますか?
筒井
ああ、入院したという人の話は聞いたことがあります。ある日、セラピーをやっている方から電話がかかってきたんですよ。「先生の『パプリカ』(他人の夢の中に実際に介入する精神療法技術が発達した世界を描く近未来SF長編)を読んでしまったクライアントがヤバい状態になってしまったので、先生自身の口から何か一言言ってくれませんか?」って。そんなこと言われても僕にゃどうすることもできないけどね。
あとは、僕の住んでいる家に来ちゃう人もいます。「私、七瀬です」なんて言ってさ(笑)。これはもう何人もいますよ。東京の家にも来ましたね。夜中に何度もインターホン鳴らすからほったらかしにしていたら、壁乗り越えて入ってきちゃった。さすがに警察に電話したら、渋谷警察署からも原宿警察署からも警官が大勢来てえらい騒ぎになっちゃって。
B
ご自宅の表札に堂々とフルネームで「筒井康隆」と書かれていますが、隠してしまおうと思ったことはないんですか。
筒井
いや、別に構わないからね。むしろ面白いです。だって、中にいると「うっそー!」とか「マジー?」とか聞こえてくるんだもん。ああ、びっくりしてやがるなっていつも面白がってる。時々お賽銭とかもらえるしね。玄関の石の上に五円玉がちょこんと置かれてたりするの(笑)。
俺がシュールなのか、
世の中がシュールなのか。
B
小さな頃から周りの人を笑わせるのは得意でしたか。
筒井
ええ。ここでみんなが笑う、っていうポイントが自分の中ではっきりしていた。その予測が裏切られたことはあんまりない。休み時間になるとみんなが僕の机の周りに寄ってくるんですよ。僕がバカなことばっかり言ってるから。
その様子が気に食わなかったんでしょうね、ある日、級長に「筒井は嘘つきだ」って吹聴されて、「嘘つき」という定評になっちまった。そりゃギャグなんだから嘘に決まってるんだけど(笑)。
B
幼稚園の頃、トイレに入った先生にイタズラして、下半身丸出しのまま立たされたというエピソードを本誌に寄せてくださったこともありますよね。
筒井
しかもカトリック聖母園に通っていながらそんな悪いことしちゃうからね。たしかに不良だったけど、反骨精神旺盛だとかそういうんじゃなくて、単に「こういうことしたら面白いだろうなあ」と思っていただけですよ。
むしろ、なんでほかのみんなが思いつかないのか不思議でした。だって、遊んでいるすぐ横に便所の汲み取り口があるんだもん。そこからいくらでもイタズラできるじゃないですか。
B
先日行われたトークイベントの際、全室禁煙の大学のホールでおもむろにタバコに火をつけて爆笑をさらっていた姿がシュールでカッコ良くて、印象的でした。
筒井
誰が止めるかな、と思ってたんだけど、けっきょく誰も止めないからそのまま吸っちゃった(笑)。しかし僕が書いた「最後の喫煙者」じゃないけど、普通にタバコ吸ってる光景がシュールになるなんて、変な世の中になっちゃったよねえ。
今回はそもそも僕が「危険な作家」ということでインタビューしてもらっているわけだけど、危険というのは自分で言うことじゃないんだよね。僕自身にとって、僕は何一つ危なくないわけだから。そりゃやっぱり読者に教えてもらいたい。とりあえず、僕の作品を一度全部読んでみてほしいですね。くれぐれも『時かけ』だけで満足しないでほしい(笑)。

★
B
最後にひとつお願いがあります。せっかくのインタヴューなのでその結末を、読者があっと驚くようなメタフィクションで締めくくっていただけないでしょうか。つまり先生に最後だけ原稿を書き足していただくことになりますが。
筒井
えっ。ぼくに書かせるの。そりゃあまあ、別段、いいよ。その分の原稿料さえ貰えるのなら。
B
いやあ、原稿料はまあひとつ、インタヴューの謝礼と込みにということで。
筒井
なんだそりゃ(笑)。ああそうか。せっかくインタヴューで高い謝礼払うんだから、せめてただで原稿書かせようってところだね。メタフィクションなんて言ってるけど、ほんとはメタフィクションがどういうものか知らないんだろ。
どういうものかよくわからないけど、それをおれに書かせて、どんな芸をするか見てやろうということか。なんだか猿回しの猿みたいだね。ほれ。何かやってご覧。ほれ。何かやってみろ(手拍子を打って)。ほれ。やってみろ、やってみろってなもんだね。
B
いえいえ。そんな失礼なことは決して考えていません。編集部としてはただ、先生のこの特集を面白いものにしようという意図しか持っておりませんし。
筒井
その面白いことを自分らではできないから、おれにやらせようっていうんでしょ。しかもただでさ。やっぱりそれは失礼なんだよ。あれっ。なんか不満そうだね。なんだよその顔は。なんで黙ってるの。黙っていたらおれが根負けして言うこときいてくれるだろうって思ってるんだろ。そういうわけにはいかんのよ。
こら(茶菓子をつまんで投げる)。なんとか言え。なんとか言いなさい。
B
わかりました。わかりました。やめてください。いやどうも、やっぱり先生は「最も危険な作家」だったわけですね。
筒井
それはねえ、ちっとも嫌味になってないんだよ。それはこの特集のタイトルでしょうが。危険な作家だなんて、そんなこと今ごろになってやっとわかったか。そもそも作家はみんな危険なんだってこと、編集者だったらよく憶えときなさい。なんだお前らは。
だいたいが無礼なんだよ。たった4ページのインタヴューに6人も押しかけてきやがって。何しにきたかわからんやつまでぞろぞろと見物について来やがって。おれは見世物か。骨董品か。ええ。そうか。わしのこの家、見世物か。博物館か。あんまり馬鹿にするなこら(茶菓子を投げる)。
B
あの、先生。ちょっと、やめてください(笑)。これはいったい何ですか。何なんですか。これがメタフィクションだぞということでしょうか。でもこれだと、ただ編集者をいじっているだけということになるんじゃないですか。
筒井
いいや、そうじゃないんだな。編集者だけでなく、読者もいじっていることになるんだよ。読者はこれを読みながら、どうなるんだろうと思ってはらはらするだろ。つまり、読者もこの状況に巻き込まれているってことになる。その意味じゃ、メタフィクションを通り越してパラフィクションになっているってことも言えるしな。
パラフィクションってわかるか。メタフィクションが読者に「これは虚構だ」と認識させることだとすれば、パラフィクションは読者に「今自分は読書している」と認識させることだ。うわあ、いやだなあ。つまらん解説させられちゃったよ。あっ。この辺のところ、カットしたり書き直したりしやがったら承知せんからな。そんなことしたら、全部わしのブログで公表してやるからな。
(カメラマンに)こらあ、お前は何だ。さっきからひとの顔にたにた笑いながらじろじろ見やがって。目ざわりなんだよ。カメラのうしろで傍観者を気取るなよ。おれが怒ってるから面白い写真が撮れると思って喜んでやがるんだろう。この野郎(湯呑み茶碗を投げつける。カメラマンは茶碗が頭に当って悲鳴をあげる)。
ええいもう、腹が立つわい(盆を投げつけて横にいる編集者を殴りつけ、首を絞めるなどして暴れはじめる)。こいつら。死ね死ね。この野郎。
B
わあっ。すみません。すみませんでした。ご勘弁を。あの、あの、それではもうこの辺で。やめましょう。やめましょう。あの、本日はどうも、ありがとうございました。