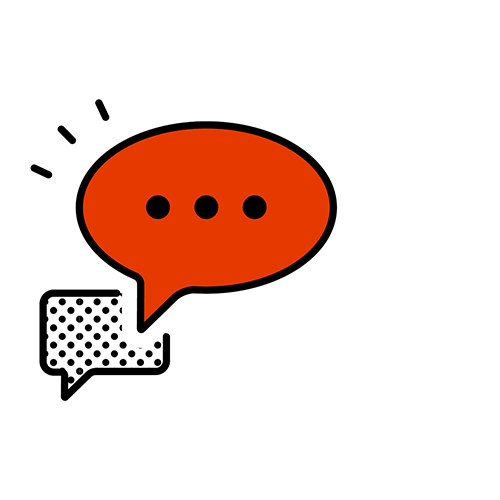世界を聴いた男、小泉文夫
『世界を聴いた男』──これは、世界のあらゆる地域、あらゆる人々の間で綿々と受け継がれてきた「音」を求めて、取り憑かれたように世界中を駆け巡り、その収集/研究/紹介にすべてを賭した男の生涯を綴った評伝のタイトルである。
「民族音楽の巨人」、故・小泉文夫が日本の音楽界に残した膨大な業績は、その死後20年近くが経とうとする現在においても、まさに空前絶後と呼ぶほかない。彼の残した資料や音源の多くは現在、かつて教鞭をとった東京藝術大学音楽学部の「小泉文夫記念資料室」に収蔵されている。
今回、その資料室を十数年ぶりに訪れたミュージシャンの早川大地さんは、まさに「YMOから小泉さんに入った世代」。小泉と同じく東京大学の文学部で美学芸術学を学んだという早川さんは中学生の頃、図書館で小泉の編集したCDを手にし、初めて民族音楽の世界に触れたという。
「最初に聴いたのがギリシャのキプロス島の音楽で、“ドラクエの音楽みたいでカッコいい”と思ったんです。それから興味が湧いて自分なりに色々調べていくうちに、坂本龍一さんが藝大生時代に小泉さんの授業に出ていたことを知ったり、YMOの音楽に民族音楽の影響が見え隠れすることがわかってきて、さらに関心が高まりました」。その後、習っていたピアノの先生から、小泉がパーソナリティを務めるラジオ番組『世界の民族音楽』(NHK-FM)のテープを借り、さらにその魅力にハマることに。
「小泉さんは、一見難しい、とっつきにくいと思われがちな音楽の世界をわかりやすく、面白く語るのが本当に上手で、興味を掻き立てられました」との言葉通り、小泉は一流の研究者であるだけでなく、生涯において数多くの著作や放送を通じて、一般の人々に民族音楽の魅力を伝えるスポークスマンであり続けた。その旺盛な啓蒙的活動の背後には、彼自身の辿った音楽体験が強く反映されている。
1927年東京で生まれた小泉は、幼い頃からバイオリンを習い、賛美歌に親しむ音楽少年として育った。クラシックを中心に西洋音楽を学び、東京大学に進学。美学美術史学科で学んでいた23歳の時、日本音楽史の講義で地歌(江戸期に発生し、上方を中心に行われた三味線音楽)の実演を聴き、その研ぎ澄まされた邦楽の美しさに激しい衝撃を受けた。
そのショックの内実について小泉は後に「私自身が日本人なのに日本音楽を知らなかったということに対する恥ずかしさも混じっていた」(『世界の民族音楽探訪』)と綴っている。明治の開国以後、欧米へのキャッチアップを目標に近代化の道を突き進んでいた当時の日本のアカデミズムにおいては、「音楽」とはクラシックを中心とする「西洋音楽」を意味し、邦楽は普遍性に欠け、研究に値しない未熟な音楽であるとされていた。
その現状に強い疑問を感じた小泉は日本音楽に興味を深めた。研究・調査活動を続ける中で、さらにその関心は世界の民族音楽にも広がっていった。そして57年、30歳にして南北インドの音楽院へ留学、インドの伝統音楽を学んだ。当然ながら、当時の留学生のほとんどの行き先が欧米だった時代である。
2年後、膨大な量の楽器とともに帰国した小泉はその後、生涯にわたり、世界中の民族のもとを訪れてフィールドワークを続け、音源を採集し、楽器を収集し、おびただしい数の資料と記録を残した。各民族の生活に密着した、生き生きとした音と歌の深い海に触れた小泉にとって、「第三世界の音楽がクラシックよりも下である」などという思い込みはまったく無意味なものとして映っただろう。
国家による西洋偏重型の音楽教育を正したいという思いから、当時の学者としては珍しくテレビやラジオなどのマスメディアに積極的に出演。あらゆる民族音楽の魅力を世に伝え続けた。
「小泉さんは世界を自分の足で渡り歩いた上で、フラットな俯瞰の視点で音楽文化全体を見ていたと思います。こんなにスケールの大きい音楽学者は、今後もなかなか出てこないだろうと思いますね」と早川さんは語る。
情熱的に民族音楽を追い続け、地域ごとに異なる豊かな音楽性を誰よりも知悉していた小泉だが、その根底にはいつも、「音楽の普遍性」に対する視線があった。なぜ人は音楽を演奏し、歌うのか。人間は音楽に何を求めるのか。音楽に心惹かれるのはなぜか……。
彼を止めどないフィールドワークの日々に導いたもの、それは世界中に溢れる「音楽の持つ力」に対する飽くなき好奇心と探究心。そこへ目を向けさえすれば、その実り豊かな音の果実を誰もが存分に味わえることを、小泉文夫は56年という短い生涯のうちに、日本の人々に伝え続けたのである。
早川大地が“小泉遺産”から選ぶ、快い民族音楽
モンゴル/オルティンドー「すずしくて美しいハンガイ」
オルティンドーとはモンゴル語で「長い歌」という意味で、その名の通り息の長い発声で1人で朗々と歌い上げる伝統的な民謡。「追分」「馬子唄」とも近く、北海道の民謡「江差追分」との類似も指摘されています。日本人の心に響く歌です。
台湾/台湾先住民(アミ族)の音楽「収穫祭の老人の歌」
台湾先住民・高砂族のアミ族に伝わる歌で、高度に洗練されたポリフォニー(合唱)が美しい。1996年のエニグマのヒット曲「リターン・トゥ・イノセンス」でアミ族の歌手・郭英男(Difang)の歌が使われ話題になったこともあります。
ジャワ(インドネシア)/ガムラン「プラブマタラム(マタラムの王)」
ガムランといえばバリ島が有名ですが、ヒンドゥー教の民衆文化として発達したバリの激しい高速のガムランに対して、宮廷文化として貴族の間で受け継がれてきたジャワのガムランはゆったりとして癒しのある音です。
バリ(インドネシア)/ケチャ「ウブット村のゴング・スリン 〜レゴッド・バウォ〜」
ケチャはバリ島で行われている男声合唱で、近代に入って伝統芸能として確立されたもの。数十人もの男性がいくつかのリズムパターンで「チャ!」などの声を出し3拍子と5拍子など違った拍子を組み合わせていく展開がツボにハマります。
ウイグル/ウイグル民謡「阿娜汗(アナルハン)」
ウイグルの美しい草原を思わせるような民謡。女子十二楽坊もこの曲を演奏しているように、中国との関係がすぐに思い浮かぶエリアですが、実際には住民の多くはイスラム教徒であり、その音楽にもアラブ圏の文化の影響が感じられます。
カナダ/カナダ・イヌイットの歌「のど鳴らし」
2人の人間がキスするくらいに顔を近づけ、1人が相手の口の中に息を吹き込み、相手が喉を開け閉めしてリズミカルな音を生み出すもの。口を共鳴胴として使う非常にユニークな音楽で、小泉さんの本で初めて読んだ時はとても驚きました。
ハンガリー/ロマの音楽「舞曲」
ハンガリーにはロマ(ジプシー)の人々が非常に多く住み、ジプシーミュージックにおいても非常に豊かな歴史を持っています。冷戦の終了後、東側諸国で育まれてきた彼らのさまざまな音源が聴けるようになったのはありがたいです。
ギリシャ/クルタ島イラクリオン地方の音楽「マティナデス」
ギリシャの音楽には西洋とアラブの文化が入り混じり、その絶妙なブレンド具合が楽しめます。歴史を感じる音ですね。そもそも民族音楽との最初の出会いがキプロス島の音楽だったので、やはりこのエリアの音には心惹かれてしまいます。
エジプト/ナイルの歌〜コプトの宗教音楽「ミハイル師の歌」
イスラム教徒が約9割を占めるエジプトで、現在も一部で信仰されているキリスト教の一派「コプト教」の宗教音楽。いわゆるキリスト教の賛美歌のような聖歌に、アラブ的な「こぶし」や節回しが入っていて、そのミックスが非常に面白い。